「絶滅動物を交配で再生」ナチス政権下のベルリン動物園が進めた危険な計画
プレジデントオンライン / 2021年2月14日 11時15分
※本稿は、溝井裕一『動物園・その歴史と冒険』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。
■第1次大戦からの復活を遂げたベルリン動物園
ベルリン動物園ほど、戦争にたいする協力と、そのあとの破滅的な結末のせいで目を引くところもないだろう。
ここを率いていたのはルッツ・ヘック(1892~1983)。ミュンヘンのヘラブルン動物園園長ハインツ・ヘックの兄である。彼は1932年に、父ルートヴィヒのあとをついでベルリン動物園園長となった。ベルリン動物園もまた、第1次大戦の影響を逃れるわけにはいかず、市民たちに愛されたチンパンジー「ミッシー」「モーリッツ」などの動物を失っている。敗戦のあとはインフレが生じて、入園料ではとてもまかないきれないほどエサ代がはねあがった。
しかし、市民たちが寄付したエサや、銀行ならびに自治体による援助、インフレ解決のおかげでなんとか苦境を脱し、園長ルートヴィヒ・ヘックはふたたび動物の補充をはかる。このとき活躍したのが長男のルッツで、アビシニア(エチオピア)や旧ドイツ植民地(タンザニア)におもむいて、キリン、カバ、サイ、シマウマ、ダチョウなどを連れてかえってきた。ルッツが父のあとをついだとき、ベルリン動物園はふたたび堂々たる規模になって、453種の哺乳類と、799種の鳥類を飼育していた。
■ナチス党員になったルッツ・ヘック
いっぽうでヘック親子は、ナチス思想に共鳴するようになっていた。もともと父ルートヴィヒには、皇帝ヴィルヘルム2世に支援されて、ドイツ産の生きものをテーマにした「祖国コレクション」を展示するなど、ナショナリスティックなところがあった。
またその言動はナチスを先どりするものであったと、みずから自伝に記している。彼は息子たちから、「父さんはすでに国家社会主義者(ナチス)だったんだよ。この言葉ができる前から、僕たちに国家社会主義的な世界観を説いていたじゃないか」といわれていた。
長男ルッツもその影響を受けたのか、ナチスがドイツの政権を獲得した1933年に「親衛隊賛助会員」になっている。親衛隊とは、ヒトラーの護衛を目的にハインリヒ・ヒムラー(1900~45)が創設した武装組織のことで、ナチス・ドイツの文化政策にも深く関与したことで知られる。親衛隊賛助会員は、毎月自分で決めた額の金を支払うことでこれに協力するのだ。
またルッツ・ヘックは、親衛隊の先史遺産研究所「アーネンエルベ」から奨励金を受けとっており、一時は親衛隊員になることさえ考えていたという。いずれにせよ1937年の時点でナチス党員にはなっていた。
■動物園のテーマを「北ドイツ」にした理由
しかもルッツ(父や弟と区別するためこうよぶ)は、ナチス・ドイツの「全国元帥」ヘルマン・ゲーリング(1893~1946)ときわめて親しかった。ともに狩猟を趣味にしていたことが大きい。1940年には、ゲーリングが傘下におさめる「全国営林局」の「最高自然保護所」を率いることになる(図版2)。

そんなルッツが率いるベルリン動物園は、ナチスにとりいるような展示をはじめた。「ドイツ動物園」がそれである。この施設は、北ドイツの家屋や風景を再現して、クマ、オオカミ、オオヤマネコ、カワウソ、オオライチョウといった土着の生きものを飼育するものだった。北ドイツがテーマになっているのは、当時「ゲルマン=ドイツ人」(アーリア人)の「人種精神」が同地方に残っているとみなされていたからだ。ナチスの鉤十字(ハーケンクロイツ)が飾られていたことは、いうまでもない。
■「絶滅動物」の再生に力を注いだ
さらにルッツが、弟ハインツとともに精力的にとりくんでいたのが、オーロックスやターパンといった絶滅動物を再生することだった。オーロックスは、現在家畜となっているウシの祖先であり、ターパンは家畜のウマの祖先にあたる。また、当時絶滅にひんしていた野牛ヨーロッパバイソンの再繁殖も試みた。
彼らは、なぜこれらの種に関心を示したのか。筆者は、この問題を調べてくわしく書いたことがあるが、ここではかんたんに説明しておこう。これら3種の生きものは、中世ドイツの英雄叙事詩『ニーベルンゲンの歌』のなかで、ジークフリートが狩ったとされている生きものなのだ。少なくともルッツはそうみていた。
『ニーベルンゲンの歌』は、残酷な殺しあいの物語(ほとんどみんな死ぬ!)であるが、ドイツ人がもつ忠誠心や勇敢さをあらわしていると讃(たた)えられ、なかでも「竜殺し」のジークフリートは人気の英雄だった。
■人種計画ともパラレルな関係、「アーリア的」帝国を目指した
つまりルッツ・ヘックらの絶滅動物再生計画は、ジークフリートが生きていたとされる時代の自然、つまり「アーリア的自然」をよみがえらせるものだったのだ。ついでにいえば、彼らの計画は「アーリア的」な形質をもつとされた人びとの子孫を増やして「純血種」を増やそうとする、ヒムラーの人種計画ともパラレルな関係にあった。ナチスは、彼らが「アーリア的」とみなす人種、文化、自然によって統一された帝国をつくろうとしたのであり、ベルリン動物園はその一翼を担っていたのだ。
それにしても、絶滅動物の再生というと難しそうに聞こえる。しかしルッツによれば、遺伝の担い手は染色体という「固体の成分」であり、すべての生きものはこれがモザイクみたいに集まってできている。つまり、現在の家畜のウシやウマから、先祖オーロックスやターパンにさかのぼる染色体だけを「切りはなし」、「結合」させればよい。早い話が、彼らが「祖先の姿に似ている」と思ったウシやウマを選んできて交配させ、子孫をつくらせるのだ(ルッツとハインツのやりかたには違うところもあったが)。
■「本物以上に本物らしい生きもの」を誕生させた
こうして、彼らの手でオーロックスもターパンも「よみがえる」ことになった(P1、図版1)。ただ、これらが本物のオーロックスやターパンなのかといえば話は別である。たとえばオーロックスについては、ヘック兄弟は科学的な調査にもとづくよりも、勝手につくりあげた「原牛」のイメージにしたがって交配をくりかえしたことが明らかになっている。ヘック版の「復元動物」は、本来の姿に近いというよりは、彼らが理想とする姿をあらわした生きもの、つまり「本物以上に本物らしい」一種の怪物であった。
ヨーロッパバイソンの再繁殖も、やはり問題のあるものだった。アメリカ大陸から連れてきたアメリカバイソンを、ヨーロッパバイソンと交配させたのである。
なぜこんなことをするのかといえば、アメリカバイソンの旺盛な繁殖力だけをいただこうというのだ。こうして生まれた子孫は、たしかに「混血」であるが、ヨーロッパバイソンと交配させていけば、いずれもとの種に近いものとなろう。アメリカバイソンの遺伝子をしだいに圧迫するわけだから、ルッツはこのプロセスを「圧迫育種」とよんでいた。
■占領地の動物相や植物相を作り変えようとしていた
彼は、こうして生まれた「復元動物」をいくつかの土地で野生化する実験をおこなった。そのひとつはベルリンの北に位置するショルフハイデであり、ここにはゲーリングの「カーリンハル」という邸宅があった。もうひとつはポーランドとベラルーシの国境にある原生林ビャウォヴィエジャである。ドイツ軍がポーランドを征服したのをいいことに、ナチ党員ルッツはオーロックスを放って自然にかえそうとしたのだった。
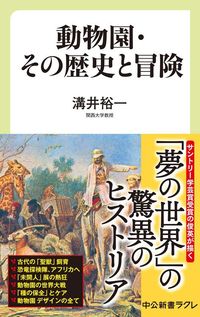
もともと親衛隊トップのヒムラーは、ドイツから東にあるエリアを征服後、ドイツ的な村や町をつくり、さらにその風景を改造することを望んでいた。ルッツもこれに便乗するかたちで、占領地の動物相や植物相をつくりかえようとしたのである。
また彼は、ドイツ軍の侵攻に乗じて東ヨーロッパの動物園を訪問し、貴重な生きものたちをドイツに移送するのにかかわった。この話は、戦時下のワルシャワ動物園をあつかったノンフィクション『ユダヤ人を救った動物園』(ダイアン・アッカーマン)にも登場する。
そこでは、彼はワルシャワ動物園から希少動物を「保護」という名目で拝借してドイツへ送っただけでなく、残った飼育動物を親衛隊仲間に遊びで射殺させるような、恐るべき人物として描かれている。おそらくこういった行為が原因で、のちにソビエト連邦軍は彼の逮捕を試みたのだろう(Artinger 1994,Heck,Ludwig 1938,Heck,Lutz 1952,Klös 1969,Vuure 2005,溝井 2017)。
【参考文献】
Artinger,Kai.‘Lutz Heck:Der “Vater der Rominter Ure”: Einige Bemerkungen zum wissenschaftlichen Leiter des Berliner Zoos im Nationalsozialismus.’Der Bär von Berlin:Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins.(1994):125‐138.
Heck,Ludwig.Heiter=ernste Lebensgeschichte:Erinnerungen eines alten Tiergärtners.Berlin:Deutscher Verlag,1938.
Klös,Heinz‐Georg.Von der Menagerie zum Tierparadies:125 Jahre Zoo Berlin.Berlin:Haude & Spenersche Verlagsbuchhandlung,1969.
Vuure,Cis van.Retracing the Aurochs:History,Morphology and Ecology of an Extinct Wild Ox. Sofia‐Moscow:Pensoft Publishers,2005.
溝井裕一、細川裕史、齊藤公輔編『想起する帝国―ナチス・ドイツ「記憶」の文化史』勉誠出版、2017年。
----------
関西大学文学部教授
1979年兵庫県生まれ。関西大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門はひとと動物の関係史、西洋文化史、ドイツ民間伝承研究。『水族館の文化史――ひと・動物・モノがおりなす魔術的な世界』(2018年)で第40回サントリー学芸賞〈社会・風俗部門〉を受賞。他の著書に『ファウスト伝説――悪魔と魔法の西洋文化史』(09年)、『動物園の文化史――ひとと動物の5000年』(14年)、『グリムと民間伝承――東西民話研究の地平』(編著、13年)、『想起する帝国――ナチス・ドイツ「記憶」の文化史』(共編著、16年)などがある。
----------
(関西大学文学部教授 溝井 裕一)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
ドイツ野党と「極右」協力に抗議 ベルリン、16万人以上がデモ
共同通信 / 2025年2月3日 9時41分
-
ドイツ首相「本当にうんざり」、マスク氏の欧州右翼支援に嫌悪感
ロイター / 2025年1月29日 11時51分
-
マスク氏、独極右政党イベントでビデオ演説 支持を改めて表明
ロイター / 2025年1月27日 7時48分
-
上野動物園、アジアゾウの展示を当面休止 4歳オス「アルン」が成長、母との交配避け、3頭とも「静かな環境」へ
ORICON NEWS / 2025年1月21日 9時49分
-
ナチスへの復讐劇『手紙は憶えている』とイスラエルをめぐるジレンマ
ニューズウィーク日本版 / 2025年1月17日 18時13分
ランキング
-
1「元の生活に戻れるのか」…八潮の陥没事故から2週間、下水道利用自粛・電話不通・通学路変更
読売新聞 / 2025年2月10日 20時52分
-
2昨年6月から行方不明の52歳妻を遺棄した疑い、35歳男を逮捕…遺体は見つからず
読売新聞 / 2025年2月10日 20時43分
-
3奈良県で道路下に空洞疑い38か所、レーダーで検査へ…大型下水管に異常なし
読売新聞 / 2025年2月10日 19時12分
-
45年前の神戸のビル火災 放火・殺人の疑いで70歳男逮捕「私は火をつけていません」58歳男性が急性一酸化炭素中毒で死亡
MBSニュース / 2025年2月10日 16時55分
-
5伊東地方創生大臣が「尿路感染症」で入院 今週中の閣議や国会審議欠席の見込み
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月10日 22時32分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










