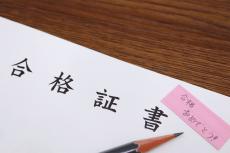低偏差値の高校に入った同級生が、意外と難関大学に合格するのには理由がある
プレジデントオンライン / 2021年5月17日 11時15分
※本稿は、外山美樹『勉強する気はなぜ起こらないのか』(ちくまプリマー新書)の一部を再編集したものです。
■身近な友人の存在はやる気に影響するのか
私たちは、たった一人で社会から孤立して生きているのではなく、さまざまな社会的相互作用の中で、有形にも無形にも影響を受けています。
そのため、どんなにやる気がある人だって、まわりからの影響を受けて、やる気がなくなることがあるでしょう。反対に、やる気がでないなと思っていても、そんな気持ちが吹き飛んでしまうこともあります。
その影響の受け方は時と場合によってさまざまです。優れた友だちの存在によって、やる気が出ることもあれば、逆に自分の不甲斐なさを思い知らされ、意気消沈したり、やる気がなくなったりします。
第四章では、周囲の人がどのようにやる気に影響を及ぼすのかをみていきたいと思います。
中高生のみなさんにとって、もっとも身近な友だちの存在がどのように人のやる気に影響を及ぼすかをみていくことにします。
■「鶏口となるも牛後となるなかれ」は本当か
突然ですが、「鶏口となるも、牛後となるなかれ」という格言を知っていますか?
これは、一般的には、牛は鶏よりも秀でているという考えから、「優れた集団の後ろにつくよりは、弱小集団でもトップになったほうがよい」というたとえになります。
心理学では、この格言が実際にあてはまるような現象が観察されています。
ここに、AさんとBさんがいるとします。
AさんとBさんは、高校入学直前までは、ほとんど同じ成績でした。ところが、Aさんは偏差値の高い進学校に入学したのに対して、Bさんはたまたま高校受験で失敗してしまい、Aさんとは異なる、偏差値がそれほど高くはない高校に入学することになりました。こういうことは、現実にもよく起こることですね。
さて、ここでみなさんに質問です。同じ成績だったAさんとBさん、その後二人の成績は変化するでしょうか? 一見すると、偏差値が高い高校に入学したAさんのほうが成績が良くなるように思えます。
高校受験に失敗して、学業レベルがそれほど高くない高校に入学したBさんは、たいそう落ち込んだに違いありません。Bさんを含めた私たちの多くが、偏差値の高い高校に入学したほうが、成績をあげるのに何らかの形で有利に働くと考えているからです。
■低い偏差値の高校に入学したほうが好成績に
さて、その後、この二人の成績はどのように変化したのでしょうか。もちろん数カ月後に変化することもあれば、一年、二年先のこともあるでしょう。
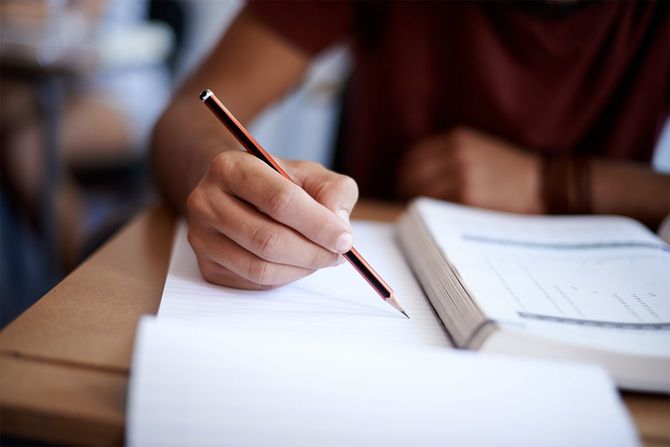
ここでは仮に一年後、高校二年生の時に、どうなったかを示してみたいと思います。
Aさんは、よくできる生徒ばかりの高校だったため、まわりの友だちも優秀な人たちばかりでした。そのため、その優秀な友だちと自分を比較してしまい、自分は本当はあまり勉強ができないのではないかと落ち込んでしまい、勉強に対するやる気を失い、最終的には能力以下の成績しか収めることができなかったという例も、よく見られます。
一方のBさんは、そこまで成績が良くない生徒が集まる高校なので、他の生徒と比べて成績が良いほうでした。自分よりも成績が悪い友だちと自分を比べて、「自分は勉強ができるんだ」と自信をつけます。そこから勉強に対するやる気もあがり、成績がさらに良くなり、一年後にはAさんよりも成績が良いというふうに変化しました。
高校入試の際には、二人の成績は同じだったのに、Aさんよりも偏差値が高くない高校に入学したBさんのほうが、最終的に良い成績を収めたのです。この現象は、一見すると不思議だと思いませんか?
それならばそもそも偏差値の高い高校を目指す必要はないことになります。
■優秀な人に囲まれると「有能感」は低下する
こうした現象は、「大きな池の小さな蛙になるよりも、小さな池の大きな蛙になるほうがよい」という意味で、心理学では「井の中の蛙効果」と呼ばれています。冒頭で紹介した「鶏口となるも、牛後となるなかれ」とも似た意味です。
ちなみに、「井の中の蛙大海を知らず」という格言もありますが、こちらは、狭い世界に閉じ込もっている井戸の中の蛙は、広い世界があることを知らないで、いばったり自説が正しいと思いこんでいたりすることを意味しており、心理学で用いられる「井の中の蛙効果」とは少しニュアンスが異なっているので、注意してください。
あらためて、学術的に説明すると、心理学で用いられる「井の中の蛙効果」は、同じ成績の生徒であっても、レベルの高い集団に所属していると、優秀な生徒たちとの比較のために有能感が低下し、レベルの低い集団に所属していると、自分よりも劣った生徒たちとの比較のために有能感が高まる現象のことをいいます。
心理学者のマーシュが行った44校の高校生7727名を対象にした調査では、同じ能力(成績)の高校生において、所属している高校の偏差値が高くなればなるほど、その人の有能感が低くなることが示されています。
ここでは、集団の例として「高校」を取りあげましたが、もちろん、高校に限らず、学校単位だけではなくクラス単位だったり、大学にも当てはまる現象です。
さらには、この現象は勉強だけに当てはまるわけではありません。高校までは野球がうまくて注目を集めていた選手が、野球がとても強い大学(あるいは実業団)に入学(入団)して、自分よりも優れた選手を目の当たりにすることで有能感が低下し、すっかりやる気を失い、最終的には能力以下の成績しか収めることができなかったという例も、よく見られます。
このように、「井の中の蛙効果」といった不思議な現象がいろいろなところで見られることは、心理学のさまざまな研究を通して確認されています。
■「有能感」とはなにか
先ほど、「井の中の蛙効果」の説明のところで「有能感」という言葉を使いました。これは少し聞きなれない言葉だと思いますので、少し説明をしておきたいと思います。なお、有能感は、心理学では「コンピテンス」や「自己概念」と呼ばれることもあります。

有能感とは「自分は○○ができる」、「自分は○○が得意である」、「自分は○○が苦手である」といったように、○○に対する自信のことを指します。
先の例では学校での成績の話だったので、「自分は勉強ができる」、「自分は勉強が苦手である」といった勉強に対する自信のことを指しています。
スポーツに関してであれば、「自分は運動が得意だ」、「自分はスポーツが苦手である」といったものになりますし、友だちとの関係だったら、「自分には友だちがたくさんいる」、「自分は友だちに嫌われている」といったものが有能感になります。
また、場面を限定しない一般的な有能感もあります。これは、「自尊感情」と呼ばれているもので、成績、スポーツ、人間関係といったケースとは関係なく、自尊感情が高ければ、さまざまなことに「自分はできる」と思い、反対に自尊感情が低ければ、「自分は無能だ」と感じてしまいます。
なお、「自分は勉強ができる」とか「自分は勉強が得意である」という認識を、心理学では、「有能感が高い」とか、「肯定的な有能感を形成している」と言います。
反対に、「自分は勉強ができない」とか「自分は勉強が苦手である」については、「有能感が低い」とか、「否定的な有能感を形成している」と言います。
■有能感を形成すればやる気は高まる
ここで有能感について説明してきたのは、有能感と「やる気」とは大きな関係があるからです。

「自分は勉強ができる」という肯定的な有能感を形成するとやる気が高まります。一方で「自分は勉強ができない、だから何をやっても無駄だ」という否定的な有能感を形成するとやる気が低下するのです。これはみなさんの実感ともあっているでしょう。
マイケル・ホワイトという心理学者による研究では、人間は誰でもこの肯定的な有能感を感じることによって、次なる行動に向かっていくやる気を持ち続けることがわかっています。
有能感は、やる気だけではなく、実際の行動においても良い結果をもたらす重要な要因になります。いかに、肯定的な有能感を形成することができるのかが、やる気を左右する重要なポイントであるといってもよいでしょう。
----------
筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授
1973年生まれ。筑波大学大学院博士課程心理学研究科中退。博士(心理学)。専門は、教育心理学。著書に『行動を起こし、持続する力―モチベーションの心理学』(新曜社)、『実力発揮メソッド―パフォーマンスの心理学』(講談社選書メチエ)、共著に『やさしい発達と学習』(有斐閣アルマ)、『ワードマップ ポジティブマインド』(新曜社)などがある。
----------
(筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授 外山 美樹)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「講習入れすぎは夏をムダにする」東大生断言の訳 復習する時間が足りない!効率いい勉強法は?
東洋経済オンライン / 2024年7月15日 8時0分
-
偏差値45から“超優良成績”で東大合格。親からの教え「30分以上勉強するな」が効果的だったワケ
日刊SPA! / 2024年7月14日 15時53分
-
10歳の時に父親が脳出血で倒れて要介護に、学校では「局部画像を撮られて女子にメールで送られる」壮絶イジメ…濱井正吾(33)を学歴厨にした“不幸すぎる学生時代”
文春オンライン / 2024年7月14日 11時0分
-
「本気で言うてんの? みんな働いてんねんで」5浪目に突入した息子(33)に年収180万家庭の母親が言い放った一言《地方×底辺校×貧困家庭の三重苦》
文春オンライン / 2024年7月14日 11時0分
-
中学受験「偏差値50の中高一貫校」は「地方トップ校」とほぼ同レベル…高学歴親ほど要注意"偏差値の落とし穴"
プレジデントオンライン / 2024年7月13日 9時15分
ランキング
-
1iPhoneの「ホームボタン」が消えていく深い意味 「心の支え」だった人はどうすればいいのか?
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 13時0分
-
2「離職率が低い大企業ランキング」トップ100社 単独従業員が1000人以上の会社を対象に調査
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 6時0分
-
3「日本でしか手に入らない」カレーパン、なぜ外国人観光客に人気? チーズ入りカレーパンに「私の心臓は高鳴った」【Nスタ解説】
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月15日 22時0分
-
417年ぶり消費増税、強気の「展望リポート」に3人反対=14年上半期・日銀議事録
ロイター / 2024年7月16日 9時8分
-
5中国は不動産バブル崩壊で「未完成ビル」と「売れ残り住宅」の山→政府当局が打ち出した“支援策”の裏にひそむ「重大な懸念点」【現地駐在員が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月15日 8時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください