「日本式の漫画は韓国・中国に惨敗」大ヒット『ドラゴン桜』『宇宙兄弟』のカリスマ編集者が挑む"ある試み"
プレジデントオンライン / 2021年5月16日 11時15分
■「日本の漫画」は韓国・中国に惨敗した
漫画アプリ「ピッコマ」などを展開する韓国企業カカオエンターテインメントが、ニューヨーク市場での上場を計画しています。その際の企業評価額として、同社は約2兆円を見込んでいるとのこと。
日本で漫画を手がけている大手出版社と比べると、事業規模が文字通りひとケタ違う。この一事を見るだけでも、日本の漫画は韓国、それから中国とのデジタル化・国際化競争において、完全に後れを取っているのは明らか。
僕は「日本の漫画を世界的なコンテンツにする!」という目標を掲げて2012年に起業したけれど、この10年の結果を見れば自分も含めてやはり、現時点では、韓国・中国のコンテンツ産業に「惨敗」したと言うしかありません。
そこは潔(いさぎよ)く認めて、現在は作戦を練り直して再スタートを切った、というのが現状です。
■世界標準は「縦スクロール・オールカラー」のスマホ漫画に
他のエンターテインメントと同じように、今は漫画もスマートフォンで読むのが世界の主流。紙の漫画誌やコミックが根強く残る日本の状況は、例外中の例外と言っていいでしょう。
スマホで読まれている漫画は、フォーマットも従来の日本のコミックとは違っています。スマホの仕様に合った「縦スクロール・オールカラー」の形式が開発されていて、これは「ウェブトゥーン(Webtoon)」と呼ばれている。日本以外ではたいてい世界中の誰もが、そのフォーマットで漫画、いやウェブトゥーンを読んでいます。
ウェブトゥーンと聞いてパッとイメージできない人でも、動画配信サービスNetflix(ネットフリックス)で世界的にヒットしたドラマ「梨泰院クラス」の原作漫画『六本木クラス』が連載されていたと聞けば、「ああ、あれか」となるのではないでしょうか。また最近では、漫画『女神降臨』が全世界累計40億PVを叩き出すなどしています。
まさに世界の漫画コンテンツビジネス界を席巻している存在といえます。
■圧倒的な「読みやすさ」と「スピード感」
なぜそんなに「縦スクロール・オールカラー」が受け入れられているのか。単純な話で、圧倒的に読みやすいから。スマホで最も見やすいかたちが、シンプルに追究された末に選ばれたのです。
韓国や中国のコンテンツメーカーはこの「世界標準」のフォーマットに、ケタ外れのスピードで大量に作品を投入しています。肌感覚としては、「これ!」という企画があったら、3カ月後には連載を始めている。
これまでの日本の漫画制作現場だったら、本気でいいものをつくろうと思えば、漫画家と企画を練(ね)り上げていって1~2年後にようやく1話目が上がるかな、というところなのに……。
良しあしや好き嫌いを云々(うんぬん)する以前に、ウェブトゥーンが世界標準なのは事実なのだから、僕らもそのしくみの中で面白いものをつくる努力をしたほうがいい。冷静になればそう思うのはごく自然なことなのに、僕も正直なところ、そこの考えを改めるのに時間がかかってしまった。
日本には長くて厚い漫画文化の蓄積があるのだから、時代が変われど、これまでのやり方をアップデートすれば何とかなる。そんな発想にこだわり過ぎてしまったのが原因です。
■コンテンツづくりの「しくみ」で勝負
現在は気持ちを切り替え、漫画をつくるクリエイターが集う「コルクスタジオ」の運営を核に据(す)え、時代に則したコンテンツを安定供給するしくみづくりを進めているところです。
コルクスタジオに属しているクリエイターはすでに20~30人。お互いがコミュニケーションを密にとりながら、最高のものをつくろうとしている。もちろん皆「縦スクロール・オールカラー」で作品を描いています。
これまで日本の漫画コンテンツづくりを担っていたのは出版社ですが、そこでは“メディアのしくみをどうつくるか”に主眼が置かれていました。それに対して僕らは今、“コンテンツづくりのしくみをどう築くか”にフォーカスしています。
新しいしくみを模索するのだから、クリエイターの才能の生かし方も変わってきます。これまでの漫画界は歯を食いしばって努力を重ねてほかと競争し、生き残ったヤツだけが表現活動できるといった、根性論ベースの考え方があったと思う。
これからはもっと「持続可能」なかたちを目指すべきです。仲間内でコーチングし合ったり仕事をシェアしながら、誰も取り残さずものをつくっていく。そのほうがいいものを量産できるようになるはずだし、そうなるようなしくみをつくりたいということです。
■「リアル・ドラゴン桜」スタイルで事業を展開
コルクスタジオというしくみをつくって世界に追いつこう! その方向に舵(かじ)を切るに際しては、僕の中で『ドラゴン桜』の影響が大きかったと感じています。
『ドラゴン桜』は自分にとってすごく重要な作品です。僕の人生はいつも『ドラゴン桜』とともにあるなとよく思います。
『ドラゴン桜』には、2003年に連載が始まったパート1と、2018年連載開始のパート2があり、内容やテーマ設定はかなり違っています。「1」では、落ちこぼれ生徒の水野直美と矢島勇介が野心家の弁護士・桜木建二に導かれて東大を目指し、暗記や長時間勉強でスパルタ式に鍛えられていく。
新卒で講談社に入って2年目のとき、僕は三田紀房さんとともに『ドラゴン桜』の連載をスタートさせました。当時の僕はとにかく「ヒット作を出すぞ!」と意気込んでいて、がむしゃらに頑張る以外の方法を知りませんでした。水野・矢島と同じように、たくさんのことをむりやりにでも暗記して、必死に成績アップ・実績獲得を目指していました。
作中で紹介している勉強法やスキルアップ術を仕事の現場で実践して、結果を出そうとしていたわけです。自分自身のやっていることがすでに「リアル・ドラゴン桜」でした。

■起業とつまずき
講談社で10年仕事をしたあと、僕はコルクという会社を立ち上げて社長になります。
起業してしばらくのあいだ、僕は出版社にいたころと同じように仕事をしていました。自分はこんなに努力して頑張ったぞ、みんなも同じように努力して頑張ってね、というスタンス。
会社員時代は自分を律して己に影響を与えればよかったけど、今や社員にもいい影響を与えなければいけないのだから、みずから範(はん)を示さなければ。そんな考えに凝り固まっていたのです。
それでどうしても、スタッフと齟齬(そご)が生まれることがあった。「なんでこっちの思ったように動いてもらえないんだろう……」と。立場がプレーヤーから経営者に変わったのなら、周囲への接し方も変わらないといけなかったのに、僕はそこにしばらく気づけなかったのです。
■『ドラゴン桜』に教わった時代の変化
自分が変わらなくちゃいけない、その事実を僕は『ドラゴン桜』のパート2から教わりました。
『ドラゴン桜2』では、桜木建二が「1」とは一転、「今の時代は頑張るな」と言い切ります。ガムシャラに頑張るのではなく、そうしなくても結果が出るしくみづくりに注力すべきという。
「1」では、ものを教わる生徒の側がいかに変わるかを説いていたのに対して、「2」は、教える教師の側に立った物語になっているのです。
では教師はどう変わらねばならないのか。従来の「ティーチング」ではなく「コーチング」できる存在になるべし。そして生徒たちは、コーチングの助けを借りながら自分たちで学びを促進できるようになれ! という話になっています。
経営者としての僕も、ティーチングではなくコーチングやファシリテーションに徹して、社員がみずから仮説を立てて仕事を実行し検証できる場をつくることに注力すべし。『ドラゴン桜2』が、明確にそう教えてくれました。
■一流作家の嗅覚への敬意と畏怖
新入社員のころの僕は、桜木建二から仕事に臨む姿勢やヒットを生むための考え方を学び、経営者になってからは時代に合った組織づくりや人の育て方を教えてもらった。
結局僕はいつも、『ドラゴン桜』著者の三田紀房さんに助けられているのだと改めて感じます。
それにしても三田さんは、なぜ桜木建二のやることを、これほど時代にぴたり則して変えられるのだろう。一緒に作品をつくっていても不思議でしょうがない。
これぞ一流作家に特有の、時代や世の中を見る鋭(するど)い嗅覚だ、ということになるのでしょうか。
■職人工房からコミュニティへ:「コルクスタジオ」の試み
僕が構想し実践する「コルクスタジオ」とはどういうものか。ひとことで表すとすればそれは、チームで効率よく漫画づくりをしていくための「場」です。
これも韓国や中国から学んだところですが、彼らはすでにチームで漫画をつくる体制を整えている。漫画家とアシスタントがいる「漫画家事務所」のようなかたちではなく、小さいアニメスタジオみたいな組織と環境をつくり、分業で作品をつくるようになっています。
従来の日本の漫画づくりでは基本的に、漫画家と出版社の編集者がコンビを組んでコンテンツをつくっていましたが、これからは4~5人でチームを組んで作品をつくるかたちに変えていったほうがいい。コルクスタジオではすでにそうしています。
4~5人が分業で作業を進めるというのは、たとえば原作、線画、カラー、演出、推敲、監修などに受け持ちを分けて漫画をつくっていく。そのほうが確実に完成までの時間は短縮できるし、アウトプットの量も安定します。
分業化は新人漫画家たちの成長も促します。ひとりで作品完成までのすべてをこなせるようになるには数年かかるでしょうけど、分業して特定の狭い分野のスキルをひとつずつ磨いていって、気づけば必要なことは何でもこなせるようになっていたという仕事の覚え方のほうが、明らかに短期間で成長できます。
スタジオを運営していく側からすれば、所属のクリエイターを育てているという感覚はもはやありません。こちらが育てるのではなく、漫画家たちがお互いに教え合ったり、いっしょに学んだりするコミュニティをつくるということが重要なのです。

■複数の漫画家が刺激し合い、高め合う「スタジオ」
コルクスタジオでは、お互いに学び合う環境をつくり雰囲気を醸成していたところ、ストーリーづくりの過程にまで漫画家同士のいわゆる「アクティブラーニング」が起こるようになってきました。
以前の漫画制作現場では、漫画家が原稿を描いて持ってきて、編集者がそれに対してフィードバックして磨きをかけていくという流れが普通でした。コルクスタジオは違う。漫画家同士が原稿を見せ合い、率直に議論し合うということが当たり前に起き出しているのです。
コルクスタジオのしくみのモデルとなっているのは、明らかに『ドラゴン桜』です。
パート2では早瀬菜緒や天野晃一郎ら生徒たちが、教師のフォローを受けながらも、みずから協力し合い成長していった。そうした「場」を、今度はリアルの世界で漫画家たちに築いてもらおうとしている。
「頑張らない」「しくみやテクノロジーに頼る」「仲間とともに楽しみながら目標へ向かう」といった『ドラゴン桜2』の作中で提唱してきた方法論が、コルクスタジオの中でも実践されているところです。
■「やりたい」が成長の原動力に
コルクスタジオに集っているクリエイターはどんな人たちなのか。よほど先進的な考えの持ち主ばかりかと思われそうですが、そんなことはありません。漫画に携わって生きていきたいと願う、ごく普通の考えを持ったクリエイターの卵たち。
ただし全員、みずから「ここで成長したい」と意思を示して入ってきた人ばかりなのは確かです。『ドラゴン桜2』で東大特進クラスの早瀬と天野が、自分で手を挙げて教室に入ってきた生徒だったのと同じですが、自発的かどうかというのはけっこう重要なポイントになります。
受験にしても、かつては「東大へ行くのが絶対的に正解だ」と言ってよかったかもしれないけれど、今は何が正解かは誰にも言い当てられない時代。自分の中にしっかり「want」があるのならその世界に飛び込むといい、くらいまでしか言えなくなっている。
クリエイターと関わるときも同じです。本人のやりたいことと僕らのやりたいことが重なっているとは限らず、正解や成功のイメージも違うことは大いにあり得る。そこがズレていると、一緒に組んでもお互いにとって不幸なこととなる。
だから今は、どこかで才能ある若手を見つけてきて、コルクスタジオに入るのを勧めるということは一切していません。
■「物語の力」で世界を変える
コルクスタジオを、世界最強のコンテンツ制作スタジオにしていくこと。それが今の僕が挑んでいる最大の課題です。
ウェブトゥーンの話をしましたが、コルクスタジオでは「縦スクロール・オールカラー」の漫画をどんどん手掛けています。紙のコミックではなく、売り上げは電子書籍でというスタンスです。
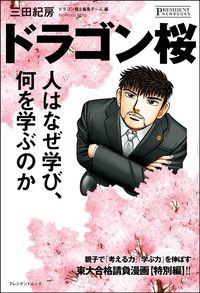
今後、このスタジオで生み出されるコンテンツは、従来の漫画という枠に収まらないものになるかもしれません。ただしどんなにかたちを変えても、それが物語の力を含んだものであることは確かです。物語の力をどう育み、広めるか。僕が焦点を合わせているのはそこに尽きます。
コルクが会社として掲げているミッションは、「物語の力で、一人一人の世界を変える」というものです。コルクスタジオをはじめ、コルクの活動のすべてはこのミッションのためにあります。
物語というと、ちょっとした暇つぶしに消費するものといったイメージかもしれませんが、そうじゃありません。これまで人の行動を変えるのはお金だったり権力だったり、有力な人からの支持だったりしたかもしれないけれど、物質的にある程度の満足を得る人が増えた今、人の行動をここからさらに変えていくのは物語の力くらいしかないと僕は思っています。
物語の力を最大限に膨らませて、世界中の人と共有する。そのための「場」として構想したコルクスタジオの活動を、どんどん加速させていきたいと思っています。
----------
編集者
2002年講談社入社。週刊モーニング編集部にて、『ドラゴン桜』(三田紀房)、『働きマン』(安野モヨコ)、『宇宙兄弟』(小山宙哉)、などの編集を担当する。2012年講談社退社後、クリエイターのエージェント会社、コルクを創業。著名作家陣とエージェント契約を結び、作品編集、著作権管理、ファンコミュニティ形成・運営などを行う。従来の出版流通の形の先にあるインターネット時代のエンターテインメントのモデル構築を目指している。
----------
(編集者 佐渡島 庸平 構成=山内宏泰)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
Webtoon制作スタジオstudio73の「マサロメリア」から第2弾!甘くて危険なオフィスラブ『暴君社長の甘い罠』先行配信開始!
PR TIMES / 2024年7月5日 11時15分
-
就労継続支援B型事業所「ラシクラボ」、新たにウェブトゥーンコースを新設
PR TIMES / 2024年7月1日 10時15分
-
Webtoon制作スタジオstudio73の少年ラブコメ新作情報解禁!異世界ハーレムで巻き起こる新感覚ファンタジー『授かり無双~子作りスキルで異世界平定』
PR TIMES / 2024年6月26日 12時40分
-
Webtoon短期研修プログラム第3弾、2024年秋ソウルで実施
PR TIMES / 2024年6月26日 10時45分
-
Webtoon制作スタジオstudio73の新作情報解禁!特殊体質ヒロイン×甲冑男子のすれ違いロマンスファンタジー『甲冑皇子の愛は不器用』
PR TIMES / 2024年6月18日 10時0分
ランキング
-
1iPhoneの「ホームボタン」が消えていく深い意味 「心の支え」だった人はどうすればいいのか?
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 13時0分
-
2「離職率が低い大企業ランキング」トップ100社 単独従業員が1000人以上の会社を対象に調査
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 6時0分
-
3中国は不動産バブル崩壊で「未完成ビル」と「売れ残り住宅」の山→政府当局が打ち出した“支援策”の裏にひそむ「重大な懸念点」【現地駐在員が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月15日 8時15分
-
417年ぶり消費増税、強気の「展望リポート」に3人反対=14年上半期・日銀議事録
ロイター / 2024年7月16日 9時8分
-
5「日本でしか手に入らない」カレーパン、なぜ外国人観光客に人気? チーズ入りカレーパンに「私の心臓は高鳴った」【Nスタ解説】
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月15日 22時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











