「フロー型からストック型に」コロナ禍でも元気な飲食店に共通すること
プレジデントオンライン / 2021年5月24日 11時15分
■コロナ前より売り上げを増やした企業の戦略とは
コロナ禍の影響をまったく受けなかったという企業は少数派だろう。とりわけ打撃が大きかったのは、休業や時短営業を求められた上に、外出自粛によりリアル顧客が激減した小売・サービス業だ。
しかし、そんな中でも売上を維持する、あるいは逆に前年よりアップする企業もある。どんな戦略をとったのだろうか。
本書では、約1500社の企業が参加する「ワクワク系マーケティング実践会」を主宰する著者が、豊富な事例をもとに、コロナ禍による顧客の“消滅”にも負けないマーケティングやビジネスの要諦を説く。
マス広告などを使って多数の「一見客」を集める「フロー型」のビジネスから、既存顧客との関係構築を重視し、継続的なコミュニケーションにより顧客を“持っておく”「ストック型」のビジネスへシフトすることが、もっとも重要なのだという。
著者は、オラクルひと・しくみ研究所代表、日本感性工学会理事、九州大学大学院非常勤講師。作家、コラムニスト、講演・セミナー講師、企業サポートの会主宰、行政や商工会議所等とのジョイントプログラム、学会などの活動を通じて、これからのビジネスとその具体的実践法を語り続けている。
2.「ファンダム」をどう作るか
3.BtoBビジネスも「ファンダム」がカギを握る
4.感性と価値で創られる市場とは
5.組織を変える、自分を変える
終.「アフターコロナ時代」に必要なもの
■コロナ禍の4月に前年比150%を達成したレストラン
「4月は前年比150%を達成しました」。あるレストランからそんな報告が入ったのは、2020年5月のことだ。その店の名前は、名古屋にあるコース料理専門の完全予約制レストラン「ことわりをはかるみせ ばんどう」(以下、「ばんどう」)。
「ばんどう」がコロナショックの影響から無縁だったわけでは、もちろんない。むしろ、元々が不要不急のニーズだっただけに、影響は甚大だった。4月に緊急事態宣言が出されると、先々まで埋まっていた予約は一気に白紙になったという。
突然、顧客が消滅してしまった中、「自分ができることは何だろう」と考えた店主の坂東俊氏は、「おいしいものを食べたいけれど外食ができないことにフラストレーションを溜めている人がいるはずだ」と思い至った。そこで、店を閉めている期間にじっくりと時間をかけて開発したのが「3000円ののり弁当」と「8000円の高級弁当」だった。
元々、フェイスブックで顧客と交流していたこともあり、その場で「究極の弁当を作ります」と宣言。その開発過程も掲載した。それを受け、顧客からは大量の応援メッセージが寄せられ、弁当の包み紙を常連の書家の先生が書いてくれることなども決定した。
そうしていよいよ発売開始となると、爆発的な注文が入った。そして、終わってみれば4月の売上は前年の1.5倍にもなっていたという。
■コロナショックを受けなかったのは常連客がいる企業・店舗
この事例で重要なのは、「顧客を持っていた」ということだ。フローのお客ではなくストックの顧客を持っていたことなのである。
フローとは「流れ」を意味し、一定期間内に流れていくもの。一方、ストックとは「貯蓄されたもの」である。これをマーケティングの世界に置き換えると、「フロー=一見客」「ストック=常連客」ということになる。
コロナショックの影響を受けなかったのは明らかに、ストックされた顧客を保持している「ストック型のビジネス」を行っていた企業や店舗であった。
フロー型のビジネスの象徴とも言えるのが、今回、大打撃を受けることになった「好立地の場所での商売」だ。人通りというフローがなるべく多いところに出店し、常に一見客が途切れないようにする。だが、フローが途切れるとあっという間に危機に陥る。
一方、「ストック型のビジネス」においては、既存顧客を徹底的に重視する。もちろん、フローも大事だが、それよりも既存顧客と継続的にコミュニケーションを取り、長く付き合っていくことを目指す。立地は必ずしも重要ではない。だから、フローがしばらく途切れてしまっても生き残ることができる。

■「生きた顧客リスト」を持っているか
コロナショックによる自粛期間中、企業の明暗を分けたのが「顧客リストの存在」だ。コロナ禍によって顧客が「消滅」し、店舗すら開けられない状態になった。多くの店が手も足も出ない状況になった。しかし、顧客リストさえあれば、手や足を出すことができた。先の「ばんどう」もフェイスブックなどを通じて顧客に発信した。
ただ、リストは、単なる名簿では意味がない。顧客リストのお客さんに対して常にいろいろな働きかけをすることで、リストを活性化させ「生きた顧客リスト」にする必要がある。これを私は「リストを温める」と呼んでいる。
まず、温める。たとえば有益な情報を定期的に提供したり、無料イベントに招待したりする。そうして仲良くなったあとに、「実はこんな商品があるのですが」とお勧めする。それによってやっと、ごく一部の人が購買行動を起こしてくれるのである。
モノを売るために関係を深めるのではなく、あくまで、まずは信用や信頼を醸成することだ。その信頼関係あってこそ、人は「買ってもいいかな」という気持ちになる。そして、その先にあるのが「ファンダム」の世界だ。
ファンダムは、「ファンコミュニティ」「会員組織」と言い換えることも可能だ。顧客消滅時代にはいかにして「ファンダム」を作り、育成していくかがあらゆる企業・店に問われる。
■企業と共創する「ファンダム」作りが重要
ファンダムの究極の姿とは、「売る側と買う側」という関係ではなく、互いに何かを創造していく仲間となっていくことだ。

愛知県蒲郡市にあるハンバーグレストラン「炭棟梁」には「炭棟梁大使」という、いわばファンクラブのような制度があるのだが、2020年には会員がついに1万人を突破した。
1万人超のファンダムを持つ「炭棟梁」では最近、真空パックのハンバーグを開発した。自宅でも炭棟梁の味を味わってほしいと思ってのことだが、自宅で手軽に調理してもらうことを考えると、どうしてもお店の味と同じものを再現することは難しかった。
そこにファン顧客の一人が、「自分がもっといい調理法を考える」と言い出した。その人は15個の真空パックハンバーグを自腹で購入し研究。その結果、店主すら驚くような家庭でできる調理法を編み出したという。今ではその調理法が公式とされ、調理工程も動画で配信、その人のアドバイスにより商品自体も微調整を行ったという。まさに一緒に創り上げていく「同志」なのだ。
「共創」という言葉がある。文字通り共に創っていくことだが、これからの時代、店と客、企業と客の関係はそういうものになっていく。
■今の顧客が求めているのは「心の豊かさ」だ
フロー型ではなくストック型に自社のビジネスをシフトしていくにあたって、必然的にすべきことがある。それは、「自分たちの提供すべき価値は何か」を明確にすることだ。
ここで勘違いしてほしくないのは、「自分たちの提供する価値とは何かを明確化すること」とは単に、「どんなモノを作るか」「どんなモノを売るか」ではない、ということだ。
今の顧客が求めているのはモノではなく「その先にある価値」であり、その本質は「心の豊かさ」だ。提供しているのはモノだとしても、その価値はそのモノを使うことによって得られる幸福感だったり、そのサービスを利用することによって生まれた時間だったりする。
また、店と顧客、関係者と顧客、顧客と顧客、関係者と関係者、それらをつなげるものは「感性」だ。
■炭棟梁の「会員だけの営業日」が教えてくれること
「炭棟梁」は昨年、店主・森下氏が「目標」としていた、会員数1万人を超えた。そこに到達したら、彼にはやってみたいことがあった。それは、会員だけを集めた、会員だけの営業日だ。その日は会員しか入店できない。
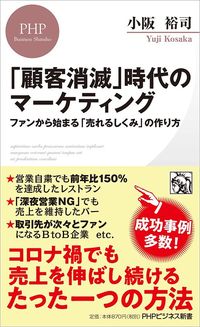
この日はチケット購入制。朝8時から発売すると、6時台から並び、チケットを死守する強者も。そうして9時前にはチケットは「SOLD OUT」。森下氏はこれがやりたくて、わざわざ本格的なコンサートチケットのような入場券を作ったとのこと。
営業が始まると、今度はこの日だけの特別な出し物が続く。ハンバーグの前説や後説、いつもは真面目なスタッフのおちゃらけたパフォーマンス、顧客内ではよく知られた著名顧客の登場、食材の生産者さんのインタビュー、新メニューのオークション、等々……。
この熱いファンたちには、会員であることの金銭的特典は一切ない。彼らは囲い込まれているわけではないのだ。彼らはここにいたいから、いる。彼らは感性でつながっている。

そうして育まれるファンダムに、この店ならではの提供価値をまた新しい形──新メニューや、顧客が思ってもみないような新サービスなど──にして投げ込んでみるとどうなるだろうか。たちまち「売れる」ことにならないだろうか。
「市場」とは、まるで元からあったもののようによく語られるが、その本質は、こういうものだ。誰かが「価値」を具現化し、世に送り出す。受け手の感性と響きあって「買う」という行動が生まれる。そこに生み出されたものが「市場」だ。そしてこれから「市場」はいっそう、感性のつながりの中、生み出されていくのである。
■コメントby SERENDIP
『ファンダム・レボリューション』(早川書房)という書籍には、ウィスキーメーカーのメイカーズマークが、同社のファンダムである「アンバサダー」に、同社のウィスキーの配合変更を伝えたところ、ネット上で“炎上”騒ぎになった例が紹介されている。
ファンダムには諸刃の剣の面があり、コミュニケーションの齟齬や、ファンの「感性」に合わないことを企業側がすることで、激しい反発を受けることがある。それを避けるには、企業側がファンの感性を深く理解しようと努め、コミュニケーションを密にしてファンとの仲間意識を育む必要がある。
先のメイカーズマークの一件では、配合変更を一方的に伝えるのではなく、ファンダムと親密な事前相談の機会を設けるべきだったのかもしれない。ファンダムとの関係性づくりに、通常のマーケティングよりも幅広く諸学問の知見を学際的に取り入れた戦略が必要になるのは間違いないだろう。
----------
----------
(書籍ダイジェストサービス「SERENDIP」)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
ドタキャン連発で店が潰れる…飲食店主が「来店しない予約客」に科した"キャンセル料金"の是非
プレジデントオンライン / 2024年7月14日 10時15分
-
洋菓子店の倒産件数が過去最多ペース…スイーツ人気は衰えないのに"日本人の洋菓子店離れ"が進んだ理由
プレジデントオンライン / 2024年7月12日 8時15分
-
「なぜか解約できない…」行動経済学の専門家がサブスクを継続してしまう巧妙な仕掛けを明かす
Finasee / 2024年7月9日 13時0分
-
JRE BANK誕生早々に申し込み殺到…特典大判振る舞いの「Suica経済圏」がトップに躍り出る日はくるか
プレジデントオンライン / 2024年7月2日 9時15分
-
フロンガスは「待望の発明」から「オゾン層を破壊する悪者」に転落…失敗したイノベーション「3パターン」
プレジデントオンライン / 2024年6月20日 9時15分
ランキング
-
1CoCo壱「わずか3年で3回目の値上げ」は吉と出るか 過去の値上げでは「客離れ」は見られないが…
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 17時30分
-
2旅客機用の燃料不足で緊急対策 輸送船を増強、運転手確保へ
共同通信 / 2024年7月16日 23時42分
-
3「日本でしか手に入らない」カレーパン、なぜ外国人観光客に人気? チーズ入りカレーパンに「私の心臓は高鳴った」【Nスタ解説】
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月15日 22時0分
-
4iPhoneの「ホームボタン」が消えていく深い意味 「心の支え」だった人はどうすればいいのか?
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 13時0分
-
5中国は不動産バブル崩壊で「未完成ビル」と「売れ残り住宅」の山→政府当局が打ち出した“支援策”の裏にひそむ「重大な懸念点」【現地駐在員が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月15日 8時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











