ネット動画だと早送りするのに、なぜテレビだとダラダラ見てしまうのか
プレジデントオンライン / 2021年5月23日 11時15分
※本稿は、本橋亜土『ありふれた言葉が武器になる 伝え方の法則』(かんき出版)の一部を再編集したものです。
■スキルの違いが尺の違いに直結している
ユーチューブ、好きですか?
多くの人が「YES」と答えますよね。
最近は、「これからはユーチューブの時代で、テレビはオワコン」なんて言われたりするわけで、テレビ業界関係者の1人として、複雑な気持ちもあります。
と言いつつ、私自身、ユーチューブがけっこう好きです。次から次へとおすすめ動画が上がってくるので、つい時間を忘れてスマホを見てしまいます。
では、もう1つ質問します。
ユーチューブ動画とテレビ番組、尺が長いのはどっち?
ユーチューブの動画って、比較的短いものが多いですよね。短いもので数十秒、長いものでも30分くらいといったところです。
それに比べて、テレビ番組は30分、1時間、2時間と圧倒的に長尺です。
この違いはどこからくるのでしょうか?
個人が限られた時間で編集をしているから、そもそも長い動画を作れないという事情もあると思いますが、それ以外にもう1つ圧倒的な違いがあります。
それは、
「構成」と「演出」があるか否か
です。
ここで言う「構成」とは、物事を伝えるための構造のこと。そして「演出」とは、物事をより魅力的に見せるためのテクニックです。
この2つの有無、もしくはスキルの違いが、両者の尺の違いに直結しているのです。
■「チャンネルを替えられない」と思わせる仕組み
一体どういうことなのか?
ここからは、番組の制作現場で実際に使われている「構成」と「演出」のテクニックを例に挙げながら、その秘密を解説していきましょう。
これからお伝えするのは、番組を作るうえで最も重要かつ多用されているテクニックです。
まずは、次の2つの文章を見てください。
まったく同じことを言っている、使っている単語もほぼ同じAとB。
しかし、ある要素を入れることで、Bのほうがより強く印象に残る文章になります。
A 社長は、「社員全員の給料を10%アップさせる決断をしたため、会社が大きな成長を遂げた!
B 会社が大きな成長を遂げるきっかけとなった、社長の決断。
それは!
「社員全員の給料10%アップ」
Bは、Aの文章に、テレビ番組でよく使われている、「振り」と「受け」という基本構造を入れたものです。Aに比べて、Bのほうがイキイキとした印象が生まれ、「給料10%アップ」がより強調されていますよね。
この「振り」と「受け」は、番組を構成するうえでとても大事な要素です。これがあるために、「チャンネルを替えられない」「次が気になる!」というテレビ特有の構成を組み立てることができるといっても過言ではありません。
■「振り」と「受け」で印象を強める
「振り」と「受け」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?
先ほどの例文を「振り」と「受け」に分割すると、次のようになります。
会社が大きな成長を遂げるきっかけとなった、社長の決断。
それは!
【受け】
「社員全員の給料10%アップ」
この文章で強調したいのは、「社員全員の給料10%アップ」という部分です。
「受け」の部分には文章の中で最も強調したい言葉を配置します。
その前の「振り」とは、「受け」を説明する言葉と、「振りワード(例文では、それは!)」をセットにした部分のことを言います。
強調したい言葉の直前に、説明と「それは!」や「そこで!」の振りワードを配置する。これが、「振り」と「受け」の構造です。
ちなみに、代表的な振りワードには、「それが!」「それは!」「そこで!」「そして!」「さらに!」などがあります。
この「振りワード」、全て馴染みのある、ありふれた言葉ですよね?
実は、そこがポイントなんです。多くの人は、自然にテレビ番組の“見方”を習得していますから、「それが!」「それは!」などの振りワードがくると、
あ、この直後に大切なポイントがくるんだ!
と無意識に認識し、意識をテレビに集中させます。
■ユーチューブ動画の尺が短い理由
たとえば、皿洗いをしながらテレビを観ていたとしても、画面から「それは!」という振りワードが流れてきた瞬間に、手を止めてテレビに注目します。
スマホをいじっていても、「それが!」というナレーションが流れてくると、手を止めてテレビ画面を観ます。
そしてテレビから、ディレクターが最も伝えたい重要な「受け」のコメントが流れてくると、「なるほどね」と納得し、また皿洗いやスマホに戻るわけです。
実は、テレビ番組は、「振り」を使って「ここ大事だよ!」とサインを出して画面に惹きつけ、「受け」た後で休憩させ、また「振り」で惹きつける……。
このパターンを繰り返しているのです。
適度に休憩させながら、大事なところはしっかり惹きつける。これによって視聴者は自分の頭を使わなくても番組の内容を把握することができます。
ここで、先ほど述べた、ユーチューブ動画の尺が短い理由を説明しましょう。
ユーチューブ動画は、長く観続けることが苦痛だからです。
■伝え方の神髄は「聞く気のない相手を聞く気にさせる」
ユーチューブの動画は、長く観ていると疲れますよね。それに比べて、テレビ番組は疲れずにずっと観られる感じがしませんか?
その大きな理由の1つに、「振り」と「受け」の有無の違いがあるのです。

ユーチューブにアップされた動画の多くは、この構造がないため、メリハリがありません。そのため、ずっと注視していなければ、話の流れをつかめないうえ、大切な部分を見逃してしまいます。
大事なポイントを視聴者自身が考えながら見つけなければいけない(=気が抜けない)。だから、長時間観ていると疲れてしまうのです。
このような経験から、無意識のうちに短めの動画が選ばれるようになり、結果的に動画の尺が短くなったと考えられるわけです。
相手に情報をしっかりと伝え、さらにしっかりと心に残すためには、「鉄則」があります。それは、
相手を疲れさせないこと。
相手に頭を使わせないこと。
たとえば、営業先のお客様や就活の面接官、また、夫や妻にいろいろな話・交渉ごとをする場面でも、「話を聞く側」というのは、私たち(話す側)が思っているほど熱量が高くありません。残念ながら、
相手は、あなたが思っている以上にあなたの話を聞きたいと思っていない。
これが現実です。
逆に考えれば、「聞く気のない相手を聞く気にさせる」ことこそが、伝え方の真髄であると言えます。
当たり前ですが、相手なしにコミュニケーションは成立しません。
同じ話でも、相手の機嫌や体調、そのときの忙しさなど、コンディションの良し悪しで受ける印象が大きく変わってきます。
つまり、情報の伝わり方は相手のコンディションに左右されるということです。
■「考える行為」は話を聞く気を失わせる
もちろん、相手のコンディションの良いタイミングを見計らってプレゼンに行くなど不可能。
であれば、「こちらから良いコンディションにさせてあげる」ことが最良の道ということになります。
その際、けっして相手に感じさせてはいけないのが、「要するに何が言いたいの?」という疑問感情です。
疑問に思う、つまり「考える行為」は非常に労力を使います。そこに労力を使わせてしまった時点でこちらの負け。そもそも聞きたいと思っていないわけですから、そこに余計な労力をかけてくれる人なんていません。余計なことを考えさせることで集中力が途切れ、さらに話を聞く気がなくなってしまうのです。
これは非常にもったいない。どうせなら、相手を「前のめり」にさせた後、こちらの話の核心に迫る「ここぞ!」というところで労力を使わせたいものです。
だからこそ、
相手を疲れさせないこと。
相手に頭を使わせないこと。
が必要になってくるのです。
「伝わりやすい構成・演出」とは、その構造が相手にとって、無理なく受け入れられる組み立てになっているということです。
事実、伝わりやすいよう構成されたテレビ番組は、ストレスなく、誰でも簡単に内容を理解することができます。そして、「面白くてあっという間に終わってしまった」「来週もまた見たいな」という印象を視聴者に与え、人気番組としての地位を確立するわけです。
■テレビには視聴者を疲れさせない仕組みがある
逆に、視聴者を疲れさせてしまったり、内容がわかりにくかったりするとすぐにチャンネルを替えられてしまいます。
そしてそれは、「視聴率の低下→番組終了→ディレクターの収入激減」という最悪の結果を招きます。そのため、各番組のディレクターたちは、生活をかけて、チャンネルをステイさせる努力をしています。その真髄こそ、
視聴者を疲れさせずに情報を伝える
ことなのです。これについては、ここまで繰り返し述べてきたので、ご理解いただけたと思います。実は、相手を疲れさせずに情報を伝えるために、とても大切なことがあります。それは、
ありふれた言葉・表現を使う。
たとえば、あなたのまわりにこんなことを言う人はいませんか?
①プライオリティをつけてから、ディスカッションしたほうがいいよね!
②ナレッジの共有がベストプラクティスにつながります。
こんなカタカナ語を多用する人、最近増えていますよね。
デキる自分を演出したいのかもしれませんが、「いかにうまく伝えるか」という視点で見ると0点であると言わざるを得ません。
■「型」さえ覚えてしまえば誰もが伝わりやすい話ができる
先ほど、「それは!」「そして!」などの振りワードは、聞き慣れた言葉だから効果があるとお伝えしました。
振りワードに限らず、聞き慣れない言葉が出てくると、頭の中に「?」が浮かびます。こうなってしまった瞬間、相手の話を聞こうとする気持ちは萎えてしまうのです。
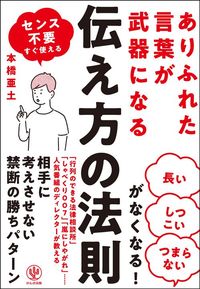
自分の意見を本当に聞いてほしいなら、こう表現すべきです。
①優先順位をつけてから、話し合ったほうがいいよね!
②知識の共有が最も効率のいい方法です。
これならよくわかりますよね。
このように、普段の会話で使う言葉や表現は、誰もが理解できる「ありふれたもの」を使うことも、物事を伝えるうえでは非常に大事なのです。
逆に言えば、語彙力を高めるために勉強したり、言葉のセンスを磨いたりしなくても、「型」さえ覚えてしまえば誰もが活用できるということです。
----------
スピンホイスト代表
1978年生まれ。大学卒業後、バラエティー番組専門の制作会社を経て、ドキュメンタリーを制作するフォーティーズに入社。同社代表で、日本ドキュメンタリー界の巨匠である東正紀氏に師事する。その後、複数の制作会社でディレクターとして『王様のブランチ』(TBS)、『行列のできる法律相談所』『嵐にしやがれ』『しゃべくり007』(全て日本テレビ)など、人気情報・バラエティー番組を制作する。その後、プロデューサーを経て2017年に独立し、スピンホイストを設立。『ニンゲン観察バラエティモニタリング』『バース・デイ』(ともにTBS)、『それって!? 実際どうなの課』(中京テレビ)などのレギュラー番組を制作。
----------
(スピンホイスト代表 本橋 亜土)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
会話で大事なのは「テンポ」…相手との距離を深められる人とそうでない人の決定的な差
集英社オンライン / 2024年7月13日 8時0分
-
「とっておきを1つ」話すよりも「3つ」用意して伝える…相手との距離感が縮まる話し方のコツ
集英社オンライン / 2024年7月12日 8時0分
-
「子どもから信頼される親」がしている話の聞き方 能動的な聞き方ならば子どもは心を開きやすい
東洋経済オンライン / 2024年7月11日 16時0分
-
モテる男性は話し方が違う! モテる男性の口癖6つ
KOIGAKU / 2024年7月3日 18時3分
-
誰もが無意識に使いがちだが…実は人間関係にヒビが入りかねない「要注意ワード」【人気エッセイストが助言】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月30日 10時0分
ランキング
-
1旅客機用の燃料不足で緊急対策 輸送船を増強、運転手確保へ
共同通信 / 2024年7月16日 23時42分
-
2CoCo壱「わずか3年で3回目の値上げ」は吉と出るか 過去の値上げでは「客離れ」は見られないが…
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 17時30分
-
3「日本でしか手に入らない」カレーパン、なぜ外国人観光客に人気? チーズ入りカレーパンに「私の心臓は高鳴った」【Nスタ解説】
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月15日 22時0分
-
4中国は不動産バブル崩壊で「未完成ビル」と「売れ残り住宅」の山→政府当局が打ち出した“支援策”の裏にひそむ「重大な懸念点」【現地駐在員が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月15日 8時15分
-
5iPhoneの「ホームボタン」が消えていく深い意味 「心の支え」だった人はどうすればいいのか?
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 13時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











