齋藤孝「テレビから消える芸人と生き残る芸人の違いは『本当の頭のよさ』にある」
プレジデントオンライン / 2021年6月14日 11時15分
※本稿は、齋藤孝『本当に頭がいい人の思考習慣100』(宝島社)の一部を再編集したものです。
■今求められている「頭のよさ」とは何か
時代が求める「頭がいい人」とは、どのような人でしょうか。まず前提として、世の中の価値観は時代とともに大きく変化していますから、その変化に対応できる力が求められます。時代が自分に求めているものは何なのか、何ができるのか。それを考える思考力をもっている人、そういう人を「頭がいい」と世の中は評価します。
お笑い芸人のみなさんはしゃべりのプロですから、たとえばプライベートな時間でお酒を一緒に飲んでいても、場を盛り上げることが得意です。私たちには真似ができません。
しかし、競争が激しい世界ですから、業界で生き残れる人たちはごくわずか。その成功者たちに通じる共通点は、制作スタッフが自分に何を求めているかが理解できているということです。
■質問に40秒かけて答えたらすべてカットされた
たとえば、トークを時間軸で捉えながら、10秒や15秒という枠の中で、言いたいことをズバリと言い尽くすことです。
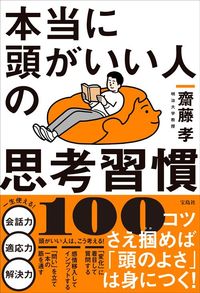
話をスタートする前に、15秒後の着地点を意識し、そこから逆算して要点をまとめ、最後にクスッと笑えるオチまでつけて話ができる人。すべてとはいいませんが、テレビの世界で残っている芸人さんの多くは、こういうタイプの人ではないかと思います。
そういう意味では、実は私も、過去にテレビで大失敗をしたことがあります。まだテレビという世界に慣れていない頃、ある番組で司会者から話をふられ、それに対し知っていることを私なりに答えたのです。
自分としては、そつなく話せたかなと思っていたのですが、あとで知ったところでは、それがすべて編集でカットされていました。理由は、私の話が長すぎたのです。ひとつの質問に対して40秒ほどかけていたため、間延びして番組が構成できなかったようです。
これはつまり、私が制作サイドの意図を正しく把握できていなかったということになるわけです。言い換えれば、相手の気持ちがわからなかった、求められているものを正しく理解できていなかったということになり、大いに反省したことを今も覚えています。
■場面に応じて求められるものは違ってくる
今紹介した例は「テレビ的な頭のよさ」ということになりますが、これがラジオであれば、時間枠は15秒よりはもっと長くなるでしょう。
さらに、大学の授業や講演会で、学生や聴衆の前で話すとなると、時間の捉え方はまた大きく変わってきます。中身のある話を100分間話し続けるのは、15秒の世界とは異なる力が求められます。
つまりは、その場その場で求められることが違うということ、それを私たちは理解しなければなりません。陸上競技であれば、短距離走者とマラソンランナーに求められるものは同じではありません。
ここで今、自分に求められているものが何なのか、それがズレずに判断できる。もし自分ができそうもないということであれば、「これは私の担当ではないな」と気づくこと。自分がすばらしいと思っているものでも、別のすべての場で通用するわけではないということがわかる人。こういう人は頭がいいといわれる人の中に多いのです。
■レジェンドですら時代に適応しようともがいている
私たちは新たなものにチャレンジして、自分を向上させていくことが必要です。マンネリ化せずに、いろいろなことを実践しながら、己の知を新鮮に保つこと。時代の要求に応えていくということです。それは一時代を築いた人も同様です。
棋界のレジェンド・羽生善治さんは、数年前に「竜王」の座を追われて以来、タイトル戦の舞台から遠ざかっていました。その期間、羽生さんが語った言葉はあまりに印象的です。10代の藤井聡太さんの将棋を「学びたい」と言ったのです。
AIの進化で戦術が大きく様変わりした今の棋界で、羽生さんはそのAIに強い関心をもち、「過去にこのやり方で勝てたという経験にあまり意味はない。最先端の感覚を取り入れなければ生き残れない」と説いています。
史上初の永世七冠にして棋界のレジェンドと呼ばれる羽生さんでも、今の時代に適応しようとしている。この柔軟性こそが、頭がいい人の特徴です。
環境が変わってきたときにどう行動できるのか、環境が変わっても「こうすればいい」「ああすればいい」と行動ができる。この問題解決能力は非常に大事なことなのです。
■頭をよくするために実践すべきこととは何か
「あなたは今、何を意識してその作業をしているのか」と聞かれて、瞬時に答えられる人は「頭がいい人」です。ピアノの練習中にそう聞かれたとき、「このパートをスムーズに弾けるように左手の薬指を意識しています」とすぐに答えを返すことができる人は、常に課題をもちながら練習している人であり、頭の中も整理されている人です。
スポーツにおいても、たとえばゴルフのスイングを練習している人が、何も考えずに1000回振っても、筋力はつきますが上達はしません。一方、「上半身は腕とクラブを同調させるように意識して振っている」人は、ひと振りひと振りに意味をもたせています。
上達は練習の「質×量」で決まりますから、質がゼロなら答えも限りなくゼロに近くなりますし、後者のように意味をもたせた練習を1000回すれば、必ずショットは上達することでしょう。要は、自分のやるべきことを鮮明にしておくということです。
■自分で課題を掲げて練習方法を組み立てる
長野冬季オリンピックで金メダルを獲得した元スピードスケート選手・清水宏保さんとお会いしたことがあるのですが、清水さんは小学生の頃から、腸腰筋という、お腹のインナーマッスルを強化する練習を徹底して行ったのだそうです。今ではスポーツ科学で大変に注目されている腸腰筋ですが、当時小学生だった少年がそこに焦点を当ててトレーニングをすることが、どれほどすごいか。課題を掲げて練習方法を組み立て、それを実践できる人こそが、頭がいいアスリートだといえるでしょう。
自分で組み立てることが難しければ、組み立てられるコーチを雇うという方法もあります。自分1人ではできないけれど、できない現実を受け入れて、他者から助けてもらう。コーチを雇う経済的余裕がないのであれば、チームメートや先輩のアドバイスでもいいでしょう。要は誰とバディ(相棒)を組むのかです。

■情報に優先順位をつける力
価値観が多様化する時代に生きる私たちは、目の前に並ぶたくさんの事項に対して、優先順位をつける力を求められています。これができるのは、頭がいい人の特徴です。世の中はうまくいくことばかりではありません。仕事に就いて何か大きなミスをしたり、トラブルに巻き込まれたりしたときは、それを隠したり、そこから逃げたりせず、まずは早めに誰かに相談をするということ。それがその場面での優先順位一位です。
自分より経験値の高い人からの知見を得ることで、危機から回避できる、あるいは損害を最小限で抑え込むことができる可能性が高まります。
厳密な意味において、社会を1人で生きている人はいません。「チーム」という概念で選択肢に優先順位をつける力は、今の時代にとても必要とされていることだといえます。
■変化のスピードが速い社会だからこそ自分の時間を持つ
世の中の変化のスピードがどんどん速くなっている中で、このスピード感への対応ということも、今の時代の大きな特徴といえます。
とはいえ、表層的な時間という川の流れがいくら速くなろうとも、地下水のようなゆったりした自分の時間を確保することは、これからの時代にこそ必要といえます。
分刻みでスケジュールを組んで仕事をしたり、家事に追われたりするのが「表流水」であるとしたら、読書の時間は「湧水」もしくは「地下水」と考えられます。この2つをもつことで知のバランスがとれるのです。『論語』という2500年ほど前の孔子の言葉をかみしめる時間は、誰にも強制されないゆったりした自分の時間です。こうした「知の湧き水」が、私たちの知を枯渇させない源泉となるのです。表面の現代社会に対応しつつも、もうひとつの時間をどうもてるか。それが今を生きる大きなヒントといえるでしょう。
■頭がいい人は睡眠の大切さを正しく理解している
また、そうした時の流れの速さに押され、足を引っ張る最たるもののひとつが、睡眠不足です。「何を当たり前のことを」と思うかもしれませんが、睡眠は多くの人が考えているよりはるかに重要です。
自分の生活リズムに合わせて十分な睡眠を確保できれば、頭がすっきりと冴え、身体も健康に保てます。健康を保てているから、頭もスムーズに回転するのです。
仕事でもスポーツでも、豊かで実りのある時間を過ごしている人は、睡眠の大切さを理解している人です。睡眠の質でホルモンの分泌も変化し、それが身体のリズムに影響を及ぼすことを知っている人です。すべての人の平等に与えられている時間をどう工夫し、寝る時間をどう確保するのか。その「知の環境づくり」が、今後の私たちの暮らしに大きく影響してくることは間違いないでしょう。
----------
明治大学文学部教授
1960年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業後、同大大学院教育学研究科博士課程等を経て、現職。専門は教育学、身体論、コミュニケーション論。ベストセラー作家、文化人として多くのメディアに登場。著書に『ネット断ち』(青春新書インテリジェンス)、『声に出して読みたい日本語』(草思社)、『語彙力こそが教養である』(KADOKAWA)『新しい学力』(岩波新書)『日本語力と英語力』(中公新書ラクレ)『からだを揺さぶる英語入門』(角川書店)等がある。著書発行部数は1000万部を超える。NHK Eテレ「にほんごであそぼ」総合指導を務める。
----------
(明治大学文学部教授 齋藤 孝)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
『秘密のケンミンSHOW』で圧倒的に登場回数が多い都道府県は?北海道でも、沖縄県でもない、納得のワケ【齋藤孝が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月27日 8時0分
-
「タイパ」重視の〈現代人〉が見落としている「無駄な時間」が、何十年ともたらす<永続的なメリット>とは【明治大学文学部教授・齋藤孝が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月26日 8時0分
-
文豪・夏目漱石が「子どもが読むものではない」と、小学生読者にレスをした『坊っちゃん』『吾輩は猫である』ではない名作とは【明治大学文学部教授・齋藤孝が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月24日 8時0分
-
会話で大事なのは「テンポ」…相手との距離を深められる人とそうでない人の決定的な差
集英社オンライン / 2024年7月13日 8時0分
-
「休日は何をしているんですか?」にバカ正直に答えてはいけない…センスのいい人が自然とやっている返し方
プレジデントオンライン / 2024年7月7日 8時15分
ランキング
-
1「子どもが野菜を食べてくれない」悩みへの回答 科学的に正しい「野菜嫌いをなくす5つの方法」
東洋経済オンライン / 2024年7月27日 15時0分
-
2G20、「デジタル課税」早期実現への決意示す…3会合ぶりに共同声明採択し閉幕
読売新聞 / 2024年7月27日 15時0分
-
3スズキ、コンパクトSUV「フロンクス」の最新情報を公開
財経新聞 / 2024年7月27日 16時36分
-
4〈最低賃金1054円に〉過去最大増なのにパート、アルバイトから大ブーイングのワケ「扶養控除ライン据え置きはオフサイドトラップ」「政治家の報酬だけは世界トップクラスだけど、賃金はオーストラリアの半分」
集英社オンライン / 2024年7月26日 18時56分
-
5「半端な対策では命にかかわる」 山善の”プレミアム水冷服”がたちまち完売、現場のニーズとどう合致した?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月27日 6時20分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











