桜井章一「神社で願かけをする人」がいつまでたっても強運に恵まれないワケ
プレジデントオンライン / 2021年6月27日 9時15分
※本稿は、桜井章一『運に選ばれる生き方』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
■運に選ばれる人の条件
「ツイてたな」
長い人生、誰しもそう感じる経験はあるだろう。小さなものから大きなものまで、実は、運はそこらじゅうに漂(ただよ)っているものであり、その恵みに触れることのない人生はない。
それにしても「運」や「ツキ」とはいったい何なのか? 運について想いを巡らすとき、あなたは不思議な気持ちにならないだろうか。
見ることができなければ、手で触れることもできないもの。どこからかやって来て、また気まぐれにどこかへ去って行ってしまう。どこまで掘り下げても、運はその「正体」を見せてはくれない。
■真剣勝負の舞台が生んだ「無敗の雀鬼」
私はかつて麻雀の裏プロの世界で20年間、真剣勝負を重ね、「無敗の雀鬼」という異名で周囲から呼ばれたことがあった。
私にとって、もはや過去のことであり、誇ることでもまったくないのだが、このときの経験が大きな影響を与え、今の私をつくったことは確かである。
「20年間無敗」と聞き及んだ人から、「なぜ運が影響するゲームで勝ち続けることができたんですか?」とよく尋ねられる。麻雀においては、ご存じの通り、「運」や「ツキ」といったものが勝負の流れを大きく支配する。「運は偶然の産物だったりするはずなのに、なぜ?」という疑問である。
だが、私は「運は偶然ではない」と考えている。しかるべき行動を取れば、運の流れというのは必然的にやって来ると思っているからだ。そのことを私は、幾度も幾度も繰り返された麻雀の真剣勝負から教えてもらった気がする。
■人が運をつかむのでなく、運が人を選んで訪れる
一度、これは凄(すご)い打ち手だなという人物と対局したことがある。「流れ」をとらえる感覚とスピード、一分の隙もない美しい所作(しょさ)、勝負に対する姿勢……いずれをとっても超一級の腕の持ち主であることは最初の一打ですぐにわかった。
水につけていた顔を洗面器から先に上げたほうが負けというような緊迫した勝負が夜を何日かまたいで続いた。最後の勝負所という局面、相手にほんの一瞬、隙が生まれ、流れが微妙に変化した。誰も気づかないような、一打のわずかな波紋である。
その微(かす)かな綻(ほころ)びを私は感じ取った。そして新たな流れをつかんだことで辛うじて勝つことができた。実力や人智を超えたところにある、ほんのわずかな違いであった。
いい流れを感じ取ってその流れに乗る。これもまた、運に恵まれるうえでは欠かせない作法のひとつである。
ものごとを正しくとらえ、正しい行動を正しいタイミングで取る。遊び心を持ちながらも自分をどこかで律する。日々のそうした積み重ねがあるかないかによって、運に好かれるかどうかも変わってくる。
運は必然の流れによってもたらされるものであり、しかるべき行動ができている人を運の側が「選ぶ」のだと思う。運は、人が呼んでやって来るようなものでは一切なく、あくまで運のほうが人を選ぶのだ。
「運に選ばれる人」になる──。これが重要なのだ。
■他力本願ではモノにできない…
「運をつかむ」「運がやって来る」といういい方をすると、運というものがあたかも実体があるかのようにも感じられる。
しかし、実際は天から降ってくるものでも、地面から湧いてくるものでもない。もちろん、そんなことはわかりきっているが、それでも何か漠然とおぼろげな形をした運が、どこかに潜(ひそ)んでいるかのような感覚を抱いている人は少なくないだろう。
歩いていたらたまたま出くわすラッキーなこと。それが運に対してしばしば持たれるイメージだ。
ただ、運は受け身でとらえている限り、そう簡単にやって来るものではない。他力本願な生き方でモノにできるほど、運は都合よくできていない。
「運よ、来い」「ツキよ、来い」と求め、願うような姿勢では運と巡り合うことはできないのだ。
■神社で「願かけ」をする人の根本的勘違い
運を先に求めるのではなく、「結果として運に選ばれる」という感覚こそ重要だ。そのためには、常日頃、運に選ばれるように準備をしておく必要がある。
「あの人は運がいいな」とまわりから思われている人がいるだろう。そういう人はよく観察すると、運に選ばれる方法をごく自然に実践しているものだ。普段の生活や仕事の中に、運やツキをもたらす“素材”をたくさん持っているのだ。
素材といっても、特段難しいものではない。運に選ばれるような努力や工夫が、運をもたらす素材であるからだ。
運やツキに恵まれていない人ほど、神社などで「どうか、いいことがありますように」などと願をかけたりする。しかし、漠然と運を願うだけでは、運はその人のところにやって来ない。
私も毎年初詣に行くが、神様に願いごとをするようなことはない。神殿に向かって手を合わせながら思っているのは、「1年、また無事に生きることができました。ありがとうございました」ということだけだ。今ここに居ることへの感謝の気持ちを、ただ捧げる。
運を当てにせず、運に選ばれるような努力と工夫を日々重ねていく。それが、運に恵まれるうえでもっとも大切なことだ。
■「これからやります」はダメな人の共通点
「仕事がデキる人」と、何をやっても結果が出ない「ダメな人」。このふたつを分けるものがあるとすれば、それはいったい何なのか。

麻雀を通してあらゆる世界の人間を見てきた。「ダメな人」を見ていて感じるのは、「これからやります」という姿勢の人が多い、ということだ。
すべてが「これからやります」の状態というのは、要は仕事が遅いということ。丁寧で遅いのならいいが、そうではなく、段取りをちゃんとつけないまま仕事を進めたりするため、無駄やミスが多い。
反対に、「デキる人」は段取りもよく、準備もぬかりなく進めているため遅れることがない。つまり、常に「間に合った」仕事をしているのである。「間に合う人」は運に恵まれ、間に合わない人は「間抜け」となる。
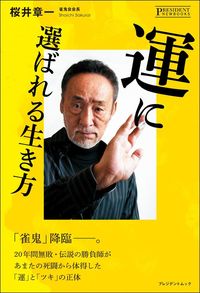
私は、日頃から麻雀に限らずなにごとも「準備・実行・後始末」が大事だといっている。「デキる人」は、この「準備・実行・後始末」が常にちゃんとできている。
準備をきちんと整えたうえで実行をし、その後の始末もしっかり行う。後始末もぬかりなくすれば、それが次の準備へとつながっていく。「準備・実行・後始末」は、円のように循環しているのだ。
「ダメな人」は、準備がおろそかで、そのため実行に問題が生じ、おまけに後始末もしないので次につながっていかないというパターンに陥(おちい)っていることが多い。
■すぐ済ませば心が研ぎ澄まされる
「デキる人」は、ちょっとした雑事もその場でさっと「済ませる」感覚を持っている。仕事をしていると雑事がところどころで入ってくるものだ。でも、それを後回しにするのではなく、その場、その場で動き、済ませていく。
「デキる人」は常に準備ができている状態にあるので、ちょっとした用事であればすぐに対応して済ますことができる。
済ますことができれば、心に余計なものがない「澄んだ状態」になる。心が澄むと、五感が研ぎ澄まされ、運の流れに気づけるようになる。心を澄ますということは、運に選ばれるために欠かせない条件のひとつなのだ。
----------
雀鬼会会長
1943年東京・下北沢生まれ。大学時代に麻雀を始め、裏プロとしてデビュー。以後、圧倒的な強さで勝ち続け、20年間無敗の「雀鬼」の異名をとる。現役引退後は、「雀鬼流漢道麻雀道場 牌の音」を開き、麻雀を通して人としての道を後進に指導する「雀鬼会」を始める。モデルになった映画や漫画も多く、講演会などでその雀鬼流哲学を語る機会も多い。著書に『負けない技術』『流れをつかむ技術』『運を支配する』『感情を整える』『群れない生き方』など多数。
----------
(雀鬼会会長 桜井 章一)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「精密機械」荒正義72歳「ツキを引き寄せるために何十年も苦労して戦ってきた」「運の強弱を見分けられずに麻雀を語るなかれ」【後編】
東スポWEB / 2024年7月14日 10時4分
-
#プライムデーで3ヵ月無料! Kindle Unlimitedで読める「麻雀放浪記」「スーパーヅガン」などおすすめ【傑作・麻雀漫画】
ASCII.jp / 2024年7月11日 20時0分
-
「ラヴィット!」大物ゲストサプライズ登場にトレンド入りの反響 ビリビリ椅子の餌食に「貴重映像すぎる」「朝から豪華」と反響
モデルプレス / 2024年7月10日 11時19分
-
手役アーティスト森山茂和「今の新人は100半荘さえ打たないらしい。強くなれるはずない」【後編】
東スポWEB / 2024年6月30日 10時14分
-
“手役アーティスト”森山茂和72歳「AIにできない味のある切り方ができてこそプロ雀士」【前編】
東スポWEB / 2024年6月23日 10時41分
ランキング
-
1iPhoneの「ホームボタン」が消えていく深い意味 「心の支え」だった人はどうすればいいのか?
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 13時0分
-
2CoCo壱「わずか3年で3回目の値上げ」は吉と出るか 過去の値上げでは「客離れ」は見られないが…
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 17時30分
-
3「離職率が低い大企業ランキング」トップ100社 単独従業員が1000人以上の会社を対象に調査
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 6時0分
-
4「日本でしか手に入らない」カレーパン、なぜ外国人観光客に人気? チーズ入りカレーパンに「私の心臓は高鳴った」【Nスタ解説】
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月15日 22時0分
-
517年ぶり消費増税、強気の「展望リポート」に3人反対=14年上半期・日銀議事録
ロイター / 2024年7月16日 9時8分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











