この2年がラストチャンス「金融緩和終わりの始まり」に有望な投資対象
プレジデントオンライン / 2021年6月26日 11時15分
2020年3月3日、臨時の米連邦公開市場委員会(FOMC)で政策金利を0.5%引き下げるというサプライズ発表後、米国連邦準備制度理事会(FRB)のジェローム・パウエル議長はワシントンで記者会見を行った - 写真=AFP/時事通信フォト
■価格高騰からのコモディティ急落はなぜ起きたか
ごく最近まで、新聞やテレビなどでもコモディティ価格の高騰が取り上げられ、インフレ懸念を想起させるような取り扱いだった。ところがここにきて、主要なコモディティが急落している。
インフレに強いとされる金相場は高値から大きく値を下げ、金と同じ貴金属であるプラチナやパラジウム、さらに非鉄金属の銅なども軒並み下げている。また、住宅向け資材不足で木材価格が高騰し、「ウッドショック」と呼ばれた現象もいまや沈静化。高値から大きく値を下げている。
さらに、トウモロコシや大豆などの農産物も需要回復などを材料に大きく値を上げていたが、ピークを付けたあとは急落している。
これまで、新型コロナワクチン接種の進捗で景気回復が進み、「需要が拡大する」との見方がコモディティ価格を押し上げていた。しかし、ここにきて急速に地合いを悪化させている。いったい何があったのだろうか。

■市場は材料を先取りして動く
コモディティには「実需」がある。コモディティは実際に消費されるため、景気回復に伴い需要が増加するのが一般的な考え方である。
確かに、今回のコロナワクチン接種の進捗は、将来のコモディティ需要の回復を想起させるのに十分な材料だったといえる。
市場は材料を先取りして動くことが少なくない。とはいえ、いますぐに需要が拡大し、供給が追いつかなくなるわけではない。それも価格が短期間で数十パーセントも上昇するような需給逼迫(ひっぱく)の状況に一夜にしてなることはあり得ない。
しかし、コモディティ価格は、いったん方向性が出ると、その方向に進みやすい特性がある。それは、将来の需給見通しに敏感に反応した結果である。重要な需給見通しの発表後に、一時的に価格が大きく動くことも確かに少なくはない。
このように、需給要因によってコモディティ価格は短期間で変動しやすい特性がある。
■市場の影の支配者は「思惑」
問題はその変動の大きさと持続性である。需給環境が一日で一変することはあり得ず、徐々に変化していくはずである。だが、実際には価格は激しく動く。その結果、今回のような急落が発生することになる。
なぜそのようなことが起きるかといえば、「思惑」が市場を支配しているからにほかならない。
コモディティは先物市場でも取引されるため、現物業者だけでなく、先物市場で運用するヘッジファンドなどの投機筋の動向の影響も受けやすい傾向にある。これらの投機筋は、それぞれの思惑で投資判断を行い、先物市場で取引をするのだが、価格の方向性についていく運用手法を取り入れる向きが多い。
これは一般的に「トレンドフォロー」と呼ばれ、いわゆる“順張り”での取引を主とする運用である。
したがって、価格が上がりだすと、彼らは買いを入れ続け、結果的にそれが価格を押し上げることになる。一方、下がり始めると、その下げに追随するように売りを仕掛けてくる。その結果、価格が短期間で大きく下げることになる。
■保有するコモディティの価値は日々劣化する
このように、実際のコモディティ価格は、短期間で見ると上下動することが少なくないのである。いわゆる「ボラティリティ(価格変動率)」が他の金融資産などと比べて高い傾向があるからやっかいである。
このような市場で個人投資家が取引するのは、きわめて難しい。
「安い」と感じたという理由だけで買うと、投機筋が売り仕掛けてくるため、いわゆる“押し目買い”にならずにさらに価格が下がってしまうことはよくある。したがって、コモディティは株式投資のように押し目買いを行い、長期で保有することはできないのである。
とくに農産物などは保管期限が限られる。「腐る」からである。長く保有すればするだけ、価値は劣化していく。つまり、現物価格の水準が変わらなくても、保有しているコモディティの価値は、実際には日々劣化しているのである。
この点を理解していない金融市場関係者はいまだに少なくない。まして、個人投資家のほとんどは理解していないだろう。
■米ドルのレートに左右されるコモディティ価格
実は金投資も同じである。
金には、目に見えない「金利」と「保管料」が実際には価格に織り込まれている。つまり、いま読者が金を保有しているとすれば、それが現物であったとしても、先物市場での取引であったとしても、価値が日々劣化している。この点を理解したうえで金をはじめとするコモディティに投資しないと、実際には収益は出ない。
また、為替の問題もある。世界のコモディティ市場は、米ドル建てで取引されている。米ドルが上昇すると、ドル建てのコモディティ価格は下落するのが一般的である。逆に米ドルが下落すると、ドル建てコモディティ価格は上昇する。
それは、ドルが自国通貨でない国がコモディティを輸出する場合を考えれば、容易に理解できるだろう。あるいは、日本の輸出企業の採算に置き換えると分かりやすいかもしれない。円安のときには、ドル建て価格を抑制しないと海外では売れなくなる。それと同じである。
このように、コモディティ価格を形成する背景はかなり複雑で、株式市場の比ではないだろう。だからこそ市場参加者が限られ、「プロの市場」という位置づけになる。

■インフレ想定時のポートフォリオの基本
とはいえ、金や銀は、欧米では個人投資家が現物やコインなどを通じて普通に取引している。富裕層で金を保有していない人はほとんどいないだろう。米国では銀も選好されることが多い。
投資家が金や銀に価値を見いだしているのは、コモディティそのものの価値以上に、「通貨の代替」としての機能に対してである。
将来インフレになれば、自身が保有する資産の価値が目減りする。これをもっとも嫌がっているのが富裕層だ。今後インフレを想定しているのであれば、彼らのように金や銀を自身のポートフォリオに入れておくのが基本である。
そして、できるだけ安いときに買うべきである。
そう言うと、「投機筋が下落相場で売ってくるから、押し目買いはダメではないか」という声が聞こえてきそうである。しかし、金や銀は通常のコモディティとは違い、金融商品のような一面もある。
現物でゆっくり買うのであれば、金や銀に限って言えば、押し目買いは有効な投資手法である。これは、持ち運びも簡単で、重量当たりの価値が高いからこそできるのである。
同じ金額の原油や大豆を持ち運ぶことは、現実には不可能であり、かつ保管もできない。まして価値が日々劣化し、現金化もままならない。だからこそ、金や銀が選好されるのである。
■利上げまで金価格下落、その後に大きく反転か
いまは、米国中銀がこれまで行ってきた緩和的な金融政策の転換の動きが出てきており、それが金利の上昇やドル高につながっている。これが直近の金価格の下落につながっている。
前回の緩和策の解除の過程では、2年程度、金価格は低迷した。そして、実際に利上げが実施されるまで、上値の重い状態が続いた。しかし、実際に利上げが実施されると、そのタイミングが底値になり、上昇し始めている。
今回も同じような状況になるかはわからないが、利上げが2023年に想定されていることから、2年弱は金価格が低迷する可能性も否定できない。しかし、そうなった場合でも、その後に金価格は上昇に転じ、2027年ごろまで上昇するだろう。
過去に金価格が上昇した際には、12年程度の上昇期間が観測されている。今回の上昇の起点は2015年末である。したがって、2027年ごろまでの上昇は十分に想定可能と考えている。
■金投資のラストチャンスは「この2年」
読者が株式投資をしているのであれば、株式を買うのと同時にその金額の2割から3割程度の金も同時に買うとよいだろう。そうすれば、将来のインフレヘッジだけでなく、株価の下落リスクのヘッジにもなるだろう。
基本的に、株価と金価格は逆に動くことが多い。とくに、株価下落局面ではその傾向が顕著である。
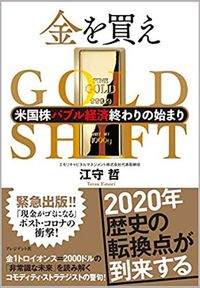
金投資をまだ始めていない方は、この2年間のうちに安値で仕込むとよいだろう。そうすれば、数年後には金価格の値上がり益も期待できるのではないかと考えている。
金を含むコモディティ価格は大きく変動する。そうした動きを逐一気にしなくてもよい程度の金額で、時間と資金を十分に分散しながら、徐々に金を買い増していくことが肝要である。
この2年が金投資のラストチャンスとなろう。もちろん、最終的な投資判断は自身の責任で行っていただくことは言うまでもない。
金投資や金に関する詳しい解説を知りたい方は、拙著『金を買え 米国株バブル経済終わりの始まり』(プレジデント社)をぜひお読みいただければと思う。今後の世界情勢や米ドルの動向、さらには米中対立の結末や金価格の将来見通しなどを知ることができるだろう。
----------
エモリファンドマネジメント 代表
1990年慶應義塾大学商学部卒業後、住友商事に入社し、非鉄金属取引に従事。英国住友商事(現欧州住友商事)に出向し、ロンドンに駐在。Metallgesellschaft Ltd.(ロンドン本社、現JPモルガン)、三井物産フューチャーズ、アストマックスを経て独立。現在はエモリファンドマネジメント代表。著書に『ロンドン金属取引所(LME)入門』(1999年総合法令出版)、『米国株は3倍になる』(2017年ビジネス社)など、共著書に『コモディティ市場と投資戦略』(2014年勁草書房)がある。新刊は『金を買え 米国株バブル経済の終わりの始まり』(2020年プレジデント社)。
----------
(エモリファンドマネジメント 代表 江守 哲)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「1ドル160円台」をひた走るドル/円だが…過去2年連続で7月に勃発している「米ドルの下落」は、今年も繰り返されるのか【国際金融アナリストの考察】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月9日 10時15分
-
「もしトラ」トレード始まる~7月のビットコイン見通し~
トウシル / 2024年7月5日 7時30分
-
投資初心者なら知っておくべき!株価の下落相場を乗り切るための4つの手法
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月26日 11時0分
-
投資成績を大きく左右する本番がある!株式投資でベストパフォーマンスを出す方法
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月25日 11時0分
-
円高転換へのリスク4関門
トウシル / 2024年6月21日 7時30分
ランキング
-
1iPhoneの「ホームボタン」が消えていく深い意味 「心の支え」だった人はどうすればいいのか?
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 13時0分
-
2「離職率が低い大企業ランキング」トップ100社 単独従業員が1000人以上の会社を対象に調査
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 6時0分
-
3「日本でしか手に入らない」カレーパン、なぜ外国人観光客に人気? チーズ入りカレーパンに「私の心臓は高鳴った」【Nスタ解説】
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月15日 22時0分
-
417年ぶり消費増税、強気の「展望リポート」に3人反対=14年上半期・日銀議事録
ロイター / 2024年7月16日 9時8分
-
5中国は不動産バブル崩壊で「未完成ビル」と「売れ残り住宅」の山→政府当局が打ち出した“支援策”の裏にひそむ「重大な懸念点」【現地駐在員が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月15日 8時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











