日本社会の勝ち組「現場の叩き上げ」が通用しなくなった根本原因
プレジデントオンライン / 2021年7月1日 11時15分
■求められる「スキル」が変わった
ある会社で社内の公用語を日本語から英語にする、というニュースがあった。「インターネットの普及で、英語力さえ備えていれば簡単に情報を得られるし、提携先企業との交渉も効率的に進められるから」だという。
これは、これまで一部の人にしか要求していなかった英語の能力を、基礎的なスキルとして全社員に求める時代になってきたことを示している。
ITについても、同じことがいえる。大型コンピュータの時代には、専門家だけがシステムを扱えればよかった。しかし、PC(パソコン)やインターネットの時代には、それらを扱えることが、すべての社員に要求される。
従来、企業で仕事を進める上で必要とされてきたのは、その企業に特有の業務上の知識だった。それは、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング:日常の仕事を通じる教育)によってしか習得できないとされてきた。
こうした知識が今後も必要とされることに変わりはない。しかし、それだけでなく、英語やITのように、社外でも通用する一般的なスキルが求められるようになってきたのである。
これは、新しい時代の到来を告げるものだ。日本社会は、そのような社会に向かって、いま大きく変わりつつある。
■「学歴」が評価の対象になってきたワケ
これまでの日本では、個人がどれだけのスキルを持っているかでなく、その人の「学歴」が評価の基準とされてきた。
大学出身か否か、そしてどの大学の出身かが、さまざまな場合に重要な判断基準とされた。とりわけ採用の際には、このような形式的な基準が重視された。
背景には、日本企業の雇用慣行があった。日本ではこれまで、大企業を中心として「終身雇用制」が支配的だった。もちろん、文字通り「終身」であるわけではないが、人生の主要期間をカバーする数十年間にわたる雇用契約が多かった。
この慣行のもとで新入社員を採用する際にもっとも頼りになる情報は、出身校名だ。なぜなら、学業成績と一般的能力の間には、一定の相関関係があるからだ。だから、学歴は、数時間の面接で得られる情報より確実な情報だ。
学歴を根拠として採用するのは、企業にとって、もっとも安全な方法だったのである。
もし学歴を無視して選考を行い、その結果不適切な人材を採用してしまえば、長期にわたる雇用契約だけに、雇用者側の損失は大きいだろう。
こうして、終身雇用慣行のもとで学歴重視が支配的になった。
■縁故・門閥よりはるかに有効だった「学歴」基準
1980年頃までの日本では、これが支障なく機能してきた。むしろ、縁故や門閥(もんばつ)などを基準とするよりも優れた人材を登用できた。
このことの意義は、決して無視できない。開発途上国では、縁故などによる採用が一般的なので、優秀な人材が重要な職に就けないことが多い。日本はそのような問題を回避したという評価も可能だ。
もちろん、学業成績は能力と完全に相関しているわけではない。とくに、創造的能力との相関は、さほど強くない。
しかし、1980年代までの日本企業で必要とされてきたのは、創造的能力ではなかった。むしろ、組織内での協調性のほうが重要だった。
それは、日本社会全体が、キャッチアップ過程にあったからだ。追いつくべき目標は、先進国というモデルとして存在していた。
このように明確な目標に対して効率を向上させるのが主要な課題である社会では、学歴重視のシステムは、比較的うまく機能するのだ。
■前提の変化:「新しいスキル」「創造性」の時代へ
しかし、時代は大きく変わった。日本をとりまく世界経済の環境が、大きく変化したのだ。
第一に、中国をはじめとするアジア諸国が工業化した。これによって、高度成長期に日本が得意としてきた産業分野、とくに製造業が、もはや日本の独占領域ではなくなった。それどころか、いくつかの分野で、アジア諸国は日本を追い抜きつつある。
第二に、インターネットなどの新しい情報技術を活用した産業が、新しい中核的産業として登場した。
こうした新しい産業では、与えられた枠内での業務を効率化するだけでなく、新しいアイディアを構想し、それを事業化していくことが求められている。単なる協調性ではなく、新しいスキルや創造力が求められる時代になったのだ。
日本をとりまく国際環境の変化や、新しい技術の発展に対応して、日本社会も大きく変わらなければならない。
第一に、産業構造が大きく変わらなければならない。そうした変革のためには、労働市場が流動化せざるをえなくなる。従来の雇用慣行は崩れ、終身雇用制は維持できなくなる。そのため、学歴社会も崩れる。
日本社会は、すでにこの段階に入っている。
第二に、新しい技術が支配的になると、年功序列制も維持できなくなる。これもすでに進行しつつあることだ。
このような傾向は、最近、加速している。デジタルトランスフォーメーション(DX)といわれるように、仕事の進め方の全体を、企業として変革する必要が生じているのだ。このため、個々の社員のITスキルが生産性のカギを握るようになった。
■「武器」を獲得するための「学び直し」
「学び直し」が必要となる基本的な理由は、このような条件変化にある。学歴にこだわっていては、今後の社会を生き抜いていくことはできない。
すでに述べたように、学歴とは、一般的な能力を示すための「シグナル」である。これまでの勉強は、シグナルを獲得するためのものだった。
しかし、新しい社会で必要とされているのは、スキルや能力そのものだ。いわば、仕事をするための「武器」である。学び直しとは、こうした意味での「武器」を獲得するためのものだ。
勉強を続けないかぎり、企業の中での位置づけは、不安定なものにならざるをえない。学び続けないと仕事がなくなるという危機感を持つ人も多い。
30代の会社員の4人に3人が「再び学びたい」と考えているそうだ。多くの人たちが、時代の変化を感じているのだ。
さまざまな調査によると、再教育へ参加する人の割合が高い国ほど、時間あたり労働生産性が高い。このため、世界の各国が、学び直しを競い合うようになっている。
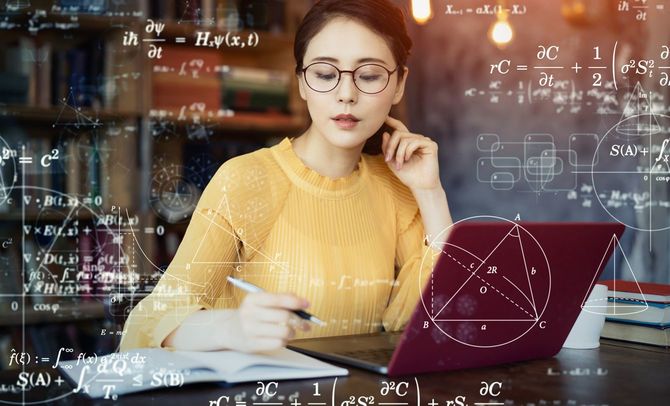
■いつまでも勉強を続けよう
学歴社会では、大学入試までは、死にもの狂いの勉強が続く。しかし、大学に入学すると、疲れきって勉強をやめてしまう人が多い。こうした人たちにとって、勉強とは大学入試までのものでしかない。
しかし、いまの社会では、常に勉強が求められる。変化する社会では、知識の有効期間は非常に短くなるからだ。学生時代の勉強から進歩しない人は、変化に取り残される。
もちろん、社会に出てからも勉強を続ける人は、これまでもいた。生涯教育の必要性は、昔からいわれてきたことだ。
しかし、これまでは、そうした努力が正当に報われたとはいい難い。それより、組織の人間関係を円滑にすることのほうが重要だった。
その状況が大きく変わり、学び直しを続けない限り生きられない時代になったのだ。
■勉強の成果が正当に評価される社会に
「受験の時代が終わったあとも勉強が続くのでは、やりきれない」という人がいる。しかし、これは二重の意味で間違いだ。
第一に、勉強は、楽しいものだ。勉強の機会がいつまでも続くというのは、ありがたいことなのだ。
「勉強をやりたくない」と考えるのは、勉強を強制され、嫌々ながらやってきたからだろう。
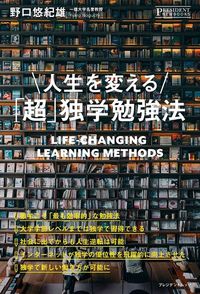
第二に、「いつまでも勉強が続く」とは、「いつになってもチャンスが開ける」ことを意味する。学び直し社会とは、勉強の成果がいつになっても正当に評価される社会のことなのである。
学歴社会では、勉強の成果が評価されるのは入試だけだ。入学試験という人生の一時点の結果だけで一生が左右されてしまう。
しかし、受験期年齢が過ぎてからのちに才能が開花する人もいる。人生の早い時期の、しかも1回かぎりのテストでその後の人生の条件が決まってしまうのは、合理的なこととはいえない。
こうした点が、学び直し社会では修正されてゆく。これは、望ましい方向への変化だ。だから、積極的にとらえるべきものである。
在宅勤務が増えて、自由になる時間が増えた。この時間を、テレビを見て過ごすか、勉強に使うか。その違いによって、その人の未来は、まったく違うものになるだろう。
----------
一橋大学名誉教授
1940年東京生まれ。63年東京大学工学部卒業、64年大蔵省入省、72年エール大学Ph.D.(経済学博士号)を取得。一橋大学教授、東京大学教授、スタンフォード大学客員教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授などを歴任。一橋大学名誉教授。専攻はファイナンス理論、日本経済論。近著に『経験なき経済危機──日本はこの試練を成長への転機になしうるか?』(ダイヤモンド社)、『中国が世界を攪乱する──AI・コロナ・デジタル人民元』(東洋経済新報社)ほか。
----------
(一橋大学名誉教授 野口 悠紀雄)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「中学受験はうちの子には不要」と考える親が「大正解」である決定的な理由【池上彰の未来予測・前編】
OTONA SALONE / 2024年7月13日 20時0分
-
小倉優子、麻木久仁子、東MAX…学び直す芸能人が増加「学歴を得る」だけじゃないタレント特有の学びのカタチ
NEWSポストセブン / 2024年7月13日 7時15分
-
日本が「4年連続1位→38位」に転落した国際的指標 韓国は20位、アジアで日本より下位は3カ国のみ
東洋経済オンライン / 2024年7月7日 11時0分
-
経営者目線 年金破綻「積立金2040年代に枯渇!?」 ワタミの宅食「うなぎ」特別弁当
zakzak by夕刊フジ / 2024年7月3日 6時30分
-
「高学歴な人ほど人生は幸せ」はウソである…日本人が誤解している「最終学歴」の不都合な真実
プレジデントオンライン / 2024年7月2日 10時15分
ランキング
-
1iPhoneの「ホームボタン」が消えていく深い意味 「心の支え」だった人はどうすればいいのか?
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 13時0分
-
2CoCo壱「わずか3年で3回目の値上げ」は吉と出るか 過去の値上げでは「客離れ」は見られないが…
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 17時30分
-
3「離職率が低い大企業ランキング」トップ100社 単独従業員が1000人以上の会社を対象に調査
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 6時0分
-
4「日本でしか手に入らない」カレーパン、なぜ外国人観光客に人気? チーズ入りカレーパンに「私の心臓は高鳴った」【Nスタ解説】
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月15日 22時0分
-
517年ぶり消費増税、強気の「展望リポート」に3人反対=14年上半期・日銀議事録
ロイター / 2024年7月16日 9時8分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











