「韓国ではプロ野球並みの人気なのに」ゲーム大国の日本でeスポーツが出遅れた本当の理由
プレジデントオンライン / 2021年8月17日 9時15分
※本稿は、中村尚樹『最前線で働く人に聞く日本一わかりやすい5G』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
■国体の文化プログラムに採用された
eスポーツは、Electronic Sports(エレクトロニック・スポーツ)の略で、「コンピューターなど電子機器を使った競技」という意味である。Electric(エレクトリック)、つまり「電気」を使うという意味ではなく、あくまで「電子」上の競技である。ちなみにeが小文字になっているのは、決まりがあるわけではない。ただ、アップル社が自社のパーソナルコンピューターに小文字の「i」を冠した製品を売り出して人気を博したことにあやかって、小文字を使うようになったのではないかと、関係者の多くは見ている。
ゲームの種類は、1対1で戦う格闘技だったり、チームに分かれて陣地を取り合う団体戦だったりと、様々だ。具体的にはFPS(シューティングゲーム)、RTS(戦略ゲーム)、MOBA(チーム戦バトル)、格闘ゲーム、スポーツゲーム、パズルゲーム、カードゲーム、ソーシャルゲーム、スマートフォン向けゲームなどがある。
国内ではプロ野球やJリーグも、それぞれの競技をコンピューター画面上で競うeスポーツの大会を開いている。海外では野球のメジャーリーグ、サッカーのFIFA、バスケットボールのNBA、モータースポーツのF1など著名なスポーツ団体が、eスポーツに参入している。2019年から国体でも、文化プログラムとしてeスポーツが競技種目となっている。
2018年には既存のeスポーツ3団体が統合して「日本eスポーツ連合」(JeSU)が発足した。eスポーツ大会の普及活動や認定、プロライセンスの発行、選手の育成や支援などを行っている。
■世界の競技人口は2億人以上
このeスポーツを、どのくらいの人が楽しんでいるのだろうか。平成30年度の文部科学省の事業として国際研修交流協会がまとめた「eスポーツ分野における先端技術活用型チームマネジメント人材養成事業」成果報告書によれば、国内のeスポーツ競技人口は約390万人、eスポーツを見て楽しむオーディエンスは約160万人と推定されている。さらに世界の競技人口は約2億人以上という。錦織選手や大坂選手の活躍で日本でも人気の高まってきたテニスの競技人口が日本で約400万人、世界では約1億1000万人だから、その世界的な広まりがわかっていただけるだろう。
また、eスポーツの優れている点は、プレーヤーに関してフィジカルな制約が少ないことだ。だから身体に障害のある人たちも、自分にあった補助器具を使うことで、健常者と対等に戦うことができる。大会の多くは、性別や年齢による区分もない。
eスポーツ人気を裏づけるように、特に海外では大会の規模が急速に拡大している。2019年に開かれた「フォートナイト」というゲームの大会では、日本円にして賞金総額約33億6300万円、1位賞金3億2500万円という大会も開かれた。各地の大会の賞金を積み上げた年間の賞金総額では、2019年の「ドータ2」がなんと、233億円である。観客動員では、「リーグ・オブ・レジェンド」の世界大会決勝戦で6万人、インターネットで配信された決勝戦の視聴者が2億人というからすさまじい。ちなみに2008年の北京オリンピック開閉会式の観客が6万人である。

■日本のeスポーツはいまだ発展途上
eスポーツ先進国はアメリカや韓国、そして中国である。それに比べて、日本はかなり出遅れているといわざるを得ない。「任天堂やソニー、セガを擁するゲーム大国日本でなぜ?」と思われるかもしれない。
eスポーツは、コンピューターを相手に戦うのではなく、電子ゲームを舞台に、複数のプレーヤーが対戦するものをいう。あくまで、人と人とが戦うのがeスポーツなのだ。1対1の個人戦もあれば、5対5の団体戦もあり、中には100人が一度に参加できる競技もある。
一方、日本では家庭用のゲーム機があまりに普及してしまったため、主にパソコンなどを使って対戦するeスポーツは出遅れてしまったのだ。加えて日本では、専用の光ファイバーを使った光回線が普及する前に、従来の電話回線を利用するISDNをはさんだため、インターネットの回線速度が他国と比べて遅かったのも理由のひとつにあげられている。
さらに日本では、景品表示法や刑法の賭博罪との関係で、eスポーツの大会に多額の賞金を出せない恐れがあったり、風俗営業法でeスポーツ特化型ネットカフェの営業時間が規制されたりすることも、日本でeスポーツが出遅れた要因といわれている。
これに対してお隣の韓国は、世界大会上位の常連であり、eスポーツ大国と呼ばれる。その歴史的背景としては、1990年代後半の世界同時不況で韓国が通貨危機に直面した際、国策としてネット事業に力を入れたことがあげられる。仕事のない若者がネットカフェに集まり、オンラインゲームに熱中するようになった。やがてeスポーツの人気は拡大し、ソウル市内にはeスポーツ専用の競技場もオープンするなど、いまや韓国を代表する文化のひとつともなっている。
■後れを取り戻しつつある日本のeスポーツの魅力
もうひとつ指摘しておきたいのは、eスポーツの、「スポーツ」という用語である。日本語でスポーツというと、身体を動かす「運動」を意味する。だからコンピューターゲームをスポーツと呼ぶことに違和感を覚える方もいることだろう。しかし欧米諸国における「スポーツ」の語源はラテン語で、「日々の生活から離れること」「気晴らしをする」「楽しむ」という意味がある。時代が下って、「競技」という意味も加わった。つまり「楽しみでする競技」というのが、欧米で理解されるスポーツなのだ。
身体を動かすのはフィジカルスポーツだ。そして頭脳で勝負するチェスやカードゲームは、マインドスポーツと位置づけられる。eスポーツも、この系譜に入る。
一方、明治期の日本政府は、外国から入ってきた「スポーツ」を「楽しみ」ではなく、教育における「鍛錬」と位置づけた。そこから日本では、身体を鍛える運動がスポーツと考えられるようになったのだ。こうしてみると、日本は「e」に対するアプローチ、そして「スポーツ」に対する受け止め方という二重の意味で、eスポーツに後れをとってきた印象がある。しかしいまではその後れも、急速に取り戻しつつある。
■かつてのプロ野球のような勢いでe スポーツが普及する
東京都eスポーツ連合会長で、日本eスポーツ学会代表理事も務める筧誠一郎はeスポーツの魅力について、若い人たちにとってゲームはきわめて身近な存在で、しかも対人性があることだと言う。
「何が若い人たちを惹きつけているのかというと、人と人とが競うという点です。その人の性格や考え方がそのまま表れるのが、eスポーツのいいところですね。コンピューター相手だと、同じ攻め方をすれば、同じ反応が返ってくる。しかしeスポーツは相手が人ですから、対戦相手によって変わるわけです。戦い方の好みも様々です。それは、対戦相手とのコミュニケーションでもあるのです」
人間関係が希薄になりつつある時代だからこそ、人びとはeスポーツに、気のおけない仲間とのつながりを求めているのかもしれない。
1960年生まれの筧は高校時代にテーブルテニス、大学時代にはスペースインベーダーやギャラクシアンに熱中した世代である。大手広告代理店の電通に入社したあとも、ファミコンやスーパーファミコン、プレステ、さらにはオンラインゲームと、ゲーム熱が冷めることはなく、ついにはゲーム制作の企画を立ち上げて、スーパーファミコンやプレステのゲームを大ヒットさせた経験もある。そんな筧がeスポーツを知ったのは46歳のときだった。韓国など海外で、eスポーツが深く浸透している状況を知り、衝撃を受けたのだ。
筧はさっそく社内に勉強会を立ち上げ、eスポーツに関する取り組みを開始した。リーマンショックで開発費が削減されると、筧は49歳で思い切りよく電通を退社した。やがてeスポーツの普及に関する事業をマネジメントする会社を立ち上げ、大会を主催したり、渋谷に日本最大規模の「eスポーツ・パブリックビューイングバー」をオープンさせたりしている。
そんな筧はeスポーツについて気負うことなく、「要はスポーツジャンルのひとつ」と語る。「eスポーツって、特殊なものと思う人もいるかもしれませんが、かつて野球が若者に支持されたように、いまの時代はeスポーツが支持されている。だからプロ野球で行われてきたことが、これからのeスポーツにもそのまま当てはまるのですね」
■「配信で一番稼げる」とIOCも重要視
近年、日本でもeスポーツの話題が増えてくるようになった。そのひとつのきっかけがオリンピックである。
すでに「アジア・オリンピック評議会」が主催するアジア版のオリンピック、「アジア競技大会」の2018年ジャカルタ大会では、公開競技としてeスポーツが行われた。そのサッカーゲーム部門では、日本チームが優勝している。また2022年に中国の杭州で行われる予定の大会では、正式種目になることが決まっている。
IOC(国際オリンピック委員会)もeスポーツに関心を示している。トーマス・バッハ会長は「eスポーツ産業の成長は無視できないし、若い世代に魅力もある。五輪に入れるかどうか話をするのは時期尚早だが、対話のドアは開けたままにしておく」(2018年12月4日付け共同通信)と述べている。
こうした状況を踏まえて筧は、「2024年のパリ大会では、公開競技か併設競技のような形で行われるのではないか。そして28年のロサンゼルス大会での正式種目は、ほぼ確定だと思っています」と展望する。その理由として筧はスポンサーの意向、そして人気の高い映像配信をあげる。「オリンピックのトップスポンサーは12社。そのうちアリババ、サムスン、インテルの3社はeスポーツ関連企業なのです。もうひとつ、国際オリンピック委員会が、テレビの次に重視しているのがインターネットの配信です。いままでテレビに頼っていた放映権料が、インターネットの配信に代わる時代が来る。そうしたとき、配信で一番稼げるのは何かというと、eスポーツなのです」
■5Gでeスポーツに変革が起きる
eスポーツに対する期待が高まる背景のひとつに、次世代移動通信システムの5Gがある。5G時代で、医療やモビリティなどの利便性向上が期待されるが、「中でも一番相性がいいのがeスポーツ」と、筧は断言する。「医療は患者と医師の1対1の関係です。一方eスポーツでは、一度に100人が同時接続するゲームもある。スマートフォンで大人数のゲームが可能となる。速度面でいえば、北海道と沖縄の距離でも、0.1秒を争うトッププレーヤーにとっては遅延が起きる。これが5Gになると、理論値的には、東京から中国の奥地くらいまで大丈夫です。トッププレーヤーの場合、5Gでもっとすごいプレーが見られるようになります」
■eスポーツ関係者が5Gを待ち望む切実な理由
第2回全国高校eスポーツ選手権で準優勝に輝いたクラーク記念国際高校。その秋葉原ITキャンパス「情報科」で教諭を務める笹原圭一郎もこう語る。
「専攻で正式に取り扱ってはいないのですが、みんなスマートフォンを使ってゲームをやっています。eスポーツを、娯楽としてのスポーツと捉えたとき、ユーザー数はダントツだと思います。そのスマートフォンで通信が途絶えたり、遅くなってしまったりしたとき、ミスをして負けてしまうのは、勝った方も、負けた方も、なんともいえない気持ちになります。それが5Gになると、それらのトラブルが格段に減ると思います。5Gの普及でeスポーツは、ますます人気が出るでしょう」
加えて5Gで便利になると期待されるのが、大規模な大会を開く際のセッティングである。
いまeスポーツの大会を開く際には、ゲームだけに使う専用回線を引く必要がある。というのは、すでにある回線を共用すると、他に利用者がいた場合、遅延が起きてしまうからだ。
そこで他からの干渉を受けないゲーム用の回線、そして配信用の回線を設営するのだが、3カ月以上前にNTTなどに申し込み、現地の下見をして配線の確認をする必要がある。これが5G時代になると、その場所だけで運用できるローカル5Gを開設することができるようになる。これまでのように有線で回線を引く必要がなく、ローカル5Gの機械を持ってくればいいだけになり、大会運営の手間が大幅に削減されると期待されている。
■5Gによって加速するeスポーツの未来
全国eスポーツ選手権の主催者のうちの一社である、株式会社サードウェーブ副社長の榎本一郎は「子どもたちが本気でeスポーツに取り組み、その後の選択肢を増やすためには、高校にeスポーツ部がなければなりません」と、熱く語る。
実は榎本自身、高校野球で甲子園を目指したが叶わず、実業団では肩を壊して野球を断念した経験があるのだ。必死に取り組んだ部活動は、その後の人生にも必ず役に立つ。
IBMやDELLといったPCメーカーで要職を歴任し、PC業界に造詣の深い榎本は、eスポーツに深い理解を持つ。しかし学校でeスポーツ部を作ろうにも、ハイスペックなパソコンがなければ難しい。
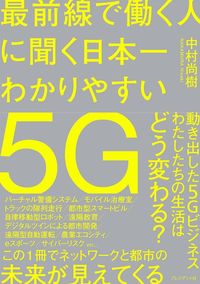
「若者の可能性を広げたい。eスポーツを文化にしたい」というサードウェーブ社長、尾崎健介の決断で、パソコンの無償貸与事業が実現することになった。
サードウェーブは全国高校eスポーツ選手権で、定価で約17万円のパソコンを、チームに必要な台数分、期間限定でeスポーツ部に無償で貸し出した。無償貸与の内容は、年度によって変わってきているが、「今後もできるだけ続けたい」と榎本は語る。
5Gになれば、eスポーツはどう変わるか、尋ねてみた。「5Gの世界になったら、クラウド側で処理できる範囲が広がるため、ハードウェアに対するスペック的な依存度が低くなり、より多くのデバイスでeスポーツを楽しめる可能性が増えていきます。環境が整っていくと、『これじゃなきゃダメ』という垣根がなくなることで、ハイエンドパソコンを手掛ける我々にとってネガティブな面もあります。しかし、どんなに環境が良くなっても、ユーザーにとって一番良い製品やサービスが選ばれます。そしてeスポーツに関わる時間が増えます。楽しめる時間とスタイルがどんどん広がるという意味で、5Gに期待しています」
■5G時代のeスポーツは従来のゲーム観を覆す
ゲーム会社各社も、5G向けコンテンツの開発を急いでいる。eスポーツはパソコンからスタートしたが、中国ではすでに、パソコンのゲーム市場を、スマートフォンが抜いている。パソコンは家や学校、職場、ネットカフェなど、使える場所が固定されるが、スマートフォンだと移動中の空いた時間にも楽しめるからだ。しかも若い世代はパソコンやテレビより、スマートフォンに馴染んでいる。そこで各社とも、5Gに相応しいゲームの開発に、しのぎを削っているのである。
5G時代になると、これまでの常識を打ち破るようなゲームソフトが出てくるはずだ。それは、練習すれば練習するほど楽しめる、奥の深いゲームとなるだろう。使われるデバイスも、3D対応のゴーグルやビューワーを使いながら、仮想の世界、あるいは拡張現実の世界に入り込むことになるかもしれない。従来なら処理できなかった大量のデータも、5Gが解決してくれる。
5G時代のeスポーツは、従来のゲーム観を覆す新しい世界を見せてくれることだろう。(文中敬称略)
----------
ジャーナリスト
1960年、鳥取市生まれ。九州大学法学部卒。専修大学社会科学研究所客員研究員。法政大学社会学部非常勤講師。元NHK記者。著書に『ストーリーで理解する日本一わかりやすいMaaS&CASE』(プレジデント社)、『マツダの魂 不屈の男 松田恒次』(草思社文庫)、『最重度の障害児たちが語りはじめるとき』『認知症を生きるということ 治療とケアの最前線』『脳障害を生きる人びと 脳治療の最前線』(いずれも草思社)、『占領は終わっていない 核・基地・冤罪そして人間』(緑風出版)、『被爆者が語り始めるまで』『奇跡の人びと 脳障害を乗り越えて』(共に新潮文庫)、『「被爆二世」を生きる』(中公新書ラクレ)、共著に『スペイン市民戦争とアジア──遥かなる自由と理想のために』(九州大学出版会)などがある。
----------
(ジャーナリスト 中村 尚樹)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
JOC、eスポーツの準加盟承認 27年3月までの期限付き
共同通信 / 2024年6月11日 19時55分
-
日本 e スポーツ連合(JeSU)の日本オリンピック委員会(JOC)準加盟に関するお知らせ
PR TIMES / 2024年6月11日 18時45分
-
JOC、eスポーツの準加盟検討 11日の理事会で審議へ
共同通信 / 2024年6月7日 19時52分
-
ワールドeスポーツチャンピオンシップ 2024「eFootball(TM)」シリーズ日本代表決定のお知らせ
PR TIMES / 2024年6月6日 14時45分
-
ワールドeスポーツチャンピオンシップ 2024への日本代表選手派遣に関するお知らせ
PR TIMES / 2024年5月28日 16時15分
ランキング
-
1中国の過剰生産「有害」=雇用保護へAI行動計画―G7首脳声明
時事通信 / 2024年6月15日 16時44分
-
2バーガー店打撃…日銀「国債買い入れ減額」で “歴史的円安”に歯止め?
日テレNEWS NNN / 2024年6月15日 13時57分
-
3アップルにEUが制裁金、世界売上高10%の可能性…デジタル市場法違反に初認定か
読売新聞 / 2024年6月15日 15時19分
-
4「阿武隈急行」の赤字穴埋めする2県5市町の補助金、宮城・柴田町が2358万円の支払い拒否
読売新聞 / 2024年6月15日 20時24分
-
5日本のIT人材が「平均年収1200万円」に達するのはいつなのか…周回遅れの日本企業に迫る「2025年の崖」という危機
プレジデントオンライン / 2024年6月15日 18時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












