最果ての極寒の地で現地のロシア人が「口にすると死ぬ」と警告した意外なモノ
プレジデントオンライン / 2021年8月15日 11時15分
※本稿は、椎名誠『漂流者は何を食べていたか』(新潮選書)の一部を再編集したものです。
■200年前に漂着した島へ向かうのは現代でも大変
光太夫らの足跡をできるかぎり追っていこう、という計画をたてていた我々は光太夫らのように千石船に乗ってアリューシャン列島にむかうわけにはいかなかったからアラスカからアプローチした(TBS「シベリア大紀行」1985年)。
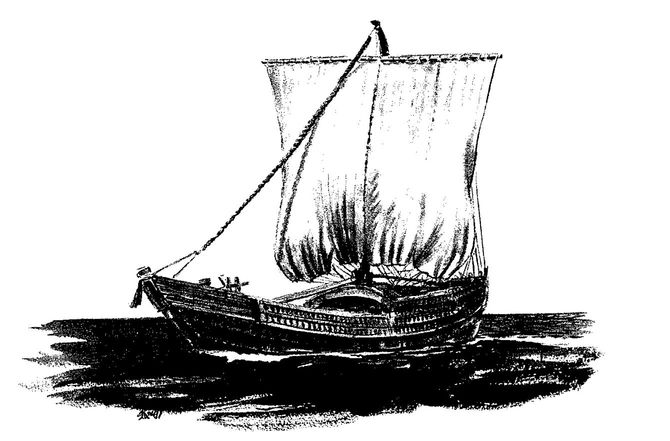
光太夫らが漂着した頃はアリューシャン列島とはよばずアレウト列島とよばれ、ここからアラスカまですっかりロシア領だった。
1867年にロシアはアラスカを720万ドルでアメリカに売った。あまりにもでかい買い物なのでどっちが得をしたのかいまだにわからないような気がするが、当時はこの不毛の北の大地をロシアもアメリカも持て余していた気配がある。
しかしその後1902年頃アラスカから大金鉱が発見されてアメリカの大儲けと言われていたものだ。1942年頃のアリューシャン列島は太平洋戦争のただなか。日本の海軍が狙っておりこの列島の西部にあるアッツ島とキスカ島を占領している。
我々は7人チームでアラスカから小型機をチャーターしてアムチトカを目指していた。
1970年代はアメリカがアムチトカで5メガトン(広島型原爆の330倍)というすさまじい規模の地下核実験をおこない、もう島としての存在感など何も持っていなかった気配がある。
我々アムチトカ探検隊の7名はコールドベイという、もう地名からしてやる気のない最果ての氷空港と一年中ブリザードという冗談のようにどうでもいい感じの飛行場の要塞兵舎のようなところから出る飛行機を確保した。10日分の食料とその倍のウイスキーを買い、あとはスパゲティと缶詰がほとんどだった。その頃ぼくはスパゲティとマヨネーズと醤油があればあとはなんにもいらない、というタイドを貫いていたので買い物も簡単だった。いざとなればアザラシを捕まえて食う、という道がある。北極圏のイヌイットの生活を見ていてアザラシのステーキに強い関心があり、できれば自分でさばいてみたかった。
■「快晴のち霰5万個」の過酷な島
アムチトカには旧日本軍が作った滑走路があるという。それだけの情報で飛行機はとびあがった。
「コールドベイをでたら3層になっているブリザードで何もみえないからその先のエーダックという島に降りることに変更する」と機長は空中にあがって15分後ぐらいに言った。
「あの機長はさっきおれらのプレハブホテルのバーで見たけどあきらかにバーボン満杯、という顔をしてたぜ」
仲間が言う。「でも機長にはなにもさからえないからなあ」
我々の不安はあたってくる。着陸したのはセイミヤというところだった。目的地に接近しているのか遠ざかってしまったのかおれたちにはまったくわからない。
漂流者のたどりついた島に行くのは現代でも大変なのだ。
結局1時間ぐらいかかって雪と氷が待っている荒涼とした島があらわれた。日本軍が40年ぐらい前に作った滑走路は上空からみてもかなりアスファルトが上下に波うっているように見える。春のさざ波の海と間違えて降りていくんじゃないよ。
エイヤッと着陸してから滑走路のどこかが陥没したとしてもおれたちはそれでおしまいだ。
機長はかなりの低空飛行をして40年前に作った滑走路を検分しているようだ。地上係員というのがまったくいないのだからすべて降りていくほうの自己責任だ。
ぼくは機長の斜め後ろにいたのだが機長の横顔が汗で光っていた。何回かタッチアンドゴーをやって「もういいや、勝負!」という感じで飛行機は運命をきめて降りていった。いそいで我々のテント、寝袋、食料をおろし、チャーター機はまるでそこでモタモタしていると滑走路全部が陥没してしまう、というような慌ただしさで帰っていった。約束の日にちゃんと来てくれるだろうか。もちろんどちらにも無線機はない。
すぐにテント(冬山用)を張ろうとしたがこの島の風は一定方向から吹いてくることがなく3、4人用のテントを張るのに1時間もかかってしまった。ちょっとしたものを落とすとすぐ突風でどこかにもっていかれてしまう。そのうちテニスボールぐらいはありそうな雹が降ってきた、というより落ちてきた。あたるとあぶない。
3日もするとわかってきたが、この島に天気予報というものがあったらこうなる。
「今日は曇りときどき晴れかと思うとすぐに雨。しかしたちまち回復するがあっという間に雹もしくはデタラメ方向から霰5万個。そのうちいきなり快晴だが間もなく豪雨になるでしょう。東西南北の風、風力さまざま」
■放射能入りの水筒を手に無人島を歩く
重くなるので水はまったく持ってこなかった。核実験で島の形が変わり、いままでなかった山のてっぺんに湖ができているという情報があった。雨が多いから沢山の小川が流れている。それを飲むことにしていた。ただし飛行機をアテンドしてくれたアラスカ野郎が言っていた。「当然ながら放射能でジイジイ鳴るところもあるよ」
光太夫の頃にはなかったものだ。そこでめしをつくるために水を汲むときガイガーカウンターで一応計測する。かなり反応があったけれどだからといってどうしていいかわからない。
「よおく煮沸すれば大丈夫なんじゃないの」などといって飲んだり料理につかったりしていた。200年前の漂流民のやり方でいくことにした。
翌日から放射能入りの水筒を持って我々7人は『北槎聞略』に書かれているらしいところを地形を見ながら調べて歩いた。
クルマというものが一切ない無人島だ。簡単な撮影機材と飲み物を持って行ったが食べ物は入れものがなく、みんな気持のどこかしらでここに着くまでどこかで食い物を売っている店があるんじゃないか、と思っていたようだ。
その日もあいかわらず5分ごとに天気がかわるような一日だったが、湖と湾はあきらかに水面の色が違うのですぐわかった。湾にはアザラシやラッコがのんびり浮かんでいる。このアムチトカにはロシア人がラッコ、アザラシ、トドなどを島人たちにとらせ、煙草や木綿、皮船を作るために用いる牛や馬の皮などと交換、というかたちの貿易をしていた。光太夫はやがてそういうロシア人らと出会うのだがさすが文明国の人なので漂流者に接する態度も親切で、なんとか日本人の帰国に役だてればという働きをしてくれた。しかし言葉が殆どわからないのでそういう親切が本格的に通じるにはまだ時間がかかる。
ロシア人らは光太夫らを倉のなかに泊まらせた。そこには越冬用に蓄えた干し魚、雁、鴨などがたくさん入っていたので、あまりの臭気に耐えがたかったらしい。
アムチトカは歩いて回るにはあまりにも広すぎるので我々探索隊は確実に見ておくべきところをまずはじめに探訪するようにした。
そのひとつはアレウト族の住居だった。これは注意して見ていくと土手の下の斜面などでわりあい簡単に見つかった。洞穴の上に流木を使ったのだろう細い丸太をならべ、その上に蔓性の草などを葺いてあったが注意しないと落とし穴のような屋根だった。獣があらしてしまったのか、その中には人の住んでいた跡のようなものはみつからなかった。
神昌丸が難破した場所らしきところも見にいった。岩だらけの小さな岬状のところがあり、その近くに洞穴があった。
■「尿樽を酒樽と勘違い」厳しい毎日の漂流記にも笑い話
『北槎聞略』に興味深い話がある。島に着いてしばらくして光太夫は神昌丸を見にいった。神昌丸は錨を擦りきらせてしまい暗礁に触れ底に穴をあけて船の積み荷の殆どが流失してしまったようだった。光太夫はちからをなくし、疲れてしまって近くの洞穴に身を横たえているとやがて寝てしまった。夕方ちかく、なにやら騒々しい音や声が聞こえる。
なにごとか、と思って覗いてみると水没した船のなかからロシア人が日本酒の樽をみつけてきて、それをみんなで飲んで大騒ぎをしているのだった。その様子をアレウト人も見ていて、自分たちも同じものを、と樽を引っ張りだしてきた。そうしてみんなでそれを急いで呑みはじめたのだがたちまち嘔吐し、ぜいぜい吐きだしている。よく見るとその樽はシケのときにふなべりからはできないので便器がわりに使っていた尿樽だったのである。厳しい毎日が綴られている漂流記だけれどときにこういう笑い話も含まれているとなんだかホッとする。
■流木から船を造り、カムチャツカへ
しかしこの想像を絶する気象変化の激しい島も、慣れてしまうと変化というのはそれだけのことで、結局はなんの希望もない打ち捨てられた絶望の島なのであった。我々はたった10日間という短い期間なので毎日あちらこちらに出向いて忙しかったが、それは(何もおきなければ)コールドベイからの迎えの飛行機がやってくることになっているからである。でも必ず迎えの飛行機がやってくるとは実はまだ何の保証もない。
それでも相変わらず「スパゲティのマヨネーズと醤油かけ。コンビーフを添えて」が基本のめしが続いているのだからすまないなあ、と思うようになった。買い物を頼まれたぼくがいまひたすら気にいっているのだから主食はそれだけであとはステーキなどを個人的に焼いている。ぼくはデカナベに毎晩1キロのスパゲティを茹でているだけだった。それを食うと眠くなるまでウイスキーを飲んでおしまい。夕食が単調だからだろうか、夜はあきてしまってウイスキーになるのだった。
光太夫たちはこのなにもない島に4年間いた。そのあいだに7人の乗組員が壊血病などで病死している。この島に漂着する前にすでに1人亡くしているので神昌丸の乗組員は9人になっていた。
光太夫らはときどき流木が独特の潮の流れを作っている湾にでかけている。我々が米軍から貰った地図にセントマカリオウス湾というのがあり、光太夫らが書いた簡単な地図とそこが一致する。
行ってみると本当にそこは夥しい数の立派な流木が漂着していた。光太夫らの神昌丸が漂着してきた方向と一致する。
我々はそこにグイと突き出た岬の先端に行ってケルン(積み上げた石)をつくり「望郷岬」と名付けた。そっちの方向が日本なのだ。しかしそこはやがて「挑み岬」というふうに変えてよぶことになった。
光太夫らが漂着して3年目に、ロシアから来ているニビヂモフらの毛皮買い付け人が故国に帰還する船がやってくることになっていたけれど、この島は果てしなく恐ろしくそして残酷なのであった。ロシアから迎えにきた船は湾内に入ると荒波に翻弄されて転覆。ふたつに割れてしまう。
絶望したニビヂモフはその絶望を怒りに変えて、光太夫らに話をもちかけたらしい。
「セントマカリオウス湾に堆積している夥しい流木を使って新しい船を一緒につくろうではないか。海峡を越えて向かいにあるカムチャツカまで渡ればあとは地続きなので何とでもなる。協力してそこまで脱出しないか」
それは光太夫たちにとっても非常に魅力的な話だった。ロシア人25人に光太夫ら日本人漂流民。それに地元のアレウト人も船建造の手伝いに加わってくれた。
『北槎聞略』をベースに書かれた井上靖の『おろしや国酔夢譚』(文春文庫)には、この底無し沼のように鬱屈した島で、光太夫らが漂着以降はじめての希望に満ちて積極的な計画とその仕事ぶりについて邁進するさまをこう書いている。
「ロシア人たちは破船した帆船の船具の収容に取りかかり、日本の漂民たちは潮に半身を埋めたまま腐りつつある神昌丸の船体から古釘を抜きとる作業に取りかかった。そうした仕事が終ると、あとは全員が手分けして周囲七里の島の海岸線を経廻って漂木という漂木を集めた。島には木らしい木はなかったので、船材は専ら漂木に頼る以外仕方なかった」
船の材料集めが終わったのは9月のはじめで、ただちに造船仕事を開始して冬の間は地下の穴蔵住居にもぐっての作業が続けられ、船が竣工に近づいたのは翌年6月のおわりであった――とあるので流木から船造りに要した期間はたっぷり10カ月かかっていたのだ。
『北槎聞略』によると、積載量600石ほどの船が完成した。ロシア人25人、日本人9人が乗船し、ラッコ、アザラシ、トドの皮、食肉としての干した魚、干し雁などを積み込んだ。
■極寒の地では食わず嫌いは死を招く
天明7年(1787年)7月18日にアムチトカを出航し、1400露里を越えて翌8月23日、カムチャツカ(の一端)に到着した。五、六十あまりの人家があった。磯辺にはパラッカといって、布でかやのように作った日除けを張ってこの土地に勤務するロシア人の妻子がヤゴデという草の実を採っていた。光太夫は郡官の家に泊めてもらい、他の8人は郡官の書役の家に泊められそれぞれ食物を支給された。到着した夜はチェブチャという干し魚と、白酒のような汁にトラヴァ(草の名。不詳)の実をいれたものを錫の鉢に盛り、食べるためにクマデのようなもの(フォーク)と小刀、大サジを与えてくれた。この2品と麦の焼き餅(パンのこと)はロシア人が日常的に食べるものであった。
宿の老女が朝と夕方に小さな桶をもって牛小屋のなかに入るので不審に思って磯吉が何をしているのかとそっと様子をみると汚い小屋にいる1頭の牛から1升5合ほども乳を絞り取るのを見て「あの白いあまい汁はきたならしいところからとってくる」としきりに言いふらしたのでその後誰も「動物関連のものは何も口にしない」といってそれらはみんな残してしまうようになった。
しかしここに5カ月ほど逗留しているうちに麦粉は食べつくし魚の干物も底をついた。このような食料不足になっているうちに与惣松と勘太郎と藤蔵があいついで股から足まで青黒く腫れあがらせ歯茎が腐って死ぬ病に倒れた。
郡官の属吏は「あなたたちは意味もなく乳や牛肉を食べないが、これから飢饉になっていくのにああいうものを食べて体力をつけないと季節をこえられない」と説教し、それ以降磯吉たちみんなは動物のものも食べるようになった。
■長く辛い絶望にかいま見える希望の旅の片鱗を体験した
5月になり川の氷がなくなるとバキリチイ(蝦夷の方言でコモロ、越後では糸魚、イトヨリダイ)の小魚が川の色が変わってしまうくらい押し寄せてきた。網でとって水煮にして食べると美味なること例えようがなかったという。これらが少なくなると今度はチェブチャという魚が遡行してきた。魚とりは主に女の仕事でこれも網で1日で3、400尾はすくいあげた。やがてこれが去ると大きな鮭がもみあうように鰭をひからせて遡行してくるのである。
天明8年(1788年)6月15日、光太夫たちはカピタン(下郡官)のチモフェイ・オシーポヴィチ・ホトケーヴィチに連れられてその地をはなれチギリというところにむかった。そのときの船は丸木をくりぬいたものでそこに光太夫ら日本の漂流民と、ロシア人15人が3、4隻に分乗した。
チギリからオホーツクへはさらに乗船者が増えたので、400石ほどの帆船になった。しかしこの人数にしては積載食料が足りず、なんとか口にできるのは水ぐらいで一度チェレムチャ(松前ではアイバカマという行者ニンニクに似た植物)の塩漬けだけが出てきたので一同大いに困って、脱走しようかという話が出てくる頃にやっと目的地のオホーツクに着いた。
しかし、この残された6人の日本人漂流者は、これで無事帰還というわけではない。むしろ位置としては日本よりさらに遠のいてしまったのである。これからまだ数年、彼らの帰郷への長く辛い絶望と慟哭、ときおりすらりとかいま見える希望が織りなす闘いがはじまる。
我々はロシアをいく漂流民、とりわけ日本人の殆どの人が体感したことのない零下50度60度などというシベリア原野への流浪の旅の片鱗をほんの2カ月間だが、生身で体験したのである。
■マイナス50度の地では「水を飲むと死ぬ」
カムチャツカからの船で光太夫らがユーラシア大陸に上陸した地はヤクーツクであった。
そこで我々もヤクート自治共和国(当時)の首都ヤクーツクにモスクワから飛行機で行った。イリューシンという独特のキーンという音をたてるジェット旅客機に乗って9時間。驚いたのはシートベルトがない席もあるし自分の席そのものがない(立ちのり、実質的にしゃがみ座りのりの)客が十数人いることであった。
モスクワはマイナス20度。ロシア人は今日はナマヌルイ、と言っていた。着陸したヤクーツクの空港はマイナス48度であった。
同じ地で200年前にカムチャツカからやってきた大黒屋光太夫をはじめとした日本人漂流民をご苦労さまでした、と心からお迎えする心境だった。
光太夫らがオンボロの手作り船でこのヤクーツクに到着したときと少し季節が違っていたが、当初17人いた漂流者がここにたどりつくまで次々に死亡し、今は6人しかいない。しかもさきほど書いたように故郷からはさらに遠のき、ロシア政府からの帰国の許しはまだ出ていない。
光太夫の不屈の闘志と努力による日本帰郷へのあらゆる糸口をたどる苦難の10年間はこれからがもっとも内容の濃い血みどろの闘いになるのである。
かれらの想像を絶するようなマイナス50度などという原野でのキビツカ(馬橇(そり))による移動や、馬での移動などぼくも凍傷にやられながら闘ってきた。原野での拷問のような生きるために食べる体験で、一番驚いたのは「水をのんだら死ぬ」という地元の人からの本気の注意だった。体のなかにあまりにも冷たいものが入ってくると臓器が持たないらしいのだ。この頃から三十数年後にぼくは同じ場所に行きついたが、やはり水をそのまま飲むと死ぬといわれた。
「嘘だと思ったらやってみろ」
と、いわれた。少し考え、嘘だと思わないからやらない、と答えた。

気温もマイナス50度などになると飛んでいる鳥が落ちてくる。人間は空中で口をあけるのが辛くなる。野外食に二度焼きのパンなどあたえられても芯まで凍っているからだろうか持って重たい、ということも驚きだった。重たい野外のパンを食べるには狼の歯が必要だ、とも言われた。でも胃のなかになにか入れないとひたすら体力は落ちていく。このジレンマが辛かった。
■黒毛の馬も汗が凍って白馬に変わる
その頃、ヤクーツクの外を歩く人は必ず毛皮の外套をつけ皮の帽子を被り、狐の皮の「そこなしぶくろ」と呼ばれるものに両手を差し込んで、鼻から下を覆って歩くのである。こうでもしないと凍傷にかかり、そうなると迅速かつ的確な治療をしないかぎりどうかすると鼻や耳が落ち、頬のあたりがただれ落ちてしまうから用心しろ、といわれた。
『北槎聞略』にはキビツカの寒さのことが書いてある。馬車に客車がないタイプのものでは牙のような向かい風にたちむかわなければならなかった。
それよりは乗っているほうも絶えず体を動かす馬での移動のほうがまだ楽だった。
けれど驚いたのはぼくが乗った馬は間違いなく黒毛だったのだが30分ほど走らせて小休止するときに降りたら乗っていた馬はまったくの白馬になっていたことだった。馬はいつでもハダカであり、マイナス60度でも50度でも走ると汗をかく。汗は全身の毛について瞬時に凍る。そうして束の間での変身。夢のような白馬の誕生であった。

こんなふうに極寒のシベリアを2カ月ほどオロオロ動き廻っているうちに光太夫の残していった一冊のノートを見せてもらった。
光太夫はもうロシア語はなんでも理解し、なんでも書けていた。あちこちに「憎むべきはベツボロドコ」という日本語の怒りのこもったなぐり書きがいくつもある。この悪徳の政治家がぺートルボルグにいるエカテリーナに帰国嘆願にいかせて下さい、という光太夫の請願をことごとく闇でつぶしていたのだった。
それから別のページにもっと優しい筆致でひっそりと「おしま」という名前がある。勿論これも日本語である。
漂流10年後に光太夫は生き残った磯吉と2人でロシア船で日本に送りとどけられる。
17人いた乗組員は13人が壊血病などで死亡。2人がロシア正教に帰依してロシアに残留。
光太夫は帰国後ただちに江戸に留めおかれ、蘭学者、桂川甫周の長い長い時間をかけた、つまりは「調書」をとられての幽閉が続き、その後、一時帰郷した。
文政11年(1828年)4月。光太夫は御薬園にて死去。享年78歳。
----------
作家
映画監督。1944年、東京都生まれ。辺境の旅人としてルポの執筆、ドキュメンタリー番組などに出演。90年『アド・バード』で日本SF大賞受賞。『ぼくは眠れない』(新潮新書)など著書多数。
----------
(作家 椎名 誠)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
カムチャツカ半島 ベズィミアニィ火山で噴火 噴煙は約1万2000m
ウェザーニュース / 2024年7月25日 9時0分
-
西條奈加氏『バタン島漂流記』インタビュー「人格者よりも欠点がある人の方が面白いし、ロマンよりも生活感を私は書きたいんです」
NEWSポストセブン / 2024年7月21日 16時15分
-
東日本大震災から9年かけて気仙沼から沖縄へ―― 途方もない道程を経た漂着物に注目「絶句した」
ねとらぼ / 2024年7月16日 20時30分
-
漂着木造船の船体の一部にハングル文字のようなもの 北海道・知内町
HTB北海道ニュース / 2024年7月5日 22時34分
-
「日本の物じゃない」木造船漂着 船名や国籍記載なし 海藻など付着、長期間漂流か 北海道・知内町
HTB北海道ニュース / 2024年7月4日 19時16分
ランキング
-
1ゴミ収集車の中から作業員とみられる男性1人の遺体が見つかる ペットボトル回収中に誤って巻き込まれたか
CBCテレビ / 2024年7月25日 9時50分
-
2当時小学生の2人に賠償命令 学校のグラウンドで女性にぶつかる
毎日新聞 / 2024年7月25日 17時0分
-
3米大統領選「確トラ」から一転…期待高まるハリス旋風 “不人気”から破竹の勢いのナゼ
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月25日 15時3分
-
4「みんなずっと吐いているすごい光景」下船した乗客が語る…航行不能の高速ジェット船 出発から約22時間 ようやく伊豆大島に到着
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月25日 10時6分
-
5遺族厚生年金、5年給付に=子なし現役世代、男女差是正―厚労省
時事通信 / 2024年7月25日 15時41分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











