「だからどこもタイトルが似ている」ネットメディアが"見出し詐欺"に使う5つの手口
プレジデントオンライン / 2021年8月19日 10時15分
※本稿は、石戸諭『ニュースの未来』(光文社新書)の一部を再編集したものです。
■インターネットと新聞では見出しの技術が異なる
インターネットメディアの世界では、ニュースに「共感」の押しつけが持ち込まれようとしています。的確に感情にアプローチし、人々がどのようにクリックするのか、どのような中身でシェアするのかを追求しています。これは新しいこと、良いニュースの追求ではありません。どれだけページビュー(PV)を稼げるか、どれだけSNSでシェアされるかの競争にすぎないのです。競争の行き着く先は「良いニュースとは数字が取れるニュース」ということになります。
数字を取るために必要な感情を揺さぶる技術は、見出し論争に集約されています。新聞の見出しは内容を端的に説明する見出しです。記事を書く部署と見出しをつける部署は分かれていて、最終的な見出しの決定権は見出しをつける部署が持っています。彼らの熟練の技は、記事を全文読まなくてもわかる見出し、つまり要約されている見出しをつける技術にあります。ところがインターネットではこの手法は不向きです。中身を読んでもらわないといけないのに、「要約」されていては誰も中身に興味を持たなくなってしまうからです。
インターネットの見出しはいかに読んでもらうか、シェアしてもらうかという観点から発展してきました。その到達点が人の感情にアプローチして、喜怒哀楽を揺さぶり、何か読まないとまずいかもと思わせる手法であると言えるでしょう。見出しのつけ方は大まかに五つの方法に分けることができるのではないかと考えています。事例を挙げてみましょう。
■インターネットの世界に「神」があふれかえるワケ
第一に、取材先が言ったもっとも強い言葉を抜き出す方法です。架空の記事から見出しを作ってみましょう。それはたとえば、【「東京の犯罪は増え続ける」 防犯のプロが明かす地下鉄の死角】といったものです。あれ、どこかで読んだなという印象を持つ読者は多いのではないでしょうか。この手の見出しは、同質的な人々が集まる空間(たとえば政権支持/不支持、政策の賛成派/反対派)でシェアされるために必須の手法と言えます。人間の言葉は共感を集めるからです。ただし、リスクもあります。同質的な空間でシェアされる以上の広がりを見こみにくくなってしまうことです。
第二に、一時期大流行した「?」をフックに使う方法です。【なぜⅩは若者に支持されるのか? すべてを変えたYという革命】といった感じでしょうか。一体何が理由なのかな、と思わせてさらにワンクリックしたくなるという手法です。
第三に、感情を揺さぶる言葉を多用することです。革命もそうですが、激白、潰す、震える、独占、真相、真実、理由、激怒、酷評、激増、地獄、驚愕、損、得といった言葉を積み重ねることで、記事を読まないと乗り遅れるのではないかと思わせるのです。この手の手法で行き着く究極の言葉は「神」でしょう。インターネットの世界には多くの神々であふれかえっています。【SNSの女神が激白 フォロワー増の秘策に心震える】といった見出しです。
■パーソナルな情報を見出しに盛り込む狙い
第四に、よりパーソナルな情報を押し出すというやり方です。年齢、性別、職業に成功・失敗、注目などを掛け合わせて見出しに盛り込む。【30歳、元販売員だった私がパリコレをレポートするまで】といったものです。情報を大量に盛り込むことで、20代のときにあるブランドの商品の販売担当だった人が、転職して販売していたブランドのコレクションレポートを書いたということがわかります。転職して成功した「私」が書いたものというサクセスストーリーに年齢や性別といった情報をまぶすことで、読者との共通点をやや強引に作り出す効果があります。
第五に、口語やネット上のスラング(俗語)や流行語を効果的に織り込む方法です。【「うっせぇわ」なんて言えない 究極のかまってニャンコ】のような見出しです。これもよく見かけましたが、流行語を使うことは諸刃の剣です。「そのとき」はいいのですが、数年後どころか数日後でも、流行語から古さを感じるようになってしまい、およそ長期間読まれるニュースになるのは難しくなります。短期の暇つぶし記事にも意義はありますので、割り切って使うのならば、記事と読者との距離感を近づける効果はあります。
流行は形を変えて繰り返されていきます。ここに列挙した五つのタイプは、読者のみなさんがすでに見たことがあるような見出しばかりではないでしょうか。
■「見出しほどおもしろくなくてがっかり」経験はないか
読んでもらうことが良いニュースの定義に含まれる以上、読みたくなる見出しの競争が進むことそれ自体は歓迎すべきです。しかし、見出し自体はあくまで一つのテクニック、手段にすぎません。手段に拘泥して中身が伴わない記事が一つでも混ざってしまうと、読者が離れていくきっかけになってしまいます。もっと言えば、似たような見出しの記事であっても「信頼」を失います。
見出しで感情を刺激され、シェアしたけれど次の日にはシェアしたことすら忘れているなんてことはないでしょうか。あるいは大して中身を読まずにシェアしていることはないでしょうか。見出し先行で「おもしろそう」と思って読んでみたら、さほど良くもなくがっかりという経験はないでしょうか。こうした経験は、メディア側の手段がすでに目的化してしまっていることを意味します。
数字やシェア数の競い合いは、僕の感覚からすると地方支局で繰り広げられる特ダネ競争ととてもよく似ています。県警ネタを一刻も早く出そうと競い合う。ゲーム的な競争の先にいるのは読者ではなく、「良い結果を残した自分(もしくはメディア)」を認めてほしいという承認欲求になっているところが特に似ています。
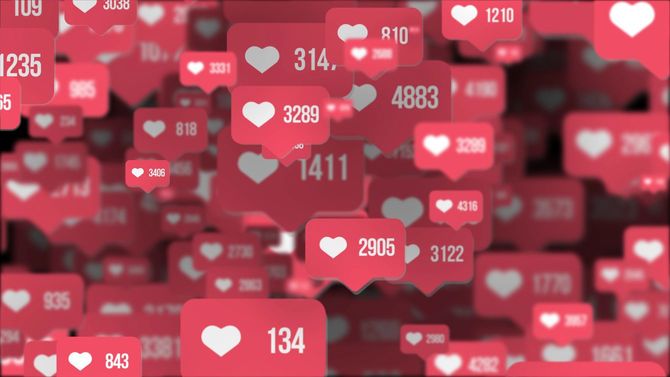
■数字主義の見出し競争は大事な信頼を傷つける
1年前にインパクトが強かった見出しであっても他に真似されて、量産されるようになればインパクトは失われます。そうなると新しい刺激を与えるため、常に新ネタを投下しなければならなくなります。
平成から令和に元号が変わるときによく見かけた、「今年は●●の終わりが始まる」「ポスト●●のキャリア」といった予測ネタの見出しはその典型でしょう。終わりが始まる、と言っておけば絶対に正解します。世の中で変わらないものはありませんし、いくつかの事例をピックアップして「ほら予測が当たっただろう」と強弁することもできます。
そもそも外れていたところで忘れられた予測は大した話題にもなりません。2018年によく見かけた「ポスト平成」論にしても、多くの議論は「ポスト●●」にかこつけて自分の願望を語っているにすぎません。良いニュースを競い合うのではなく、「数字を残せば良いニュース」という発想で感情を刺激する見出し競争は、いっときのPVと引き換えにニュースにとってもっとも大事な信頼を傷つけるというリスクを背負うのです。
■荒唐無稽な「デマ」をシェアする人たちの心理
そして最大の問題である「分断」です。感情刺激競争は、分断も加速させる。イタリア・IMTルッカ高等研究所のウォルター・クアトロチョッキらの研究「ネットの共鳴効果」(『日経サイエンス』2017年7月号)や、インディアナ大学のフィリッポ・メンツァーらによる「SNSがしょうもない情報であふれるメカニズム」(『日経サイエンス』2021年8月号)の研究が含意しているのは、人は荒唐無稽な「デマ」に対して正しいと思ってシェアするのではなく、「自分が信じる世界観」と合致するからシェアするということです。これは逆の集団にも言えます。
2020年から続いている新型コロナウイルス禍、東京オリンピック開催か中止かをめぐる議論はその典型です。分断が進行すると、意見の合致する集団同士が固まり、お互いの集団が違う意見を「敵」とみなす議論が進み、結局のところ議論は一向に進まず、現場を踏まえた実務的な解決策から遠のく議論ばかりが展開されます。

■新聞にもテレビにも出版にも価値がある
では、どうしたらいいのか。僕は長期的には、人間のバイアスやインターネットの現実を踏まえたうえで、課題を乗り越えていく方法はあると思っています。
そのために必要なのは、迂遠(うえん)ですがメディア(個人で発信している場合は個人)と読者との間で「良いニュース」の文化を創ることです。文化というのは長期の積み上げのもとに成り立つ信頼を意味します。短期的な合理性で考えれば、感情を刺激して満たすニュースを出し続ければいい。そのほうがネット上でのプレゼンスも高まります。ですが、長期的に考えれば、常に読者に刺激を与え続けるという選択肢しかなくなります。刺激は慣れていきますので、より強い刺激を与え続けないといけないということになります。
僕がインターネットメディアに移ってから自覚したのは、新聞には当人たちが考えている以上の信頼という価値があることでした。テレビにも出版にもその価値がある。彼らは歴史的に長期的に積み上げた実績があるからです。しかし、内部にいる人たちほど、その価値を信じられなくなっています。
■「良いニュース」の文化を創るには
フェイクニュースにどう対峙(たいじ)するかはインターネットとニュース業界全体の課題です。フェイクに対して、ファクトチェックをして「正しい事実」を伝えれば問題は解決するというのは、人間の認知をめぐる科学的知見から考えれば甘すぎるくらい甘い発想です。それで問題は解決するなら、とっくに解決しています。ファクトチェックは対症療法にすぎないと僕は思うのです。
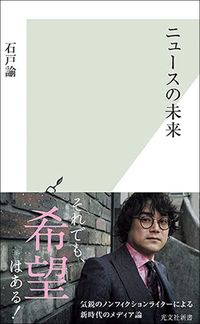
この先も技術的な進歩とともに、新しいフェイクニュースやプロパガンダは洗練されていくでしょう。そのときに、より根源から向き合うには信頼の醸成、つまり「文化」がインターネット時代のニュース業界にとっても不可欠になります。文化を創るというのは地道な積み上げです。短期的な合理性をある程度捨てるためには耐える時間も必要です。長く続けるために将来に投資をすることで、その人や、そのメディアにしかできない代替不能な価値をもたらします。これは長期的に考えれば合理的な選択であると言えるのではないでしょうか。
短期の競争に追われるのと、長期的な活動とどちらが良いでしょうか。僕はすぐに消費され尽くさない「良いニュース」を継続して世の中に送り出したいと思っています。そのような人たちが増えてほしいとも思っています。ここから先は、小手先の技術論が必要だという人たちには相当物足りないものになるでしょう。
インターネットという時代の転換点をもたらしたテクノロジーが進展する時代において、「良いニュース」とは何か、という考察を深めてきました。僕自身もこうした考えにすぐたどり着いたわけではありません。いくつかの手痛い失敗、インターネットの理想に燃えた過去と「現実」に向き合った結果としての敗北、そしてあらゆるメディアと関わるという選択――。すべての実践が学びであり、同時に「良いニュース」への試行錯誤でした。
----------
記者/ノンフィクションライター
1984年生まれ、東京都出身。2006年立命館大学卒業後、同年に毎日新聞入社。岡山支局、大阪社会部、デジタル報道センターなどで勤務。BuzzFeed Japanを経て独立。著書に『リスクと生きる、死者と生きる』(亜紀書房)、『ルポ 百田尚樹現象』(小学館)がある。
----------
(記者/ノンフィクションライター 石戸 諭)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
だから相手が「ぽかーん」となる…何でも野球や戦国武将にたとえる人に決定的に欠けている視点
プレジデントオンライン / 2024年7月6日 15時15分
-
Google検索も不要に? 検索AI「Perplexity」がスゴすぎてちょっと怖い
ITmedia NEWS / 2024年7月5日 19時16分
-
イタリアンレストランでコピーライターはメニュー名が気になる…そのときピラティス講師が持つ意外な視点
プレジデントオンライン / 2024年7月3日 15時15分
-
【元日経新聞記者へインタビュー】平均年収の高いビジネスパーソンたちが好んで読む「面白いネタ」の共通点
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月3日 8時15分
-
萩原利久、意識するのは「自分の言葉で発信する」こと 『朽ちないサクラ』では“クリーンさ”をテーマに
マイナビニュース / 2024年6月27日 19時0分
ランキング
-
1ゴミ収集車の中から作業員とみられる男性1人の遺体が見つかる ペットボトル回収中に誤って巻き込まれたか
CBCテレビ / 2024年7月25日 9時50分
-
2当時小学生の2人に賠償命令 学校のグラウンドで女性にぶつかる
毎日新聞 / 2024年7月25日 17時0分
-
3米大統領選「確トラ」から一転…期待高まるハリス旋風 “不人気”から破竹の勢いのナゼ
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月25日 15時3分
-
4「みんなずっと吐いているすごい光景」下船した乗客が語る…航行不能の高速ジェット船 出発から約22時間 ようやく伊豆大島に到着
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月25日 10時6分
-
5遺族厚生年金、5年給付に=子なし現役世代、男女差是正―厚労省
時事通信 / 2024年7月25日 15時41分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











