「情熱大陸」に出た元祖ノマドワーカーがすべてのSNSを削除することになったワケ
プレジデントオンライン / 2021年9月15日 12時15分
※本稿は、安藤美冬『つながらない練習』(PHP研究所)の一部を再編集したものです。
■たった数時間でFacebookの友達申請がパンクした
私は2010年代のはじめ、TwitterやFacebookなどの“自分メディア”を使って発信をすることで、文字通り人生が変わった一個人だ。
SNSでの発信から人とのご縁をいただき、仕事が創られ、テレビをはじめとするマスメディアに多数出演。それらの番組は毎回大変な話題となり、SNSのフォロワー数はTwitterだけでも5万人を軽く超え、毎日のようにメールや手紙、フォローが押し寄せた。
ある日、たった数時間でFacebookの友達申請の数がパンクして、「★マーク」(おそらく、1000人以上)になったこともある。
まったく無名のOLが、退職してからたった1年半で、雑誌やwebの連載を何本も抱え、時々報道番組のコメンテーターとして出演しながら、連日メディアのインタビューや対談、講演をこなす日々を送るようになったのだ。
組織に属さず、個人がスキルを武器に働く「フリーランス」という形態は、今や自由に働く人の代名詞として広く知られる。
無料Wi-Fiが設置され、コワーキングスペースが全国各地につくられ、企業にも「テレワーク」「リモートワーク」が浸透するにつれて、カフェでパソコンを広げて仕事をする「ノマドワーカー」を見かけるのも、日常の風景となった。
■全SNSを退会し、ネットの利用時間も減らした
こうした変化の一端を担えたかはわからないが、ともかく当時の私は、若者世代を中心に「生き方」と「働き方」の意識をアップデートし、SNSでの発信を推奨する「SNSの伝道師」だったのだ。けれども、その後の数年間で、私の気持ちや考え方に大きな変化が起きた。2017年にネットから距離を置くようになり、翌年、すべてのSNSを退会。スマホには極力触れないようにして、ネットの利用時間も制限した。
理由は3つある。
1:自由な時間が減った
1日平均5、6時間、パソコンやスマホからネットにつながっていた。ネットに触れていない時間も自分の投稿に“対する”反響や反応が気になり、仕事とプライベート両面で“今”に集中しにくくなってしまう。発信することも仕事だという意識もあって、危機感を持たないまま、SNSは生活そのものになった。
2:のびのびと発信ができなくなった
フォロワー数が増え、認知度が高まるにつれて、以前のような気ままな発信ができなくなった。発信には気を遣っているつもりでも、下手をすれば誰かに指さされ、最悪の場合炎上する。
大好きだったはずのSNSが、だんだん億劫になり、一体、何のためのSNSなのだろうと感じるようになった。
3:“つくられた世界”への違和感
これには自分の発言だけでなく、誰かの発言も含まれる。当たり障りのない言葉や、小さな噓、自分を取り繕うような態度……。
そうした“大人としての振る舞い”に対しても、うんざりした。
ネット上で“本当の関係”を築くのは難しいと感じたし、ここに莫大なエネルギーを注ぐ意味が見出せなくなってしまった。
■チャンスやつながりを失うのが怖かった
とはいえ、すぐにSNSやネットの世界から離れられたわけではない。
SNSをやめるときに最も怖れていたのは、チャンスやつながりを失うことだった。
実際のところ、やめてすぐは、私の世界は限定的だった。つながりが、リアルな友人や仕事相手に限られるのだから当然だが、裏を返せば、SNSをやめれば切れる人間関係がそれだけ多いということ。
「本当のつながりとは何だろう」と、考えさせられた。
■「ネットがつながらない」という贅沢な時間
世界中どこでも、ネット網がはりめぐらされている。街中には無料で使えるWi-Fiがいたるところにあって、サハラ砂漠にすら、ネットのつながる場所があると聞く。
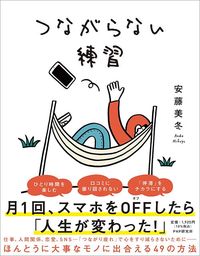
この世界では、ネットがつながらないことはもう、不便というより“貴重な体験”となりつつある。ネットがつながらない離島への旅を旅行会社が「圏外旅行」として売り出したり、スマホやテレビが禁止の宿が話題になったりするくらいだ。
私も、以前、そんな貴重な体験をしたことがある。世界一周船「PEACEBOAT」の水先案内人(船内で乗客に向けて講演をする役)として乗船したときだ。海上でも衛星回線を使えるが、料金はそれなりで回線も不安定になりがちで、まったくつながらないエリアを数日間航行することもある。
それなら、とネットを使わないことに決めた。
こうして3週間の乗船仕事は、図らずも「圏外旅行」となった。
ネットとつながらない期間が3日過ぎ、1週間を過ぎると、次第にこうした“異様な”環境に慣れてしまった。そこで思った。どうしてあんなに近況報告に忙しかったのだろう、と。
船に乗る直前までは、「パスポート片手に、空港に向かいます!」「アメリカに到着しました」「今、メキシコにいます!」と、節目ごとに画像と文章をアップしていたし、そのことに何の疑問も抱かなかった。これは仕事の一環だという意識もあった。
でも、気づいてしまった。講演の仕事がない自由時間、デッキに出て、ゆっくりと進む船が海面に残していく波の跡を眺め、青い空を見上げ、風に吹かれていると、近況報告など、どうでもよくなってくる。
船は飛行機の24倍遅く進む。
つまり飛行機が1時間で到着する距離を、まる1日かけて進むのだ。
それを非効率だと怒り出す人はいるだろうか? それと同じで、ゆっくり日常を生きる日があってもいい。
月に1日でいい。スマホを家に置いて外に出てみよう。
■戻ってきたらSNSへの熱意がしぼんでいた
図らずも「圏外旅行」となった3週間の船旅から帰国した後、SNSに向けていた熱意は急速に萎んでいった。日課となっていた近況報告や(仕事の)宣伝、オンライン上のつきあいに、以前ほどの価値を見出せなくなったからだ。
多少の影響力、発言力を得て、インフルエンサーとしての様々な仕事、そして著名人やファンとの交流を楽しんできたのは事実だ。でも、莫大な時間とエネルギーを、「これも仕事の一環だ」と自分をだましながらSNSに注ぐ現実もある。
1日6時間前後のネット生活を7、8年。「スマホ(SNS)依存」そのものだ。いや、「承認依存」「つながり依存」と呼ぶべきか。
発信を楽しみにしてくれる人や仕事のことを考えると、迷いが出る。けれども最後は、「ネットのない世界に生きよう」と、本心に従うことにした。
■「1日2時間機内モード」から始めていった
とはいえ、長く依存してきたSNSと訣別するのは大変だった。
「Facebookはもう見ない」と誓っても、“パブロフの犬”のように朝起きればスマホに手を伸ばし、アプリを開こうとしてしまう。
同世代で頑張っている友人たちの華々しい投稿を想像すると、「私だけが立ち止まっていいんだろうか」と、急に不安になる。
SNSをやめるために約2年間をかけて、以下の3つのステップを踏むことにした。
ステップ1:時間を制限する
ステップ2:スマホからアプリを削除する
ステップ3:アカウントを退会する
ステップ1は、「時間制限」だ。手始めに、起床後の1時間と就寝前の1時間は「機内モード」にして、SNSだけでなく、ネット自体を使えないようにした。さらに仕事がオフの日は、「午前中は見ない」「午後の13時から16時までは見ない」と、オフラインの時間を延ばす。
ダイエットと原理は同じで、いきなり制限をかけると反動でやりたくなる。
だからこそ、SNSをやりたい気持ちに蓋をせず、機内モードの時間を少しずつ増やすことによって、ソフトランディングで「つながらない生活」に自分を慣らしていった。
■半年で「全アプリ削除」までたどりついた
踏ん張り続けて半年も経たつと、つながらない生活にだいぶ慣れてきたため、ステップ2「スマホからアプリを削除(アンインストール)」へ。Twitter、Facebook、Instagram、ブログと、発信で使っていた全アプリをスマホから削除した。ただしここでも、パソコンからはアクセスできるようにして逃げ道をつくった。当時の私は原稿執筆と資料作成だけはパソコンで、それ以外はスマホの利用だったため、効果はテキメン! 特定の仕事以外ではアクセスしなくなり、SNSのことを次第に忘れ、やりたい欲求も薄れていった。
最終段階のステップ3では、遂に「SNSアカウントを退会」。アカウントを退会したのは、ちょうどグループで海外視察に出発する日の朝だった。周囲の数名に「今から退会するよ」と声をかけ、断髪式のように実行。「本当にやったか〜」「この経験はいずれ誰かの参考になるね」と、様々な言葉をかけてもらったことを思い出す。日本を発つ飛行機の中でSNSと共に生きた思い出に浸りながら、「SNSのない新しい世界」への希望に胸を膨らませたのだった。
ステップ1だけでも効果はある。就寝前、起床後の1時間だけでも「機内モード」にしてみよう。慣れてきた人はステップ2、ステップ3にも挑戦してみよう。
■すべてに「いいね!」しなくていい
来たメッセージにはすぐに返信する。友達やクライアントの投稿には「いいね!」を押して、コメントや「いいね!」がついたら礼儀として返す。電話がかかってきたら、緊急でなくても折り返す──。
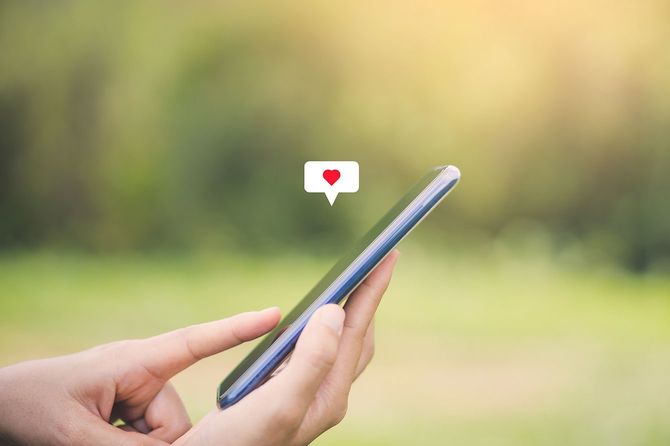
最近ではテレワークが一般化して、仕事の関係者や会社の同僚らとつながる時間が増えた人も多いだろう。休日もメールが来たり、SNSを通じて仕事の依頼や連絡が来たりすると心が休まらないばかりか、それがネガティブな内容ならなおさら、休日が台無しになったような気持ちになる。こうして「相手軸のルール」でいると、自分がどんどん苦しくなってしまう。
大切なのは、「相手軸」ではなく「自分軸のルール」を持つことだ。私はこれを「マイルール」と呼ぶ。
たとえば、「SNSの通知をオフにする」「電話は緊急の用件以外出ないと伝え、メッセージに限る」「時間を決めて、機内モードにする」といった工夫や、「2日おきに1日はFacebookを休む」「いいね! やコメント返しは親しい友達だけに限る」など。
■罪悪感は最初だけ、そのうち消えていく
こうしたマイルールを決めて、実践するのだ。できれば、知り合いには周知しておくのがいい。フリーランスなど、自分の裁量で仕事をしている人は特に、それを伝えた上で仕事を受けるようにすると、その後がスムーズに運ぶ。
「罪悪感」や「申し訳ない気持ち」は最初のうちだけで、次第に消えていく。マイルールをつくり、きちんと伝えることで、相手にも「自分はこういう人」と受け入れてもらうきっかけにもなる。
事務局スタッフのAさんは、「土日は仕事をしない」「平日の20時以降はレスを返さない」など、最初から私に対してはっきりと基準を示してくれたおかげで、お互いにストレスになることを避けられた。腹の底に抱えているものが少ないと、信頼関係も築きやすい。
こうした文化が、私たちのような個人だけでなく、会社などチームで働く人たちの間でも育っていくのを願う。勇気を持って境界線を引き、「マイルール」で動く人が増えると、お互いがより心地よく関わり合えるからだ。
自分のために「マイルール」を持とう。罪悪感は次第に消える。
----------
作家
1980年生まれ、東京育ち。慶應義塾大学在学中にオランダ・アムステルダム大学に交換留学を経験。新卒で集英社に入社、7年目に独立。本やコラムの執筆をしながら、パソコンとスマートフォンひとつでどこでも働ける自由なノマドワークスタイルを実践中。最新刊に『売れる個人のつくり方』(clover出版)、『新しい世界へ』(光文社)がある。
----------
(作家 安藤 美冬)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
スマホばかりで本が読めない...。なぜ仕事と読書の両立は難しい?現代人の"あるある"悩みに迫る。
東京バーゲンマニア / 2024年7月12日 18時0分
-
ボケ防止には「匿名でネットに書き込み」は悪くない…脳神経内科医が「高齢者こそSNSを使うべし」というワケ
プレジデントオンライン / 2024年7月2日 10時15分
-
「無茶な話だよ」《教え子とデート報道》安藤美姫の“意味深”投稿が物議、過去にも“2ショット削除”
週刊女性PRIME / 2024年6月27日 18時30分
-
スマホ通知の"ダイエット"する人としない人 自分にとって「本当に必要な通知」を考えてみる
東洋経済オンライン / 2024年6月27日 12時30分
-
LINEで勝手に友だち追加されたときの原因と対処法
マイナビニュース / 2024年6月25日 16時40分
ランキング
-
1CoCo壱「わずか3年で3回目の値上げ」は吉と出るか 過去の値上げでは「客離れ」は見られないが…
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 17時30分
-
2iPhoneの「ホームボタン」が消えていく深い意味 「心の支え」だった人はどうすればいいのか?
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 13時0分
-
3「日本でしか手に入らない」カレーパン、なぜ外国人観光客に人気? チーズ入りカレーパンに「私の心臓は高鳴った」【Nスタ解説】
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月15日 22時0分
-
4「離職率が低い大企業ランキング」トップ100社 単独従業員が1000人以上の会社を対象に調査
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 6時0分
-
517年ぶり消費増税、強気の「展望リポート」に3人反対=14年上半期・日銀議事録
ロイター / 2024年7月16日 9時8分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











