「政治家とマスコミがズブズブのままでいいのか」日本の常識は海外の非常識と断言できるワケ
プレジデントオンライン / 2021年10月6日 11時15分
※本稿は、牧野洋『官報複合体 権力と一体化するメディアの正体』(河出書房)の第3章「リーク依存型取材の罪」の一部を再編集したものです。
■目の前で犯罪行為を目撃したのに、報道しない記者たち
2020年5月、週刊文春のスクープによって権力とマスコミの癒着体質が白日の下にさらされた。新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言が出ているなか、マスコミ関係者3人が東京高検検事長の黒川弘務と賭けマージャンをしていたというのだ。
黒川は次期検事総長の最有力候補といわれていた。検察権力のトップに最も近い位置にいたわけだ。一方、マスコミ側は産経新聞の司法担当記者2人と朝日新聞の社員1人。朝日の社員は司法担当記者時代に黒川と取材を通じて知り合いになっていた。
マスコミ業界には逆風が吹いた。記者は目の前で犯罪行為を目撃していたのに、なぜ報道しなかったのか。権力に密着取材しているのではなく権力と癒着し、何も報道できなくなっていたのではないか。
マスコミ業界の独自基準に従えば、3人は間違いなくスター記者だ。検察ナンバー2と定期的に雀卓を囲むほど権力に食い込んでいたのだから。「特ダネ記者の中の特ダネ記者」であり、社内では肩で風を切って歩いていたはずである。
■ジャーナリズムに欠かせない批判精神を失ってしまう
事実、日本で最も有名なジャーナリストともいえる池上彰も筆を執り、3人の食い込み力に感嘆している。次は朝日のコラム「新聞ななめ読み」からの引用だ。
〈黒川検事長という時の人に、ここまで食い込んでいる記者がいることには感服してしまう。自分が現役の記者時代、とてもこんな取材はできなかったなあ。
朝日の社員は、検察庁の担当を外れても、当時の取材相手と友人関係を保てているということだろう。記者はこうありたいものだ〉
個人的にはがっかりした。日本を代表するジャーナリストがいわゆる「アクセスジャーナリズム」を肯定するような発言をしている、と感じたからだ。
アクセスジャーナリズムとは、記者が権力側に気に入られ、特別に情報をリークしてもらう手法だ。「リーク依存型取材」と言い換えてもいい。少なくともアメリカの報道界では邪道とされている。
権力側との「アクセス(接近)」を重視するあまり、ジャーナリズムに欠かせない批判精神を失ってしまう――これがアクセスジャーナリズムの本質である。日本では司法記者クラブを筆頭に権力側に配置された記者クラブがアクセスジャーナリズムの一大拠点として機能している。
■産経新聞は権力への密着取材継続を表明
もちろん池上は手放しで3人をたたえていたわけではない。「上司から言われたことは忘れられません。記者の心得として、『密着すれど癒着せず』という言葉でした」と付け加えている。
このような考えは異例でも何でもない。日本の大手メディアで働く記者の多くも同じ思いを抱いている。事実、賭けマージャン発覚後、既存メディア側からは次のような発言が相次いだ。
〈記者は権力の懐に飛び込まなければ駄目。密の関係を築いておかなければディープは情報を取れない〉
〈賭けマージャンは駄目だけれども、一緒に酒を飲みに行ったり、ゴルフに出掛けたりするのは必要。本音で話してもらうために〉
〈親しくなるのは大切。本当に報じるべきニュースを聞いたときには、相手を裏切ってでも書く覚悟でいればいい〉
当事者である産経は賭けマージャン発覚後、「極めて不適切な行為であり、深くおわび申し上げます」としながらも、「報道に必要な情報を入手するために取材対象者に肉薄することは記者の重要な活動」と書いている。
つまり、緊急事態宣言と賭博行為という2点で記者の行為は不適切であるけれども、取材先との密着取材は必要不可欠である、という判断を示したのだ。「権力との密着取材は今後も続ける」と表明したといえる。
■密着と癒着は紙一重で線引き難しい
「密着は必要だけれども癒着は駄目」という考え方は一見すると正論だ。だが、実際には矛盾している。密着と癒着は紙一重であり、線引きは一筋縄ではいかないからだ。
記者は癒着しないように取材先と一定の距離を置くよう求められているというのに、ディープな情報を得るために密着取材しなければならない――。とんでもなく難しいだろう。
ディープな情報を得るために「仲間」を装って取材先の懐に飛び込み、最後に「実は記者として近づいていた」と言って裏切ればいいのだろうか。言うまでもなく、ここには報道倫理上の問題がある(報道以前に人間としての倫理上の問題もある)。
ならばアクセスジャーナリズムを否定すればいいのではないか。権力側とお酒を飲んだりゴルフしたりするのを一切やめ、常にオンレコ(記録あり)で正々堂々と取材するのだ。
こうなると、マスコミ業界の古参記者の間から必ず反論が出てくる。記者は権力側からディープな情報を取れなくなり、国民の知る権利に応えられなくなる、というのである。そんなことはない。権力に密着しなくても――正確には権力に密着しないからこそ――ディープな情報を取れるのである。
■アマゾン創業者ベゾスに密着取材せずに特報
海外に目を向ければお手本はいくらでもある。例えば2021年3月中旬にニューヨーク・タイムズに載った調査報道「アマゾンはどうやって労働組合をつぶしたか」だ。
当時、アマゾンでは初の労働組合結成の是非を問う従業員投票が進行中であり、世界的な注目を集めていた。そんななか、同紙の独自取材によって、アマゾンによる強圧的な組合つぶしの歴史的構図が明らかになったのである。
コロナの感染拡大を背景にアマゾンの物流倉庫で働く従業員は過酷な状況に置かれていた。何千万人ものアメリカ人にとってアマゾンは必要不可欠なツールになり、倉庫内の従業員(全米で合計50万人以上)は感染リスクにさらされながら限界状態で働かされていたのだ。
ニューヨーク・タイムズはどうやってスクープをモノにしたのか? 創業者兼最高経営責任者(CEO)のジェフ・ベゾスに密着取材して真相を暴いたのだろうか?
私は非常勤講師を務める早稲田大学大学院で、ジャーナリスト志望の大学院生に聞いてみた。すると、異口同音に「ベゾスに取材しても駄目。従業員側に取材して情報を集めたはず」との答えが返ってきた。正解だ。プロのジャーナリストでなくとも答えは簡単に分かるのである。
記事中で同紙は取材の経緯を明らかにしている。それによれば、内部文書を入手するだけでなく従業員側に密着取材してウラ取りを進め、経営側による脅しの実態を暴いている。
同紙は明らかにベゾスには直接取材できていない。それどころか、公式取材をすべてはねつけられている。常に「ノーコメント」という対応しか得られていないのだ。出入り禁止状態にあったといえよう。
仮に記者がベゾスと一緒に酒を飲んだり、ゴルフを楽しんだりする関係を築いていたとしよう。ディープな情報を得て国民の知る権利に応えられただろうか。
早稲田大の大学院生が見抜いたように、酒を一緒に飲んでいるからといって、組合つぶしての実態についてベゾスが赤裸々に語るはずがない。アマゾンの不利益になるからだ。むしろ「組合=悪」という図式を持ち出して、猛烈に記者を丸め込もうとするだろう。
■国務長官をファーストネームで呼べる記者は無用
アメリカで調査報道の金字塔とされているウォーターゲート事件特報を振り返ってみよう。時は1970年代前半。民主党本部への盗聴・侵入事件を端に発した一大政治スキャンダルであり、最終的にはニクソン政権が退陣に追い込まれている。
ウォーターゲート事件をすっぱ抜いたのは、ワシントン・ポスト紙のボブ・ウッドワードとカール・バーンスタインだ。2人も20代後半の若手記者であり、ワシントン政界の権力中枢からは相手にされていなかった。
当時の同紙編集主幹ベン・ブラッドリーは「国務長官ヘンリー・キッシンジャーをファーストネームで呼べるような記者は、ウォーターゲート事件の報道では無用の長物だった」と語っている。賭けマージャン式の密着取材を頭から否定しているのだ。ここからは本物の特ダネは生まれないと考えているのだろう。
ちなみに、2人の取材源は「ディープスロート」として紹介されるだけで、謎に包まれていた。しかし事件から数十年後になってディープスロートの正体が明らかになった。事件当時の連邦捜査局(FBI)副長官マーク・フェルトだ。
誤解のないように一つだけ指摘しておきたい。フェルトへの取材は権力への密着取材とは異なるということだ。リトマス試験紙となるのは、正体がバレた場合に取材源が組織に報復されるかどうかである。フェルトは明らかに報復される状況下に置かれていた。だからこそ何十年にもわたって取材源秘匿の原則が適用されたのである。
■エンロン事件、経営トップに毛嫌いされて大スクープ
アメリカ史上最大の粉飾事件として2001年に話題になったエンロン事件はどうだろうか。粉飾を暴いた記者は同社のCEOジェフリー・スキリングや会長ケネス・レイに密着取材していたのだろうか。
密着取材どころか毛嫌いされていた。
エネルギー大手エンロンが粉飾決算によって株価をつり上げている可能性をいち早く指摘したのは、有力経済誌フォーチュンの記者ベサニー・マクリーンだ。高成長企業の代表格としてエンロンがウォール街でもてはやされていた真っただ中の2001年3月に、「株価が実態を反映していない」と書いて経営陣の逆鱗(げきりん)に触れている。
マクリーンは投資銀行ゴールドマン出身という経歴をフルに生かした。エンロンの財務諸表をしらみつぶしに分析したほか、エンロン株を持つヘッジファンドなど機関投資家にも幅広く取材。その結果、「事業内容は複雑怪奇。どうやって利益を出しているのか理解不能」と断じたのである。
エンロン経営陣はマクリーンを徹底的に排除しようとした。メディア批評家のハワード・カーツによれば、CEOのスキリングは彼女からの問い合わせに対して「君はちゃんと調べずに取材しており、記者倫理を欠いている」と言い、電話をたたき切った。会長のレイはフォーチュン編集長に連絡を入れ、「エンロン株急落でもうけようとしている空売り筋に彼女は利用されている」などと直接抗議した。
そんな圧力にも屈せずにフォーチュンはマクリーンの記事を掲載した。最終的には記事の正しさが証明され、同年12月にエンロンは経営破綻に追い込まれた。
■アクセスジャーナリズムはPRと同じ
アマゾン組合つぶし、ウォーターゲート事件、エンロン事件――。権力への密着取材とは無関係に生まれたスクープという点で共通する。
だとすれば、マスコミは今すぐにでも「権力への密着取材からスクープが生まれる」という幻想を捨て去るべきだ。
アクセスジャーナリズムが根付くと、記者は事実上政府や企業のコントロール下に置かれてしまう。ネタ欲しさのあまり相手に都合が悪いことを一切報じなくなり、政府や企業を持ち上げる「よいしょ記事」ばかり書くようになる。
記者クラブ内でいわゆる「特オチ」を嫌がる文化が根強い点も見逃せない。他社が一斉に同じニュースを報じているなかで一社だけ蚊帳の外に置かれる状況だ。そのためクラブ内ではどのメディアもこぞって権力側にすり寄ろうとする。こうなるともはやジャーナリズムではなく、事実上「政府広報紙」「企業広報紙」と変わらなくなる。
イギリスの作家ジョージ・オーウェルは「権力が報じてほしくないと思うことを報じるのがジャーナリズム。それ以外はすべてPR(広報活動)」と定義している。これに従えば、アクセスジャーナリズムはPRと実質的に同じである。
その意味では、特オチとは「政府(あるいは企業)が報じてほしい情報を一社だけ報じていない状況」である。
米ジャーナリズム専門誌『コロンビア・ジャーナリズム・レビュー』の2014年2月号によれば、アクセスジャーナリズムは取材相手に説明責任を求める「アカウンタビリティージャーナリズム」の対極に位置する。アカウンタビリティージャーナリズムは調査報道と同義と考えていい。同誌によれば、両者は次のように対比できる。
〈権力側が持っている内部情報を報じるのがアクセスジャーナリズムであり、権力側に位置する組織や人間について報じるのがアカウンタビリティージャーナリズム。前者は権力側が言ったことをそのまま読者に伝え、後者は権力側の行動を監視して読者に伝える報道形態である〉
■河野太郎が語る「風呂場の番記者」
いかにアクセスジャーナリズムが日本のマスコミ界にはびこっているのかを示す衝撃的エピソードが一つある。権力者の自宅に上がり込み、風呂場の浴槽の中に隠れる番記者の話である。
私が「風呂場の番記者」の話を聞いたのは2012年のことだ。同年、衆院議員の河野太郎が拙著『官報複合体』の単行本版を読んで気に入り、数回にわたって私との対談に応じてくれた。その中で自分の若いころを振り返り、父・河野洋平を担当する番記者の話をしたのである(父・洋平は外相や衆議院議長を歴任した大物政治家)。
対談をまとめた共著『共謀者たち』の中で、河野は「風呂場の番記者」について次のように回想している。

〈夜、父が帰ってくると、一緒に父の番記者が、ぞろぞろと宿舎に上がってきた。次々と入ってくる記者たちの革靴で、玄関は埋め尽くされた。
私はしばらく記者たちにビールやウィスキーの水割りをつくって出したりしていたが、父が記者たちと懇談している最中にひと風呂浴びてしまおうと、その場を抜けて浴室に向かった。風呂場に入り、浴槽の蓋を開けると、スーツを着て、靴を持った男と目が合った。
私はびっくりして後ずさりした。男は口に指を当て、小さく「シッ」。私も知っている記者だった。
「どうしたの、こんなところで」
「他の記者がいたら聞けない話があるから隠れている。オヤジさんも知っているから、みんな帰ったら呼んで」〉

ここには権力者との「アクセス」を求めて血のにじむような努力をしている記者の姿がある。権力者に気に入られ、耳寄りな情報をいち早くリークしてもらうためには、何でもしなければならない――。アクセスジャーナリズムから「権力のチェック役」は生まれない。
■タブーに果敢に挑戦するというスタイルを貫いている
私は河野と対談しているうちに「政治家の中では彼は問題意識も行動力も頭一つ抜けている」との印象を抱くようになった。
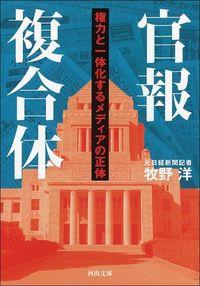
2020年9月に菅政権の行政改革大臣に抜擢され、次期首相の一人としても注目されるようになった河野。昔からタブーに果敢に挑戦するというスタイルを貫いている。
例えば、対談中には具体的な数字を示しながら、「電力業界が原発政策を有利に進めようとして、言論抑圧を狙ってマスコミに多額の広告費を使っている」などと断じていた。経産省とマスコミを敵に回しても怖くない――そんな気概を見せていた。
自分で証拠を集めて問題点を浮き彫りにするというのが河野流であり、ここには調査報道と共通する部分がある。彼にとってアクセスジャーナリズムが奇異に見えるのも当然である。(文中敬称略)
----------
ジャーナリスト
1960年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業、米コロンビア大学大学院ジャーナリズムスクール修了。1983年、日本経済新聞社入社。ニューヨーク特派員や編集委員を歴任し、2007年に独立。早稲田大学大学院ジャーナリズムスクール非常勤講師。著書に『福岡はすごい』(イースト新書)、『米ハフィントン・ポストの衝撃』(アスキー新書)、訳書に『TROUBLE MAKERS』(レスリー・バーリン著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『マインドハッキング』(クリストファー・ワイリー著、新潮社)などがある。
----------
(ジャーナリスト 牧野 洋)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
平成事件史 戦後最大の総会屋事件(14)ー大手新聞社の「前打ち報道」に特捜部長は激怒…記者と検察“異常な緊張感”
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月18日 6時0分
-
テレビ局の現役社員が描く『報道協定』 初瀬礼氏、葛藤の中でリアリティ追求「ここまでだったら」
マイナビニュース / 2024年7月16日 12時0分
-
検事長の定年延長問題に見る、日本の民主主義が「カミワキ頼み」な現状
ニューズウィーク日本版 / 2024年7月12日 17時45分
-
大谷翔平を激怒させた「新居報道」にフジ社長は謝罪したが…"迷惑取材"をやめないテレビ局の本当の問題点
プレジデントオンライン / 2024年7月11日 17時15分
-
かつて野中広務が田原総一朗に渡そうとした裏金の額とは?「いいお茶を渡したい」喫茶店で渡された紙袋の中には100万円の封筒がひとつ、ふたつ…
集英社オンライン / 2024年6月26日 8時0分
ランキング
-
1SNS投資詐欺、拠点のビル一斉捜索で8人逮捕 大阪府警、スマホ1800台超を押収
産経ニュース / 2024年7月23日 21時16分
-
2〈華麗なる一族、親子トップ2人が辞任〉報告書で暴かれた小林製薬のヤバすぎる製造管理体制…従業員が異変を報告も品質管理担当者は「青カビはある程度は混じる」記者会見は開かず逃げ切りか?
集英社オンライン / 2024年7月23日 20時6分
-
3「県民の負託、理由にならない」 堺市の永藤市長 兵庫の斎藤知事疑惑巡り突き放し
産経ニュース / 2024年7月23日 20時17分
-
4睡眠時のエアコン「つけっぱなし」と「切タイマー」どっちが快適?節電できる風量は「弱」?「自動」?
RKB毎日放送 / 2024年7月23日 20時11分
-
5「600円しかなく…ガスも電気も止められた」DV受けうつ病なったシングルマザー「生活保護」申請したのに受け付けられず 女性は知人男から殴打され死亡 遺族ら大阪市に要望書『受給できてたら死なずにすんだ可能性』
MBSニュース / 2024年7月23日 15時20分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











