「日本経済新聞を辞めてよかった」私が15年前に編集幹部と怒鳴り合ったこと
プレジデントオンライン / 2021年10月7日 11時15分
■「経営者100人に取材するように言われていただろ」
日本経済新聞社に24年以上勤めていて、怒鳴り合いをするほど編集幹部と対立したのは一度だけだった。会社を辞める半年前のことだった。15年前でもう時効だと思うので、辞めたいきさつを記しておきたい。
2006年暮れ、都内のレストラン。私は信頼する編集幹部Nと食事中だった。
「ニーマンフェローに応募したいので、協力してほしい」
ニーマンフェローとは、米ハーバード大学のジャーナリスト奨学研修制度のこと。私はいったん報道現場から離れ、もう一度充電して知見を高めたかった。だが、冷たい反応しか得られなかった。
「駄目だね。俺が直属の上司ならペケにする」
「なぜですか?」
「産業部に異動したばかり。経営者100人に取材するように言われていただろ」
当時、私は40代の半ばであり、日経産業部所属の編集委員として主にコラムや解説を担当していた。社内的にはすでにベテラン。にもかかわらず「ペケにする」と言われ、まるで新人記者のように扱われた気持ちになった。
■「経団連企業に密着取材し、もっと耳を傾けろ」
怒りを抑えられなくなった。レストラン内に大勢の食事客がいたにもかかわらず、怒鳴り合いに突入した。隣にいた若手記者一人はぼう然としていた。
ニーマンフェローを拒否されても仕方がない。すでに20代後半で米コロンビア大学大学院ジャーナリズムスクールへの留学を認めてもらっていた手前、ぜいたくを言える立場でもなかった。
ショッキングだったのは「経営者100人に取材」である。意味しているところはよく分かっていた。経団連企業に密着取材し、彼らの言い分にもっと耳を傾けろ――このようにNは言っていたのだ。
Nは直属の上司ではなかったものの、私にとっては長らく良き理解者であった。Nがいる限りは、社内でどんなに理不尽なことがまかり通っていても、日経にとどまるのも悪くない――このように私は思っていた。
それなのに経団連企業に密着取材しろとは……。はしごを外されていたのだと悟った。レストランを後にするころには、すでに会社を辞める腹を固めていた。実際、数カ月後に正式に退社の意思を表明し、翌年5月末に辞めた。
■経団連トップを刺激する記事は、忖度で締め出された
私はM&A(企業の合併・買収)やコーポレートガバナンス(企業統治)を主な分野にして活動していた。その延長線で日本経団連とぶつかることが多かった。もともと証券部に所属して投資家側の視点で取材し、大企業経営者とは一定の距離を置いていたためだ(Nは大企業を取材する産業部畑)。
問題だったのは、日経が完全に経団連――大企業中心の団体――寄りの紙面を作っていたということだ。東京・大手町の日経本社ビルが経団連ビルと隣り合わせであるように、日経本社トップと経団連トップも近い関係にあった。
となると編集局内で忖度がはびこる。経団連トップ――当時の会長はキヤノンの御手洗冨士夫――が気に入らない日経記事を目にすると、事実上のホットラインでそれが直ちに日経本社トップに伝わり、編集局内部で共有されるのだ。
結果として、経団連トップを刺激しかねない記事は忖度によって紙面上から一斉に締め出された。多くは私の記事だった。
2006年当時、経団連が毛嫌いする動きが二つあった。一つは「三角合併」の解禁であり、もう一つは「アクティビスト(物言う株主)」の台頭である。両方とも私が追い掛けていたテーマだった。
■三角合併で敵対的に買収する外資は一社も現れなかった
まずは三角合併解禁。拙著『不思議の国のM&A』(日本経済新聞出版社)に詳しく書いてあるが、当時は経団連を中心に外資脅威論が吹き荒れていた。2007年5月の会社法施行で三角合併が解禁されると、巨大外資が日本企業を敵対的に買収し、貴重な技術が海外流出してしまう――これが経団連の主張だった。
資本自由化を背景に日本企業が一斉に株式持ち合いに乗り出した1960年代に戻ったかのような騒ぎだった。「失われた10年」から「失われた20年」になろうとしているなか、外資を排除して成長を目指すような戦略は理にかなっていたのだろうか。
私から言わせればまったくピント外れだった。
第一に2005年に対日直接投資は1996年以降で最低を記録していた。国内総生産(GDP)比で2%にとどまり、世界平均の23%を大きく下回っていた。直接投資の半分以上はM&Aであるから、外資脅威論ではなく外資歓迎論を盛り上げなければならない状況に日本は置かれていた。
第二に経団連は「三角合併解禁で時価総額が小さい中小企業が狙われる」と主張していた。だが、三角合併とは現金ではなく株式を対価とした株式交換公式のM&Aのこと。現金では買収できないような大型M&Aが念頭に置かれており、中小企業買収でわざわざ三角合併が使われるというシナリオは荒唐無稽だった。
実際、その後の15年間を見れば、経団連の主張が本当にピント外れだったことが証明されている。三角合併をテコにして日本企業を敵対的に買収する外資は一社も現れなかったのである。
■反対の急先鋒は「国際派」として鳴らした御手洗会長
ところが、当時は経団連の三角合併反対キャンペーンが功を奏し、経済界では「外資が日本企業を食い物にしかねない」といった不安が共有されていた。三角合併反対の急先鋒が「国際派」として鳴らした御手洗だった。日経も経団連と同じ論陣を張っていた。
在日米国商工会議所(ACCJ)は怒り心頭に発した。プレスリリース発表に合わせて私に大量の資料を送り付け、経団連の対応がいかにおかしいかを力説した。一方、日経はACCJのプレスリリースを黙殺し、経団連側の主張を垂れ流し続けた。
そんな状況下で、私は2006年10月31日付夕刊の1面で「外資脅威論」という見出しのコラムを書いた。ACCJの主張を紹介しながら経団連をチクリとやったわけだ。これに経団連はピクリと反応し、日経本社トップにクレームを入れた。
経団連は露骨だった。日経から編集局幹部と共に論説委員や編集委員を呼び寄せ、レクチャーしていたのだ。私はなぜか除外されていた。三角合併問題に最も詳しいと自負していたのに。
■署名記事でボツにされたのは私の原稿だけだった
私は編集委員だから自分の責任で署名記事を書いていた。だから経団連が反発していても忖度する気持ちはさらさらなかった。数週間後に「国際M&Aで株式交換を禁止している先進国は日本だけ」といった趣旨の原稿を書き、デスクに送った。定期的に書いていた署名入りコラム用だった。
ところが原稿は社内的に物議を醸した。オフィスでゲラ刷りを受け取り、内容をチェックしていたら、デスクから電話が入った。「申し訳ないですが原稿は預かりになりました」。実際には預かりではなくボツにされていた。
署名入りコラムがボツにされるのは前代未聞だった。しかも夜遅くゲラ刷りが出ていた段階で。私の愚痴を聞いた同僚の編集委員は絶句した。「僕も長く日経にいるけれど、そんなことがあり得るのか……」
その後、私は三角合併について何も書けなくなった。部長・デスク段階で忖度が働き、原稿執筆の依頼が来なくなったのだ。当時の同僚から聞いた話では、三角合併解禁を支持するインタビュー記事などもボツにされていた。ただし署名記事でボツにされたのは私の原稿だけだった。
■「ハゲタカ外資」という差別的言葉
次にアクティビスト台頭。経団連で外資脅威論が広がっていたのは、外資系投資ファンドが日本国内でアクティビストとして目立つようになっていたからだ。それを反映してメディア上では「ハゲタカ外資」という差別的言葉が飛び交っていた。
私は内外の投資家やガバナンス専門家への取材を重ねているうちに「日本にこそアクティビストが必要」という確信するようになっていた。2001年には雑誌「日経ビジネス」上で元祖ハゲタカファンドの米リップルウッドを取り上げ、「ハゲタカが日本を救う」という巻頭特集を手掛けた。当時の状況を踏まえれば、相当アバンギャルドな特集だったと思う。
日本では長らく株式持ち合いが横行して株主権が封殺され、いわば「経営者至上主義」が蔓延していた。株主のチェックを受けずにワンマン社長が跋扈すれば、日本企業は競争力を失う。そんななか、私はアクティビストに光明を見いだしたのである。
■なぜ村上世彰と堀江貴文は排除されたのか
ハゲタカ外資と同列で語られていたのが日本版アクティビストの草分けともいえる元通産官僚の村上世彰だ。通称「村上ファンド」を立ち上げ、保守的な経済界に変革を起こそうと意気込んでいた。
しかし村上はメディア業界から敵視され、「拝金主義者」のレッテルを貼られていた。フジテレビに経営改革を迫るなどメディア業界にも投資先を広げていたからだろう。読売新聞グループ本社会長の渡辺恒雄からは「ハゲタカ」と一蹴されていた。
「ホリエモン」ことライブドア社長・堀江貴文も忘れてはならない。村上と近い関係にあり、フジテレビの筆頭株主であるニッポン放送株の買い占めでメディア業界を敵に回していた。やはりハゲタカ外資と同列で語られていた。

アクティビスト問題でも日経は経団連と歩調を合わせていた。系列のテレビ東京株を取得されていたからなおさらだった。編集局内では「村上ファンドの宣伝になるような記事は書かないように」という暗黙の合意が出来上がっていた。忖度である。
2006年前半、村上ファンドは阪神電気鉄道株を大量取得し、世間をにぎわしていた。そんななか、村上はシンガポールへ移住した。メディアからの激しいバッシングに耐えられなくなったからだ。
■村上世彰を一度も取材していない記者が1面で解説記事
私は古くから村上を取材し、当時の日本国内では携帯電話で彼を自由に取材できる唯一の記者だった(海外ではニューヨーク駐在の同僚記者がパイプを持っていた)。実際、誰も知らないネタをいくつか仕入れ、そのたびに担当デスクに報告していた。
ところが、どんなに面白いネタを本社に伝えても原稿執筆依頼は来なかった。実際には担当デスクは「ぜひやりましょう!」と前向きになってくれながらも、編集局上層部の判断を覆せなかった。
結局、私は村上ファンドについて何も書けないまま無為に過ごし、同年6月を迎えてしまった。同月に村上はインサイダー取引の疑いで電撃的に逮捕されたのだ。たったの半年間で時代の寵児が立て続けにつぶされ、変革の期待はあっと言う間に萎んでしまった(堀江は同年1月に証券取引法違反の疑いで逮捕されていた)。
村上の逮捕当日にも私の出番はなかった。村上バッシングにくみしなかった私は煙たがられていたのかもしれない。逮捕翌日の日経1面では、村上を一度も取材したことがない記者が解説記事を書いていた。
■日経にとどまる意味を見いだせなくなった
私はもともと証券部に籍を置き、マーケットを担当していた。企業取材であれば経営者側ではなく投資家側を重点的に取材するわけだ。しかし2006年3月――それからおよそ9カ月後にNとレストランで怒鳴り合うことになる――に産業部へ異動になっていた。産業部の主な仕事は大企業経営者への取材だ。
異動に際して言われていたのが「経営者100人に取材」だ。要するに、経団連の主張にもっと耳を傾けろという意味合いを持った人事異動だったのだ。当時の編集局長からは直接「将来、本社コラムニストにしようと思っている」と言われていたのだが、経団連企業への密着取材が前提になっていたわけだ。
非常にやりにくかった。それでも「Nのような幹部がいる限りは日経も捨てたもんじゃない」と思っていた。実際、日ごろ私が経団連に批判的な記事を書いても、Nはいつも「正論を書いている。社内のことは気にするな」とサポートしてくれていた(少なくとも私にはそのように見えた)。
だから、社内の風当たりが強くなり、書きたい記事を書けない状況に置かれても、日経を辞めようとは思っていなかった。署名入りコラムをボツにされた後でも、である。
だが、レストランで怒鳴り合いになってショックを受けた。いざというときに一番サポートしてもらいたかったNにはしごを外されていたということがはっきり分かったからだ。そもそも、著名入りコラムをボツにした張本人がNだったのだ。
これ以上日経にとどまる意味を見いだせなくなった。就学前の長女と長男と一緒の時間を増やし、ワークライフバランスを見直したいとも思っていたので、渡りに船だった。
■編集局の独立性が担保されていない
私が辞めた経緯からも分かるように、日経はガバナンス上の構造問題を抱えている。生涯ジャーナリストのキャリアパスが限定的にしか用意されておらず、経営の素人である記者が経営を担う仕組みとなっている。現に、Nは後に経営幹部として大出世している。
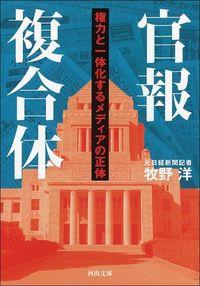
編集局の独立性を担保するファイアウォール(業務の壁)が築かれていないわけだ。結果として編集局は経営側の意向を無視できず、経団連をはじめとした権力に対して強く出られなくなる。
日経は経済新聞であり、本来であれば自由な資本主義経済の信奉者であるはずだ。外資やアクティビスト、起業家といったアウトサイダーにも市場を開放し、古い企業の退場・新しい企業の育成という形で産業の新陳代謝を促す――ここに日経の立ち位置があるべきではないのか。
2006年には村上と堀江というアウトサイダーが立て続けに逮捕され、既存秩序に挑戦する機運は一気に後退した。起業家精神が立ち消え、産業の新陳代謝が思うように進まなくなった。
古い大企業を代表する経団連が日経を使って外資警戒論を煽り、村上ファンドとライブドアつぶしに加担してイノベーションの芽を摘んだのだとしたら……。「失われた20年」――あるいは「失われた30年」――の責任の一端が日経にあると言われても仕方がないだろう。
■日経にとどまっていたらあり得ない展開に
日経を辞めて良かった、と私は思う。辞めたことで、所属する会社に左右されずに、自由にジャーナリズムを語れるようになった。
しかも、本を出したことで多くの若手記者――日経も含めて――と知り合えた一方で、早稲田大学で大学院生を相手にしてジャーナリズムを教えるチャンスも得られた。コロンビア大留学体験を踏まえて若い世代に自分の知見を伝えていると、充実感を覚える。
きっかけは、現在日銀副総裁を務めている経済学者・若田部昌澄だった。早稲田大教授時代の2012年に本書の単行本版を読み、「アメリカから一時帰国する際にはぜひ講演してほしい」と連絡してくれた。それが縁になって私は大学院の非常勤講師になれた。日経にとどまっていたらあり得ない展開だった。
予想外の出会いは若田部にとどまらなかった。例えば政治家・河野太郎だ。大臣になる前に新幹線で移動中に本書の単行本版を読み、共感してくれた。共著『共謀者たち』(講談社)の出版を快諾し、何度か対談に応じてくれた。

対談をしているうちに私は河野の行動力に感銘を受けた。「彼こそ調査報道記者にふさわしいのではないか」と思ったほどだ。そのような政治家と共著を書くような展開は夢想だにしていなかった。
会社を辞めて分かったのは、日本のメディア業界でも人材の流動化は進みつつあり、チャンスが広がっているということだ。きちんとスキルを身に付けている記者であれば、既存メディアから飛び出しても仕事を見つけられるし、年収を維持したまま新興メディアへ転職もできる。
現に、私の後を追って独立し、成功している日経記者は多い。みんな優秀なジャーナリストであり、誰も独立したことを後悔していない。メディア業界全体で同じような動きがどんどん広がり、業界全体の新陳代謝が進む――こんな展開に私は期待を寄せている。(文中敬称略)
----------
ジャーナリスト
1960年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業、米コロンビア大学大学院ジャーナリズムスクール修了。1983年、日本経済新聞社入社。ニューヨーク特派員や編集委員を歴任し、2007年に独立。早稲田大学大学院ジャーナリズムスクール非常勤講師。著書に『福岡はすごい』(イースト新書)、『米ハフィントン・ポストの衝撃』(アスキー新書)、訳書に『TROUBLE MAKERS』(レスリー・バーリン著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『マインドハッキング』(クリストファー・ワイリー著、新潮社)などがある。
----------
(ジャーナリスト 牧野 洋)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
物議醸す「ダイドー株売却」の内幕を丸木氏語る 大幅増配公表直後で批判を向けられた物言う株主
東洋経済オンライン / 2024年7月19日 18時0分
-
大谷翔平を激怒させた「新居報道」にフジ社長は謝罪したが…"迷惑取材"をやめないテレビ局の本当の問題点
プレジデントオンライン / 2024年7月11日 17時15分
-
投資家に転身したマネックス創業者が「しまむら」に株主提案の波紋(有森隆)
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月10日 9時26分
-
【元日経新聞記者へインタビュー】平均年収の高いビジネスパーソンたちが好んで読む「面白いネタ」の共通点
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月3日 8時15分
-
“お騒がせ”イメージはもう古い…!? 「物言う株主」アクティビストとは何者で、何のために“物言う”のか
Finasee / 2024年6月25日 18時30分
ランキング
-
1SNS投資詐欺、拠点のビル一斉捜索で8人逮捕 大阪府警、スマホ1800台超を押収
産経ニュース / 2024年7月23日 21時16分
-
2〈華麗なる一族、親子トップ2人が辞任〉報告書で暴かれた小林製薬のヤバすぎる製造管理体制…従業員が異変を報告も品質管理担当者は「青カビはある程度は混じる」記者会見は開かず逃げ切りか?
集英社オンライン / 2024年7月23日 20時6分
-
3「県民の負託、理由にならない」 堺市の永藤市長 兵庫の斎藤知事疑惑巡り突き放し
産経ニュース / 2024年7月23日 20時17分
-
4睡眠時のエアコン「つけっぱなし」と「切タイマー」どっちが快適?節電できる風量は「弱」?「自動」?
RKB毎日放送 / 2024年7月23日 20時11分
-
5「600円しかなく…ガスも電気も止められた」DV受けうつ病なったシングルマザー「生活保護」申請したのに受け付けられず 女性は知人男から殴打され死亡 遺族ら大阪市に要望書『受給できてたら死なずにすんだ可能性』
MBSニュース / 2024年7月23日 15時20分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











