軽い気持ちで不動産投資に手を出した40代会社員の末路【2020年BEST5】
プレジデントオンライン / 2021年11月16日 10時15分
※本稿は、永井ゆかり『1万人の大家さんの結論! 生涯現役で稼ぐ「サラリーマン家主」入門』(プレジデント社)の一部を抜粋・再編集したものです。
■「かぼちゃの馬車」事件とは何だったのか
3月25日、スルガ銀行は、シェアハウス「かぼちゃの馬車」のオーナーに不正な融資を行っていた問題で、東京地方裁判所に調停を申し立てていた257人のオーナーに対し、東京地裁の調停に基づいて担保物件の物納を条件に借金返済を免除する手続きを実施したと発表した。


「かぼちゃの馬車」の投資トラブルは、そもそも不動産投資ができるほどの資産がない人たちが、実勢価格より高値のシェアハウスをフルローンで購入し、運営会社が販売時に説明した家賃では入居者が集まらず、破綻。オーナーの手元には収益性が低いシェアハウスと多額の借金だけが残ったというものだ。
融資したスルガ銀行も、シェアハウスの購入契約を結んだオーナーに融資する際、審査を通りやすくするため顧客資料を改ざんするなど不適切な融資を行ったことで、2018年10月、金融庁から6カ月の不動産投資向けの業務停止命令を受けた。今回スルガ銀行は、オーナーに担保物件を物納させ、ローン残高と同額の解決金を支払い、融資物件の債権を第三者に譲渡した。他のオーナーに対しても要望があれば同様の対応をとり、この問題に決着をつけたいとしている。
■事件の背景にあった4つのポイント
私は、2018年5月から8月まで当社が発行する「週刊全国賃貸住宅新聞」に「シェアハウスの投資検証」という連載を10回にわたって書いた。このような事件が起きた背景には4つのポイントがある。
1つ目はマイナス金利だ。2016年に日銀がマイナス金利を発動したことにより、金融機関は融資を積極的に行わなければならなくなったが、そのときスルガ銀行をはじめ地銀がこぞって目を付けたのが、個人の不動産投資への貸し付けだった。担保が取れる不動産は、融資しやすかったからだ。
当時、いくつかの地銀の融資額が、本社のある地元よりも東京にある支店の方が多いという話をよく耳にしたが、中でもスルガ銀行は群を抜いていた。サラリーマンに対し、他行が金利1~2%前後で融資していたとき、4.5%と金利は高かったが、年収に応じてフルローンで融資した。取材したある年収1500万円のシェアハウスのオーナーには3億円の融資枠が設定された。そんな融資枠を提示されたため、そのオーナーは2棟も買ってしまったという。
2つ目は長寿化だ。長寿化と年金不安によって、人々の老後生活への不安は一層高まった。
■一見便利なサブリースの落とし穴
3つ目は、金融機関の融資姿勢の変化の結果とも考えられるが、不動産投資で成功したと語る人の話を直接聞いたり、テレビや新聞・雑誌で見かけたり、セミナーで聞いたりする機会が増え、給料以外の収入の道を模索していたサラリーマン層に、「自分にもできるのではないか」と感じさせる空気が醸成されていった。とはいえ本業があるので、賃貸経営との両立ができるのかとの不安は残る。
その懸念を4つ目の「サブリース」という仕組みが払拭した。サブリースとは、運営会社がオーナーから1棟丸ごと借り上げることで、家主は空室による家賃収入の減額リスクを回避できるばかりか、自分の代わりにシェアハウスの管理・運営をしてくれるという一見便利な仕組みだ。
しかし、サブリースにもデメリットはある。最初に提示された家賃でずっと借り上げてもらえるわけではなく、入居状況が悪ければ、予想以上に家賃を下げられるリスクがある。前述した「かぼちゃの馬車」のサブリース家賃は実際、絵に描いた餅で、運営会社は経営破綻し破産に追い込まれている。
■なぜ素人たちは「不動産投資は儲かる」を信じたのか
それにしても、およそ1200人もの人たちは、なぜ、どのようにして「かぼちゃの馬車」のオーナーになったのか。その1人、関口さん(仮名)の話を紹介しよう。

関口さんは、都内に住む40代のサラリーマン。2016年に、スマートデイズが運営するシェアハウス「かぼちゃの馬車」を購入した。購入のきっかけは、スルガ銀行の支店で開催されたセミナーに参加したことだった。「都内の新築不動産で利回り8%」「東京で働きたいという地方にいる女性を応援するシェアハウス」「賃料0円でも儲かる新不動産ビジネス」などと聞こえのいい言葉が並べられたスマートデイズ元社長の話に、「これはいい」と共感したという。
都内に自宅以外の不動産を持てるステータス感、銀行の預金金利や投資信託よりはるかに高い利回り、新築というプレミア感、さらに、賃貸経営で不安な空室による家賃収入の不安定さを払拭する家賃外収入を得るビジネスモデルと、女性の社会進出を支援する社会貢献度の高いビジネス。これだけ聞けば、不動産経営の経験がない一般のサラリーマンでも「うまくいく」と信じてしまうのも無理はない。
セミナー参加後、購入を決意した関口さんは、半年後には、シェアハウスオーナーとして家賃収入を得ることになった。セミナーの説明通り、毎月定額の家賃が振り込まれた。当時は、その振り込みが続くと思って疑うことはなかった。
■「これは危ない」――不安は的中した
だが、それから1年後。支払う家賃の変更に関する通知が届いて、安定した生活は一変した。運営していたスマートデイズが、オーナーに支払う毎月の家賃を全額は支払えなくなったというのだ。当面、銀行への借金返済額のみの支払いになるという通知と同時に、銀行との融資交渉を勧める案内が同封されていた。
これは危ない──。そう思った関口さんは、融資を受けたスルガ銀行に返済条件の見直しについて相談したり、知り合いの不動産会社、弁護士などに、今後の対応について相談したりしながら、家賃全額が振り込まれなくなる日も近いのではないか、と戦々恐々としていたが、不安は的中した。
2018年1月、スマートデイズからオーナー向け説明会の案内が届き出席したところ、「オーナー様に家賃を支払うことが困難な状況です」という説明があったのだ。聞けば、サラリーマンや医者などに、シェアハウスを販売し急拡大してきた同社だったが、入居者獲得に苦戦し、全体の入居率はわずか30%台だった。会場内には「なぜ、こんなことになってしまったのか」と、頭を抱えるオーナーの姿が多く見られた。
スマートデイズ倒産後、関口さんは管理を別の会社に委託した。家賃は下がってしまったものの、スルガ銀行との交渉でなんとか金利を下げ、元本返済も待ってもらっている──。そんな状況だった。
「かぼちゃの馬車」オーナーに共通するのは、不動産投資や賃貸経営についてろくに学ぶこともせず、シェアハウス販売業者のセミナーや営業マンと化した知人の甘い言葉に夢を見て買ってしまったことだ。もちろん「かぼちゃの馬車」に限っていえば、銀行も業者と結託していたという不正もあり、不動産業界に精通していないとわからない取引もあった。それだけに不動産投資をする際には、まず十分な情報、知識の習得が必要になる。
■判断を誤らせる「買いたい病」
ここからは、不動産投資を行う際、特に初心者が陥りやすい失敗について説明していくが、その前に不動産購入時に忘れてはいけない大前提について確認しておきたい。それは、「不動産を購入する目的」だ。本来の目的を見失って資産を減らしかねない事態に陥るケースもあるからだ。
いざ収益不動産を買おうと思っても、買いたい不動産はそう簡単に手に入るものではない。自分が買いたいと思うような物件は、同じように多くの人がいい物件と考え、競争率が高くなる上に、売主も不動産業者も着実に高値で買ってくれそうな買い手を選ぼうとするため、経験の浅い買い手は不利になる場合が多い。
欲しいと思った不動産がなかなか買えないと、永遠に買えないのではないかと不安になり、焦る。本来、焦りは禁物だが、なかなか買うことができないと、いつの間にか、目的は収益性の高い「いい不動産」を買うことではなく、買うこと自体が目的になり、徐々に「買える不動産」に買い付けを入れるようになる。
そのような状況に陥ることを「買いたい病」に罹るという。「頭では理解しているつもりでも、つい気持ちが先走ってしまう」ことは、不動産に限らずいろいろな場面で遭遇することだ。だからこそ、最初はなかなか買えなかったとしても、「不動産はご縁」だからとグッと我慢して、本来の目的をかなえるための不動産を地道に探し、買い付けを入れていくことが重要だ。
■不動産広告の「満室想定利回り」に用心せよ
収益不動産の広告を見たことはあるだろうか。不動産の概要や不動産価格の他に「満室想定利回り」という文字がある。収益不動産を買うとき、収益性が高いのか低いのかを判断するための重要な指標だ。
利回りの計算方法は、年間家賃収入を不動産購入費で割って算出する。例えば、不動産購入費が5000万円、満室想定年間家賃収入が500万円なら、満室想定利回りは10%。計算上は、不動産購入費用を10年間で回収することができるという意味だ。不動産購入費が1億2000万円、満室想定年間家賃収入が600万円なら、満室想定利回りは5%となり、この数字を比較すると、前者の物件の方が収益性が高いということになるが、この満室想定利回りを見るときは次の4点に気をつけなくてはいけない。
まず、満室想定利回りは、あくまでも「満室」時の家賃収入をベースに計算されていることだ。賃貸経営で満室を維持するのは実はかなり難しい。実際広告に出ている不動産も、満室でない可能性が高い。満室でなければ、この利回りは机上の空論に過ぎないということになる。
次に、新築物件にありがちだが、そもそも家賃の値付けに問題があるケースだ。例えば、地域相場と建物の仕様・設備を考慮して、新築の家賃が6万円しか取れない地域なのに7万円に設定すると、1棟10戸の賃貸住宅の場合、月10万円、年間で120万円もの差が生じてしまう。そのことを知らずに購入しても後の祭り。たとえ広告に想定利回り7%と表示されていても、実際は6%になってしまう。しかもそれはあくまで満室時の利回りだ。募集がうまくいかなければ、利回りはさらに下がることになる。
■「家賃収入=手取り収入」ではない
3つ目は、満室想定利回りのベースとなる家賃は、そのまま何年も続くとは限らないということだ。周囲に同じようなタイプの新築の物件が増えれば、競争上、家賃を下げないと入居者が決まらないという状況になるのが一般的だからだ。実際、10年間家賃を下げなくていい物件は珍しい。
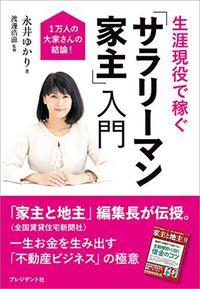
4つ目は、広告に表示されている利回りは表面的な利回りであり、実際の利回りではないということだ。賃貸経営にかかるコストは、不動産購入費だけではない。契約する際には仲介手数料や広告料がかかり、管理会社に委託すれば管理費がかかる。設備の故障や建物が老朽化したときには修繕費がかかる。最大の支出である借金の返済が重くのしかかる上に、税金も払わなくてはいけない。
時々勘違いする人がいるが、「家賃収入=手取り収入」ではない。売り上げにあたる家賃収入から、こうした費用を差し引いた金額がキャッシュフロー(手残り)となり、これがいくらなのかを考慮して算出する実際の利回り、「実質利回り」を把握し、確保できるかどうかを見極めることが重要だ。
----------
『家主と地主』編集長
全国賃貸住宅新聞社 取締役。1975年、東京都生まれ。日本女子大学卒業。98年、「亀岡大郎取材班グループ」に入社。住宅リフォーム業界向け新聞、ベンチャー企業向け雑誌等の記者を経て、賃貸不動産オーナー向け経営情報誌「家主と地主」編集長、賃貸住宅業界向け新聞「全国賃貸住宅新聞」編集長、2004年、全国賃貸住宅新聞社取締役に就任、現在に至る。新聞、雑誌の編集発行の傍ら、家主や不動産会社向けセミナーでの講演活動を行う。本書が初の著書となる。2児の母。
----------
(『家主と地主』編集長 永井 ゆかり)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「実質利回り13%」のアパートを購入したのに…2年後にキャッシュフローが赤字となったワケ【税理士が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月20日 16時15分
-
「5円で買った家」が毎月4万円の利益を生む…元サラリーマン投資家が「空き家投資は儲かる」と説くワケ
プレジデントオンライン / 2024年6月19日 9時15分
-
「国内不動産はやめとけ」…投資初心者が手を出しがちな日本不動産、今は“リスクたっぷり”だと言える5つの理由
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月15日 9時15分
-
実家を放置→ツタだらけのお化け屋敷状態に…「年間家賃収入54万円」、驚異の「利回り45%」のお宝物件に激変したワケ【不動産投資の実話】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月13日 9時45分
-
「不動産投資EXPO2024」2024年7月24日(水)開催のお知らせ
PR TIMES / 2024年6月7日 11時15分
ランキング
-
1ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分
-
2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分
-
3関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?
乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分
-
4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!
乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分
-
5上海の伊勢丹が営業終了、中国で日系百貨店の閉店相次ぐ…高島屋は売上高が減少傾向
読売新聞 / 2024年6月30日 20時56分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












