「グーグルの収入源はあなたのプライバシー」便利な検索が無料で使える本当の理由
プレジデントオンライン / 2021年11月11日 11時15分
■ネット生活で欠かせないグーグルのサービス
日本で一番アクセスの多いウェブサイトといえば何を思い浮かべるだろう? ヴァリューズの調査によれば、2020年の訪問者数1位はGoogleで、推計訪問者数は年間1億1155万人にも上る。2位はAmazon、3位は楽天市場、4位はYouTubeで、5位にYahoo! Japanが入るという構成だ。意外(?)かもしれないが、SNSのTwitterは7位、Facebookは9位となっており、いわゆる「プラットフォーム」の中でもGoogleの存在感がかなり大きいことがわかるだろう。
そのGoogleの親会社Alphabetの2021年第3四半期(7~9月)決算が10月26日に発表された。それによると、売上高は5四半期連続で過去最高を記録し、特に今期の広告売上は対前年比43%増と非常に好調だという。
Googleは、検索エンジンを中心的なサービスとしつつ、GmailやGoogleマップ、AndroidやGoogle Chromeなど、ネット生活の基盤となるようなサービスを多岐にわたって展開している。意識する/しないにかかわらず、スマートフォンを持ち歩く生活をしている私たちはほとんど毎日のようにGoogleのサービスに接触しているといっても過言ではない。そしてそのサービスのほとんどは無料である。
■なぜ広告主の透明化を進めているのか
決算からもわかるとおり、この無料のサービスが実現可能なのは、Googleが広告ビジネスを収益源にしているからだ。実際、Googleの収益の8割以上は広告によって賄われており、Googleは世界最大のネット広告配信プラットフォームになっている。
2021年9月22日、Googleは「広告の透明性向上」のために広告主の出稿履歴を公開する計画を発表した。このことによって、ユーザー自身がGoogle広告の広告主が誰であるかを識別できるだけでなく、その広告主が過去にどのような広告を出稿していたかを確認できるようになるという。本稿ではこの変更の背景と、一般ユーザーへの影響について検討したい。
■何気なく目にしている広告が実はグーグルによるもの
私たちはGoogleを頻繁に利用しているにもかかわらず、多くの場合その収益の仕組みがどうなっているかは意識されていない。Googleの広告には多数の種類があるが、ここでは特に目にすることの多い「ディスプレイネットワーク」と呼ばれるバナー広告について考えてみたい。
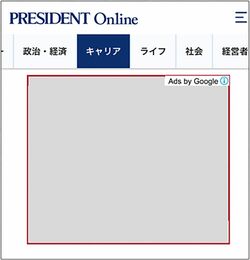
Googleに限らず、ウェブページにはさまざまな広告が掲示されている。特に長方形や正方形の画像を使った図のようなタイプの広告は一般に「バナー広告」とも呼ばれ、もっとも頻繁に目にするネット広告といってもよいだろう。実際、このプレジデントオンラインの記事中にもバナー広告が差し込まれている。
この広告、実はプレジデント社と広告主が直接契約したものではない。バナー画像の右上をよくみてみると、小さなiマークがあり、iマークをクリックすると「Ads by Google」などと書いてあるのがおわかりになるだろうか。まさにこのバナー広告が、Googleの「ディスプレイネットワーク広告」である。
■行動履歴を追いかけてくるクッキー広告のカラクリ
さて、今みなさんの端末上にはどんな広告が表示されているだろうか? もしかしたら、最近検索していた商品や、関心の強い分野のサービスなどが表示されているかもしれない。この広告は、プレジデント社が指定して掲載しているのではなく、Googleの契約に基づいて、Googleのアルゴリズムが選択して掲載しているものだ。
その基本的な仕掛けはこうである。
Googleは、プレジデントオンラインのような広告掲載先との契約を多数結んでいる。一方でGoogleは、広告主となる商品メーカーや、販売をするECサイトなどとも広告出稿の契約を多数結んでいる。それぞれのウェブサイトでは契約に基づき、「クッキー」というブラウザー識別の仕組みが共通化され、それぞれのサイトでのユーザーの行動履歴がGoogleのデータベースに蓄積されている。
たとえばあるユーザーが自動車メーカーの広告主Aのサイトで、新発売の車種Xの情報を見たとする。その車種Xのウェブページからは、クッキーを介してこのユーザーが車種Xのページを閲覧したという履歴がGoogleに送信される。
次に、同じユーザーがGoogleと契約した広告掲載先のサイトを訪れると、Googleはクッキーによってそのユーザーを識別し、以前に閲覧した商品の情報を基に広告主Aのバナー広告を優先的に表示する。ユーザーがその広告をクリックすると、広告主Aにクリック数に応じた広告料が請求される仕組みになっている。
■ネット広告に既視感を覚えることはないか
このような広告は、「行動ターゲティング広告」と呼ばれ、近年では極めて多くのウェブサイトで採用されている仕組みである。Googleのディスプレイネットワークは、この行動ターゲティング広告において世界最大のプラットフォームを提供している。
直接Googleを使っていなくても、ユーザーがどのような商品を閲覧したか、といった行動履歴がGoogleに送信され蓄積されており、それがGoogle以外のサイトでの広告表示に利用されている、ということになる。たとえば、プレジデントオンラインで表示されたバナー広告と同じ広告が、別のサイトに行った時も表示されるなどは、多くの方が経験されているのではないだろうか。
このように、自分が意識していないところで過去の行動が蓄積され、広告表示がアルゴリズムによって「ターゲティング」されることから、ユーザーから見ると自分の関心に合わせた広告が多く表示される一方で、追いかけられているような薄気味悪さが伴う。このようなユーザーデータの利用には近年プライバシーの観点から批判が強まりつつあり、Google広告もさまざまな形でその批判に「対応」するように変化してきている。

■批判を避け、広告収益を維持する経営戦略
先ほど紹介した、バナー広告の右上のiマークは、ユーザーが広告の素性を知るために設けられた対応策のひとつだ。これまでも、iマークをクリックすることで、その広告の表示理由や広告主の情報を調べたり、その広告の表示を拒否したりすることができた。先述した2021年9月の発表は、広告主の信頼性を確認するこの機能を強化するものだ。
Googleは、2020年4月の発表に基づき、「広告主身元確認プログラム」をスタートさせている。これによって、事前に広告主の身分証明書や事業の実施を証明する書類等の確認・審査を受けた広告主しかディスプレイネットワークに出稿できなくなるという。また、今回の発表により、「広告主ページ」という広告主の情報を集約したページが公開され、同じ広告主が過去にどのような広告を出稿していたか、確認できるようにするという(ただし、実施は米国から順次他の地域に展開するということで、2021年10月現在日本では未実施)。
これらの対応は、一般ユーザーから見れば歓迎すべき方向性といえるだろう。一方で、Googleが継続的に広告収益を上げていくための、したたかな戦略であることも見逃してはならない。
私たちが無料のサービスを利用することと引き換えに、さまざまな「プライバシー」を巨大なプラットフォーム企業に提供し、Googleはそれをアルゴリズムでターゲティングさせることによって多くの収益を得ている。この根本原理は変わらない。
Googleの動きは、このような「プライバシー」をお金に換えるビジネスを、社会的な批判をかわしながら維持・拡大するための戦略的な防衛と言える。換言すれば、Googleは、広告主にも、ユーザーにも、「透明性を高める」手段を提供することで、Google自身が広告の内容に責任を負わずに済むような口実づくりをより強化しているともいえるのだ。
■「薄気味悪い」広告を減らしたいときはどうするか
バナー広告の「iマーク」を含めて、これらの対策は多くの場合ひっそりと行われる。これらは、何か問題が起きたときに「確認をしていないユーザー」に責任を転嫁できるしかけでもあるからだ。だからこそ、わたしたちユーザー自身がこのような機能を積極的に活用し、自身のデータがどのように使われているのか確認していくことが重要である。
「iマーク」だけでなく、Googleの「アカウントページ」に行けば、自分の情報がどのように広告に結びつけられているかを調べ、不要なものは拒否したり削除したりすることもできる。たとえば、「広告のカスタマイズ」自体を「オフ」にすれば、行動履歴による広告表示を停止することができる。ただし、この場合は一般向けの広告が表示されるようになるため、関心のない広告でも個別にオフにすることはできなくなる。
不快な広告をなくすには、関心のないジャンルや、好みでない広告主の広告をひとつずつオフにする作業が必要だ。筆者の画面例の場合でいえば、「Apple iOS」の広告を見たくなければ、この画面で「Apple iOS」をクリックして「オフ」にすることで、90日間関連する広告を見なくて済むようにできる(90日経たなくてもオンに戻すこともできる)。面倒ではあるが、このようなチェックを行うことは自身のデータがどのように追跡されているのかを自覚するきっかけにもなるし、「薄気味悪さ」の軽減にもつながるだろう。

■「プライバシー」依存の広告を暴走させないために
無料なのが当たり前とされてきたインターネットサービスにも、サブスクリプション方式やフリーミアムモデルなど、さまざまなビジネスモデルが導入されつつある。たとえばYouTubeはサブスクリプション方式で広告を削除できる「YouTube Premium」を導入したが、「広告削除機能を宣伝する広告がTV CMで流される」という笑えない矛盾も起きている。
「無料で便利だから、とりあえず使い続ける」ことから抜け出し、「対価を支払うにふさわしいサービスを選別する」視点をもちたい。無料であってもその対価として支払っている「プライバシー」の価値は決して低くはない。
まずはユーザー自身が「プライバシー」の価値を自覚し、一人ひとりがその所有権を主張していくことが重要だ。アカウント管理のしくみは、ある意味プラットフォームが自己弁護のために用意した機能だが、積極的に活用すればユーザー自身のデータを一定程度管理することができる。
このような機能の利用者数や利用頻度が増えていけば、プラットフォームの側もその必要性を無視するわけにはいかない。「プライバシー」に依存した広告の健全性を回復し、収益重視の姿勢に歯止めをかけていく一定の「圧力」を加えることができるのだ。
----------
メディア論研究者
1977年東京生まれ。東京藝術大学・早稲田大学非常勤講師。東京大学大学院学際情報学府博士課程在学。京都大学総合人間学部卒。専門はメディア論、メディア史。インターネット企業にて、デジタル・マーケティング、UXデザインなどに従事する傍ら、デジタル・メディアにおけるランキング・システムとプラットフォームの関係性に着目し、研究を行っている。著書に『ソーシャルメディア・スタディーズ』(分担執筆、北樹出版)。
----------
(メディア論研究者 宇田川 敦史)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
JTBコミュニケーションデザイン、クリムタン、IAS 3社連携による「triconcier(TM)(トリコンシェル)」新たな機能を追加し、サービス提供を開始
PR TIMES / 2024年6月25日 14時15分
-
地域情報サイト「ジモティー」に出稿できる運用型広告配信プラットフォーム「ジモティーAds」で下部に固定表示されるアンカー広告の配信を開始
PR TIMES / 2024年6月20日 15時45分
-
VTuberライブプラットフォームとSNS等による効果的な広告配信サービスを開始
PR TIMES / 2024年6月19日 13時15分
-
VTuberライブプラットフォームとSNS等による効果的な広告配信サービスを開始
PR TIMES / 2024年6月19日 13時15分
-
VTuberライブプラットフォームとSNS等による効果的な広告配信サービスを開始
PR TIMES / 2024年6月19日 12時15分
ランキング
-
1意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分
-
2ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分
-
3関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?
乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分
-
4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!
乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分
-
5障害者雇用未達で「社名公表」寸前からの挽回劇 法定雇用率クリアへの3年で見えた成果と課題
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












