ビットコイン発案者が唱えた「マネーはデータである」という言葉の本当の意味
プレジデントオンライン / 2021年11月16日 10時15分
※本稿は、野口悠紀雄『データエコノミー入門 激変するマネー、銀行、企業』(PHP新書)より一部抜粋・編集したものです。
■そもそも“マネー”とはいったい何か
マネーは、決済手段としてだけでなく、ビッグデータを収集する手段としても重要であることが分かってきた。最初に「マネー」と呼んでいるものが何を意味するのかについて、説明しておこう。これは、日常用語では「おかね」と呼ばれているものだ。
「マネー」という言葉を聞いて多くの人がすぐに思い浮かべるのは、日銀券などの「中央銀行券」だろう。しかし、現代の社会では、決済・支払い・送金等に中央銀行券が用いられるのは、少額の対面取引にほぼ限られている。離れた相手に対する送金や多額の支払いの場合には、銀行の口座振込を使うのが普通だ。したがって、「銀行預金」もマネーの一種とされている。
以上は、日本銀行の「マネーストック統計」が対象としているものだ。なお、これらは「通貨」と呼ばれることもある。また、日銀券と政府貨幣の合計を「現金通貨」と呼び、銀行預金を「預金通貨」と呼ぶ。
中央銀行券は中央銀行の負債であり、預金通貨は民間銀行の負債だ。現在では、残高で見ると、預金通貨の方がはるかに多くなっている。2021年6月末において、現金通貨が110.3兆円、預金通貨が862.8兆円だ(「M1」と呼ばれる通貨概念の場合)。
■デジタル通貨が発行されれば世界は大きく変わる
ところで、最近では、「マネー」と呼ばれるものが、以上で述べたもの以外に、いくつも登場している。あるいは、登場することが予想されている。
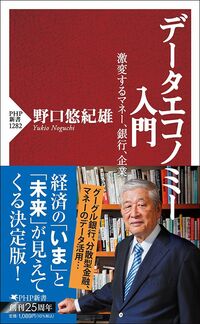
その第一が「電子マネー」だ。中国では、Alibabaの子会社であるAntグループが、Alipayを提供している。また、中国最大のソーシャルメディアであるWeChatを展開するTencentも、WeChat Payを提供している。これらが、中国での二大電子マネーとなっている。
もう一つは、「仮想通貨」(暗号資産)だ。2009年に登場した「ビットコイン」が有名だが、それ以外にも、多数の仮想通貨が発行されている。仮想通貨は銀行システムとは全く無関係に発行されている。
以上のほかに、中央銀行が発行するデジタル通貨(「中央銀行デジタル通貨」CBDC)や、Diemと呼ばれるデジタル通貨のように法定通貨に対する価値が大きく変動しない大規模な仮想通貨(大規模ステーブルコイン)の発行が計画されている。これらは、まだ実現はしていないが、近い将来に発行されると考えられている。これらが実現すれば、マネーの世界は大きく変わることになるだろう。
■電子マネーと仮想通貨は何が違うのか
仮想通貨とは、インターネットでやりとりされる送金のデータのことである。ビットコイン型の仮想通貨もDiemのような大規模なステーブルコインも、基本的な仕組みは同じだ。
利用する側からいえば、電子マネーも仮想通貨も、使い勝手の差があるだけで、基本的な機能は同じだ。どちらも、スマートフォンのアプリである「ウオレット」を用いて入出金する。そして、送金や決済を行なう。
しかし、それらの仕組みや運営のされ方、そしてその本質は、全く違う。マネーのデータ利用を考える際には、仕組みの違いが大きな問題となる。したがって、これらの違いを正確に理解しておくことが必要だ。
ビットコインでは、「アドレスからアドレスへの送金情報の送付」が行なわれる。ここで、「アドレス」とは、秘密鍵から生成されるものだ。秘密鍵とは、ビットコインの場合には、16桁の数字と記号の組み合わせである。
この取引内容はブロックチェーンに記録され、公開される。ブロックチェーンの記録は改竄することができないので、ブロックチェーンに送金の記録が残されれば、ビットコインの受け取り者は、ビットコインの正当な保有者であると主張できる。これによってビットコインの送金が完了したことになる。
■ビットコイン発案者が唱える「マネーはデータである」
つまり、「取引内容を改竄できない記録に残す」ということが、ビットコインの送金なのだ。この過程においてやりとりされているのは、データだけである。つまり、「マネーはデータ」なのだ。
ビットコインの発案者であるSatoshi Nakamotoは、このことを、ビットコインの最初の論文である「Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System」(2008年)において、“We define an electronic coin as a chain of digital signatures.”(電子署名の連鎖を電子コインと定義する)と表現している。
この簡潔な文章の中に、「マネーはデータである」という本質が凝縮されている。つまり、正しい送金記録が改竄できない形で公表されれば、銀行システムに依存することなく、インターネットを通じて送金ができるのである。ただし、取引者の名前が分かってしまうと問題なので、暗号で保護するのだ。
中央銀行券は、匿名の支払い手段だった。だから、それをデータとして用いることはできなかった。銀行預金の口座振込は、原理的にはデータとして使える。
しかし、現実には、銀行は、そうしたデータを利用しようとはしなかった。マネーをデータとして利用するようになったのは、電子マネーになってからのことだ。
中国本土では、AlipayやWeChat Payのような電子マネーが非常に広く普及した。これによって、マネーの取引が詳細に把握できるようになった。
なお、これまでは用いられていなかった銀行のデータについても、銀行APIという仕組みを用いて利用しようとする試みが始まっている。
■マネーのデータはなぜ強力か
これまでビッグデータとして利用されてきたのは、主として検索やSNS、マップなどから得られるデータだった。しかし、マネーのデータは、それらより詳細で正確だ。したがって、マネーのデータの相対的重要度が増すだろう。
まず、SNSのデータには数量化できないものが多いが、マネーのデータは数量化できているので、分析に使いやすい。また、すべての人がSNSで発信しているわけではない。SNSを使っているのは年齢的にいえば若い人が中心であり、高齢者はあまり使わない。若くても、検索エンジンやSNSやマップを使わない人もいるだろう。
つまり、これまでのビッグデータは、すべての人を網羅するものではない。偏ったデータであり、必ずしも社会全体を表すデータとは言えない。また、SNSから得られるデータは、経済分析に使えるとは限らない。
■圧倒的に詳しく正確なプロファイリングが可能になる
これに対して、マネーのデータは、非常に重要なデータになり得る。まず、マネーは、あらゆる経済取引の裏側にある。誰もが、日常生活の様々な場面で、毎日何度も支払いを行なっている。だから、マネーのデータは、ほとんどすべての個人や企業について存在する。

しかも、数値的に処理できる正確なデータだ。したがって、マネーについての大量のデータが利用できれば、それを用いて、SNSなどで得られるデータより、はるかに詳しい情報処理ができる。プロファイリングも、ずっと正確になるだろう。
半面で、マネーのデータはきわめてセンシティブなものなので、その扱いについて、十分な注意が必要だ。とりわけ、個人情報の侵害にならないように注意する必要がある。
■マネーのデータは個別でも価値がある
SNSのデータや検索データなどこれまでビッグデータとして用いられてきたものは、膨大な量のデータが集まることによって初めて価値を発揮する。一つ一つのデータをとってみれば、ほとんど価値がない。プロファイリングは、統計的な推定式によって見当をつけているだけである。だから、間違いもある。
しかし、マネーのデータは、これとは違う。何をどれだけ購入しているのか、誰にいくら送金をしているのか、誰から送金を受けているのか。仮にこうしたデータが得られたら、その人がどのような人であり、何をやろうとしているかは、かなり正確に分かってしまう。
つまり、一つ一つのデータであっても、価値が高い場合が多いのだ。例えば医療費の支払いが多いことが分かれば、健康上の問題を抱えていることが分かってしまう。プロファイリングというのはあくまでも統計的な推計に過ぎないが、マネーのデータは有無を言わせない証拠になる場合もある。
こうした意味で、マネーのデータは、従来のビッグデータより強力なのである。
----------
一橋大学名誉教授
1940年東京生まれ。63年東京大学工学部卒業、64年大蔵省入省、72年エール大学Ph.D.(経済学博士号)を取得。一橋大学教授、東京大学教授、スタンフォード大学客員教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授、早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター顧問を歴任。一橋大学名誉教授。専攻はファイナンス理論、日本経済論。著書に『「超」整理法』『「超」文章法』(ともに中公新書)、『財政危機の構造』(東洋経済新報社)、『バブルの経済学』(日本経済新聞社)ほか多数。
----------
(一橋大学名誉教授 野口 悠紀雄)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
20代から高めておきたい投資・資産運用の目利き力 第110回 ビットコインはイングランド銀行以来の発明、と改めて感じた夜
マイナビニュース / 2024年6月21日 9時0分
-
モッピーがソラナ、ジパングコイン等の4通貨へのポイント交換を開始
PR TIMES / 2024年6月14日 17時40分
-
賃上げに喜ぶ日本人を襲いかねない「今後の展開」 販売価格に転嫁される賃上げは何を意味するか
東洋経済オンライン / 2024年6月9日 10時0分
-
DMMビットコイン「流出482億円」補償の胸算用 自己資本81億円でも「全額補償を即日発表」の背景
東洋経済オンライン / 2024年6月5日 18時0分
-
訂正-ドイツ銀、オーストリア暗号資産交換業者と提携 顧客の入出金処理
ロイター / 2024年6月4日 18時13分
ランキング
-
1ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分
-
2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分
-
3関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?
乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分
-
4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!
乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分
-
5上海の伊勢丹が営業終了、中国で日系百貨店の閉店相次ぐ…高島屋は売上高が減少傾向
読売新聞 / 2024年6月30日 20時56分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












