累計200万個の「体にフィットするソファ」に赤やオレンジといった色が存在しないワケ
プレジデントオンライン / 2021年11月26日 9時15分
※本稿は、松井忠三『無印良品の教え』(角川新書)の一部を再編集したものです。
■無印の「売れ筋」が多めに仕入れてある理由
大企業病に陥ると、現場とリーダーの意識が乖離(かいり)していきます。
それを埋めるには、まずリーダーが現場に出向いてスタッフの声を聞くしかありません。
私は社長に就任してすぐに、全国の店舗を行脚(あんぎゃ)して回りました。当時常務の金井政明をつれ、直営店107店を一軒ずつ回っていきました。
ただ視察するだけでは、表面的なことしかわかりません。夜は店長らスタッフと共に飲みに行き、そこで腹を割って話す場を設けました。
最初は警戒して他人行儀な話しかしなかった店長らも、こちらが話を聞く態勢でいるとわかると、徐々に本音を話しだします。
そうして、本社にいるだけでは決してわからない現場の問題点が色々と見えてきました。過剰在庫の問題も、店を訪れて気づいた点です。
救いだったのは、本社は意気消沈していたけれども、店は元気だったこと。無印良品は店長もスタッフも、もともと無印ファンだった人が多いので、店を愛する思いが強かったのでしょう。スタッフは元気に声を出して接客していましたし、店ごとにあれこれ工夫して売ろうとしていました。
そして現場のスタッフたちの「自分たちが頑張らないと!」という思いから、さまざまな知恵が生まれました。
過剰在庫の問題に気づいてから、前年のデータをもとに、売り場の在庫管理と自動発注を連動させる仕組みをつくりました。今はどこの会社でもITで管理していますが、当時はまだ電話やFAXでのやり取りが主流で、パソコンで管理できるようにするだけでも画期的な取り組みでした。
ただし、コンピュータだけに頼っていると、キャンペーンや特売をしたときや、気温の変化が激しかったときなどに対応しきれず、売り場に穴が空くという事態も起こります。すると売り場から、売れ筋の商品を多めに仕入れたほうがいいのではないかという意見が寄せられました。
この意見を精査したうえで、「売れ筋ベスト10の商品を常に店で把握し、その商品は目立つ場所に陳列する」という仕組みにしました。これを「売れ筋捜査」と呼んでいますが、この仕組みのおかげで、在庫管理がさらに円滑にできています。
■スタッフの売りたい商品は「2割引き」で売る
また、「一品入魂」という制度も、現場から生まれたアイデアです。
これは「店のスタッフ一人ひとりが売りたい商品を一つ決めて、お試し価格として二割ほど安くして売る」という手法です。なぜその商品がお薦めなのか、スタッフが自分でコメントを書いてアピールするので、自然と力が入ります。
このような自発性があったため、厳しい業績の間でも、現場サイドは非常に前向きでした。だから無印良品は立ち直りが早かったのだと思います。
業績が低迷している現場で、いくらリーダーが売り上げアップを説いたところで社員は動かないでしょう。まずは現場との溝を埋めて、不満に耳を傾け、一緒に解決策を考える――今の時代のリーダーに必要なのはカリスマ性ではなく、現場でも自由にものを言えるような風土をつくり、その意見を仕組みにしていくことです。
そうして現場の自発性が育てば、自ずと実行力のある組織になっていきます。
■「お客様の声からヒット作をつくる」具体策
よく「クレームは宝」といわれていますが、お客様の声を活用する具体的なシステムを整えている会社は少ないのではないでしょうか。
「お客様の声を集める」仕組みは大事です。無印良品にも、電話やメールなどで、お客様からの要望が毎日のように寄せられます。
「商品がほつれている」「前に買ったものよりゴムが緩い」といったご指摘もありますし、「キャスター部分の交換はできるのか」という問い合わせもあります。こうしたご意見は、「声ナビ」というソフトに入力し、毎週一回、関係者でチェックし、商品に反映するかどうかを決めています。

同時に、「くらしの良品研究所」というサイトを立ち上げ、お客様とコミュニケーションをとりながら商品開発をしていく仕組みを整えました。
くらしの良品研究所には、「蒸れない帽子をつくれませんか」「このサイズの机をつくってほしい」など、さまざまなリクエストがあります。それも週一回、関係者で吟味(ぎんみ)し、商品化するかどうかを決めます。
お客様の声から生まれた商品の代表格は、なんと言っても「体にフィットするソファ」でしょう。
四角いボックス型のソファの中身に微粒子ビーズを使用し、伸縮性の異なるカバーをかぶせることで、よりかかっても上に寝転んでも身体になじむ仕様になっています。
これは、「部屋が狭くてソファが置けないならば、大きなクッションにソファの機能を付けたらどうだろう」というお客様のリクエストから生まれました。
あまりに快適すぎて立ち上がれなくなるなどとSNS上でも話題となり、累計で200万個以上も売れている大ヒット商品です。
くらしの良品研究所では、自分の声がどう商品に反映されているのかがわかるので、お客様も積極的に参加してくれるのでしょう。こうした仕組みも無印良品の商品力を強化することに役立っています。
クレームもリクエストも、実際に役立ててこそ、本当の宝になります。そう考えると、どの企業にも、アイデアの宝が山ほど眠っているのではないでしょうか。
■無印ブランドを守るためにやってはいけないこと
どこの企業でも、どんなチームでも、業績が低迷すると、商品やサービスを見直します。今までにない商品を開発して心機一転を図ったり、流行を取り入れてみたりと、思いつく限りのことを試してみるでしょう。
それでヒット作が出るならいいのですが、たいていは不発で終わります。貧すれば鈍するの典型で、目先の利益に飛びついてしまうからです。
無印良品も、業績が悪化したころは混迷を極めました。
たとえば、赤やオレンジなど華やかな色合いの衣料品を販売していた時期があります。
もともと商品づくりでは、自然界にある色と天然素材でつくることをコンセプトとしてきました。そうすると、衣料品も自ずと色合いは白やベージュ、黒、藍、グレーなどのベーシックな色が中心になります。
時折、お客様から「モノトーンだけでは飽きるから、もっとカラフルな服があったらいいのに」という要望が寄せられることがありました。そして、商品を開発している人が、「そこが、業績回復の突破口になるのではないか」と飛びついたのです。
社員も必死になっているので、新しいタイプの服が出来上がると、懸命にPRして売り出します。すると、いつもの無印良品とは違う新鮮さがあるからか、確かにしばらくは売れました。
しかし、それも長続きはしません。多くのお客様は他店にはないものを求めてお店に来ているのに、「他店にはない、無印らしさ」を失ってしまったら、無印良品で買う意味がなくなってしまいます。
自然界にある色と天然素材を使い、シンプルなものをつくるというブランドの根幹に当たる部分を変えてはいけなかったのです。
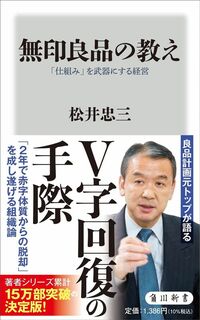
業績が悪化したときに戦略や戦術の見直しを図るのは必要ですが、ぶれてはいけない軸がぶれてしまうと、お客様は離れていきます。日本の多くのものづくりのメーカーが低迷している理由も、そこにあるのではないでしょうか。
これはたとえば、寿司が売れないからと客の要望を聞いてツマミを増やした結果、居酒屋と大差なくなり、結局ほかの居酒屋に負けるのと同じです。
流行に流されるほうが楽ですが、流行は文字通り一過性であるケースが大半です。
お客様第一で要望を聞き入れるのは大事であっても、どこまでも聞いていてはブランドのコンセプトが揺らいでしまいます。足元を固めるために、自社が目指してきたコンセプトをしっかりと再確認したうえで、それを進化させる形で経営戦略を立てるべきなのです。
----------
良品計画 前会長
松井オフィス社長。1949年、静岡県生まれ。73年、東京教育大学(現・筑波大学)体育学部卒業後、西友ストアー(現・西友)入社。92年良品計画へ。総務人事部長、無印良品事業部長を経て、初の減益となった2001年に社長に就任。08年に会長に就任。10年にT&T(現・松井オフィス)を設立したのち、15年に会長を退任。著書に『無印良品は、仕組みが9割』(KADOKAWA)など。18年2月には日本経済新聞に「私の履歴書」を掲載。
----------
(良品計画 前会長 松井 忠三)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
便利で手頃だから支持される!無印良品の売れ筋「生活雑貨」【買って得モノ&夏のトレンド大調査】
&GP / 2024年6月29日 20時0分
-
【無印良品】SNSで話題沸騰! 夏に備えてゲットしておきたい「薬用ブライトニング」シリーズをレビュー
オールアバウト / 2024年6月22日 21時25分
-
ATELIER MUJI 企画展「文化を味わうものづくり 『にほんのさけ』 展」開催のお知らせ
PR TIMES / 2024年6月14日 16時15分
-
無印良品 冷凍和菓子 リニューアル発売のお知らせ
PR TIMES / 2024年6月14日 12時45分
-
関西限定 「古都華いちご いろいろ使えるシロップ」 数量限定で新発売
PR TIMES / 2024年6月4日 12時45分
ランキング
-
1ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分
-
2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分
-
3関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?
乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分
-
4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!
乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分
-
5上海の伊勢丹が営業終了、中国で日系百貨店の閉店相次ぐ…高島屋は売上高が減少傾向
読売新聞 / 2024年6月30日 20時56分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












