すべてのページは読み切れない…無印良品が2000ページのマニュアルを作る本当の理由
プレジデントオンライン / 2021年11月29日 9時15分
※本稿は、松井忠三『無印良品の教え』(角川新書)の一部を再編集したものです。
■無印良品のレジ後ろの棚にある2000ページの“マニュアル”
皆さんが無印良品に行く機会があれば、レジの後ろの棚をそっと覗いてみてください。そこに「MUJIGRAM」と書かれたファイルがずらりと並んでいるのが見えるかもしれません。
無印良品の店内のディスプレイも接客も、棚や冷蔵ケースなどの配置や照明の具合も、すべてMUJIGRAMで決められています。無印良品はMUJIGRAMでできているのです。
それとは別に、本部(本社)には、店舗開発部や企画室、経理部などすべての部署の業務をマニュアル化した、業務基準書というマニュアルがあります。
MUJIGRAMは2000ページ分、業務基準書は6000ページ超にも及び、なかには写真やイラスト、図もふんだんに盛り込まれています。
これほどの膨大なマニュアルをつくったのは、前述したように、個人の経験や勘に頼っていた業務を“仕組み化”し、ノウハウとして蓄積させるためです。
仕事で何か問題が発生したとき、その場に上司がいなくても、マニュアルを見れば判断に迷うことなく解決できる。たったこれだけのことでも、現場の実行力が生まれ、生産性は高まるでしょう。
■“マニュアル”ではなく“MUJIGRAM”
「無印良品には大量のマニュアルがある」という話を聞き、驚かれた人も多いでしょう。
無印良品の店舗に行ったことがある方ならわかると思いますが、スタッフがお客様に商品を積極的に売り込んだりするわけではなく、決まり切ったセールストークをしているわけでもありません。お客様は、自分のペースで商品を見て回れる雰囲気になっています。
この雰囲気こそ、無印良品を無印良品たらしめている特徴といえます。
ただ、この雰囲気をつくりあげるのは、スタッフ一人ひとりの個性ではありません。MUJIGRAMをもとに店づくりをし、スタッフを教育して、無印良品らしさをつくりあげています。
日本では、マニュアルという言葉にネガティブなイメージがあります。
マニュアルを使うと、決められたこと以外の仕事をできなくなる、受け身の人間を生み出す、と否定的な意見を耳にします。画一的で無味乾燥なロボットを動かすプログラムのようなイメージがあるようです。
しかし、そういう人をつくるのが無印良品の目的ではありません。そこで、マニュアルと言わず、MUJIGRAM、業務基準書と呼ぶことにしました。
■従うのではなく、つくる人になれるか
MUJIGRAMも業務基準書も、目的は「業務を標準化する」ことです。
それまでの無印良品では、店長が思い思いに店をつくり、スタッフの指導も店ごとに違っていたので、バラつきがありました。
どこの地域の無印良品に入っても、お客様に「無印らしさ」を感じてもらえるようにするには、店づくりも接客などのサービスも統一する必要がありました。
「この仕事は、あの人にしかできない」という状況は、本人にとっては誇りになるでしょう。無印良品にも、そのように社内で一目置かれている社員はいました。
しかし、本人が定年退職や突然の病気、転職などで抜けたら何も残りません。組織の未来のためには属人化ではなく、標準化するのが最善の道でした。
MUJIGRAMを読まずに店舗のスタッフが本部に質問しても、「それはMUJIGRAMで確認してください」と突き放すことになります。もしMUJIGRAMに書いていなかったら、それは新しいノウハウとしてMUJIGRAMに追加されることになります。
そこまでマニュアルを重んじていたら、社員やスタッフが自分の頭で考えなくなり、マニュアル人間化してしまうのではないか、と思う人もいるでしょう。
しかし、そもそも無印のマニュアルは社員やスタッフの行動を管理し、制限するためにつくっているのではありません。むしろ、マニュアルをつくり上げるプロセスが重要で、全社員・全スタッフで問題点を見つけて改善していく姿勢を持ってもらうのが狙いです。
ただマニュアルに従うのではなく、「マニュアルをつくる人」になれば、自然と自分の頭で考えて動く人材になります。
■マニュアルをつくったところから、仕事はスタートする
社員がマニュアルに依存してしまっているとしたら、そのマニュアルのつくり方や、使い方に問題があるのでしょう。
マニュアルによって、社員の仕事のレベルを均一にしたいのか、コストを削減したいのか、作業時間を短縮したいのか……企業によっても部署によっても、解決したい問題は異なります。これが定まっていないと、効果のないマニュアルになりかねません。
無印良品の店舗では店長が必ず常駐しているわけではなく、休暇や出張などで不在にしている場合も多くあります。そのうえ、店長でもマネジメントは不得手な人もいる。
それでもMUJIGRAMがあるから、いつでも滞りなく現場にいる人だけでお店を回せるようになっています。
店長などの社員は店舗の異動もあります。それでも現場が混乱しないのは、MUJIGRAMでどこの店でもすべての作業が標準化されているからです。新しい店長になっても指示内容が変わることはないので、スタッフは今までと同じ作業を続けます。
MUJIGRAMは変更点があっても、すぐに全店で共有されます。すると、基本的にお店の全員が同じ作業をするので、そこで「自分はこうやろう」「面倒だから、これを省こう」と、自分だけ違うやり方をすることにはなりません。空気のように当たり前の仕組みになれば、100%実行されます。
マニュアルは常に社員全員でつくりあげる“仕事の最高到達点”であるべきだと、私は考えています。そのためには、定期的に改善し、更新していく必要もあります。
マニュアルをつくったら、そこで一つの仕事は完成し終わったと考えてしまいがちですが、そうではありません。マニュアルをつくったところから、仕事はスタートします。MUJIGRAMに完成はなく、永遠に進化し続ける、生きたマネジメントツール(仕事の管理をする道具)なのです。
■なぜ「仕組みをつくる」と「実行力が生まれる」のか
私がマニュアルで実現しようとしたのは、次の5点です。
・業務のムダをなくし、生産性を上げたい(効率化)
・仕事を属人化しない(見える化)
・社員やスタッフの教育ツールとして使いたい(教育)
・無印良品の哲学、理念を隅々まで浸透させたい(社風づくり)
この5点が機能すれば現場のフットワークが軽くなり、実行力のある組織になると考えていました。
かつての無印良品では、本部が全国共通の販売企画を考えても、各店で実行されるまでに相当なタイムラグが生じていました。
一方でイトーヨーカ堂が強いのは、本部から通達があると翌朝にはすべての店の売り場が出来上がっているぐらいに、実行力に優れているからです。セゾングループではそれが、一週間から10日ぐらいかかっていました。店ごとに商品の配置を考えたり、企画を独自にアレンジしたり、まったく足並みがそろっていなかったのです。
機動力のある現場にするためには、仕事を標準化するのが第一です。たとえば、新生活応援キャンペーンを店舗で開催する際には、何日までに冷蔵庫とレンジと洗濯機を店のどの位置に置くか、パネルをどこに飾るかなどをすべて決めてあるので、翌朝までに売り場をつくることができます。
こういう判断を店側に任せるのではなく、すべてマニュアルで定めておくと、現場のスタッフが判断に迷わないだけではなく、入ったばかりの新人スタッフでも対応できます。誰でも、いつでも実行できるようにするのが、標準化の強みです。

■自分の頭で考えるには、基本となる“型”がいる
実際にMUJIGRAMを作成し、運用するうちに、マニュアルには以下のような想像以上の効果があると感じました。
① 「知恵」を共有できる
人は、一人でできる仕事は限られていますし、経験も知識も限界があります。自分で経験することなく、多くの人の知恵や知識を身につけられたら、成長をショートカットする効果があります。それを実現できるのがマニュアルです。
MUJIGRAMは本部だけでつくるのではなく、現場(店)で働いているスタッフの知恵をすくい上げて一つにまとめています。これにより、すぐれた知恵や経験を全員で共有できるようになり、個人の経験や知識を組織に蓄積できます。
② 「標準なくして、改善なし」
能の世界には「型破り」という言葉があります。伝統的な能の“型”を、実力のある演者がアレンジして新たな創造につなげています。
そういった創意工夫は、基本の“型”があってこそできるもの。無印良品のマニュアルも、“型破り”を繰り返しながら進化する、“血の通ったマニュアル”です。
仕事を標準化させるということは、その業務の最善・最適な方法を一つだけ決めるということになります。
たとえばフォルダの管理の仕方は、人によっても部署によっても異なり、必要な時に欲しいデータがなかなか出てこないのはよくある話です。これを部署で「この関連の資料はこのフォルダに入れる」と決めれば、担当者が休んでいても誰でも対応できるようになります。
そのように一つのフォーマットをつくりあげると、さらに使いやすくするアイデアが集まってきます。そうやって実行と改善を繰り返すうちに、業務はより洗練され、進化していきます。
標準をつくらないうちに改善しようとしても、迷走するだけです。何事も基本なくては応用がないのと同じで、無秩序な創意工夫は力になりません。
仕事も基本となる標準を固めないと、社員が応用して自分の頭で考えて働けるようにならないのです。
■細部を考えて実行し、人の役に立てる喜びを実感
③ 社員、スタッフの意識をそろえられる
それぞれの業務を何のためにするのかという「目的」を確認することは大事です。これをマニュアルに明記すると、それぞれの判断で勝手に動くことがなくなり、組織の一貫性がつくられます。
加えて、マニュアルは組織の理念を繰り返し伝えるためのツールでもあります。会議や全体集会などで、企業の理念やミッションを意識して伝えることも大事ですが、それだけでは浸透するのに時間がかかります。
だからクレド(企業の信条をまとめたもの)などを作成して、毎日みんなで読んで意識に刷り込ませようとしている企業が多いのでしょう。
マニュアルは日常的に、そこに書かれてある業務を通して組織の理念やミッションを浸透させる効果があります。理念を伝え続けると、チーム全員の志を一つにできる。すなわち全社員、全スタッフの意識をそろえられます。
④ 仕事の基礎力を身につけられる
マニュアルをつくる段階で、普段何気なくしている作業を見直すことになります。
たとえば、時間が足りないからと毎日のように残業をしているのなら、本当に時間が足りないのか。自分では必要だと思っている作業に、ムダがあるのではないか。そうやって仕事を見直すうちに、時間がないのではなく、自分の仕事の仕方に問題があるのだと気づきます。
多くの人はそれを考えずに、「残業しないで済む会社に転職しよう」と他に解決策を求めるかもしれませんが、それは根本的な解決策にはなりません。どんな会社でどんな仕事をしても、効率的に仕事をしなければ結果は同じでしょう。
逆に、マニュアルで仕事の効率化が身についたら、どこの会社に行っても通用します。社会人としての基礎力を身につけるのにうってつけのツールです。
⑤ 仕事の本質を考えるようになる
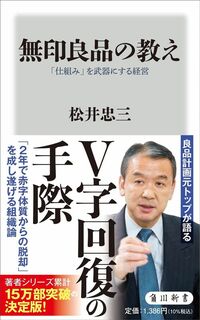
いいマニュアルは、「どのように働くべきか」「何のために働くべきなのか」という仕事の本質を考えるきっかけを与えることができます。
そもそもマニュアルは、お客様に満足してもらうのがゴールであり、単に社内を統率するためにつくるわけではありません。お客様に満足してもらうために、どう動くか。それを細部にわたって考えて実行するうちに、人の役に立てる喜びを実感できるようになるのだと思います。
自分や家族のために働く、それも一つの考え方です。しかし、どんな仕事でも人の役に立てるのであり、社会貢献につながるのだと思えたら、仕事の取り組み方も変わってきます。
----------
良品計画 前会長
松井オフィス社長。1949年、静岡県生まれ。73年、東京教育大学(現・筑波大学)体育学部卒業後、西友ストアー(現・西友)入社。92年良品計画へ。総務人事部長、無印良品事業部長を経て、初の減益となった2001年に社長に就任。08年に会長に就任。10年にT&T(現・松井オフィス)を設立したのち、15年に会長を退任。著書に『無印良品は、仕組みが9割』(KADOKAWA)など。18年2月には日本経済新聞に「私の履歴書」を掲載。
----------
(良品計画 前会長 松井 忠三)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
【無印良品】今こそ買いたい! 梅雨シーズンに役立つ元無印社員のイチ推しアイテム3選
オールアバウト / 2024年6月21日 20時20分
-
ATELIER MUJI 企画展「文化を味わうものづくり 『にほんのさけ』 展」開催のお知らせ
PR TIMES / 2024年6月14日 16時15分
-
可児市と共同で「一般社団法人 カニミライブ」設立のお知らせ
PR TIMES / 2024年6月10日 12時45分
-
スタッフ1人の1時間当たりの「平均歩数」を見ればわかる…人がどんどん辞める職場に共通する特徴
プレジデントオンライン / 2024年6月7日 9時15分
-
関西限定 「古都華いちご いろいろ使えるシロップ」 数量限定で新発売
PR TIMES / 2024年6月4日 12時45分
ランキング
-
1上海の伊勢丹が営業終了、中国で日系百貨店の閉店相次ぐ…高島屋は売上高が減少傾向
読売新聞 / 2024年6月30日 20時56分
-
2ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分
-
3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!
乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分
-
4意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分
-
5毎回"完売"続出。築地銀だこの「ぜったいお得な回数券」は、PayPay併用でさらにお得!
東京バーゲンマニア / 2024年6月30日 9時3分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












