「本番前に勝負はついていた」南極点到達レースに見る"成功する組織"と"失敗する組織"の差
プレジデントオンライン / 2021年12月24日 12時15分
■レースで鍵となる食糧貯蔵所「デポ」づくり
イギリス・ノルウェー両隊による南極大陸での大レースは、「デポ作戦」によって本格的に始まったといえよう。
「デポ」という言葉は、フランス語で「貯蔵所」を意味し、日本でも登山界でよく使われている。極点まで約1500キロの長い道のりを往復するための食糧や燃料は、全体では大変な量になる。一度にすべてを積みこんで極点へ旅立つことはとてもできない。
そこで本隊が出発する前に、途中に食料をあらかじめ点々と配置しておけば、それをたよりに往復することができる。そのようにして配置された食糧貯蔵所を「デポ」と略称した。またこうした方法はヒマラヤ8000メートル級の初期の大登山でも応用されて「極地法」と呼ばれた。
これから冬を越して、次の夏が来たらできるだけ早く本隊が出発するためには、冬のくる前にこのデポをつくっておく必要がある。それもできるだけ奥地まで、またできるだけ数多く配置するほど有利になる。
■先手を打ったスコット隊は十分な成果を出せず
このデポ作戦には、スコット隊のほうがアムンセン隊よりも早く出発できた点、まずは有利だった。1月24日、スコット隊長以下12人のデポ隊が、エバンズ岬の基地を出発する。馬ソリ8台(馬8頭)、犬ゾリ2台(犬26匹)で人畜の食糧7週間分をのせているが、うち5週間分は自分たちの消費用だから、デポ用は2週間分だ。
しかしながら、途中で人馬ともにさまざまな事故があり、最終的なデポ地点に行ったのは7人と馬5頭と犬ゾリ2台だった。とくに誤算だったのは馬である。途中の吹雪で3頭が弱りはてて返され、うち2頭は帰途に死んでしまった。残る1頭ものちに死んだ。
結局、スコット隊のデポ作戦は南緯79度29分、エバンズ岬の基地からは300キロたらずの位置が終点だった。ここに食料や飼料など合計約1トンを残して「1トンデポ」とよぶことになる。すでに2月17日になっていた。
デポ作戦隊がマクマード湾に帰ったのは2月下旬だが、スコットの犬ゾリが途中でクレバス(氷河の裂け目)に落ちて間一髪で助かるなど、馬の死とともに暗い材料が目立った。何よりも、デポが南緯80度までも達していない点はとても成功とはいえない。
では、アムンセン隊のほうのデポ作戦はどうだったか。
■犬ゾリで快調に前進するアムンセン隊
アムンセン隊はデポ作戦を2回にわけてやることにし、第1次デポ作戦にはアムンセン隊長以下4人が2月10日に出発した。ソリ3台、犬は各6匹で合計18匹。デポ用の食糧は合計約750キロ。ソリ1台あたり全荷物の重さ約350キロ。全員スキーをつけている。
出発はスコット隊よりも十数日もおそいが、犬ゾリのスピードは圧倒的だった。少ない日でも27キロ、多い日だと40キロ。しかも犬たちに何の支障もなく、わずか4日目の2月14日にはもう南緯80度に到達した。ここに最初の「80度デポ」をつくって帰り、荷のなくなった犬ゾリは、なんと1日最高100キロの速さで、しかも時には人間がソリの上で寝そべって走った。これはソリ旅行としては「猛スピード」である。途中1泊しただけで、15日の夜にはフラムハイムに帰着していた。
つまり、スコットのデポ隊は12人が往復1カ月もかかって南緯79度29分までだったのに、こちらは4人で往復たった5日間のうちに南緯80度へ第1のデポをつくったことになる。
犬ゾリ走行に大きな自信を得たアムンセンは、つづいて2月22日、第2次デポ作戦に出発した。こんどは8人でソリ7台、犬は合計42匹。つまりアムンセン以下全隊員9人のうち、料理係1人だけが留守番に残って出発したのだ。いささか荷を積みすぎたのと、すでに零下45度にもなる低温でさすがの犬も弱ったことで、スピードは第1次デポ作戦ほど出ないが、それでも3月3日には南緯81度に達した。

■最初のデポにアザラシ肉を追加貯蔵
ここに「81度デポ」をつくると、8人のうち3人は基地へ帰り、5人はさらに南進したが、犬のやつれが目立ち、3月8日の南緯82度までがやっとだった。できれば83度までと考えていたアムンセンも、重すぎた荷と寒すぎとですっかりやせてしまった犬たちを見て断念し、ここを「82度デポ」地とした。帰りの旅ではついに8頭の犬が力つきて死んでしまい、基地についたのは3月21日だった。
しかし、アムンセンは重ねて第三次デポ作戦を実行する。これはデポをもっと南に作るのではなく、南緯80度の「80度デポ」にさらに1.1トンのアザラシ肉を追加する目的だ。本番の極点攻略行にさいして、ここで犬が腹いっぱい食うことに、作戦上の重要な意味があった。
3月28日、この探検で初めて極光(オーロラ)を見る。
第三次デポ作戦は、3月31日から4月11日にかけて7人が犬ゾリ6台で実施したが、アムンセン自身は今回は基地に残っていた。
■日本の白瀬隊も漁船で南極大陸に挑戦していた
アムンセン隊の探検船フラム号もスコット隊の探検船テラノバ号も、両隊がデポ作戦をやっているあいだに、2月中ごろロス海を去った。次の夏がくるまで、もう南極大陸にはイギリス隊25人(ほかに6人の別動隊)とノルウェー隊9人が残るだけとなる。
同時期に南極大陸へのりこんだ日本の白瀬矗(のぶ)中尉の率いる南極探検隊は、流氷域を突破できなかったため、3月14日に南緯74度14分から引き返してオーストラリアへ向かった。5月1日にシドニー港にはいって、次の夏に再度挑戦をこころみるべく待機する。貧弱な漁船で、また極地探検の歴史もない当時の日本隊が、アムンセンやスコットの大探検隊に対抗したのであるから、かなわぬ相手だったとはいえ、やはり白瀬は大した人物だったといえよう。
さて、冬の闇を迎える前の両隊のデポ作戦はこうして終わったが、この段階での勝敗はもう明らかである。スコット隊が大人数で長時間かけて1回だけ、しかも80度までも到達できなかったのに、アムンセン隊は少人数で3回も往復し、82度まで進んで、デポした量もスコット隊の3倍になる。この大きな差はどこからきているのだろうか。
■アムンセン隊がエスキモー犬を主力にした理由
直接的には、スコットが馬を主力にし、アムンセンが犬を主力にした点にあるだろう。いくら寒い地方出身の小型馬(ポニー)だといっても、吹雪の中で雪にくるまって平気で眠るエスキモー犬にはかなわないし、危険な氷のクレバス(裂け目)も犬はよく予知し、落ちても軽いので引き綱でぶら下がって助かる。それは同時に、人間の落下を事前に防ぐという重大な役割をも果たす。

馬は大量のマグサを運んでゆく必要があるのに、犬はアザラシやペンギンなどで現地調達ができ、いざとなれば犬の肉自体がエサにされる。実際、アムンセンの第2次デポ作戦の帰りには、死んで埋葬された犬の死体を、夜中に他の犬たちが掘りだし、食べる順位をあらそって大乱闘になるほどだった。
反対にスコット隊のデポ作戦では、旅に出た8頭の馬のうち3頭を失い、さらにそのあとマクマード湾の海氷上を移動中にまた3頭を失って、わずか2頭が生き残るだけとなる。基地の1頭も死んで、全体としては残った馬が10頭だった。
■スコット隊はデポの量、質ともに完敗
しかし、スコット隊の敗れた最大の理由は、なんといっても極地に対する全般的な体験の浅さや、寒地での訓練不足であろう。イギリス隊も少し犬をもっていたとはいえ、ノルウェー隊のように自由に駆使するほどなれていない。スキーとなると、イギリス隊は南極で初めて習った者もいるほどで、ゲタのように使いこなしているノルウェー隊とは雲泥の差だ。
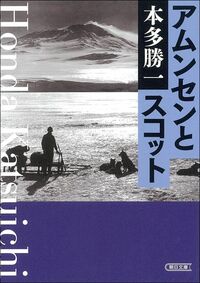
馬などをイギリス隊がこれほどあてにしたのは、それ以前のイギリス探検隊が使って、ある程度の成果があったし、もともと北極圏のシュピツベルゲンでイギリス隊が馬を使って以来の「伝統」だったことによる。この伝統はしかし、犬の能力とよく比較した上での選択ではなく、アムンセンから見れば、馬などを南極で使うなんて狂気のサタに思われただろう。白瀬隊さえもカラフト犬による犬ゾリを使ったのである。
こうした実力の差は、デポの量ばかりか、質の差に現れた。スコット隊はデポの位置に旗などを立てて目印にしただけだから、あとでさがす際に不安で、通りすぎたのではないかといつも心配しなければならなかった。
これに対してアムンセン隊は、進路にそって15キロごとに点々と竹や干し魚で目印を立てていったほか、デポの位置を通りすぎないように独特の確実な方法を考えている。すなわち進行方向に直角の線で、デポの両側に10本ずつの竹竿をたて、間隔は約900メートルにして黒い旗をつけたのだ。
つまり18キロもの長さで進路をさえぎる旗の列があり、それぞれの竹の番号によってデポの方角と距離がわかるようにしてあった。白一色の世界で、これはたいへん目立つやりかただ。
■メンタルケアにも心を砕いたアムンセン隊長
それに、隊員の心理的な面でもアムンセンはよく気をつかった。極地のような異常な環境に長くいると、神経がまいってイライラし、ノイローゼになる傾向があり、「探検病」とか「極地病」などといわれる。これを防ぐには、できるだけ心理的にゆとりをもたせることだ。たとえば毎日のテントは、3人用のものに2人ずつ寝た。のちに3人用の2個をつないで6人用とし、それに4人が泊まっている。
ところがスコット隊長は、ときには反対に4人用テントに5人つめこむといったことさえあり、人間の神経にとって実にまずい方法を摂った。
デポ作戦中にこうして明らかになった両隊の違いは、本番の極点到達レースにさいしても出てくるのは当然である。しかし、両隊は接することがぜんぜんないのだから、相手がどんなデポ作戦をやっているのか互いに知るすべもなかった。
----------
ジャーナリスト
1931年長野県出身。京都大学卒。朝日新聞記者、同社編集委員を経て、『週刊金曜日』編集委員。著書に『カナダ・エスキモー』(講談社文庫)、『日本語の作文技術』(朝日文庫)など多数。
----------
(ジャーナリスト 本多 勝一)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
KDDI MUSEUM、南極観測をテーマにした企画展を開催
PR TIMES / 2024年7月16日 16時45分
-
8月20日、国立極地研究所で小学生を対象にした「南極・北極からSDGsを考える」ワークショップを開催
PR TIMES / 2024年7月5日 15時45分
-
「艦」と「船」どっちなの? ふたつの“肩書”を持つ「しらせ」のナゾ 南極調査員を乗せずに出港も!?
乗りものニュース / 2024年6月29日 18時12分
-
テレ東、日本で唯一の砕氷艦「しらせ」に密着 ディレクターが南極観測隊員に同行
マイナビニュース / 2024年6月27日 16時0分
-
「露天風呂からオーロラを見る夢かなった」南極観測隊に参加した男性が語った思い出とは
京都新聞 / 2024年6月25日 7時30分
ランキング
-
1「発見」通報の女逮捕=殺人容疑、マンション男性遺体―京都府警
時事通信 / 2024年7月21日 22時54分
-
2トランプ氏銃撃、民主主義脅かす不安「感じる」76%…読売世論調査
読売新聞 / 2024年7月21日 22時0分
-
3エレキギターを持ったロック歌手がズブ濡れのファンとハグし感電死
東スポWEB / 2024年7月21日 14時57分
-
4政令市で唯一、福岡市の「夜のごみ収集」ピンチ…深夜のコンビニ休憩に「サボり」通報増加中
読売新聞 / 2024年7月21日 16時0分
-
5衆院選投票に裏金事件考慮73% 与野党伯仲半数望む、共同調査
共同通信 / 2024年7月21日 19時42分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











