「マーガリンはピンク色にするべき」そんなヤバい法律がアメリカで成立寸前になったワケ
プレジデントオンライン / 2022年1月6日 10時15分
※本稿は、久野愛『視覚化する味覚』(岩波新書)の一部を再編集したものです。
■バターの安価な代替品として生まれたマーガリン
酪農家らがバターの色の重要性をより強く認識するきっかけとなったのが、マーガリンの誕生である。これは、「バターの安価な代替品」として生まれたマーガリンが、バター生産者にとって大きな脅威となったためである。ヨーロッパ諸国では、バターの生産量が少ない年には、脱脂乳や牛脂などを使ってその代替品を作ることが古くから行われてきた。だがこれら代替品の生産はあくまで臨時的なものであり、大々的なビジネスとして確立されたものではなかった。
今日のようなマーガリンがバターの「代替品」として生産・販売されるようになったのは、1860年代末、フランス人化学者イポリット・メージュ=ムーリエがナポレオン三世の命を受けて開発したことに始まる。メージュ=ムーリエは、主原料に牛脂からとれるオレオ油を用い、それに少量の牛乳と着色料を混ぜることで価格を抑えた代替品を作り出し、これを「人工バター」と呼んだ。
彼は、1869年にフランスとイギリスで特許を取得し、2年後にはオランダのバター問屋アントニウス・ヨハネス・ユルゲンスとその息子らに売却した。その後ユルゲンスは、マーガリンの商業生産を本格的に始め、間もなくヨーロッパ周辺諸国にも広がっていった。ちなみに、後にユルゲンスの会社は他の複数の企業と合併し、今では世界有数の消費財メーカーとなったユニリーバが設立された。マーガリンはユニリーバの主力商品の一つだったものの、同社は、2017年、マーガリン部門の売却を発表した。
特にオランダやドイツ、デンマークでは、1900年までにマーガリンの消費量が、バターとほぼ同程度もしくはそれ以上にまで増加した。例えばデンマークでは、1900年の国民一人当たりの年間バター消費量が約7キロだったのに対し、マーガリンは8キロ近くに及んだ。
マーガリン消費拡大の理由の一つが、その価格である。それまでバターを購入できなかった労働者階級や農業従事者ら低所得者層の多くが、バターの代わりとしてマーガリンを使うようになったのである。また、バターの多くは、イギリスをはじめとする他のヨーロッパ諸国へ輸出されていたことも、自国でマーガリン消費が拡大した要因である。
■日本では「人造バター」として販売
マーガリンは、工業化と大量生産システムの進展を背景に生み出された最初の加工食品の一つである。また、ヨーロッパ以外の国・地域でも生産が始まり、最初にグローバル化が進んだ食品の一つでもあった。例えば日本では、マーガリン誕生間もない1887年に初めて輸入され、「人造バター」として販売された。
一方、バターが日本に入ったのは14世紀で、当時は形がかまぼこに似ていたことから、「牛かまぼこ」と呼ばれ「牛酪」と書くようになった。1908年には、横浜に本社を置く帝国社(後の帝国臓器製薬。現在のあすか製薬)が初めてマーガリンの国内生産を始めた。第二次世界大戦後には、植物性硬化油の採用、脱臭技術の進歩、ビタミン強化などによって、味も風味もバターに引けをとらないものができるようになり、その生産が拡大していった。1954年には、「人造バター」に代わり「マーガリン」を統一名称として販売されるようになった。
■マーガリンの販売を抑制しようとしたバター業界
アメリカでは、メージュ=ムーリエが同国の特許を取得した1873年以降、一挙にマーガリン生産が広まり、1880年代までに少なくとも80のマーガリン生産工場があったといわれている。マーガリンの主原料は、バターと異なり牛乳ではなく牛脂だったため、食肉加工業大手のアーマー社やスウィフト社らもマーガリン生産に乗り出した。これらの食肉業者は、マーガリン生産のみならず、牛脂を他のマーガリン製造業者に販売し、原料供給者としての役割も担っていた。
マーガリン消費量が拡大したヨーロッパ諸国とは異なり、生産開始後もアメリカでは依然としてバターの需要が高かった。マーガリン消費量が初めてバター消費量を抜いたのは1957年のことである。それにもかかわらず、バター生産者らは、1ポンド(約450グラム)当たり10から20セント程度安く販売されたマーガリンに市場を奪われることを恐れ、マーガリン業者に激しく反発した。そして、酪農業者協同組合や州・連邦政府とも協力し、マーガリンの生産や販売を阻む施策に乗り出したのである。
当時、酪農は、アメリカの農産業の中で特に強い力を持っていた。酪農生産者、卸問屋や小売店など関連業者を合わせると全国でおよそ500万人もが従事する一大産業で、政府に対するロビー活動の圧力は強力なものだった。マーガリン生産が始まった19世紀末のアメリカは、重工業が発展しつつあったものの、依然として農業国であり、特にウィスコンシンやニューヨーク、ペンシルベニア、ミネソタなど酪農が重要な産業となっていた州では、政府も酪農生産者らに同情的で、新興産業であるマーガリン業者への風当たりは強いものであった。
こうした州では早々にマーガリン規制法が制定され、生産・販売を禁止する州も出てきたのである。
■「自然な黄色はバターだけのもの」という主張
マーガリンを規制するにあたって、バター業者らは、偽装販売から消費者を守ることを理由にその取り締まり強化の必要性を主張した。マーガリンの販売が開始された当初、マーガリンもバターも現在のように個包装されていたわけではなく、小売店のカウンターに置かれたマーガリンもしくはバターの塊から、客の注文に応じて必要な分量をとり販売する方法がとられていた。そのため、生産工場から小売店に運ばれた後は、消費者の目にはマーガリンもバターも同じ黄色い塊にしか見えず、区別することができなかったのだ。
小売店の中には、バターの方が価格が高いため、安いマーガリンを仕入れ、バターと偽って販売する者も出てきた。酪農業者らは、バターとの違いが一目でわかるようにするため、マーガリンを別の色で販売するよう法律で義務づけるべきだと訴えた。
さらにバター生産者らは、「自然が作り出す黄色」はバターの「トレードマーク」であるとして、バター生産者が「占有する権利」を保持しており、バターの代替品、模造品として作られているマーガリンにはその黄色を使う権利はないと主張したのである。
これに対しマーガリン業界は猛反発した。そもそもバターの色も、必ずしも「自然な」状態のものではなく、特に冬場は着色されることが多かった。だがバターの着色を規制する法律はなく、マーガリン生産者らは、マーガリンの着色のみ規制するのは不公平だと訴えた。そして、もしバターの黄色が自然のものであるならば、誰も自然を所有する権利はなく、尚更バター生産者のみが独占すべきではないと反対したのである。
バター生産者のみならず、マーガリン生産者、さらに多くの消費者の間では、バターの「本来」の色は明るい黄色だという認識が強かった。そのためマーガリン業者および酪農家ともに、バターの代用品であるマーガリンは黄色以外(つまりバターには見えない色)では売れるはずがないと考えていた。すなわち色を規制することは、マーガリンの競争力低下とその生産・販売規制を意味していた。こうして、色がバターとマーガリンの対立の最重要争点の一つとなっていったのである。
■バターの色の標準化に動く酪農業界
マーガリンの誕生によって、バター生産者らは、より一層、色の重要性を強調するようになった。これまでは季節にかかわらず同じ色のバターを提供することが目的だったが、マーガリンが脅威となったことで、マーガリンと差異化を図るという新たな目的が加わったのである。バターのように見えるマーガリンと区別をするため、バターを「よりバターらしい」色にするという状況が生まれたのだ。
1900年代初頭、酪農業者らによる全米組織「全国酪農組合」の幹部委員は、組合のメンバーに向けて通知を出し、「酪農業界の救済」のためには、マーガリンと「区別できるよう、バターの標準色を維持し続けなければいけない」と語った。そして、バターの標準となる色は、マーガリンメーカーが真似できないほどの明るい黄色にすべきであり、これによって偽物を排除できると述べた。
しかし、色を含めバターの標準化は容易ではなかった。アメリカでは1910年頃まで、酪農業、特にバター生産は小規模農家が乳業やその他の農業生産の傍らに行う副業的な傾向が強く、その流通も地域ごとに行われていた。1860年代にはクリーマリーと呼ばれるバターやチーズの製造所が各地に作られ、農家が生産した牛乳を収集しまとめてバターやチーズを生産・出荷するようになった。だが、1910年代末までは、こうした製造所は小規模で、依然として農家ごとにバター生産は行われていた。
このため、バターの質は個々の農家のスキルや知識、保有している生産機械等に左右され、全国で画一的なバターが販売される今日の状況とは大きく異なっていた。バターの色についても標準化からはほど遠く、酪農産業向けの業界紙や農業新聞は、バターの色に常に注意を配るよう農家らに訴えた。
ある記事は、多くの農家がバターに使用する着色料の量をきちんと計らず、目分量で入れている状況を指摘し、こうした「軽率さ」ではバターを同じ品質で作ることはできないと批判した。酪農組合や地元の政府機関は、酪農技術や知識を広めるため、バターの基本的な作り方をはじめ、常に同じ色のバターを作るための指導を度々行ってもいた。
■餌によって色を変えたバターは「自然」といえるのか
ただ、バター生産者全てが着色に賛成していたわけではない。酪農産業界の中では少数派ではあったものの、特に着色料を使用することには、消費者を騙すことにつながるという声があった。だが、着色料使用反対派の間でも、ある程度画一化された黄色いバターを生産することは必要だという見方が強かった。
一部の新聞は、着色料を使うのではなく、例えば牛の餌にニンジンなど黄色(またはオレンジ色)の色素を含む植物を混ぜて食べさせることで、牛乳およびバターに黄色っぽい色味をつけることを推奨した。着色料は「人工的」な色の操作だが、餌の材料を調整することはあくまで「自然な」生産方法だと考えたのである。
だが、バターの色素が餌の一部に由来するものであったとしても、故意(人工的)にバターの色を作り出していることに変わりはなく、「自然」と「人工」の線引きの難しさ、その境界のファジーさを示唆しているといえよう。
■「マーガリンはピンク色に着色せよ」という法案まで登場
アメリカでマーガリンが登場してからおよそ10年後、1880年代に入ると、多くの州政府は、マーガリンの色に特化した規制を敷くようになった。これらの規制は、通称「反着色法(anti-color law)」と呼ばれ、例えば1886年に全国で初めて色によるマーガリン規制を導入したニュージャージー州は、「バターに似せた」色で着色したマーガリンの製造と販売を禁止した。
1898年までに26の州で反着色法が成立し、ヴァーモント州やニューハンプシャー州など一部の州では、着色そのものを禁止するのではなく、マーガリンはピンク色に着色して販売しなければならないという法案まで出された。
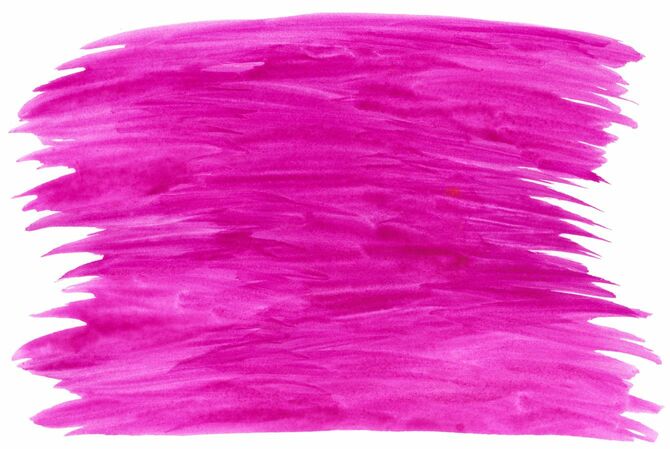
従来のマーガリン規制では、色によらずマーガリンとして製造されたものは全て規制対象となっていた。だが、前述の通りバターとの見分けのしづらさなどから、取り締まることが難しかった。そのため、マーガリンの見た目(色)が明らかにバターと異なるように生産・販売させることで区別しやすくするとともに、マーガリンの販売を抑止する効果を狙ったのである。当時販売されていたマーガリンのほとんどは黄色く着色されていたため、実質的にマーガリン業界全体の規制につながると考えられていた。
これは、バター業者も政府関係者らも色の市場価値や有効性、さらには色が競争力を高めも弱めもする武器となりうることを理解し、それを規制手段として用いたことを意味している。
■食べ物の色は政治的にも規定されてきた
こうした政府規制は、裁判所の判決によってその正当性や合憲性が認められることとなった。1894年、合衆国最高裁判所は、バターに見えるよう着色したマーガリンの販売を禁止する州法は合憲であると判断した。判決では、マーガリンは「バターの模倣品」として「人工的に着色」されたものであり、本来その「自然な」色は「薄い黄色」だという認識が判断の基準となった。
一方、少数派であったものの、この判決に反対票を投じた判事の一人は、マーガリンの「自然な色」はそもそもバターと同じ色であるとして、バターも人工的に着色して販売されているためマーガリンの着色のみ規制すべきではないと主張した。
ここで興味深いのは、判事らの間でマーガリンの色がバターと同じか否かという点では意見が割れたものの、そもそもバターの「自然な」色は濃い黄色であるという前提では一致していたことである(バターは必ずしも黄色ではないにもかかわらず)。さらに、この判決では人工着色すること自体は争点にはなっておらず、またそれが違法だという見解も出ていない。つまり、19世紀末の時点ですでに、食品を人工的に着色することは、食品の生産過程において合理的かつ必要なプロセスだと認識されていたということである。
黄色い(バターを真似た)着色の規制は合憲とされた一方、マーガリンをピンク色に着色することを定めた法律は違憲であるという判決が1898年最高裁によって下された。マーガリンを「自然な状態」ではない色にすることは強制できないとし、ピンク色のマーガリンが市場に出回ることはなかった。
ただこれも、マーガリンの「自然な」色が何であるのかを裁判所が判断を下した一例として興味深い。どのような色が法規制の対象となりうるのかや、マーガリンの色がいかに規制されるべきなのかを、政府そして裁判所が判断したことは、食べ物(この場合はマーガリン)のあるべき色が生産者や市場によって決められるだけでなく、政治的にも規定されてきたことを示唆している。
■黄色いマーガリンには40倍の課税
これらの規制は州ごとの法律だったため、州を跨いでの拘束力はなかった。そのため、バター業界は全国規模の規制を連邦政府に求めロビー活動を行った。1886年に制定された最初の連邦法「マーガリン法」は、マーガリンが着色されているか否かによらず、一律1ポンド当たり2セントの税金を課した。その後、連邦政府は、さらなる規制強化を求めるバター生産者らに対応する形で、1902年には改正法を制定した。
1886年法ではマーガリンの色は規制対象とはされていなかったのに対し、1902年の改正法は、色が規制の重要な基準とされた。黄色く着色されたマーガリンには、1ポンド当たり10セントという前回の5倍もの税金が課され、一方、着色されていないものは、課税額が引き下げられ1ポンド当たり4分の1セントの課税となった。
アメリカでこうしたマーガリン規制法が制定されたのに先駆けて、ヨーロッパ諸国ではすでにマーガリンの生産や販売を制限または禁止する規制法が成立していた。イギリスでは、法令として成立しなかったものの、マーガリンを赤色にするよう定めた法案が出された。
■マーガリンと着色料の「セット販売」
酪農大国でもあったデンマークやフランスは、バターの色に似せてマーガリンを着色することを禁止した。これらの法案や規制の内容からもわかるように、ヨーロッパ諸国でもアメリカでも、バター生産者および政府関係者らは、バターとマーガリンの見た目を明確に区別することが最も効率良く、そして有効にマーガリンの生産と販売拡大を阻止できると考えていた。

マーガリンの生産量および消費量が特に拡大したデンマークでは、マーガリン業者が生産規制に対抗して新たな施策を打ち出した。その一つが、黄色い着色料を小さな容器に入れ、マーガリンと一緒に提供することであった(通常、着色料は無料でマーガリン購入者に手渡された)。
消費者は、自宅で自ら着色料を混ぜてマーガリンを黄色くし、食したのである。マーガリンは、ラードなどのように料理に混ぜて使われる場合もあったが、バターの代わりとして使われる場合には、そのまま食卓に出してパンに塗ることも多かった。バターの「自然な」色は黄色だと考える消費者は多く、その代替として使うマーガリンも黄色いものを求めたのである。
このデンマークの事例はアメリカでも取り入れられ、1902年法の成立後、多くのマーガリン業者は、高額の税金を避けるため、着色をしていないマーガリンを製造販売すると同時に、黄色い着色料をカプセルに詰めて無料でマーガリン購入者に配布した。
マーガリン業者の一つ、ジョン・F・ジェルク社は、こうした新しい販売方法と家庭でのマーガリン着色を周知するため、消費者向けに発行した冊子の中で着色方法をイラストつきで説明していた(図表1)。このような家庭でのマーガリンの着色は、課税法が撤廃される第二次世界大戦後まで続き、家事労働の一つとして次第に定着していった。

----------
東京大学大学院情報学環准教授
東京大学教養学部卒業、デラウエア大学歴史学研究科修了。2021年4月より現職。近著に『Visualizing Taste: How Business Changed the Look of What You Eat』(ハーバード大学出版局)がある。
----------
(東京大学大学院情報学環准教授 久野 愛)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
米酪農場で鳥インフル感染拡大 「政府に反感」米国人の頑迷さが大流行の原因にも
産経ニュース / 2024年7月15日 13時0分
-
近所のスーパーは「鶏肉100グラム80円」なのでよく利用しています。母に「安すぎるのは危ない」と言われたのですが、大丈夫ですよね? そもそもなぜ安いんでしょうか…?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月14日 5時10分
-
北海道士幌町のふるさと納税返礼品「自慢の乳製品」6選
マイナビニュース / 2024年7月6日 8時0分
-
アイルランド政府食糧庁Bord Bia(ボード・ビア) 2023年度 対日乳製品輸出量12%増(*) サステナブルで高品質なアイルランド産乳製品を安定供給
PR TIMES / 2024年7月5日 23時40分
-
「ご飯が見えない…」とうもろこし農家が教える「炊き込みご飯」が“黄色い宝石箱” 14万いいねの大反響
よろず~ニュース / 2024年6月29日 11時20分
ランキング
-
1投資信託「以外」のほったらかし投資の選択肢とは 年利10%ならおよそ「7年で資産が倍」になる
東洋経済オンライン / 2024年7月21日 9時0分
-
2コメが品薄、価格が高騰 米穀店や飲食店直撃「ここまでとは」
産経ニュース / 2024年7月21日 17時41分
-
3サーティワン、大幅増益 「よくばりフェス」や出店増が奏功
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月19日 18時48分
-
4ウィンドウズ障害、便乗したフィッシング詐欺のリスク高まる…復旧名目に偽メール・偽ホームページ
読売新聞 / 2024年7月22日 0時0分
-
5物言う投資家エリオット、スタバ株を大量取得=関係筋
ロイター / 2024年7月20日 5時59分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











