「"努力は実を結ぶ"なんてウソである」理不尽な世界で生き残るために本当に必要な知恵
プレジデントオンライン / 2022年2月22日 10時15分
※本稿は、斎藤学『「毒親」って言うな!』(扶桑社)の一部を再編集したものです。
■「努力すればなんとかなる」という無責任なセリフ
私は、普段「それ言っちゃおしまいよ」と思うだろうことをたくさん言います。
例えば、「世の中は結局、親次第。親が裕福かどうか美貌の持ち主かどうかで、子どもの運命の8割は決まってしまうよね。その差を努力で埋めようとしても無理でしょう」などと言います。
意地悪な言い方だとは思いますが、理由があって言うのです。「努力すればなんとかなる」という無責任な、しかし耳触りのいいセリフを打ち消すためのフレーズなのです。これを言うことによって、努力の空回りの中にいる人を救おうという企(たくら)みです。
そもそも、恵まれた環境に生まれた人を見ていると、それほど幸せそうでもない。みんなに期待をかけられるから、背負うものが大きすぎて大変そうです。しかも、日本では上流階級といってもタカがしれているし、階層が不安定ですから、ちょっと油断しているとすぐに没落してしまいます。
■「努力が足りないからダメ」という考えをやめる
だから名門というと、いわゆる古典芸能の世界がわかりやすいのですが、幼少時から芸能を強いられるので、それはそれで大変。なぜそんなことを知っているのかというと、名家に生まれて、息抜きのしかたがわからないまま、ドラッグやアルコールの依存におちいった人々が私を訪ねてくるからです。彼らに比べれば、そこいらを気軽に歩けて、通りすがりに他人から声をかけられることもない生活のほうがずっと楽です。
「とりあえず、“努力が足りないからダメ”って考えるのをやめようよ。がんばればなんとかなるって本当? もう気づいているだろうけど、世の中は努力だけじゃないだろう? そこを努力でなんとかなると思うところが、きみの苦しさだよ」
努力を否定するわけではありません。「うまくいかないのは、まだまだ努力が足りないからだ」と思い込み、自分を責めてしまうのをやめさせるためです。
■努力が報われない人にかけるべき言葉
「あなたの悩みのほとんどは、自分の努力が効果を持たないことによるけど、それは当たり前のことだ。いくら努力しても、一流のピアニストになれる人もいれば、そうでない人もいる」
一見、残酷で、救いがないように思えるかもしれません。けれども、世間様に刷(す)り込まれた観念をはずした先に救いがあるのです。
いわゆる“世間の常識”というのは、かなり強固な観念です。世間様の言うことを信じている「世間様教」の信者は、世間様の目が気になります。世間様がよしとすることから、少しはずれてしまった自分に罪悪感がある。だから、私は世間で聞かないようなことを言うのです。
「いくら努力しても一流のピアニストになれない。しかし、きみはまったくピアノをやる気のない人に比べたら格段に上手じゃないか。その証拠に、今まで全然ピアノを弾いたことがなくて音符も読めない人に、ものすごく上手に教えられるじゃないか」
その人の努力はちゃんと実っているにもかかわらず、ただ本人が自分の努力の結果を認めたくないだけなのです。「一流のソリストになれないのは、私の努力がまだまだ足りないから」と思うのをやめれば、自分の努力がちゃんと実を結んでいることが見えてきます。
■信じている価値観を疑ってみることが大事
自分を責める(自罰)のをやめ、親に責任転嫁する(他罰)のもやめると、だいぶん楽になって、まともにものを考えられるようになってきます。そうすると、ほかの選択肢も見えてくるはずです。だから、まずは、さまざまな思い込みをいったん疑ってかかるとよいでしょう。
「俺はやればできる」→本当にそうかな?
「人間みな平等」→とは言えないかもしれない。
「努力は報われる」→こともあるかもね。
「親孝行しないと罰があたる」→だからどうした。
あなたが信じている価値観を否定して捨て去れというのではなく、いったん疑ってみると選択肢が増えるということです。そこから、もう一度選び直してみてはどうですか?もっとあなたが生きやすい価値観を再構築するために、ちょっと思い込みをゆるめてみませんか?
「それ言っちゃおしまいよ」というタブーをはずしてみると、そこに新しい世界への扉が開いているものです。
■「これを選べばうまくいく」絶対の正解はない
私がクリニックでやっていることは、最初から最後まで患者さんの凝(こ)り固まった“価値観念をはずす”ということにつきます。
あれでもよい、これでもよい、こういう方法もある……とたくさんの選択肢を柔軟に検討できる。その中から自分で「これがよい」と思ったものを選択し、選択した結果を他人のせいにしない。これは大人の条件です。何もかも100%うまくいく正解などはありませんから、うまくいかなかった部分は再検討すればよい。
ところが、直線的因果(いんが)論で“これを選べばうまくいく”という正解があると思っている人は意外に多いようです。その正解を選べずに道を踏みはずしてしまったのは、親の育て方のせい。無駄にしてしまった時間を取り戻すために、どこかで近道してうまくいく方法を探しているのが「毒親期」なのでしょう。できれば、うまく点数を稼げなくなったゲーム(人生)はリセットして、子ども時代に戻ってやり直したい。
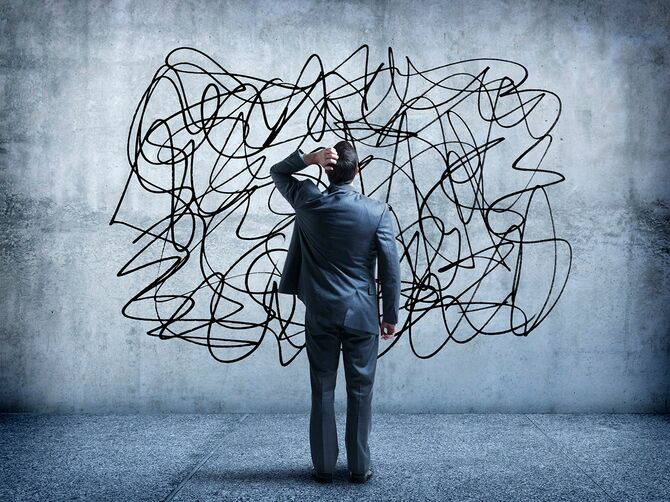
■凝り固まりがちな人はもっといい加減になろう
しかし、人生をリセットすることなどできませんから、そこから変化させていくほかありません。どこかに新しい句読点を打って、変化させてみる。そのためには頭を柔軟にほぐしたほうが楽なのですが、いくらほぐしても、もともと固まりたい人は何かの主義主張にすぐ凝り固まってしまいます。
主義主張(イズム)に凝り固まると、ほかの選択肢が見えなくなるし、自分が信じていること以外の選択肢を選んだ人を攻撃したくなります。もっといい加減になって、もう少し幅広く受容し、柔軟に人生に対処してほしいのです。
例えば、「お母さんの希望する大学を順調に卒業して、お母さんの願っているような会社員になろうとしなくてもいいんだよ。ほかにもいろんな生き方があるでしょ」と言うのは、「お母さんが言った通りにしてはダメだ」と言っているわけではありません。
「お母さんの望みに対して正反対の人生を生きよう」というのではなく、「お母さんの望んだ人生を選んでもいいし、ほかの生き方に目を移して選んでもいい。自分で選びとってね」というメッセージです。決めるのは本人ですが、“ほかの選択肢もありかもね”と考えられるようになってほしい。“この行動を選びなさい”という提案ではなく、あくまで“観念をゆるめましょう”です。
■観念に縛られていると次の一歩が踏み出せない
例えば、“働かざる者食うべからず”というのも、かなり強力な観念です。働いて自分の食い扶持(ぶち)を稼ぐのが一人前の大人だという考えは、私も間違っているとは思いません。しかし、その観念に縛られているばかりに、次の一歩が踏み出せず、がんじがらめになって立ち止まってしまう人もいます。
そういう人には、いったん「働かなくても食ってよい」と思ってもらうことが有効な場合があります。立ち止まったままでいるよりも、縛りを少しゆるめて動き出したほうが、変化が訪れるからです。
「あなたね、頭の中でまともに“早く仕事をしなければ”とか考えてない? それが、そもそもの間違い。今まで仕事、仕事って真面目に考えていい思いしたことあるの? ちょっとでも天職だと思った仕事はあったの? そうじゃないから困っているんでしょ」
「今まで一生懸命やってきたことの結果は、あなたに借金しか与えなかった。案外違うところに、あなたの成功が待っているのかもしれないよ。でも、それを見つけるのは容易なことじゃない。そう考えれば、数年休んだっていいんだ。とにかくきみは今、なぜ失敗に終わったかという原因探しばかりやっていて、その仕事に意味があったか、その仕事を社会が要求していたかを考えていない。間違ったことに一生懸命頭を働かせているから結論が出ない」
■「うまくいかない今」から視点を変えるインパクト
「そもそも、仕事をしていない今の時間を無駄だと思っていることも間違い。今の時間が、きみにとってすごく大事なんだ。中途半端に仕事をしていたときのほうが、何かをやっているつもりで本当は何もやっていなかったのかもしれない。人は悩まないと伸びないんだし、自分はダメだって悩みがあるんだったら、それを利用しない手はないじゃない」
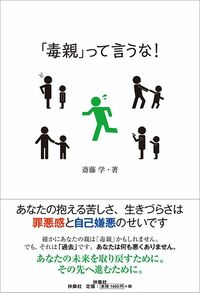
こんな会話で気が楽になり、「この前の話で、頭がすっきりしました」と動き出す人もいます。思わぬ挫折(ざせつ)に茫然(ぼうぜん)として、うまくいかなかったことの原因探しでいっぱいになっていた頭と身体を切り替え、これからどうするか、行動していくほうにパワーを使えるようになれば、変化はあっというまに起こります。進むべき方向が見えてくる。そして、これは本人にしか出せない答えです。私は、彼らの気持ちを楽にして頭をほぐすだけ。
平たく言えばポジティブシンキングですが、「前向きに考えようよ」と勧めたからといって、すぐポジティブになれるわけでもない。だから、具体的な会話をしながら物事の見方を変え、別の視点を提出します。今の「ダメだ」と思っている自分もダメではない、それはそれで意味があるんだという価値を見つけてほしいのです。
----------
精神科医
1941年東京都生まれ。1967年慶應義塾大学医学部卒。同大助手、WHOサイエンティフィック・アドバイザー(1995年まで)、フランス政府給費留学生、国立療養所久里浜病院精神科医長、東京都精神医学総合研究所副参事研究員(社会病理研究部門主任)などを経て、医療法人社団學風会さいとうクリニック理事長、家族機能研究所代表。温かさや安心感などが提供できない機能不全家族で育った「アダルト・チルドレン」という概念を日本に広めた。著書に『すべての罪悪感は無用です』『「愛」という名のやさしい暴力』(ともに小社刊)など多数。
----------
(精神科医 斎藤 学)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
松下幸之助は「ダメな部下」をどう叱ったか…入社18年目の課長に「会社を辞めて、しるこ屋になれ」と説いたワケ
プレジデントオンライン / 2024年5月30日 10時15分
-
過保護に育てられた女性の「困った恋愛傾向」4選
KOIGAKU / 2024年5月25日 17時53分
-
無神経な言動にモヤモヤ...「一緒にいると疲れる人」と距離を置く5つの方法
PHPオンライン衆知 / 2024年5月24日 12時0分
-
子育てにイライラ「叱らずに」済むテクニック 石田勝紀×天野ひかり「子育て」対談ー後編ー
東洋経済オンライン / 2024年5月23日 16時0分
-
子どもが友達の悪口を言っていたらどうするか…児童精神科医が「やめなさい」の一言をグッと飲み込んで口にした"ある質問"
プレジデントオンライン / 2024年5月12日 9時15分
ランキング
-
1「富士山を黒幕で隠す」日本のダメダメ観光対策 「オーバーツーリズム」に嘆く日本に欠けた視点
東洋経済オンライン / 2024年6月2日 8時0分
-
2サクラクレパスの「こまごまファイル」が“想定外”のヒット、なぜ?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月1日 8時10分
-
3「みどりの窓口削減計画」はなぜ大失敗したのか…JR東が誤解した「5割がえきねっとを使わない」本当の理由
プレジデントオンライン / 2024年6月2日 7時15分
-
4PIAAからヘッド&フォグ用LEDバルブ 6000K「超高輝度」シリーズ・5製品が登場
レスポンス / 2024年6月2日 10時30分
-
5なけなしの貯金と「年金月14万円」で暮らす70代女性、冷房代が払えず「“タダで涼める”スーパーへ避難生活」が続くも…「店長のひと言」で人生が一変したワケ
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月29日 9時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










