「平均的なサラリーマン」は消滅した…この10年で雑誌の部数が激減した本当の理由
プレジデントオンライン / 2022年2月23日 9時15分
※本稿は、廣田周作『世界のマーケターは、いま何を考えているのか?』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。
■ミシェル・オバマが身につけていたアイライナーの正体
Fentyというブランドをご存じでしょうか。Fentyは、バルバドス出身で、現在米国で活躍しているアーティストのリアーナ・フェンティが立ち上げたブランドです。
リアーナと言えば、音楽の世界で多くのビッグヒットがあるので、アーティストとして知っている人も多いと思うのですが、実は、アパレルやビューティの業界において、事業家としても大成功しています(現在、アパレルについては、休止中)。Fentyにはビューティ事業があり、彼女の音楽のファンのみならず、広く支持されています。
なぜ、支持されているのかと言えば、リアーナが、黒人の女性として「なぜ自分の肌の色に合うファンデーションが売られていないのか?」という視点を持って、さまざまな肌の色の人たちに合う化粧品を開発しようと企画したところに理由があります。
「なぜ、ビューティ企業は白人のモデルばかり起用するのだろう?」「なぜ、自分の肌の色に合ったメイク用品がないのだろう?」そう思っていた人たちから、リアーナの「気づき」に対して、大きな共感と支持が集まったのです。
Fentyが謳っているのは、「Beauty for All」。
つまり、「すべての人たちにビューティを」ということ。
既存の美容業界は、セレブリティや大手メディアなどの「エスタブリッシュメント」が中心となって、ビューティのトレンドを決めてきました。
ビューティのブランドは、広告を通じて「今、これがトレンドのスタイルなので、みんなもここに憧れてください」というメッセージを発信し、煽り続けてきたわけです。
ビューティ業界は、トレンドをつくり、フォロワーに追いかけさせるという「憧れの連鎖」を、広告活動を通じて巧みに構造化してきたとも言えます。
しかし最近、「ビューティとは誰かから押しつけられるものではなく、使う人自身を表現するツールである」という考え方が出てきました。
「ビューティは自己肯定感をあげるもの」、あるいは「自分を表現するもの」「アイデンティティを守るための道具」というように、美の在処を「メディアやセレブリティ側が持っているもの」ではなく、「あなたの中に本来あるもの」だとする考え方です。
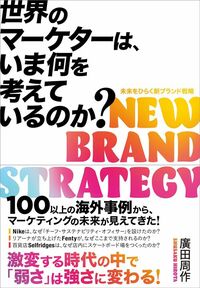
今、支持されている美容ブランドは、既存の業界とユーザーとの関係を逆転させ、「ビューティは、ユーザーの中にある魅力を引き出し、肯定するツールだ」と再定義し始めているのです。
2021年、バイデン大統領の就任式に参列していたミシェル・オバマ氏が、身につけていたアイライナーが、まさにFentyのものだったのは記憶に新しいでしょう。
私は、これは非常に象徴的なシーンだったと思います。もちろん、当のFentyにしてみればプロモーション的な側面もあったでしょう。
ただ、それ以上に、「ミシェル・オバマがFentyをつけていた」こと自体が、多くの人を励ます大きなパワーを持っていたのではないでしょうか。
■大手の化粧品メーカーはなぜ真似できないのか
この話を聞いて「たかだか、アイライナーやファンデーションにさまざまな色を加えただけでしょ」と思ってしまうと、本質を捉えることはできません。
資本力のある大手の化粧品メーカーであれば、表面だけを真似ることは簡単にできます。
実際、ある企業が、Fentyよりも色の数を増やしたファンデーションを発売しましたが、鳴かず飛ばずの結果でした。売り方だけ真似をして、何色ものファンデーションを出したとしても、リアーナの気づきや勇気、振る舞いが抜けてしまえば、ブランドとしては支持されないのです。
ブランドとして重要なのは、リアーナのように「本気で未来への約束ができるか」ということなのです。つまり、現代のブランドは、技術力や商品ラインナップだけではなくて、お客さんと向き合う姿勢や、振る舞い、「世の中を本気で変えていこう」とする勇気が問われている。かたちだけ真似をしても意味がないんです。
「多様性が流行っているから、ブランドのアンバサダーにレインボーカラーのドレスで登場してもらおう」といった表面的な企画では全くダメなんですね。そういう「おためごかし」は、簡単に見抜かれてしまいます。
もちろん、リアーナが「言っていること」のみならず、それを「体現しているプロダクト」も高いクオリティにあることが大事です。
思想的な約束をするのであれば、当然品質も高くなければなりません。モノも、製造プロセスも、信念も、売り方も、ブランド活動、ブランド接点、すべてに一貫性が問われる時代になったのです。
■企業は消費者に、未来の安心を約束できるか
マーケティングの教科書では、市場のどこにニーズがあって、どこにターゲットがいて、その人の課題は何かを細かく特定して、それを解決していくことが必要だと習います。
いわゆる、コトラーのSTP戦略ですね。要は消費者のニーズを掴み、そのニーズを満たせばプロダクトは売れるということです。
しかし、現代はSNSなどを通して、企業の姿勢そのものが人々に見えやすくなったこともあり、単に消費者のニーズを満たしていれば売れるというわけにはいかなくなっています。
これまで、消費者に見えているのはせいぜい広告かプロダクトだけで、企業内の活動は「密室」で行われていても、問題視されることはありませんでした。
しかし、情報公開や、透明性が求められるようになると、企業の経営者の思想や発言、製造プロセス、従業員の振る舞い自体が大いに問われるようになったんですね。スキャンダルも揉み消せなくなっています。
そこで、ニーズを満たすこと以上に重要になってきているのが「企業が消費者に、どこまで未来の安心を約束できるか」ということなのです。
ブランドのストーリーや思想はもちろん、それをどのようなプロセスでかたちにしているのか、どのように売ろうとしているのか、具体的な行動も問われているのです。
■LGBTQのタレントやモデルを起用しなかったブランドの顛末
ここで、ちょっと悪いケースですが、ヴィクトリアズ・シークレットの事例を紹介しましょう。
同社は高級女性下着メーカーで、毎年、派手なショーをテレビで中継したりして、話題をつくってきた会社です。
しかし、2018年に同社の幹部のひとりが、ショーにLGBTQのタレントやモデルを起用しないということを発言して大問題となりました。大変なスキャンダルとして、ニュースで取り上げられたこともあり、みなさんの記憶にも新しいと思います。
その下着がいかに、高級で素晴らしいデザインであったとしても、幹部の思想や振る舞いに差別的な視線があったことで、不買運動にまで発展してしまったのです。そして、その直後、同社の株価が半減する事態に陥りました。
ちなみに、私は、たまたま見たネットフリックスのドキュメンタリーで、かの「児童売春」で有罪となったジェフリー・エプスタインが、一時期、ヴィクトリアズ・シークレットの幹部だったという話を知り、さらにゾッとしました。
対照的に、先述したリアーナは、当時、ヴィクトリアズ・シークレットの顛末を意識して、彼女らしく、インクルーシブな視点を大事にした下着のブランド「Savage X Fenty」を立ち上げることを宣言し、大きな共感を集めました。
面白いことに、このリアーナの立ち上げた下着ブランドの「Savage X Fenty」のショーに、これまでヴィクトリアズ・シークレットのショーに出ていたモデルたちが、一斉に出演したのです。
もちろん、下着そのもののデザインに関する好みや機能性の違いはあるかもしれませんが、「一連の顛末を見て、あなたはどっちのブランドを支持しますか」と問われた時、圧倒的にリアーナのブランドに支持が集まるのは想像に難くありません。

リアーナは、さまざまな体型の人にも似合うサイズの下着をつくり、「包摂性の高いブランド」を通して、未来への約束を人々と結ぶことができたのです。考え方、行動、プロダクト、これらすべてに一貫性があることが、ブランドにとって非常に重要なのです。
■共感を得られる「マスニッチ」の事例
最近、「今までのようにモノが売れない」という声をよく聞くようになりました。
それもそうです。市場が成熟し、モノやサービスが溢れている中で「まだ行き渡っていないけれど、『みんなが欲しい何か』がある」という考え自体が幻想に近いのです。
一方で、局所的にはモノが売れている市場もあります。先ほど紹介したリアーナのブランドはもちろん、こだわりの強いハイブランドの製品はなかなか手に入りにくいですし、ヨーロッパで流行っている競技用のe-bikeなどは、あまりの人気で購入までに1年以上待たなければなりません(2021年10月現在)。
私個人でいえば、京都にあるサンガインセンスというお香のD2Cブランドからラベンダーの香りの線香を購入しようとしていたのですが、見るたびに売り切れていて、一時期、なかなか手に入らないこともありました。
グローバルのマーケティングの世界では、こういった局所的にモノが売れる現象を、よく「マスニッチ」という言葉で説明しています。
これは、一見ニッチなインサイトでしかないけれど、よくよく掘り下げてみると、意外にも「実は、私も気になっていたんだよね」と多くの人からも共感を得られるという意味合いで使われるマーケティングの用語です。
例えば、米国に「Modern Elder Academy」という、離婚をしたり、仕事を失ったりと、人生の難しさや苦さを味わっているような、「中年の危機」に悩む大人向けの研修サービスがあります。
つらい経験をしている人たち同士が集まって、お互いに悩みを語り合うことで、一緒につらさを乗り越えていこうとする試みです。
当初は、相当ニッチなサービスだと想定して開始したそうなのですが、蓋を開けてみると、実は、多くの人が「そういう場こそ、求めていた」ということで、思わぬ反響があったそうです。まさに、マスニッチの事例と言えます。
■「平均的な人」は、今存在しているのか
モノがなかった時代には、「平均的なニーズ」を考えるセンスがあればモノは売れました。
平均的なサラリーマンであれば、こういうスーツを着るはずだ。こういう栄養ドリンクを飲むはずだ。こういう車が欲しいはずだ。平均的な主婦であれば、きっとこんなドラマを見るはずだ。こういう服が欲しいはずだ、というように。
しかし、そのような「平均的な人」は、今存在しているのでしょうか。立ち止まって考えてみると、全部が平均みたいな人なんてどこにもいませんよね。
現実に暮らす人々は、年収も、趣味も、暮らし方も、仕事の内容も、もはや、みんなバラバラです。貧富の差が広がり、二極化しているといわれますが、価値観に絞っていえば、二極どころではなく、多極化しています。
例えば、昔はよく売れていた「総合ライフスタイル系ファッション雑誌」の部数が、ここ10年で激減していますよね。
出版社の人は、出版部数の激減の理由を、「デジタル化」への対応の遅れであると考えがちですが、私は「平均=マス」向けの「ライフスタイル」なんて、もう存在しなくなってしまっていることの方が原因として大きいと思います。
雑誌でまとめられるよりも、個々にインスタグラムで好きなインフルエンサーを追いかけていた方が参考になるからです。
もう、「平均的なトレンド」への需要はないのかもしれません。
アパレル業界だって、ビッグサイズや、スモールサイズを扱うようになっていますよね。3Dプリンタなどの技術を用いながら、その人のサイズにぴったりと合った縫製をするアパレルも増えてきています。
例えば、スタートアップ企業のunspunは、3Dプリンタを使ってすべての人にぴったりのジーンズをつくることを売りにしています。
■マス的な発想からはもうヒット事例は出てこない
よく、「これからの時代は、モノじゃなくて、コトを売るんだよ。やっぱり体験だよ」なんてわかったような、わからないようなことをいうマーケターがいますが、「モノか、コトか」という議論に、私はそんなに意味はないと思っています。
「ニッチでも、価値観がはっきりあるモノやコト」は売れるケースがあるけれど、「全員が買う」という現象がなくなっただけではないでしょうか。私は、今後のブランドのヒット事例は、マス的な発想からはもう出てこないと思っています。
マスニッチのように、ある少数の人のインサイトを深く掘っていくと、意外にも多くの人にも共感されるようなヒットはあっても、最初から「平均的なみんな」を想定するマスマーケティングの発想からは、深く共感される価値を導くことが難しくなってきているからです。
先ほど言及したFentyはまさに「平均」ではなく、「私(たち)」から発想されたブランドでした。平均的消費者像を描いてみたり、最大公約数的な価値観を延々議論したりするだけでは、到底「ヒット作」をつくれなくなっているのが現実です。
■対話して価値観を引き出すNYのメディア
Refinery29という、アメリカのニューヨークから広まった、ファッションやビューティをテーマにしたオンラインメディアを知っていますか。
今や、VogueやElleなどの大手オンラインメディアのアクセス数をしのぐとまでいわれている、新興の分散型メディアです。まさに、このメディアも既存のファッションや、美容業界の考え方をひっくり返そうとしています。
私も過去、2度ほどニューヨークのオフィスを訪問させていただいたことがあるのですが、とても活気に溢れたメディアカンパニーだなという印象でした。
同メディアは「私たちは、女性たちがビューティを自己表現の手段として使いこなせるようにツールとしてのビューティ情報を女性に提供します。私たちは、女性に力を与えます。私たちは、ビューティのあり方を再定義するメディアです。
私たちは、既存の慣習を変えることに挑戦し、伝統にとらわれないものを支持し、今日の美容界で最も影響力のある“声”として読者との会話をリードします」と、自らのコンセプトを語っています。
要するに、Refinery29は「トレンドを押しつける」のではなく「対話して、価値観を引き出す」アプローチで成功したメディアだといえます。
基本は、ファッションや美容に関係する記事が多いのですが、政治社会やアイデンティティに関する記事も多いのも特徴です。記事の文体も、「みんなはどう思う?」と語りかけ、対話を活性化させるように気を配っています。
■「美しさの正解」を押しつけてはいけない
「対話して引き出す」のは、従来のマス広告中心のマーケティングにはあまりなかった姿勢で、セレブリティを模倣させたり、読者にトレンドを押しつける従来のやり方とは一線を画すものです。
あなた自身の表現の幅を広げるにはどうすればいいのか、あなた自身のよさを引き出すにはどうすればいいのか、という視点をブランド(Fenty)やメディア(Refinery29)が明確に持つことが大事です。ユーザー自身が「主人公」として関与できる関係性が支持されているのです。
言い換えれば、企業が消費者を型にはめ、一斉にマス広告を投下し、同じ製品をたくさん売りつけるという態度は、もはや支持されなくなったということです。
あくまで語るのはユーザーであり、ブランドはそのサポートに回るべきなのです。
ところで、マーケティング戦略を立案する際に、「パーソナライズ」という言葉をよく聞くようになりました。これは、企業がお客さんに関連するパーソナルデータや、ビッグデータを用いて、お客さんの特性に合わせた商品やサービスをレコメンドするという意味で捉えられています。
ですが、本来はユーザー側の論理に、企業が合わせるという意味で使うべき言葉だと思います。例えば、ユーザーが主人公になった場合、どのように企業としてサポートできるのかという視点ですね。パーソナライズして売りつける発想ではなく、パーソナライズして関与してもらう視点が大事です。
よく見かけるようになった「ボディ・ポジティブ」という言葉も、この文脈で考えるとわかりやすいと思います。
いままでは、“痩せてシュッとした”体型のモデルがビューティのスタイルを牽引してきました。しかし、世の中にはさまざまな体型や体格の人がいます。
そして、人が何を美しいと思うかは、多様でいいはずですよね。
誰にもジャッジされる必要はなく、自分で自分に自信があればそれでいいんです。
お客さん側からすれば、メディアやブランドが勝手に決めた「美しさの正解」を押しつけられても、人によっては、そこに居場所がないと感じてしまいます。
「これが美しい」という発信は、同時に「あなたは美しくない」という意味を言外に伝え、疎外感を与えてしまう場合もあるのです。
そうではなく、やはり「ビューティはあなたの中にあり、それを引き出すためにはどうすればいいのか」という視点が重要です。
ちなみに、ここで公正のために述べておきたいのは、Refinery29のような「リベラル」なメッセージを売りにしている企業でさえ、「上層部は、白人女性ばかりが声が大きく、差別的で、有害な職場だ」という声が内部から上がり、編集長が交代するようなニュースがありました。念のため、ここでお伝えしておきます。
「100%素晴らしい」とは全面的に紹介できないところに、現代のブランドの難しさがあります。
いやはや。
----------
ブランドリサーチャー
1980年生まれ。放送局でのディレクター、広告会社でのマーケティング、新規事業開発・ブランドコンサルティング業務を経て、2018年8月に、企業のブランド開発を専門に行うHenge Inc.を設立。英国ロンドンに拠点をもつイノベーション・リサーチ企業Stylus Media Groupのチーフ・コンサルタントと、Vogue Business(コンデナスト・インターナショナル)の日本市場におけるディレクターも兼任。
----------
(ブランドリサーチャー 廣田 周作)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
美貌のトップモデルが「よく間違われる」と吐露 似すぎているモデルは1歳違いの同じブラジル人
よろず~ニュース / 2024年5月31日 12時15分
-
【2403人調査】3人に1人は故障したタイミングでキャンプ用品を売る!?~キャンプ用品の買取に関するアンケート~
PR TIMES / 2024年5月30日 11時45分
-
ホームセンターの生き残りをかけたPB戦略 大手メーカーが支配する市場参入のカギは細分化
ORICON NEWS / 2024年5月29日 10時17分
-
“ユニクロの対極をいく”アパレル企業が、「創業から5年8ヶ月」で新規上場した納得の理由
日刊SPA! / 2024年5月22日 8時53分
-
「ハイチュウ→HI-CHEW」になってどうなった? 意外な人に売れた秘密
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月9日 9時5分
ランキング
-
1「富士山を黒幕で隠す」日本のダメダメ観光対策 「オーバーツーリズム」に嘆く日本に欠けた視点
東洋経済オンライン / 2024年6月2日 8時0分
-
2サクラクレパスの「こまごまファイル」が“想定外”のヒット、なぜ?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月1日 8時10分
-
3「みどりの窓口削減計画」はなぜ大失敗したのか…JR東が誤解した「5割がえきねっとを使わない」本当の理由
プレジデントオンライン / 2024年6月2日 7時15分
-
4PIAAからヘッド&フォグ用LEDバルブ 6000K「超高輝度」シリーズ・5製品が登場
レスポンス / 2024年6月2日 10時30分
-
5なけなしの貯金と「年金月14万円」で暮らす70代女性、冷房代が払えず「“タダで涼める”スーパーへ避難生活」が続くも…「店長のひと言」で人生が一変したワケ
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月29日 9時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










