「セックスの不満は我慢するしかない」女性用風俗の利用者が男性セラピストに伝える共通する悩み
プレジデントオンライン / 2022年3月30日 17時15分
■意外にも性感より「デート」の需要が高い
女性用風俗――。略して“女風”が勢いづいている。私はこの世界を数年にわたって取材しているが、最近は店舗数が増えますます活気を増しているという実感がある。女性用風俗の男性従事者は、セラピストと呼ばれる。
なぜ、彼らはこの世界に足を踏み入れたのか。そして、日々どんなことを考えているのか。セラピストの思いと、そこから見えてくる現代社会を生きる女性たちの生きざまを追った。
女性用風俗のセラピストで多くを占めるのは、あくまで本業は別に持ち、本業の空き時間に働く“兼業セラピ”だ。彼らは昼間、社会人として一般企業に勤めていたりする、いわば普通の男性たちである。兼業セラピストの本業として多いと感じるのは、アパレルや美容関連といった日常的に女性と接する職種だ。しかし、中には一部上場企業やIT関連勤務のサラリーマン、塾講師などもいる。
「風俗」と名がつくと、エッチなサービスである性感をイメージすることが多いが、女風では、意外とデートをメインとするセラピストの需要も高い。彼氏のように一緒に買い物をして、キッチンに立ち料理を作ったり、一緒に映画を見たりして癒やしの時間を過ごす。いちゃいちゃしたりハグしたりはするが、性感はあくまでおまけという位置づけだったりする。
セラピストも玉石混合で、中には芸能人顔負けのルックスを売りにする容姿端麗なセラピストがいたり、逆にルックス度外視で、自らの「なめ技」などのテクを武器として、エロを売りにするセラピストもいる。
女風店舗「シェアカレ」で新人セラピストとして勤めるユニさん(27歳)は、コロナ禍真っただ中に入店した男性の一人だ。ユニさんの女風の勤務歴は、1年ほど。ユニさんの本業はスタイリストだ。ユニさんは、爽やかで清潔感のある少年タイプだが、これまでは風俗の業界とは全く縁がなかったという。
■「女性の心や体をもっと知って、人間として成長したい」
コロナ禍のデビューということもあり、経済的な事情での入店かと思いきや、そうではないという。ユニさんは、女風デビューの動機をこう語る。
「これまで自分が人間として未熟だなと感じることがあって、成長したいと思ったんです」
話を聞くと、入店の動機は、最後に付き合った彼女の存在が大きかったという。ユニさんは年上の女性が好きで、これまでも付き合ってきた女性たちのほとんどが年上だった。それは自分の母親のような強い女性に憧れていたからに他ならない。歴代の彼女たちは、母親のように世話を焼いてくれたし、それが当たり前だと思っていた。
しかし最後に付き合った女性は、そんなユニさんの勝手な“彼女像”をことごとく打ち崩したのだという。
例えばこれまでの彼女は、家でご飯を食べるときも料理が出てくるまで待っていれば良かった。しかしその女性は、一緒に料理を作ることを求めてきた。「自立した」男と女の在り方を、ユニさんはそのとき人生で初めて知ったのだ。
「いざ自分がキッチンに立つと、何をどうすればいいのか、全くわからなかったんです。これまで自炊をしたこともないし、そんな自分が歯がゆかった。でも、この自分の幼稚さは料理だけの問題じゃない。自分の人生において全て通じることだと感じたんですよ。このままだと自分は人間として小さいままだし、マズいと焦ったんですよね。女性の心や体をもっと知って、寄り添いたい。女性の欲の根源の部分に触れることで、本質が見えるんじゃないか。それが、僕が女風をやってみようと思った動機ですね」
結局、女性とは別れることになるのだが、その経験がきっかけとなり女風の世界へと足を踏み入れることを決めた。
■男女で違う「欲望の質」
ユニさんは一般的にはモテるタイプだろうと推測できる。相手には不自由しないため、「これまでの自分」のままであり続けることもできたはずだ。しかしユニさんは性的なサービスを女性に提供する職種にあえて身を置くことで、女性への一種の甘えを断ち切り大人の男性への階段を上りたいと感じたのだろう。
まだ新人セラピストということもあり、うまく女性をエスコートできずに壁にぶつかることもある。しかし、そんな困難も人生の学びになっている。
「僕たち男は竿に振り回されてる感じがあるけど、女の人って精神的なものを求めていて、欲望がもっと真っすぐでピュアだなと思うんです。そんな女性の欲望と向き合えて、心の底からすごくうれしいんです。誰にも言えなかった秘められた欲望や無防備な姿を晒してもらえるという快感もある。今まさに、ずっと知りたかった女性の本質を知りつつある最中なんです。女風によって、自分の人生の深いところを学んでいるなと感じますね」
日々の努力もあってか、年明けからリピートも少しずつ入り始め、新人という名前からは変わりつつある。初対面では緊張気味だった女性が、帰り際に心も体も解放されてとびきりの笑顔になる。それがユニさんの何よりの喜びだ。ユニさんは女風を通じて、初めて女性たちと真っ正面から向き合い、かつての自分自身からも脱皮しようとしているのかもしれない。
■さまざまな性的な悩みに対して柔軟にサービスを行う
エンタメ系企業で営業職を務めるタカシさん(仮名・30歳)は、いわば女風の「出戻り組」のベテランセラピストだ。タカシさんは10年ほど前、学生時代に借金を負い、その返済のために女風に足を踏み入れた。借金の返済後は特に業界に関わることもなく、サラリーマンとして働いていた。しかし、ここ数年で女風がはやっているということを知り、「今の女風はどんな感じになっているのだろう」という興味から再びこの世界に戻ってきた。タカシさんは、多い時で月に30件ほど予約が入る。
女性が性的に喜んでいる姿を見るのが昔から好きだった。タカシさんは、自分の射精にはあまり興味がない。自分がイクことよりも女性が喜ぶ姿を見ているほうが興奮するし、女性の体を開発するという性的探究心もある。
女風には、性的な悩みを抱えている女性が多い。そんな女性に対して、タカシさんは相手の欲望の形によって変幻自在に姿を変えることを得意としている。タカシさんは、Sキャラを求められていることが多いが、ガンガンおもちゃで犯してほしいと言われれば犯すし、逆に自分がペニバン(ディルドにバンドを付け腰に固定できるようにした性具)で犯されることもあるという。
ある意味、進んで女性たちの欲望のおもちゃになれる。自分が操っているようで、実は相手の欲望のままに動くのだ。相手の喜びに応じ尽くすことが、自分にとって極上の喜び。「だから僕の本質は、実は根っからのM気質なんです」タカシさんは自らの性癖をそう分析する。

■「セックス嫌い」は「挿入が嫌い」なだけ
話を聞いていると、タカシさんはまるで軟体動物のようだと感じる。相手の欲望の形を素早くキャッチし、それに合わせて自らの性欲の在り方も柔軟に変えることができる。
タカシさん自身がまさに女性の欲望を映し出す合わせ鏡のような役割を果たしている。だからこそ、タカシさんは女性たちに絶大な人気を誇るのだろう。
タカシさんは、女風の現場に長年携わる中で、セックスに苦手意識を持つ女性たちを多く見てきた。
「セックスが嫌いという女性によくよく聞いてみると、挿入が嫌いと言ってるだけのことが多いんです。多くの男性は勘違いしがちなのですが、女性からすればデートの瞬間から、前戯に入っているといえる。そもそも僕は挿入だけがセックスだと捉えてはいないんです。挿入がないセックスもあっていいし、もっと自由であるべきだし、たとえ挿入しなくてもゆっくりことを進めていけばいいと思うんです」
■ブームの背景には“現代女性の性への不満”が…
性には無数のバリエーションがあっていいし、必ずしも「挿入=セックス」ではない。しかし多くの女性たちにとって、これまで挿入ありきのセックスしか経験がないので、セックスは苦痛の代名詞のイメージがある。そんな性の固定観念から解き放ち、全く別の世界へと誘うのが、タカシさんの得意とするところである。
タカシさんの話を聞いていると、多くの女性たちがリアルの異性関係に不満や不全感を抱えているが、いざ体の関係を持つことになると、口を閉ざさざるを得ないという歪な構造が浮かび上がってくる。
そしてそんな女性たちの置かれた現状にタカシさん自身、危機感を感じていることがひしひしと伝わってくる。しかしこれは、何もタカシさんから聞く話だけではない。これまで取材してきた多くのセラピストたちが、この危機感を口にするのだ。
しかし私自身振り返ってみても、いざ性的なことになると相手に対して口をつぐんだり、我慢してやり過ごした経験が幾多もあったことに気づかされる。
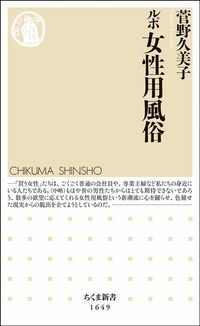
女風がブームとなっている背景の一因には、そんな現代社会を生きる女性たちの心と性のあり様が反映されていると感じずにはいられない。私はいつだって、「性」とはその社会を映す鏡だと考えている。そういった意味で、セラピストたちは女性たちの心と体を正面から受け止め向き合っている稀有な存在だともいえる。
昨今の流れとして、女風は低価格化の波や、SNSの台頭などにより、「売る側」も「買う側」もより一般に向けて門戸が開かれつつある。ユーザー側も大学生や主婦、会社員など、ありとあらゆる客層へと広がり、かつてのように限られた女性たちのものではなくなってきている。令和は、もはや現実の世界では手に入らないであろう女性たちの見果てぬ夢が、さまざまな偶然と欲望とテクノロジーによって具現化しつつある新時代なのかもしれない。
----------
ノンフィクション作家
1982年、宮崎県生まれ。大阪芸術大学芸術学部映像学科卒。出版社で編集者を経てフリーライターに。著書に、『超孤独死社会 特殊清掃の現場をたどる』(毎日新聞出版)、『孤独死大国 予備軍1000万人時代のリアル』(双葉社)、『大島てるが案内人 事故物件めぐりをしてきました』(彩図社)、『家族遺棄社会 孤立、無縁、放置の果てに。』(角川新書)などがある。また、東洋経済オンラインや現代ビジネスなどのweb媒体で、生きづらさや男女の性に関する記事を多数執筆している。
----------
(ノンフィクション作家 菅野 久美子)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
年収200万円台の30歳女性が「2回デートすると必ずフラれる」残念な理由。“気を使える人”なのになぜ
女子SPA! / 2024年7月6日 15時47分
-
親が死に、還暦のひきこもりがゴミ屋敷で孤独死…8050問題の次に訪れる「在宅ホームレス」問題
プレジデントオンライン / 2024年7月6日 7時15分
-
終わったら毎回寝落ち…もしかして、愛されてない?“賢者タイム”の平均値を女医が解説
女子SPA! / 2024年7月2日 15時45分
-
60代以降に「週2回セックス」で驚きの効果…和田秀樹「ED治療薬の使用に関して絶対に知っておくべき知識」
プレジデントオンライン / 2024年6月30日 15時15分
-
高畑充希“婚外恋愛と風俗どっちが許せる?”を明かす。大河ドラマから「セックスレス夫婦ドラマ」まで話題
女子SPA! / 2024年6月30日 8時45分
ランキング
-
1ユニクロでブラジャーなど大量万引き 1200万円超す被害 ベトナム国籍の女3人を逮捕・送検
ABCニュース / 2024年7月19日 19時2分
-
2コロナ「第11波」、変異株KP・3が主流 流行期入りで夏に感染拡大か
産経ニュース / 2024年7月19日 21時4分
-
3ゆれる兵庫県庁 「解明が務め」と百条委、「自分も処分?」と疑心暗鬼になる職員も
産経ニュース / 2024年7月19日 20時1分
-
4防衛相、海自元隊員逮捕は「昨晩知った」 与野党から批判の声
毎日新聞 / 2024年7月19日 18時0分
-
5こども園の通園バスに置き去りにされた園児死亡 元園長ら控訴せず判決確定(静岡)
Daiichi-TV(静岡第一テレビ) / 2024年7月19日 9時31分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











