「社員全員が決算書を読める」照明や家具の"コイズミ"が300年続く企業になったワケ
プレジデントオンライン / 2022年4月19日 12時15分
※本稿は、田宮寛之『何があっても潰れない会社 100年続く企業の法則』(SB新書)の一部を再編集したものです。
■ルーツは近江の行商人
小泉産業株式会社は、照明のコイズミ照明株式会社、家具のコイズミファニテック株式会社、インテリアから家電、内装材、省エネなど施設関連の機器販売および施工の株式会社ハローリビング、物流のコイズミ物流株式会社、什器や家具の搬入・設置サービスの株式会社ホリウチ・トータルサービスを擁する持株会社だ。
そのルーツは、1716年(享保1)、近江(現在の滋賀県)で、武士の家系でありながら行商を始めた小泉太兵衛にある。
勤勉な性格の太兵衛は、まず田を購入して農業に励んだ。ところが、その田は米がうまく育たない悪田だった。そのままでは年貢を納められないため、太兵衛は、わずかな資産を切り崩し、近江産の麻布を仕入れて行商を始めた。時代の変化を敏感に感じ取った太兵衛の大きな決断であった。
戦国の世が終わり江戸時代に入って以降、日本各地で荒れ地の開発が進み、新たな村が誕生し、人口増加と共に新たな商品市場が生まれた。それに呼応するかのように、近江国の北部を治めた彦根藩では商業自由化政策がとられた。そこで「これからは農業ではない、商業だ」と考えた太兵衛は農業を見限り、行商に専念することにしたのだ。
■「信用第一で正々堂々と仕事をせよ」
行商といえば、まず信用がなくてはならない。客の要望を知って応えれば、まずある程度は信用される。さらには客自身ですら気づいていない内なる要望を察知して提供する。そこで生まれる客の感動によって、また新たな信用が醸成される。
商いというものは、このように信用をベースに広がっていく。それは今も昔も変わらないのだから「信用第一で正々堂々と仕事をせよ」と、小泉産業グループ(以下、小泉産業)の社員は新入社員のころから教わるという。
さて、武士から農家、農家から行商人へと転身した初代・太兵衛だったが、小泉家が実店舗を構えたのは、それから100年余り後のことである。
1847年(弘化4)には京都の富小路六角に近江屋新助商店を開業。続いて1871年(明治4)には大阪・船場に立木屋森之助商店を出店。時代は明治。国を挙げて富国強兵と文明開化が推し進められ、活気みなぎるなかでの開業だった。
さらに1904年(明治37)には同族5人で小泉合名会社を設立、1915年(大正4)には小泉重助商店を開店、という具合に、太兵衛の子孫たちは麻布の行商から始まった商いを着々と拡大し、小泉家は一大商家へと成長していく。
■シカゴのデパート経営者の衝撃的な一言
300年以上にもおよぶ小泉産業の歴史のなかでも、特筆すべきは3代目・重助だ。3代目というのは、太兵衛の後、経営に携わった人物の一人である5代目・新助の分家の初代・重助から数えて3代目ということである。
小泉合名会社を設立した同族5人のうちの一人だった3代目・重助は、1915年(大正4)に小泉重助商店を開店する。小泉重助商店は1941年(昭和16)に法人化されて株式会社小泉商店となった。商家としての小泉家の始祖を小泉太兵衛とすれば、3代目・重助は現在の小泉産業の実質的な創業者といえる。
3代目・重助は人一倍の好奇心を持って世界に目を向けた。商売のヒントを求めてのことだったが、最初に訪れた中国でも、次に訪れたアメリカでも大きな収穫はなかった。しかし、シカゴのデパート経営者・マーシャルフィルドとの出会いだけは衝撃的だったと言い伝えられている。
問屋の進むべき道について問うた3代目・重助に、マーシャルフィルドは、こう答えたという。
「日本の問屋は悪性のブローカーだ。真の問屋として生きるには『特殊特徴品』によって生きなければだめだ。マーシャルフィルド・デパートの卸部はそれをやるためにある」
■「不況がもっとも好きである」の真意
真の問屋として成功したいのであれば、どこにでもあるものではなく、ましてや、まがい物でもなく、特殊で特徴のある自社ならではの品物を扱え。その考えにいたく感銘を受けた3代目・重助は、以来、「特殊特徴品」を商いの精神的支柱の1つとした。後でも触れるが、この理念は現在の小泉産業にもたしかに継承されている。
その3代目・重助が残した言葉に、「不況がもっとも好きである」というものがある。1930年(昭和5)の世界恐慌の折、3代目・重助が社員に配布した「不況対策と小泉商店」という冊子の中にある言葉だという。好況時、人は儲けだけを求めすぎ、後でその余波に苦しむ。一方、不況という逆境こそ、人の心を引き締めて真剣にさせるので、店はより強くなる。だから「不況がもっとも好きである」と記したのだ。

権藤浩二現社長も次のように話す。
「正直に言って、うちにはいわゆる秀才はほとんどいないと思います。しかしビジネスでは秀才たちに勝るという自信がある。なぜかといえば、困ったときに2倍働く、2倍考える、あるいは、お客様のところに2倍出向く──要するに倍努力すれば足りないところは補えるんだと繰り返し教わるからです」
人一倍の努力をもいとわないバイタリティこそが成果につながるという、ある種、泥臭い仕事意識は小泉産業が持つ強みの1つということだろう。
■社員全員で決算書を読み、経営者感覚を育てる
会社という組織にとってもっとも大事なのは、会社を継続的に成長させ、会社を潰さないようにすることだ。そのための第一の課題はもちろん、しっかりと収益を出すことであり、それには社員が経営者感覚を持つことが重要である。
小泉産業では、「社員全員が決算書を読めるようにする」ということを通じて、社員一人ひとりの経営者感覚を養っているという。
新入社員にいきなり決算書を見せても何もわからないだろうが、会社の数字は小さな数字の集積だ。会社全体の数字は各事業部の数字の集積であり、各事業部の数字は各課の数字、各課の数字は各チームの数字、そして各チームの数字は各個人の数字の集積である。
このように会社の数字を個人レベルにまでブレークダウンしたところから、数字の見方、考え方を教えているという。
たとえば1つの事業部で年間3億円の売上、5000万円の営業利益という数字は何を意味するのか。売上とは何か、営業利益とは何か、あるいは経費とは何かなども含めて、数字の意味するところを現場で教える。そして、目標達成のために自分が所属する部は、課は、チームは、そして自分自身はどれくらいの数字を出せばいいのかを考えさせる。

■小さな数字がわかれば、大きな数字も読みこなせるようになる
数百億円というグループ全体の巨大な数字は具体的にイメージしにくくても、自分が所属する事業部くらいならば、たとえば「自分が使った交通費は経費として利益から差し引かれる」というレベルから考えられる。そうしているうちに、みな次第に大きな数字も読みこなせるようになっていく。
「一社員であっても経営者感覚を持って仕事に臨め」というのは、よく聞く言葉だ。だが小泉産業では、それを企業風土として浸透させ、個人任せにするのではなく、所属部署にかかわらず手取り足取り数字の見方を教える。こうして現実的に一人ひとりが経営者感覚を持てるようにしているのだ。
数字の教育を施す以上、会社の数字はグループ全体の決算書から事業部ごとの収支まで、すべて全社員に公開しているという。だから、たとえば自分が所属するA営業部と隣のB営業部とでは何が違うのかといった比較をすることもできる。それにより「負けてられない」と奮起することもあるだろう。
■社員は家族、会社の利益は社員のがんばりの結果
それにしても、なぜここまで社員にオープンにしているのか。「社員は家族」というのが権藤社長の答えだ。家族に隠し事はしないという、さも当然といった風情である。さらにその視線は、社員自身の家族にも注がれている。
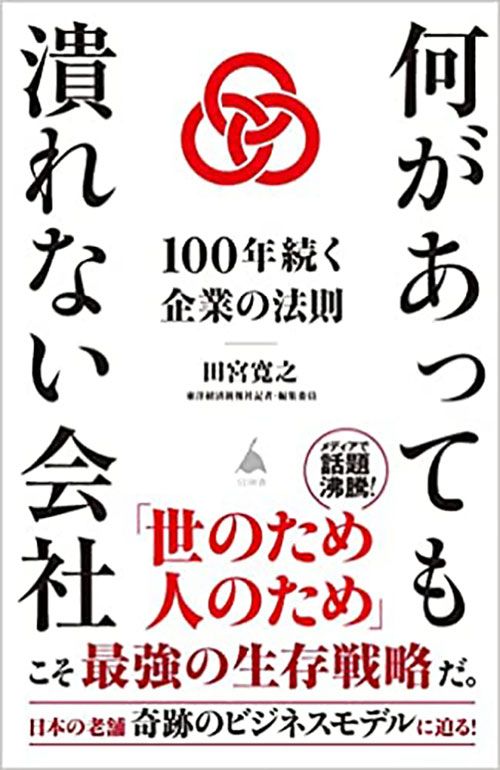
「自分がどんな会社に勤めているのか、数字的なことも含めてきちんと説明できたほうが、ご家族を安心させられるでしょう。そのためもあって、ただ数字をオープンにしておくだけでなく、毎年、決算期には私から社員に向けて決算報告をしています。そのほうが真実味が増しますから」
会社の数字が理解できれば、今の自分のがんばり方も見えやすい。明確な目標を立て、それに向かって着実に努力することができる。そして会社の利益は社員のがんばりの結果として還元される。
会社は株主のためにある、というのが昨今の企業に顕著な姿勢だが、小泉産業の意識は、より社員に向けられているようだ。それは、経常利益の何割かを業績賞与として、固定賞与に上乗せするかたちで社員に還元している点にも現れている。
経営者感覚を育てるという社員教育の根幹にあるのは、ただ努力を惜しまず会社に貢献できる人材になれ、という考えではない。社員全員に「アイ・ラブ・コイズミ」になってほしいとの願いだという。会社の数字を理解し、損失も利益も「自分ごと」として捉える。そのなかで培われる愛社精神が、同じ志を持つ者の集合体としての会社の絆を強くするのだ。
----------
経済ジャーナリスト
東洋経済新報社編集局編集委員、明治大学講師(学部間共通総合講座)、拓殖大学客員教授(商学部・政経学部)。東京都出身。明治大学経営学部卒業後、日本経済新聞グループのラジオたんぱ(現・ラジオ日経)、米国ウィスコンシン州ワパン高校教員を経て1993年東洋経済新報社に入社。企業情報部や金融証券部、名古屋支社で記者として活動した後、『週刊東洋経済』編集部デスクとなる。2007年、株式雑誌の『オール投資』編集長に就任。2009年、就職・採用・人事などの情報を配信する「東洋経済HRオンライン」を立ち上げて編集長となる。これまで取材してきた業界は自動車、生保、損保、証券、食品、住宅、百貨店、スーパー、コンビニエンスストア、外食、化学など。『週刊東洋経済』デスク時代は特集面を担当し、マクロ経済からミクロ経済まで様々な題材を取り上げた。2014年に「就職四季報プラスワン」編集長を兼務。2016年から現職。
----------
(経済ジャーナリスト 田宮 寛之)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
サイゼリヤ「優待廃止ショック」も国内復活の兆し 株主優待廃止で一段の成長が求められる局面に
東洋経済オンライン / 2024年7月13日 9時0分
-
「星野トマムを売却」中国企業の"謎だらけの行動" 売却に至った複雑事情、売却先は何者なのか?
東洋経済オンライン / 2024年7月5日 17時0分
-
最新「四季報」分析で判明「今期大きく伸びる業種」 全産業ベースでの営業利益は前期比7.1%増
東洋経済オンライン / 2024年7月5日 9時0分
-
「自分では営業できないくせに」社員に無視され陰口をたたかれた"二代目社長の妻"が採った組織立て直しの秘策
プレジデントオンライン / 2024年6月28日 9時15分
-
90分学べば誰でも「会社の数字」がわかる…中小企業の奥さんが社員を変えた"風船と豚"会計メソッドの効用
プレジデントオンライン / 2024年6月27日 8時15分
ランキング
-
1TBS退職→Netflixと5年契約「50代P」選んだ道 「不適切にもほどがある」「俺の家の話」手掛けた
東洋経済オンライン / 2024年7月18日 12時30分
-
2半世紀も"主役"フロッピーディスクの栄枯盛衰 「なにそれ?」と知らない世代も増えてきた
東洋経済オンライン / 2024年7月19日 8時0分
-
3マクドナルド 約3割の店舗が営業停止 レジに障害
日テレNEWS NNN / 2024年7月19日 11時46分
-
4電話番号案内「104」終了へ…NTT東・西、スマホ普及で需要落ち込む
読売新聞 / 2024年7月18日 22時18分
-
5三菱UFJが首脳3人処分へ 報酬減額、情報無断共有で
共同通信 / 2024年7月18日 18時25分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











