「尿カテーテルをつけ尿バッグをコートで隠し新幹線に乗った」24時間介助が必須な最愛の妻に夫がやったこと
プレジデントオンライン / 2022年4月2日 11時30分
関東在住の中野篤さん(仮名・60代・既婚)は、仙台育ちの一人っ子。編集者をしていた妻は53歳ごろから頻繁につまずくように。一方、仙台で一人暮らしの母親は、年齢を重ねるごとに転倒が増え、86歳のときには顔に大あざを作った。中野さんは母親を「ケアハウス」に入所させた。その頃、妻は、「ALS」と診断され、日に日に身体が動かなくなっていき、自発呼吸も難しくなり、人工呼吸器の使用を開始。さらに胃ろうを造設。母親は施設入居後、心不全、肺炎、盲腸炎から派生した敗血症、胃がんステージ4が発覚するも、母親の希望で、最期までケアハウスで過ごすことに。妻が退院すると、本格的な在宅介護生活が始まった――。
■母親の逝去
「この度は看取りを受け入れていただきありがとうございます」
2018年、仙台の実家に住む母親は90歳を超え、心不全、肺炎、盲腸炎から派生した敗血症、胃がん(ステージ4)……と次々に病魔に襲われ、終末期病院への転院も考えたが、母親の希望で、ケアハウスに戻ることになった。
病院のソーシャルワーカーから、母親が入居していたケアハウスの寮母長への手紙には、冒頭のように書かれていた。関東地方在住の中野篤さん(仮名・60代)は、「ああ、いよいよ看取るのか」と母親の死を覚悟した。
中野さんは退院やケアハウスへの移動など、すべてをケアハウスのスタッフに一任して関東の自宅に帰り、7年前に国指定の進行性難病であるALS(筋萎縮性側索硬化症)を発症した妻の介護にかかりきりの生活に戻った。
ところが2017年10月。母親が退院して施設へ移る2〜3日前から、中野さんはソワソワ。「退院からケアハウスの部屋のベッドで寝付くまで、母のそばにいてあげたい」と思った中野さんは、妻のヘルパーの会社に相談し、退院日は仙台に終日いられるようにシフトを組んでもらった。
当日、中野さんは朝イチで仙台へ。病室に着くと、もう寮母長やスタッフたちが退院の準備をしていた。そんな中、中野さんの顔を見るなり母親が「篤、また来たの⁉」と大声を上げた。
以前、「あんた誰?」と名前を忘れられてショックを受けていた中野さんは、かつての母親の姿に嬉しさがこみ上げた。
中野さんと母親は、寮母長たちとともにケアハウスに到着。ケアハウスのアイドル犬やスタッフたちが出迎えてくれた。母親は元いた部屋のベッドに就き、2人は最終の新幹線まで過ごした。
「母はあまり喋りませんでしたが、眼力が強く、私に何かを語りかけていました。今思えばたぶん、『さようなら、元気でね』だったのだと思います」
関東に戻った後、2〜3日に1回くらいの頻度で、「危ないから来てください」という電話を受け、ついに同年10月31日午後3時ごろ、「亡くなりました」との連絡があった。
中野さんは、あらかじめ妻の主治医やソーシャルワーカーに母親の状態を説明していたので、母親の逝去を伝えると、翌朝の妻の入院の手配をしてもらうことができた。
翌朝一番に妻とともに大学病院に向かい、病室のベッドに妻が収まるのを見届けてから、準備しておいた荷物を再確認すると、急いで新幹線に飛び乗った。
仙台に着くと、夕方からの葬儀社との打ち合わせにギリギリ滑り込み、その後ようやく母親の顔を見ることができた。すでに棺に収められた母親のまぶたは閉じていたが、口は少し開いていて、何か話したそうに見えた。中野さんは、妻がALSだと分かったときも、気管切開をしたときも涙は出なかったが、このときばかりは涙が溢れ、「ここまで育ててくれてありがとうございました……」とつぶやいていた。
■葬儀後の救急搬送
葬儀が終わり、納骨も済ませると、中野さんはケアハウスの部屋と実家の片付けを始めた。あまり長くは時間をかけられないので、テキパキと作業を進める。
しかし、片付けを始めてから3日後、あらかた片付けが終わった頃、中野さんは突如尿が出なくなり、腹部が膨張し始め、立っていることさえままならない状態に。中野さんは床に倒れたまま、携帯で救急車を呼んだ。

母親が入院していた救急病院に運ばれると、カテーテルを入れてもらい、尿は排出できた。だが、前立腺炎と肺炎を併発していることが分かり、発熱。中野さんが医師に、妻と母親のダブル介護生活の話をしたところ、「お母さんが亡くなり、蓄積された疲労が一気に出たのでしょう」と言われ、入院を勧められる。
しかし中野さんは、関東の病院に妻が期限付きで入院していることを説明。医師は紹介状を書いてくれた。
「身体だけではなく、精神的にもボロボロでした。『私はどうなってしまうのだろうか』と、不安でたまりませんでした……」
病院を出た中野さんは、発熱した身体で尿カテーテルを付けたまま、尿バッグをズボンのベルトに引っ掛け、コートで隠して新幹線に乗った。
■私を私で居させてくれるもの
気管切開し、人工呼吸器を使っている妻は、声を出すことができない。身体を動かすこともできないため、文字を書くこともできない。
しかし中野さんは、コミュニケーションを取るための最新機器を調べ、福祉機器メーカーや販売会社に直接連絡を取り、公的な支援を得ながら、在宅介護生活に導入する活動もこなしてきた。
2017年には、体圧を常に感知して分散するマットレスの情報をALS患者会の会合で知り、いち早くメーカーに問い合わせ、公的な支援を得られる福祉機械販売会社を探し出し、タッグを組んで導入。
2018年には、パソコンに接続した視線入力装置を駆使し、モニター上の文字盤を視線で操作して文章を書き上げ、それを喋らせる装置「オリヒメアイ」と、Wi-Fiにつなげたパソコンに接続したロボットを使い、世界中どこにロボットを連れて行っても妻はベッドでロボットを操作できるという装置も導入。
中野さんがロボットを「落語の会」に連れて行くことで、中野さんは妻と落語を楽しむことができ、妻はベッドの上で落語を楽しむことができたわけだ。
この装置の導入には、自治体の公的支援も受けたが、妻が通っていた合気道道場の仲間たちによる寄付にも助けられたという。
同じ年の5月ごろからは、文字盤と視線入力装置「オリヒメアイ」を併用し、緩和ケア担当医師と中野さんとで、「身体が一切動かなくなったら、どうするか・どうしてほしいか」などを妻から聞き取った。
すると、いくつかの要望の中に「本を読んでほしい」というものがあった。小説の編集者をしていた妻は、根っからの“本の虫”だったのだ。
そこで中野さんは、大学の先輩に相談すると同時に、本を読み聞かせる方法を考える。
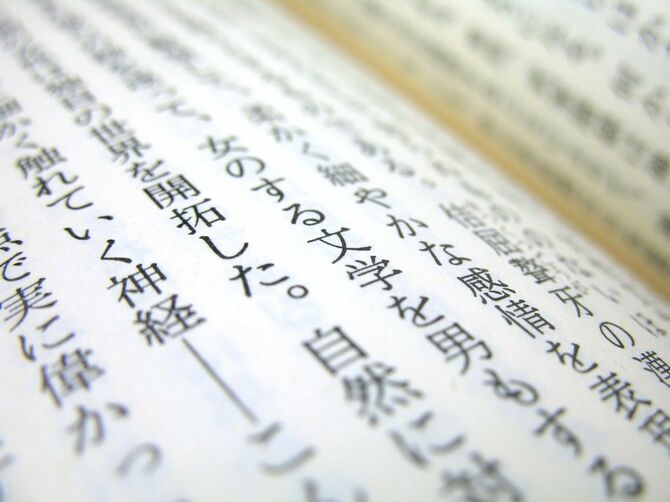
妻は、全く身体を動かせないため、鼻水や唾液、痰などを、機械を使って吸い取ってもらったり、身体の位置を頻繁にずらしてもらったりする必要があるが、ベッドサイドで読み聞かせるとなると、介助の邪魔になってしまう。また、読み聞かせをしてくれる人自体は、妻との共通の友人やその知り合いなど50人近く見つかったが、相手の時間や交通費などの負担を考えると心苦しくなった。
やがて中野さんは、「相手の都合の良い時間に、朗読をスマホなどで録画・録音し、クラウドに上げておいてもらえばいいのではないか」とひらめく。そうした進捗を妻に報告すると、妻の目は文字盤を追った。
「“本読み”は、私を私たらしむもの」
中野さんは息をのんだ。
「妻は、たとえ身体のどこもかしこも動かなくても、自発呼吸ができなくて人工呼吸器を使っていて声を出せなくても、『私を私でいさせてくれるのが“本読み”』だと言ったのです」
こうして本読みプロジェクトは進行し、現在クラウドには、300以上もの書籍の朗読データが上げられるまでになった。
そして2019年2月には、脳から出ている身体を動かすための生体信号を、センサーで検知する装置も導入し、57歳になった妻は、使いこなすための練習に励んだ。
■出口の見えない介護生活
こうして懸命の介護を続ける中野さんだったが、利用できる制度を駆使しても、最新の医療機器を導入しても、出口の見えない介護生活に耐え切れず、睡眠障害に悩まされた。2016年12月には心療内科を受診。双極性障害と診断され、現在も通院と大量の服薬、週1回メンタルヘルスの看護師の訪問を受けている。
2018年6月ごろからは腰が痛み始め、徐々に歩けないほどになり、松葉杖をついて歩くように。病院を受診すると、「広域脊柱管狭窄症」と診断され、リハビリを開始。ところが、症状は悪化の一途をたどり、歩行器を使い始めた。
同じ年の12月、中野さんが何度目かの排尿障害を起こすと医師は、「すぐに手術をします。入院してください」というが、妻を1人で自宅に置いておくわけにはいかない。事情を説明し、妻を入院させる手続きをしてから、自分も入院した。
結局、2019年1月に入院、手術を経て、2月に退院。
中野さんが「広域脊柱管狭窄症」と診断されたとき、妻のケアマネが「広域脊柱管狭窄症も国指定の難病のひとつなので、65歳を待たずに介護保険の対象者になりますよ」と助言。中野さんは介護認定調査を受け、入院中、病院での介護認定調査では介護2と判定された。公的サポートが利用できることは朗報だったが、そうとも言えない部分も大きかった。
「在宅介護は、“家庭”という非常にプライベートな空間に、個性も価値観も行動パターンも出自も知らない、ひょっとしたらどう頑張っても理解し合えないかもしれない第三者、赤の他人であるヘルパーさんが入り込んでくるため、“家庭”が“作業場”に変化してしまうことを意味します。介護業界では“介入する”と言うようです。“軍事介入”という言葉はニュースで耳にはしましたが、まさか自分の家庭ごときで“介入”という用語を使うとは夢にも思いませんでした」
24時間介助が必要な妻のために、夜間も休日も関係なく、ヘルパーが自宅を出入りする。「仕方がない」と頭では理解できていても、感覚的には「受け入れがたい」生活を続けるうちに、中野さんの精神はむしばまれていった。

「プライベートな生活に“介入”されて、普通の家庭生活はできなくなる……。この感覚や現状を、どう説明しても理解できない妻に怒鳴ったことがあります。『わが家はもうわが家じゃない。ただの作業場になってしまった』と……」
妻は何も言わず、ただ申し訳なさそうな様子を見せた。
2019年7月には、自傷行為や自殺未遂もしたという。しかし、妻を遺して死ぬことはできなかった。
「私の事業がなかなかうまく行かなかった時期があり、アルコール依存症に陥り、リハビリ施設にお世話になったことがあります。事故で大腿骨頸部を骨折し、3カ月入院したこともあります。癌を疑われた胃潰瘍で、手術入院をしたこともあります。何度も病気にかかりましたが、いつも妻が励ましてくれました。妻が難病にかかり、私が面倒をみなければならないと分かった時、私は妻に『人生はあらなえる縄の如し』と言いました。今度は私が恩返しする番だと言う意味で口にしたのです」
■離れればもっと優しくなれる
中野さんが妻を介護し始めて、もう6年が経とうとしている。
妻の主治医は、「人工呼吸器で療養している患者はいつも死への恐怖を感じている。不安を取り除くためには、いつでも側にいてあげてください」と言う。

一方、「妻のことが頭から離れない」という悩みをカウンセラーに相談したら、「(離婚して)早く新しい人を見つけて自分の人生を歩みなさい」と言われたという。
中野さんはそのどちらもできず、ただ涙が溢れた。
「24時間365日の介護体制を完成させましたが、いつも妻のことが頭から離れず、好きな仕事にも身が入らない。私にもしものことがあったときのために、ホスピスの見学と検討もしましたが、やっぱり離婚なんて無理だと思いました。かといって常にそばにいたら私が壊れてしまいます。自分の人生を生きたいです。時間ができたら音楽学校に通って、作曲を勉強したいです」
中野さん自身、現在は要介護1のため、時々ショートステイを使って自宅を離れたり、精神病院の「ストレスケア入院」というものを利用するなどして、つらくて苦しくてどうしようもないときは、介護から“逃げた”。
「在宅介護の私のスローガンは、”離れればもっと優しくなれる”です。今、在宅介護をされている介護者の方は、社会資本、公的支援を遠慮なく使って、在宅介護をプロに任せて、介護から手を離してください。保護者としての責任やペーパーワーク、役所やドクター、ナースとの打ち合わせなどはしなければいけませんが、それ以外はとにかくプロに任せて、患者から離れることです。それができれば、介護者の心にも平穏が訪れますし、心に余裕ができれば、もっと患者に優しくなれます。在宅介護で親族殺人が起きるケースが後を絶たないですが、あれは被介護者との距離が近すぎるからです、『薄情だ』などと言わないで、できるだけ離れてください」
近くに理解者も協力者もおらず、孤独に介護する人が多い中、中野さんには近所に大学の研究室時代の先輩夫婦、友人家族などがおり、ケアマネも助けてくれる。
29歳の頃から34年間連れ添った妻には、「寄り添ってくれてありがとう」と言われるという中野さん。そんな彼にとっても、介護は精神的にも金銭的にも負担が大きく、心も身体もむしばんでいく。
介護は家族や親族がしなくてもいい。家族や親族がするべきは、「親身に寄り添い続けること」なのかもしれない。
----------
ライター・グラフィックデザイナー
愛知県出身。印刷会社や広告代理店でグラフィックデザイナー、アートディレクターなどを務め、2015年に独立。グルメ・イベント記事や、葬儀・お墓・介護など終活に関する連載の執筆のほか、パンフレットやガイドブックなどの企画編集、グラフィックデザイン、イラスト制作などを行う。主な執筆媒体は、東洋経済オンライン「子育てと介護 ダブルケアの現実」、毎日新聞出版『サンデー毎日「完璧な終活」』、産経新聞出版『終活読本ソナエ』、日経BP 日経ARIA「今から始める『親』のこと」、朝日新聞出版『AERA.』、鎌倉新書『月刊「仏事」』、高齢者住宅新聞社『エルダリープレス』、インプレス「シニアガイド」など。
----------
(ライター・グラフィックデザイナー 旦木 瑞穂)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
いいリハビリ病院を見分けるには看護師が重要なのはなぜか【正解のリハビリ、最善の介護】
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月17日 9時26分
-
「洗面器で大量の即席メンを食べた」「自分の局部を撮影」…欲求に歯止めがきかない老父に50代娘が感謝したワケ
プレジデントオンライン / 2024年7月13日 10時16分
-
「父も母も鬱病」担任教員に容姿や成績の悪さを揶揄され不登校の小3女子…40年後に"ワンオペ両親介護"の不遇
プレジデントオンライン / 2024年7月13日 10時15分
-
「母さんといることが限界だ」と涙の訴え…定年退職した父が“夫婦別居”を望んだ「切実な理由」
Finasee / 2024年7月12日 13時0分
-
「とどめ刺したのは社労士の兄」脳と心臓がやられた親4人、不登校の息子、自分も大借金…40代女性の壮絶戦記
プレジデントオンライン / 2024年6月22日 10時16分
ランキング
-
1クラスに2~3人……“水が飲めない”子ども増加ナゼ? 「味がしないから苦手」「スポーツドリンクで」 水嫌いへの対応は
日テレNEWS NNN / 2024年7月19日 10時45分
-
2ユニクロでブラジャーなど大量万引き 1200万円超す被害 ベトナム国籍の女3人を逮捕・送検
ABCニュース / 2024年7月19日 19時2分
-
3気に入らないと机叩いて怒ったり、激高すること日常茶飯事…元県民局長、兵庫知事の素行を陳述書に残す
産経ニュース / 2024年7月19日 15時8分
-
4防衛相、海自元隊員逮捕は「昨晩知った」 与野党から批判の声
毎日新聞 / 2024年7月19日 18時0分
-
5【独自】「死のうと思ってガス栓開けた」部屋にいた中国籍の男が説明 埼玉・川口市マンション爆発 埼玉県警
日テレNEWS NNN / 2024年7月19日 11時2分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











