「ほかの恒星系には宇宙人もいる」じつは世界有数のレベルだった"江戸の宇宙論"を究めた3人の日本人
プレジデントオンライン / 2022年4月20日 15時15分
※本稿は、池内了『江戸の宇宙論』(集英社新書)の一部を再編集したものです。
■畏れ敬うものから愛でるものとなった星空
古代中国においては優れた景物として盛んに星を詩文に詠み込んでいるのだが、日本の最初の歌集である『万葉集』には星の歌がほとんどない(海部宣男『宇宙をうたう』)。その理由として、古代の人々には、星は人の魂が天に昇ったもの、不吉なものと見做(みな)す思想があったのではないかという説がある。あるいは、天が地の異変を予言して天文現象として表れるとする占星術が信じられており、人々は天の事象を畏(おそ)れ敬う心が強かったのではないかとも言われている。
この傾向は平安末期から鎌倉時代にまで続き、七夕の歌は詠われてもそれは地上の恋の物語に焼きなおされているのである。しかし江戸時代になると、文芸の幅が和歌のみに留まらず、五七五の俳諧(はいかい)や川柳、五七調を基調とするさまざまな俗謡へと広がって、ようやく星空の美しさに感嘆した歌が多数詠われるようになった。星空を純粋に「愛でる」気持ちを吐露するようになったのである。
■星空を「究める」には限界があった
それと軌を一にするように、江戸時代に入ってから、夜空に見えるあの星々はどのような運動をしているのか、そこに規則性はないのかを調べる人間、つまり「星空を究める」人間が登場した。麻田(あさだ)剛立(ごうりゅう)や天文方として雇用された高橋至時(よしとき)、それに加えて間(はざま)重富(しげとみ)など、暦作成のための基礎データの測定を目的に太陽や月、そして惑星を観測し、その運動を計算する暦算家が登場するようになったのである。
併せて、岩橋善兵衛(1756〜1811)や国友一貫斎(いっかんさい)(1778〜1840)などが望遠鏡を製作し、太陽黒点や月の表面などの詳細な観察図を残している。これは「星空を愛でる」そして「究める」姿勢の表れと言えるかもしれない。
しかしそれでも限界があった。暦算家は、恒星が張り付いている天球が日周運動で回転し、その天球上を太陽・月・諸惑星が地球を中心として逆行運動するという説で満足した。これに対して儒家たちは、すべてが同一方向に動いており、恒星・外惑星・太陽・月という順で回転が遅くなっているとの恣意(しい)的な説で納得した。これらは天球や惑星の配置と動きが観測結果と矛盾しないよう工夫をした考察で、当時の「宇宙論」だとも言える。
しかし、いずれも太陽系の構造から積み上げた論理的な考察ではなく、いかにも間に合わせの(アドホックな)議論でしかない。実生活においてはそれ以上を考える必要が認められなかったのである。
■日本で地動説に触れた最初の日本人
ところが、蘭学を通じて西洋の天文学の知識を学ぶうちに、自ら輝く太陽を中心として、地球を含めた太陽の光を反射する、当時確認されていた六つの惑星が太陽の周りを回っているとの説を知る者たちが現われるようになった。地動説である。
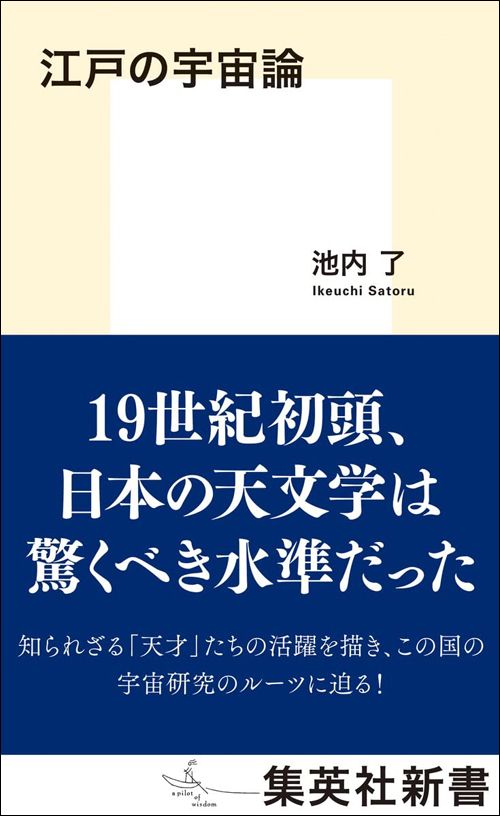
日本で最初にコペルニクスの地動説の存在を知ったのは長崎通詞(つうじ)(幕府により公式に認められたオランダ語の通訳)の本木(もとき)良永(りょうえい)で、彼は1774年に、オランダ人ブラウの第一部天動説と第二部地動説を対照して記述した本を『天地二球用法』として抄訳した(天地二球とは太陽と地球の二つの球体のこと)。
ただ良永は、当時の学問の常識である朱子学が天動説の立場であり、世間の誰もが地球中心説を信じていたこともあって第二部を削除しており、地動説の立場を打ち出さなかったのである。
しかしながら、長崎の通詞仲間とは日常的に地動説のことを話していたようで、仲間内ではいわば常識となっていたらしい。というのは、三浦梅園(ばいえん)が1778年に長崎を訪れて吉雄(よしお)耕牛(こうぎゅう)などと交流したとき、太陽中心説が当たり前のように説かれ、梅園は天球儀(太陽を中心とした太陽系模型)を手に取って見ているからだ。
■日本の科学の発端となったコペルニクス説の訳本
おそらく良永は、コペルニクス説をきちんと紹介しておきたいとの気持ちが強くあったのだろう、幕府からの密命を受けて、イギリス人ジョージ・アダムスが書いた本(ジャック・プロースが蘭訳)を『星術本原太陽窮理了解新制天地二球用法記(太陽窮理了解説)』(1792〜1793年)として翻訳した。太陽が中心にあって、その周囲を回転する地球という描像の下で、私たちの世界を太陽系宇宙として客観視する視点(=太陽窮理)に到達したのである。
西洋から250年遅れていたが、同書の翻訳は理を窮(きわ)めることによって新しい知の地平に達する、その素晴らしさを体得していく契機となった。これが日本において「窮理学」と呼ぶ「科学(理学)」の発端となったと言えるのではないか。幕府ご用達(ようたし)の通詞が出した訳本は公に広く刊行することはできなかったが、写本としてかなり広く伝わり、地動説が日本に受容されていったのである。
まさに、この写本を読んで地動説に魅せられたのが司馬江漢(こうかん)であった。
■地動説に魅了された絵師・司馬江漢
司馬江漢は、狩野派・浮世絵・唐画・洋風画という当時の絵画の全流派から画法を学んで自分のものとし、稀代の絵師として歴史に名を残す人物であるが、それ以外にも日本の歴史において重要な役割を演じている。
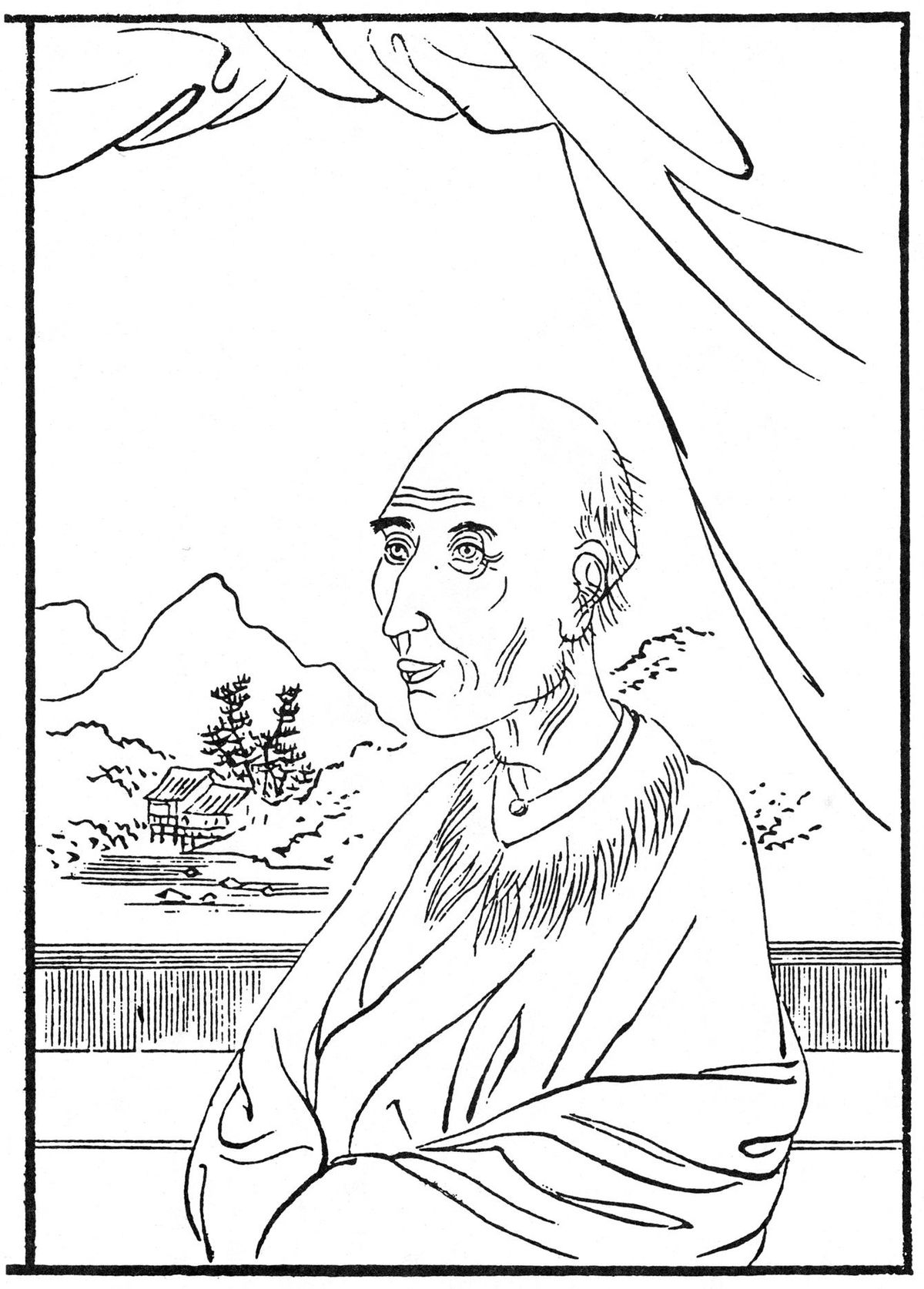
一つは、日本で最初にエッチング法によって銅版画を制作したことである。蘭学が隆盛になり始めた頃に彼は前野良沢(りょうたく)に弟子入りして蘭語を学び、エッチングの手法が書かれている本を読み解こうとした。しかし、良沢はよい先生ではなく、江漢もよい弟子ではなかったので、江漢は蘭語をモノにできなかった。
そこで江漢は、若き大槻玄沢(げんたく)の蘭語読解力の助けを得てエッチング技法を学んで完成させたのであった(1783年)。この頃、蘭学者はまだ少なく、草創期の学問の徒として互いに助け合っていた。しかし、それから10年経った頃には、玄沢は蘭語の先駆者として蘭学界を背負って立つ大物となり、幕府に蘭学を認知させて官学化することによって、蘭学を日陰の存在から陽の当たる学問へと昇格させたいと考えるようになっていた。
他方、江漢は絵師としての評価は上がったのだが、野人のまま自由に振る舞うことを望み、幕府の政策や封建体質を非難することも吝(やぶさ)かではなかった。そうなれば、当然ながら幕府擁護派の玄沢と幕府批判派の江漢の間には軋轢(あつれき)が生じ、二人は衝突するようになり、江漢は蘭学仲間から追放に近い処分を受けた。その詳細は、私の前著『司馬江漢』(集英社新書)に譲るとして、この仲たがいが江漢にもう一つの重要な役割を演じさせる遠因となったのである。
■地動説から宇宙の構造にまで空想を広げた
そのもう一つの重要な役割とは、江漢が1788〜1789年に長崎を訪れ、耕牛や良永と交流を持って地動説を知ったことから、科学のコミュニケーターとして地動説を日本で最初に唱道したことである。良永の翻訳で地動説は日本に紹介されていたが、その訳書は幕府内に留め置かれ、一般には写本によってでしか知られなかった。
江漢も、最初は地動説を奇異な説と受け取っていたのだが、この写本を見て地動説こそ正しいと確信して人々に宣伝することを自分に課すことにしたらしい。まず著書の『和蘭天説』(1796年)で地動説への理解を徐々に深めていく過程を正直に述べた上で、ついに『和蘭通舶』と『刻白爾(コッペル)天文図解』(1809年)によって、地動説から宇宙の構造にまで空想を広げ、星々の世界の全体像を考える宇宙論を提示するに至ったのである。
つまり地動説、そして宇宙論を人々に唱道した最初の日本人になったのだ。また窮理学としての蘭学の面白さをわかりやすく語った著作『おらんだ俗話』(1798年)も出版し、人々を啓蒙(けいもう)することに貢献したのであった。江漢は日本最初の科学コミュニケーター、と言っても過言ではないだろう。
彼が自伝のつもりで書いた回顧録『春波楼(しゅんぱろう)筆記』(1811年)には、「天は広大なもので、遠くから地球を視(み)れば、一粒の粟(あわ)のようなものである。人はその一粒の粟の中に生じて、微塵よりも小さい。あなたも私もその微塵の一つなのではないか」という文章がある。広大な宇宙に生きる小さな存在としての人間を省察する、そんな哲学的な境地を正直に語っている。
■エッチングで江戸の人々の「宇宙を見る目」を養った
曇天が多く、湿度が高い日本の気候では、星空は遠くまで見えにくいため、天はロマンの対象で「愛でる」対象でこそあれ、太陽系の運動や宇宙の全体構造までを論じる天文・宇宙にまで想像力を広げて「究める」ことがなかった。
ところが、江漢が自ら開発したエッチングの腕を活かして「地球図」(1793年)、「天球図」(1796年)を披露するとともに、先に述べた著作による啓蒙活動を行ったことによって、地動説・宇宙論を受け入れる人たちが少しずつ増えていったのではないかと思われる。
弟子にあたる片山円然(えんぜん)(1764〜?)が『天学略名目』(1810年)において、江漢の説を繰り返し述べていることからわかるように、人々の宇宙を見る目を一気に広げたのである。江漢は単に西洋の説の受け売りをしたに過ぎないと言われ、事実そうなのだが、私はその背景にある彼の科学的空想力の豊かさを高く評価したいと思う。
■宇宙の広大さと人間のちっぽけさを表現した志筑忠雄
同じ頃、長崎通詞の志筑(しづき)忠雄(ただお)は、西洋の天文学・物理学入門の文献を『暦象新書(れきしょうしんしょ)』として翻訳して(上編1798年、中編1800年、下編1802年)、ニュートン力学を日本に紹介した最初の人となった。志筑は、この『暦象新書』において、太陽系という小宇宙における地動説から広大な宇宙空間に星が点々と散らばっているとする無限宇宙のモデルまで、最新の宇宙像を紹介している。
江漢は「芥子(けし)粒が点々と散らばる宇宙」とか「荒野に馬があちこちに散策しているような宇宙」を想像したが、志筑も極大の宇宙空間に生きる人間の小ささを述べている。さらに「附録」として付けた「混沌分判図説」において、自らの創意に基づいて宇宙における天体形成過程の仮説を提案していることは高く評価できる。この「附録」で彼が論じた太陽系の形成過程の仮説は、カント・ラプラスの太陽系起源論と遜色がない。
何より強調すべきなのは、志筑が翻訳によって紹介した無限宇宙論(宇宙は有限ではなく無限の広がりを持つという考え方)は、江漢のような文学的想像力によって空想したものではなく、ニュートン力学に基づいた科学的思考によって提起されたものだということである。
また、「附録」の太陽系形成論では、回転体において遠心力と求心力が拮抗(きっこう)する下での惑星誕生という天体の発現過程を、あたかも実際の場をシミュレーションするがごとく極めてリアルに描いている。議論したり相談したりする同好の人間が誰もいない中での、彼の的を射た考察には頭が下がる思いがする。
■江戸時代に「宇宙人があちこちにいる」思想にたどり着いた山片蟠桃
一方、この『暦象新書』の写本を真剣に読み込み、無限宇宙に思いを馳(は)せたのが大坂で大名貸しを営む升屋の番頭である山片(やまがた)蟠桃(ばんとう)であった。実は、『暦象新書』は写本でしか出回らなかった上に、せっかくそれを入手しても数理的素養のない者にとっては非常に難解で、理解できた人間は少なかっただろうと想像されている。いくらニュートン力学の「入門書」の翻訳とは言っても、力や速度や運動などという概念に不慣れな人間には歯が立たなかったと思われるからだ。
では、蟠桃はどうかと言えば、おおよそは理解したが、完全に自信は持てないというところではなかったか、と思っている。
そのように私が言う根拠は、以下の点にある。
蟠桃が番頭職の合間合間に学習し思索して、自らの思想を書きとめて集大成した『夢の代』では、その最初に「天文第一」を掲げ、地動説から宇宙論に至る西洋天文学の知見を詳述している。その極めつきが、「宇宙には点々と恒星が分布し、恒星の周りにはさまざまなタイプの惑星が付属し、その惑星には人間が生きている星もたくさんある」という先進的な宇宙像を提示したことである。

実際に宇宙人があちこちに生息しているとする、現在の私たちが抱いている宇宙の描像を当たり前のように図示しているのだ。ところが、そこに行きつく直前の根拠を示す段落では、ほとんど『暦象新書』を丸写しにした文章が並んでいる。つまり、蟠桃は志筑の論を下敷きにして論を立てたのだが、その理解が不十分であるかもしれないと心配して、わざわざ志筑の文章を詳しく引用しているのではないかと想像されるのだ。
蟠桃は、おそるおそる自らの論を提示している風情なのである。自分の文章は多くの人が読むわけではないが、正確を期しておこうと考えたのだろう。とはいうものの、宇宙の至るところに人間が存在するという彼の宇宙論が色(いろ)褪(あ)せるわけではない。
以上のように、江漢・志筑・蟠桃という3人の異なったタイプの人たちが、蘭学隆盛の時代に地動説から無限宇宙論へと想像力を膨らませたのであった。私はこれを「江戸の宇宙論」と呼んでいる。蘭学が移入されて日本において大きく花開き、一瞬とはいえ日本の宇宙論が世界の第一線に躍り出たことを高く評価したいと思う。
----------
総合研究大学院大学教授
総合研究大学院大学教授・学長補佐。1944年、兵庫県生まれ。67年京都大学理学部卒、72年同大学院博士課程修了。72年京大理学部をはじめ、北大、東大、国立天文台、阪大、名大、早大と転籍。2006年より現職。著書に『ノーベル賞で語る現代物理学』『疑似科学入門』『科学を読む愉しみ』など。大佛次郎賞、講談社科学出版賞選考委員。
----------
(総合研究大学院大学教授 池内 了)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
海があるかも? 太陽系外惑星「LHS 1140 b」をウェッブ宇宙望遠鏡が観測
sorae.jp / 2024年7月18日 12時0分
-
80テーマ全文に朗読音声付き! 壮大な宇宙に魅せられながら「声で癒される宇宙科学本」が刊行!
PR TIMES / 2024年7月5日 13時45分
-
遠い恒星へと旅するのに必要な驚愕のエネルギー 光速の50%を超える速度で飛行するとしたら
東洋経済オンライン / 2024年6月27日 15時0分
-
すばる望遠鏡、カイパーベルトの外縁を超える可能性のある天体を発見
マイナビニュース / 2024年6月27日 14時54分
-
人類が遠い惑星に住むための独創的なアイデア どうすれば人間が居住可能な世界にできるのか
東洋経済オンライン / 2024年6月24日 15時0分
ランキング
-
1百条委提出の音声データにイチゴや塩の受け取りも示唆する発言 兵庫知事、相次ぎ受領か
産経ニュース / 2024年7月18日 21時46分
-
2埼玉・川口のマンションで爆発音、男性搬送…窓ガラスの破片飛び散り通行人らがけが
読売新聞 / 2024年7月19日 0時45分
-
3兵庫県知事「今、記憶がない」“特産品の要求音声”直撃に… パワハラ告発男性が残す
日テレNEWS NNN / 2024年7月18日 21時22分
-
4米軍関係者の性的暴行、他県でも非公表 「住民の被害を隠蔽」
毎日新聞 / 2024年7月18日 21時9分
-
5バブル期に各自治体へ1億円…「ふるさと創生」とは一体何だったのか 小学校に作った“巨大電飾看板”のその後
東海テレビ / 2024年7月19日 6時34分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











