「不安の9割は実際には起きない」禅僧が教える不安に潰される人、プラスに変えられる人の決定的違い
プレジデントオンライン / 2022年5月6日 12時15分
※本稿は、枡野俊明『やめる練習』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
■心を縛る「妄想」を手離す
人の世は一瞬たりともとどまることをせず、絶えず変化をしています。常が無い、つまり無常です。常に変化していれば、未来に何が起こるかは人の理性では予測できません。人生とはそういうものですから、不安のない人などいません。
「莫妄想(まくもうぞう)」という禅語があります。「妄想するなかれ」という意味ですが、この場合の妄想は心を縛るものすべてを指します。不安はその最たるものでしょう。
試験に受かるかという不安、果たして望んでいる会社に入れるだろうかという不安、新しいプロジェクトがうまくいくか見通せない不安、ちゃんと生活を送っていけるのかという不安、家族に何か起こるんじゃないかという不安、病気になるんじゃないかという不安、死に対する不安……。
じつにさまざまな「不安」が人生にはつきまといます。
■人が生きていくうえで「不安」は必要
小さなことから大きなことまで、次から次へと何らかの不安を感じながら生きていくのは、人間の宿命ともいえます。
もっとも、不安を持つことはマイナスな面だけではありません。プラスの面もしっかりあります。
さまざまなリスクから自分を守るには、それを敏感に察知する感覚がアンテナとして必要だからです。もし不安というものをいっさい持たない人がいれば、さまざまな危険やトラブルを予測できず、大変なことになってしまうでしょう。
人が生きていくには不安はある程度、必要だということです。
■「不安になる時間」の大部分は無駄
問題は、どうでもいいようなことに不安を覚えたり、考えても仕方ないことに不安を感じたりすることです。
不安に思っていることの9割は現実化しないものです。つまり、不安の多くは杞憂に終わっているわけです。「不安になる時間」の大部分は結果的には無駄な時間ということです。
あなたが感じる不安の多くは、そのような類の不安だと思っておくといいでしょう。
もちろん、不安を感じることに対して具体的な解決策を案じたり、それを避ける工夫を凝らしたりすることは大切です。
■自分を鼓舞する呪文
一方で、あれこれ考えを巡らせても、何ら解決への道筋をつけることにならないものは考えても仕方がないのです。このような類の不安は、気持ちがそこに囚われないようにするべきです。
それでも不安に囚われてどうしようもないときもあります。そんなときは、「大丈夫!」と自分にいい聞かせましょう。自分を鼓舞する言葉を呪文のように唱えると、気持ちが落ち着いてきて不安も和らいできたりするものです。
どんなときも希望を失わず、明るく物事を見る。常にそういう姿勢を心がけていれば、不安に対して不必要に囚われるようなことはなくなっていくはずです。
■「孤独」にはプラスもマイナスもある
一人暮らしの人が増えていることもあって、孤独をどう生きるかということがいろいろ論じられています。
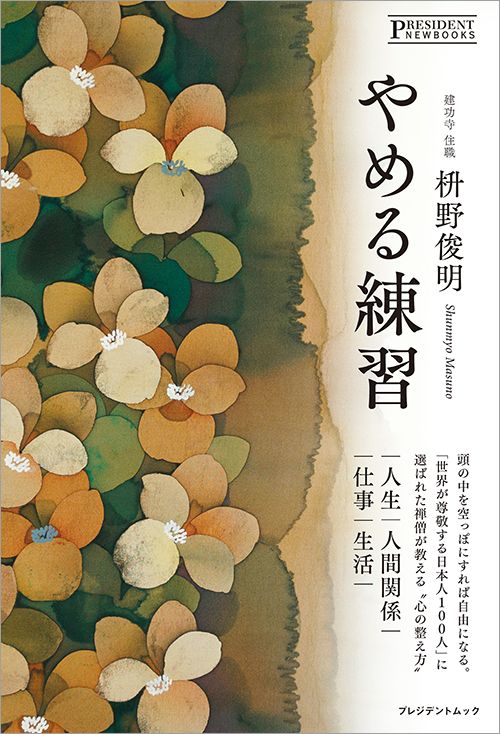
孤独というと不安で寂しいものというマイナスのイメージがつきまといますが、果たしてそうなのでしょうか。
孤独と一口でいってもいろいろな面があります。人と交わりたいのに誰も相手にしてくれないという孤立した状態はたしかに寂しいものです。
しかし、孤独には積極的な意味もあります。自分の心と静かに向き合い、そこに流れる、ゆったりとした時間を楽しむ。人と一緒にいては持ちえない滋味豊かな時間です。
孤独を掘り下げることで、心がわくわくするような新しい発見をすることもあるでしょう。これなど、孤独が与えてくれる醍醐味ではないでしょうか。
■良寛さんの「孤独を堪能する」生き方
江戸後期の僧侶、良寛さんは孤独を愛した人です。山のなかに庵を結び、光や風を感じながら自然と一体となった生活を送りました。小鳥のさえずりや川のせせらぎに心を遊ばせ、坐禅を組み、孤独のなかにある限りない豊かさを愛しました。
一人静かな時間を大切にしながらも、一方では食材を携えてときおり訪ねてくる村人とおしゃべりを楽しみ、子どもと鬼ごっこや手毬といった遊びに興じることもあったそうです。
良寛さんの生活には、孤立という寂しさはなく、孤独を堪能することで生まれる心豊かな時間が穏やかに流れているかのようです。
■眠っている「宝」の存在に気づく
良寛さんに限らず、禅僧は孤独を好みます。百丈(ひゃくじょう)禅師という高僧は、この世でいちばんありがたいことは何ですか、と問われたとき、今いるこの山(寺のこと)に一人坐っていることだと答えたそうです。
孤独は恐れるものではありません。人生を深く楽しむ時間をプレゼントしてくれるのが孤独なのです。
孤独にはまだ知らない宝がたくさん眠っている。そう思って孤独と向き合ってみませんか。
■雑な振る舞いをしない
禅の世界では、立ち居振る舞いや所作を整えることも重要な修行の1つです。そこに自らの心が素直に映し出されると考えるからです。
つまり、粗雑な心をもって振る舞えば粗雑な振る舞いになり、乱れた心で所作を行えば乱れた所作になるのです。
禅の修行における大きな目的は心を正しく整えることです。心を整えれば振る舞いや所作は整ったものになり、また反対に振る舞いや所作を整えることは心を整えることになります。
■心が整う「美しい所作」のコツ
それでは整った立ち居振る舞いや所作とはどのようなものでしょうか。その基準は「美しさ」にあります。整った振る舞いや所作には、流れるような美しさが感じられるものです。
心が整っているとき、心は澄み切っていて雑音がありません。迷いや不安、煩悩といったものから雑音は生じます。
同様に美しい振る舞いや所作にも雑音はありません。
たとえばオリンピックに出るようなトップアスリートの身体パフォーマンスは美しいものですが、それは運動力学的に理にかなった無駄のない動きをしているからです。そこには余計な力みなどの雑音がいっさいありません。
■粗雑なふるまいを顧みる
ひるがえって、粗雑な振る舞いや所作には雑音が満ちています。
会社で部下を理不尽に怒ってばかりいる上司、電車のなかでお化粧をしている女性、平気でゴミを路上に捨てる若者、スーパーの店員に些細(ささい)なことでクレームをつける老人、ネットで誰かを誹謗(ひぼう)中傷する人……どれもこれも美しくありません。

粗雑な振る舞いをしてしまうのは、いうまでもなく心が整っていないからです。
自分の振る舞いや所作はどうなんだろうと、気をつけてよく見てみたとき、「なっていないな」と感じることがあれば、ふだんの振る舞いや所作を美しくすることを心がけましょう。
■心と振る舞いは表裏一体
必ずしも「心を整えることからしなくては」などと考える必要はありません。
心と振る舞いは相互に密接な影響を与えますから、振る舞いや所作を整えればおのずと心も整ってくるものです。
ふだんの振る舞いや所作が美しいか、美しくないか。まずはそこへ意識を向けることから始めてみてください。
----------
「禅の庭」庭園デザイナー、僧侶
1953年生まれ。曹洞宗徳雄山建功寺住職、庭園デザイナー、多摩美術大学環境デザイン学科教授。大学卒業後、大本山總持寺で修行。禅の思想と日本文化に根ざした「禅の庭」を創作する庭園デザイナーとして国内外で活躍。著書に、『心配事の9割は起こらない』(三笠書房)、『傷つきやすい人のための 図太くなれる禅思考』(文響社)、『禅、シンプル生活のすすめ』(知的生きかた文庫)など。
----------
(「禅の庭」庭園デザイナー、僧侶 枡野 俊明)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「いい人」のはずが「都合のいい人」になっている訳 「よかれと思って」が他人には迷惑になることも
東洋経済オンライン / 2024年7月12日 18時0分
-
周りから「魅力的」と思われる人が日々している事 好かれたいと思うほど嫌われてしまう禅的理由
東洋経済オンライン / 2024年7月5日 18時30分
-
「ハイキュー!!」関連書籍が台湾・誠品書店の新刊ベストセラー5位に―台湾メディア
Record China / 2024年7月3日 7時30分
-
【ベストセラー著者の最新刊】禅僧であり世界的庭園デザイナーの著者が贈る「ぎすぎすしない生き方」46のヒント。新刊『迷ったら、ゆずってみるとうまくいく』本日発売!
PR TIMES / 2024年6月29日 12時40分
-
やりたくない仕事も「縁」と捉える人に訪れる良縁 私たちが誤解している「因縁」のポジティブな力
東洋経済オンライン / 2024年6月28日 19時0分
ランキング
-
1去勢された「宦官」は長寿集団だった…女性の寿命が男性よりもずっと長い理由を科学的に解説する
プレジデントオンライン / 2024年7月18日 8時15分
-
2結婚相談所は知っている「いつまで経っても、結婚できない男女の“意外な問題点”」
日刊SPA! / 2024年7月18日 15時50分
-
3iPhoneは「128GB」か「256GB」どちらを買うべきですか?【スマホのプロが解説】
オールアバウト / 2024年7月16日 21時25分
-
4ロシア軍の対空ミサイルを「間一髪で回避」ウ軍のドローンが“マトリックス避け”を披露 その後反撃
乗りものニュース / 2024年7月17日 11時42分
-
51日5分で二重アゴ&首のシワを解消!魔法の顔筋トレ「あごステップ」HOW TO
ハルメク365 / 2024年7月17日 22時50分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











