アニメ業界が激務薄給になった「元凶」と批判も…『鉄腕アトム』を激安で作った手塚治虫の誤算
プレジデントオンライン / 2022年5月12日 10時15分
※本稿は、津堅信之『日本アニメ史』(中公新書)の一部を再編集したものです。
■異例の1話30分放送に込められた手塚治虫の意図
『鉄腕アトム』で画期的だったのは、「毎週1回・1話30分・連続放送」という形式である。
毎週決まった曜日に30分枠で放送されるテレビアニメは、当時世界的にほとんど例がなかった。欧米のテレビアニメは1話5~10分程度と短く、その多くがショートギャグである。1話10分では、複雑なストーリーやキャラクターの心理描写は困難だが、子ども向けのシンプルな娯楽が定番だった欧米では、そもそもそんな野心はなかった。1話30分は、キャラクターの喜怒哀楽など心理描写を盛り込みたかった手塚治虫の意図が込められたものだった。
日本では1話30分が主流になり、その1話が次回へ続いて、半年以上をかけて壮大なドラマが描かれるテレビアニメも出現した。現在でも、毎週数十タイトルものテレビアニメが同じ形式で放送されていることを考えると、『アトム』がその後の日本アニメを決めてしまったともいえるわけである。
その『アトム』放送に至る虫プロの試行錯誤は、次のようなものだった。
■1話の制作に必要なアニメーターは660人以上
まず、そもそもテレビアニメとして何を作るかである。誰もが考えたのは、設立者たる手塚の漫画を原作にした作品だった。いくつかの候補は挙がったが、当時から手塚の代表作で、人間の心をもったロボットのアトムを通じて科学技術の危うさや矛盾を描いた『アトム』に落ち着いたのは自然な流れだった。
次に、毎週1話30分で放送するとして、それをどう作るかである。
設立時の虫プロは東映動画出身者が中心で、フルアニメ(*)派が大半だった。山本暎一はおとぎプロでリミテッドアニメを身につけていたが、ともかくフルアニメで、アニメーター1人あたりの平均的な作業量(動画の枚数)を加味して毎週30分のフィルムを作るとなると、実に660人以上のアニメーターが必要だとわかった。ベテランと新人合わせて十数名のアニメーターしかいなかった虫プロでは、どう考えても無理である。
(*)セルアニメなど描画系アニメーションの作画法には、フルアニメーションとリミテッドアニメーションがある。フルアニメは、キャラクターの全身を豊かに動かして表現する作画法、一方のリミテッドアニメは、たとえば口だけパクパク、眼のまばたきのように、身体の一部分だけ動かして表現する作画法。
■打開策は動いていない絵の「見せ方」を工夫すること
そこでフルアニメを捨ててリミテッドアニメを採用すること、また30分(CMなどを除けば実質約25分)のアニメを制作するために何人が必要かではなく、現有のアニメーター陣が1週間で描ける枚数で、どうやって「動いているように見せるか」を考えた。
その結果、1話あたりの動画枚数は1500~1800枚と決まった。これは当時の常識からして10分の1以下の枚数である。そのかわり、動いていない絵のカメラワークを工夫する、単純な歩きや飛行など繰り返し使える動画をストックして何度も兼用する(これを「バンクシステム」と呼んだ)、1カットあたりの時間(秒数)を短くしてスピーディーな展開にするなど、さまざまな「見せ方」が考案された。
そして最後に制作費である。『アトム』1話の制作費として虫プロが受け取ったのは55万円だった。実際には250万円はかかっており、放送局はもっと出せたというが、手塚がそういう超廉価に決めたのである。普通なら値上げ交渉をするのが手塚の役割のはずだが、手塚は値上げどころか「値下げ」したことになる。
■55万円で制作すればテレビアニメを独占できる
手塚の胸中には、当時の子ども向けテレビ番組の制作費を考えると55万円が妥当で、かつそれだけの廉価で制作すれば他社が追随できずテレビアニメを独占でき、虫プロスタッフをもってすれば、それは可能だとの目算があった。
『アトム』放送前年の秋、手塚は「ボクのところのこの方式ならふつうのテレビ・ドラマなみの制作費で作れます。5、60万円ですか? いや、その辺はご想像にまかせます」ととぼけてみせ(「東京新聞」1962年11月19日付)、第1話放送直後には「正直いって第1話は、試作費をふくめて130万円、第2話が90万円と、たいへんな赤字です。だが、だんだん安くできるようになりますよ。1クール(13週)おわるころには、契約の60万の線にいくでしょう」などと、わざわざ制作費を明かしている(「サンケイ新聞」1963年1月4日付)。
この手塚の姿勢と、あまりに安すぎる制作費は、この後手塚が批判される元凶になるのである。
■同業者と視聴者の反応は真っ二つに分かれた
『鉄腕アトム』第1話の視聴率は27.4%で、きわめて好調なスタートだった。放送開始から約1年半後の第84話「イルカ文明の巻」は40.7%を記録した。
『アトム』を見た東映動画の大塚康生は、「『あれじゃ誰も見ない』と思うほどのぎこちない動かし方で、アニメーションは動かすものだ(中略)と信じていた私たちにとっては到底受け入れ難い」と批判した。
しかし、視聴率に反映されたように、観客は受け入れた。日本では『アトム』放送前からアメリカ製アニメが多数放送され、リミテッドアニメによる「動かないアニメ」も多かった。似たような技法のCMアニメも放送されていた。つまり、日本のアニメが『アトム』を境にして質が変わったというのは俗説である。
そして、手塚が制作費を公言したため、手間もコストもかかるテレビアニメの国産化は困難と考えていた制作業界に波紋が広がり、次々と他社がテレビアニメに参入した。
まず、テレビCM用アニメ制作のTCJが、63年9月から『仙人部落』、10月から『鉄人28号』、さらに11月から『エイトマン』、実に3つのテレビアニメの放送を開始した。

■『アトム』の1年後、アニメ放送は9タイトルに
『鉄人28号』は横山光輝の漫画が原作で、巨大ロボットものの先駆け的作品だが、注目すべきは『仙人部落』である。小島功(こお)の大人向けの漫画が原作で、放送は23時40分からの15分間だった。深夜放送帯のアニメは2000年代に入って急増したが、放送枠に関する限り、その第一作は『アトム』と同年だったのである。
次に、東映動画の『狼少年ケン』は63年11月から放送開始、翌64年の1月からはピー・プロダクション(ピープロ)制作による『0戦はやと』の放送が始まった。ピープロは、漫画家のうしおそうじが1960年に設立した映像制作会社で、『アトム』に刺激されてテレビアニメに参入した。
64年8月から放送されたのが『ビッグX』で、原作は手塚治虫の漫画だが、制作はテレビアニメ参入を目的に新設され、後に『ルパン三世』を手がける東京ムービーだった。創業者はそれまで人形劇団を主宰していた藤岡豊(1927~96)で、アニメには無縁だった。
65年5月放送開始の『宇宙エース』は、タツノコプロのテレビアニメ第一作である。後に『タイムボカン』シリーズを手がけるタツノコは、漫画家の吉田竜夫(1932~77)が漫画執筆の工房として設立したが、やはり『アトム』成功の流れの中でテレビアニメに参入した。
『アトム』放送開始からちょうど1年後の64年1月、テレビアニメは週9タイトル、65年10月には12タイトルもの放送数になった。
■主題歌やタイアップしたお菓子は飛ぶように売れた
『アトム』はまた、現在では当たり前になったアニメに付随するビジネスを興した。
まず、オープニングの主題歌である。子ども向けのテレビ番組の主題歌には『月光仮面』(1958~59年)など先行例はあるが、『アトム』主題歌を収録したソノシート付きの『鉄腕アトム・第1集』は120万部を売り上げたという。谷川俊太郎作詞、高井達雄作曲の主題歌は現在でも我々の耳に馴染み、以後、テレビアニメの主題歌は「アニソン」として、ときには本編のアニメから独立し得るポップカルチャーになった。
『アトム』のスポンサーとなった明治製菓の看板商品の一つ、マーブルチョコの発売は『アトム』放送開始の2年前である。当時は子ども向け菓子商品の販売競争が激烈で、トップメーカーの森永製菓がよく似たコンセプトの菓子「パレード」を発売すると、それまでマーブルが糖衣チョコの9割を占めていた市場シェアが3割にまで落ち込んだという。
偶然にも『アトム』のスポンサーだった明治製菓は糖衣チョコの市場を取り戻すべく、63年7月、マーブルチョコのフタ2枚を送るとアトムシールがもらえるキャンペーンを実施した。
■人気漫画のテレビアニメ化が定番となったワケ
すると、連日数万通もの応募の封筒が届き、100人以上のアルバイトを雇ってさばいた(社内報「メイカ」第9巻第8号、1963年8月)。翌年3月から、アトムシールは「おまけ」としてマーブルチョコに封入されることになり、人気アニメとタイアップする菓子、そしておまけというビジネスモデルの先駆けとなった。
そして、『アトム』の最大の成果は、人気漫画のテレビアニメ化である。連載中の人気漫画をアニメ化すれば、その漫画の読者はアニメの視聴者となる。一方、アニメで初めてその作品に接した視聴者は、原作漫画の新たな読者になり得る。アニメと漫画、視聴者と読者との双方向性が明瞭になり、後続のテレビアニメに活かされた。
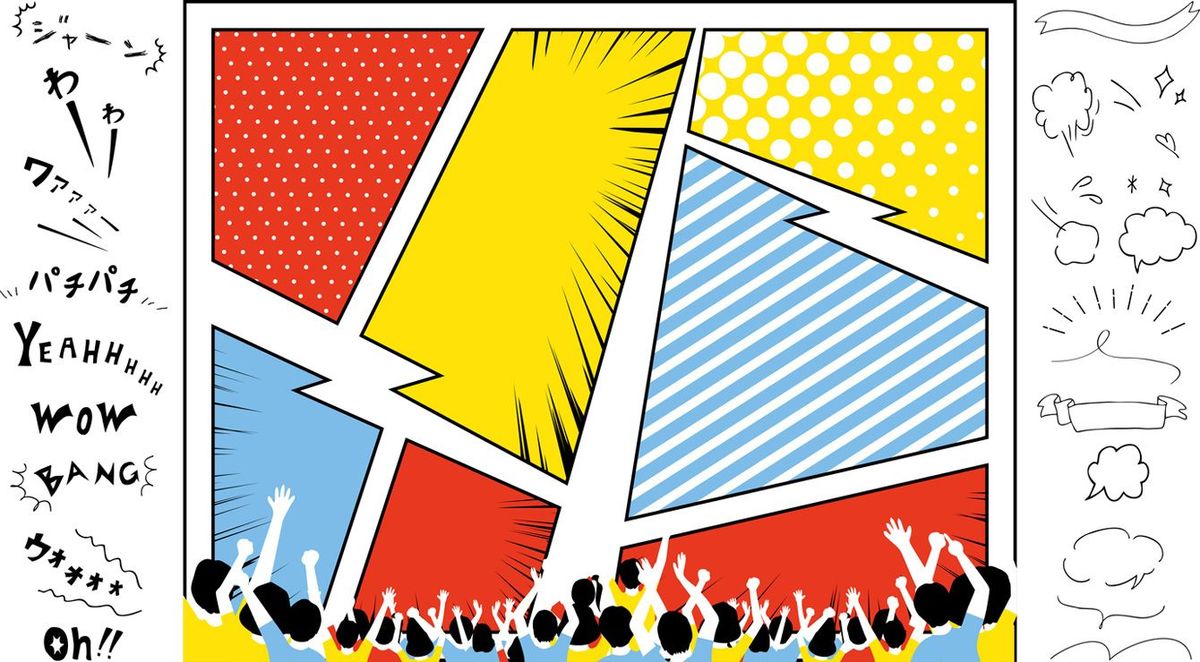
■数字が一人歩きした手塚治虫の「1話55万円」契約
『アトム』を語る際、超廉価だった制作費の問題は避けられない。手塚治虫の独断に近い形で、制作費を1話55万円で契約した前例が、現在までアニメ制作費を安く抑え、制作現場の劣悪な労働の元凶になったとさえ言われてきたからである。しかしこの制作費は、数字が一人歩きした側面もある。
まず、約4年間・全193話放送された『アトム』は、その期間ずっと1話55万円だったのではない。当時の虫プロスタッフの証言によると、話数を重ねる中で徐々に上積みし、最終的には1話300万円程度までになっている。また、1965年10月放送開始のテレビアニメ『ジャングル大帝』では、制作現場に投入される予算は1話250万円で管理された。
さらに、『アトム』の当初契約1話55万円は、あまりにも安すぎるとして、手塚には告げない形で虫プロの事務方が再協議し、代理店(萬年社)が1話あたり100万円を補填(ほてん)して、合計155万円で制作していたとの証言もある。
■労働環境が改善されていない責任はだれにあるのか
手塚の口から「1話55万円」が世間に流布した結果、テレビアニメは安く作れるとの話が当時どこまで真実味をもって理解されたかは明らかではない。だが、事実として『アトム』以降テレビアニメに参入する制作会社が続々と現れた。
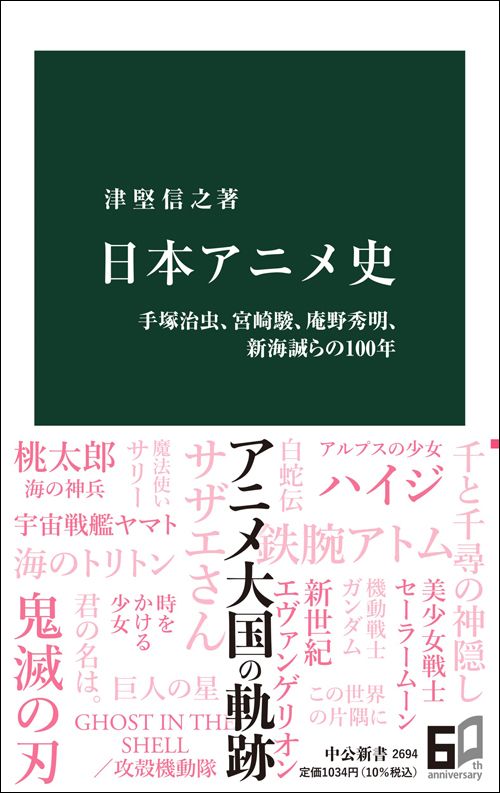
それでも、『アトム』以来半世紀以上を経た現在まで、安い制作費の原因を手塚に押しつけるのは、話を飛躍させすぎている。自社が制作する作品の価値を認識し、それを権利として獲得することは、後続のアニメ制作会社にも課せられていたはずである。そういう後続他社の努力の欠如、もしくは変えられなかった責任を問う声は、なぜか小さい。
東洋のディズニーとして劇場用長編アニメ制作を軌道に乗せた東映動画の仕事は、ディズニーの『白雪姫』公開からは約20年を隔てて、日本のアニメ界を近代に導いた。
一方『鉄腕アトム』は、何かに追随したというよりも、発想の転換で新しいアニメの形を示し、世界的視野から見た日本のアニメの独自性を追求するきっかけを作った。
そして、本格的にディズニーの方法を取り入れた東映動画は技術的モダニズムを日本のアニメ界にもたらし、商品としてのアニメを形成した虫プロは産業的モダニズムをもたらしたと言い換えることもできるだろう。
----------
アニメ―ション研究家
1968年兵庫県生まれ。近畿大学農学部卒業。日本大学藝術学部映画学科講師。専門はアニメーション史。近年は映画史、大衆文化など、アニメーションを広い領域で研究する。主な著書に、『日本のアニメは何がすごいのか』(祥伝社新書)、『ディズニーを目指した男 大川博』(日本評論社)、『新版 アニメーション学入門』『新海誠の世界を旅する』(ともに平凡社新書)など。
----------
(アニメ―ション研究家 津堅 信之)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
『三つ目がとおる ミッシング・ピーシズ』が7月10日に発売 『ブラック・ジャックミッシング・ピーシズ』に続き、手塚治虫の編集術を堪能できる貴重な1冊!
PR TIMES / 2024年6月27日 13時40分
-
カプコン・手塚治虫がトキワ荘ミュージアムでコラボ 「アトムの昇龍拳」「フランスパンとメンチカツ持って行く」ファン期待
iza(イザ!) / 2024年6月21日 13時23分
-
「ガンダム」生みの親が語る日本エンタメ史の裏側 安彦良和氏が驚愕した才能、原作のアニメ化に思うこと
東洋経済オンライン / 2024年6月15日 11時0分
-
実は原作改変にあらず 昔の特撮やアニメはなぜあんなに同題マンガとは別物だったのか
マグミクス / 2024年6月9日 6時25分
-
NYのグッズ売り場にデコピン登場 敵地で生まれた大谷翔平人気に米国ファン「オオタニ効果」
THE ANSWER / 2024年6月7日 12時3分
ランキング
-
1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」
Sirabee / 2024年6月29日 4時0分
-
2若々しい人・老け込む人「休日の過ごし方」の違い 不安定な社会、「休養」が注目される納得理由
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分
-
3忙しい現代人が“おにぎり”で野菜不足を解消する方法。野菜たっぷりおにぎりレシピ3選
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時53分
-
41年切った「大阪・関西万博」現地で感じた温度差 街中では賛否両論の声、産業界の受け止め方
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 14時0分
-
5水分補給は昼コーヒー、夜ビール… 「熱中症になりやすい人」の特徴と対策
ananweb / 2024年6月29日 20時10分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












