「1人で勝手に早口で話す人」はキケン…周囲のイライラを増やす「絶対に近づいてはいけない人」の共通点
プレジデントオンライン / 2022年5月20日 9時15分
※本稿は、小林弘幸『気がついたら自律神経が整う「期待しない」健康法』(祥伝社)の一部を再編集したものです。
■35歳を過ぎるとはじまる体の不調とどう向き合うか
生物学的に見ると人間の体の機能的ピークは、20~35歳の時期だといわれています。
この時期は骨の強度が一生のうちでもっとも強く、すべての器官がスムーズにはたらきます。
肉体的にも多少の無茶が利くし、疲れからの回復も速い。
食事バランスや運動などを意識せずとも、日々を元気に過ごせる。
幸運にも大病をしないまま中年になった多くの人にとっては、こうした状態が35歳頃までの「普通」だったのではないでしょうか。
ところが、40代、50代と年齢を重ねていくと、どんなにタフな人でも次第に体に無理が利かなくなってきます。
肌の水分が失われるため、シワが増えていきます。目のかすみや老眼、聴力の衰えなども徐々に始まります。一晩寝ても疲れが取れない日も珍しくないでしょう。
内臓の消化機能も衰えていくため、かつては好物だった揚げ物や丼物、こってり系ラーメンなどのボリュームのある食事もつらくなってきます。
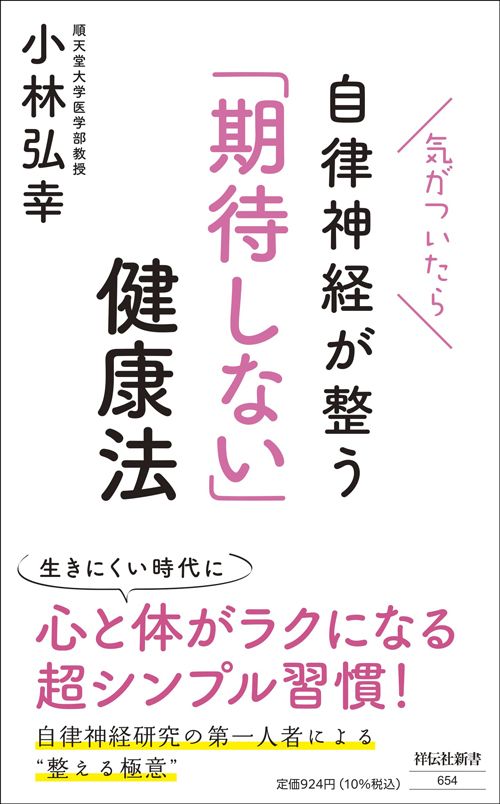
一方で、日本人の平均寿命の数値はいまだに延び続けています。厚生労働省の最新の調査(「令和2年簡易生命表」)によると、女性は87.74歳、男性は81.64歳と男女ともに過去最高を更新しました。
しかし、いくら平均寿命が延びても、医学の技術が進歩しても、人間の生き物としての体のピークが20~35歳であることは変えられません。個体差はあっても、ヒトという生物を見たときにこの平均値は動かせません。
つまり、「元気が普通」でいられるボーナスタイムは、人生序盤のわずかな期間だけにすぎないということです。
現代人は体の機能やコンディションが衰えてから生きる時間のほうが、ずっとずっと長いのです。
■毎日の積み重ねで好調なコンディションはつくれる
だからといって悲観することはまったくありません。
毎日の生活習慣をちょっと意識するだけで、好調なコンディションはつくれるようになるからです。
もちろん、その鍵を握っているのは自律神経です。
ゆったりした呼吸や日常のちょっとした工夫によって交感神経と副交感神経がうまく釣り合うようになれば、血液の流れがスムーズになり、腸内環境が改善されることで、体と心が整った状態に導かれていきます。
免疫力が高まるため、アンチエイジング効果も期待できます。小さな不調も悪化させる前に解消できれば、重大な病気の予防にもつながっていくでしょう。
本書の第4章では日常生活の中のちょっとした工夫によって、自律神経を整える習慣を身につけるコツをお伝えしていきたいと思います。
お金を払ってジムに行く必要も、運動用のシューズやウエアを用意する必要もありません。誰でもすぐにできる簡単なものばかりですので、ぜひ今日から生活に取り入れてみてください。
■ベストを尽くしながら、期待値だけは意識して下げておく
もう一つ、大切なのが本書のキーワードである「期待しない」ことです。
私たちががっかりしてしまうのは、常にそこに期待があるからです。
他人や自分、起きる出来事に期待をかけてしまうからこそ、そうではない結果にがっかりして、自律神経のバランスを乱してしまうのです。
10~20代の若い時代であれば、期待が裏切られても、その都度回復できる力がたいていは備わっていますが、30代以降になると乱れた自律神経がなかなか元に戻らなくなります。
だからこそ、日々の暮らしの中でも「期待」を手放すことで、心を整えることを意識していきましょう。
期待をすべて捨てろ、という極端な話ではありません。
過剰な期待をそっと削ぎ落とすことで、意識的に自分の中の期待値を下げるコントロールをするのです。
「絶対に大丈夫だと信じていたのにダメだった」と、「多少の期待はあったがやはりダメだった」では、結果が同じでも直後の頭と心の切り替えがまったく違ってきます。
前者は期待をかけたぶん失望が深くなり、落ち込んで感情が乱されるため、冷静に何がダメだったかを検証する目も曇りがちです。
対して後者は、失望はあれども想定の範囲内ですから、思考と感情の切り替えが早くなります。「今回は何が足りなかったのか」と問題点を冷静に検証できるため、次に活かしていけるでしょう。

ベストを尽くしつつも、期待値だけは意識して下げておく。
これは人間関係や仕事はもちろん、日常で起きるあらゆる出来事に対しても同じです。いつまでも小さなことに一喜一憂してばかりいると、自律神経はいつまでも乱れっぱなしで心が整いません。
日常生活に新しい習慣を取り入れるときも同じです。
自分に過剰な期待はしない。
一方で、「まずは試してみよう」「頑張ろう」というまっすぐな思いは大事に持っておく。
新しいことを始めるときは、常にこの二点を心に留めておきましょう。そうすれば、目の前のことに淡々と自然に集中できるようになります。
期待をしないことは、最初から手を抜いたり、投げやりになったりすることとはまったく違うのです。
■「ゆっくり」話せば、失言やうっかりミスが減る
では、ここからは日常生活ですぐに実践できる「期待しない習慣づくり」を具体的にご紹介していきましょう。
まず、すべてに共通するといってもいいのが「ゆっくり」行なうことです。
ゆっくり深く呼吸をすることのメリットについては、本書の第3章で詳しくお話ししましたが、「ゆっくり」の効果が発揮されるのは呼吸だけに限りません。
ゆっくり話すことを心がけるのも、自律神経を整える上ではとても大切なポイントになります。
ゆっくり話すということは、しっかり呼吸をしながら対話ができるということでもあります。すると酸素が血液に十分に取り込まれ、良質な血液が脳や体の隅々まで行き渡ります。頭がクリアになるため、失言やうっかりミスも減るでしょう。
また、ゆっくり話すことを意識すると、言葉を選ぶ余裕が生まれます。感情が言葉に乗りすぎないため、相手をむやみに傷つけることもなくなります。
エモーショナルな言葉が効果的な場面もありますが、人は感情が入れば入るほど、話すスピードも速くなります。そんなときに他人からムッとするようことを言われると、反射的にきつい言葉で返してしまいがちです。
■早口は相手の自律神経をも乱す
チッと舌打ちしたり、乱暴な言い方をしたりした瞬間に、イライラは増幅します。すると、とたんに交感神経が優位になり、早口でまくしたてることで、余計に興奮します。相手を傷つけてしまう失言や暴言は、たいていは早口から生まれます。
また、早口になっているときは、呼吸も浅く速くなります。
すると交感神経のはたらきだけが高まり、瞬間的にはやる気が湧き上がるものの、それが長く続くと血管が収縮し、血流が悪くなります。そのため、仕事や作業におけるパフォーマンスも下がってしまいます。
さらに、早口や乱暴な言葉は、口にしている当人だけでなく、聞いている相手の自律神経をも乱してしまいます。
伝えたいことは、ゆっくり静かに話す。
その一点を常に心がけるだけで、コミュニケーションが丁寧な人として周囲にも好印象を与えられるでしょう。好感度が上がれば、相手も「この人がそう言うなら」と力になってくれる場面が増えるはずです。
■「自分から話さない」はメリットだらけ
コミュニケーションで自律神経を乱さないために有効な方法の一つとして、「自分から会話の口火を切らない」ことをおすすめしています。
これは私が実体験から学んだことです。昔の私は非常に早口でおしゃべりな人間でした。そのせいで口を滑らせて余計なことを口走っては、あとで自己嫌悪に陥る、というループに陥っていたのです。

そんな繰り返しを経て思いついたのが、「自分からは話さない」というルールを決めることです。もちろん、ただ感じ悪く黙り込むのではなく、質問をされたときにはきちんと答えます。けれども、自分から「何かを言ってやろう」というアクションは起こさない。
この基本ルールを決めただけで、驚くほど失言が減りました。落ち込むことも減ったため、自律神経のバランスが乱れることもなくなりました。
かつての自分を振り返ってみると、「自分からたくさん話す」ことで、私は自分の存在をアピールしようと無意識のうちに躍起になっていたのでしょう。ちょっとした沈黙に耐えられなかったのも、自信のなさの表れだったように思えます。
うっかり失言するパターンが多い人は、ぜひ実践してみてください。「余計なことは話さない」と決めるだけでも、会話に穏やかな空気感が漂うはずです。
もう一つ、自分から話さないことのメリットは、相手が勝手にこちらの事情を想像してくれる点です。「そうですね」と一言シンプルに返すだけで、相手は自分のいいように解釈をし、言葉を重ねてきます。
すると、こちらは状況を的確につかめるようになります。自分から話し出さないことは、余計な波風を立てないために非常に有効なコミュニケーション術です。
----------
順天堂大学医学部教授
1960年、埼玉県生まれ。スポーツ庁参与。順天堂大学医学部卒業後、同大学大学院医学研究科修了。ロンドン大学付属英国王立小児病院外科、トリニティ大学付属小児研究センター、アイルランド国立小児病院外科での勤務を経て、順天堂大学医学部小児外科講師・助教授などを歴任。自律神経研究の第一人者として、トップアスリートやアーティスト、文化人のコンディショニング、パフォーマンス向上指導にも携わる。順天堂大学に日本初の便秘外来を開設した“腸のスペシャリスト”としても有名。近著に『結局、自律神経がすべて解決してくれる』(アスコム)、『名医が実践! 心と体の免疫力を高める最強習慣』『腸内環境と自律神経を整えれば病気知らず 免疫力が10割』(ともにプレジデント社)。新型コロナウイルス感染症への適切な対応をサポートするために、感染・重症化リスクを判定する検査をエムスリー社と開発。
----------
(順天堂大学医学部教授 小林 弘幸)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
これで1日のストレスをリセットできる…自律神経の名医が勧める「寝る前の3行日記」の2行目に書くこと
プレジデントオンライン / 2024年6月25日 7時15分
-
1日2~4杯飲めば幸せホルモンが増え、うつ病のリスクが低下…ハーバード大が効果を実証した身近な飲み物
プレジデントオンライン / 2024年6月19日 7時15分
-
便秘が解消される…医師が解説!正しい「腸もみ」と「腸にきくツボ」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月18日 8時0分
-
更年期「だる重疲れ」対策に!睡眠の質を上げる「自律神経改善プログラム」夜編
ハルメク365 / 2024年6月14日 21時0分
-
更年期の「だる重疲れ」スッキリ解消!自律神経改善プログラム「朝昼編」
ハルメク365 / 2024年6月7日 21時0分
ランキング
-
1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」
Sirabee / 2024年6月29日 4時0分
-
2「モノ屋敷の実家を片付け」嫌がる母と攻防の顛末 「絶対に捨てられない母」をどう説得したのか
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 13時0分
-
3朝ドラ「虎に翼」後半戦がますます面白くなる根拠 「パイオニアとしての成功物語」からどう変わる?
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 11時0分
-
4まもなく上場「タイミー」やって見えた本質的課題 ガチの隙間時間ではできず、微妙に使い勝手に難?
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 12時0分
-
5「A-10を退役させろ」ついに年貢の納め時? スーパー攻撃機も「現代戦では使えない」を示したロシアのライバル機
乗りものニュース / 2024年6月29日 6時12分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












