マンモス、サーベルタイガー…人類の祖先が壁画に描いた巨大動物「メガファウナ」はなぜ大絶滅したのか
プレジデントオンライン / 2022年7月8日 11時15分
ロンドンの自然史博物館で、氷河期の大型動物を紹介する企画展の内覧会を訪れた子供たち。写真の模型は左から、ショートフェイスベア、サーベルタイガー、マンモス(2014年5月21日、イギリス・ロンドン) - 写真=EPA/時事通信フォト
※本稿は、高橋瑞樹『大絶滅は、また起きるのか?』(岩波ジュニア新書)の一部を再編集したものです。
■人間が引き起こしている「6度目の大絶滅」
「毎日、最大150種もの生きものたちが、この地球上から姿を消している」
国際連合(以下、国連)の生物多様性条約事務局がこのショッキングな見積もりを発表したのは、2007年のことでした。絶滅の速度は加速し続け、現在も生きものは減り続けているのです。
生きものたちは「食う―食われる」「寄生や共生をする」「食べ物やすみかをうばい合ったり、提供したりする」など、たがいに関係しあって生きています。しかし、多くの個性的な生きものたちが姿を消し、彼らがつないできた「生きものの輪」は、いま地球規模で壊れつつあります。研究者たちはこれを6度目の大絶滅と呼んでいます。
じつは、地球では過去にも5度、生きものたちが大絶滅した時期がありました。けれども、いまの私たちが直面している6度目の大絶滅は、過去の大絶滅とは大きく異なります。それは、過去の大絶滅は地質学的な原因によって引き起こされたのに対して、今回の大絶滅はたった1つの生物種、私たち人間が、引き起こそうとしているからです。
■人類の進化は不安定な気候環境のなかで起こった
人間はいつ頃から多くの生きものを絶滅に追いこみ始めたのでしょう?
二足歩行をする私たちの祖先(ヒト属)がチンパンジーの祖先と枝分かれしてアフリカ大陸で誕生したのは、600万〜700万年前のことでした。その後、約258万年前から、地軸(ちじく)(北極点と南極点をつらぬく、地球が自転する際の軸)の傾きが4万1000年周期で22.1〜24.5度の間で振(ふ)れるようになったため、地表が受ける太陽エネルギーの量が変化して、氷河期と間氷期(かんぴょうき)(氷河期と氷河期の間の、比較的温暖で安定した期間)がくり返されるようになりました。
ちなみに、北半球で夏は暑くて冬は寒いという季節変化が生じるのは、地軸の傾きがあるためです。そして私たちはいま、間氷期に生きています。現在の地軸の傾きは約23.4度ですが、少しずつ傾きが小さくなって、氷河期に向かう段階にあります。つまり、ヒト属の進化は、氷河期と間氷期がくり返される不安定な気候環境のなかで起こったのです。
そしてこの気候の不安定さこそが、ヒト属が道具を利用したり社会性を獲得したりして、環境適応能力(自然環境を都合の良いように操作する能力)を高めながら進化を続ける土台になった、と考えられています。
■人類が分布を拡大した地域で大型動物が絶滅していった
ヒト属の一員として私たち現生人類ホモ・サピエンスは約20万〜30万年前にアフリカ大陸に現れて、ユーラシア大陸、オーストラリア大陸へと広がっていきました。そしてアジアを経由し、アメリカ大陸に到達したのが約1万5000年前と考えられています。日本では縄文時代の前の、旧石器時代のできごとです。
ちなみに、ヒト属にはホモ・エレクトス・ペキネンシス(北京原人)やホモ・ネアンデルターレンシス(ネアンデルタール人)なども存在しましたが、私たちホモ・サピエンス以外のヒト属は絶滅してしまいました(ただし、近年の研究で、ネアンデルタール人はホモ・サピエンスと混血していて、現生人類の一部はネアンデルタール人の遺伝情報をわずかながら受け継(つ)いでいることがわかっています)。

アフリカからヒトが分布域を拡大するにともなって、行きつく先々で、メガファウナと呼ばれる大型動物たちが絶滅しました。
「メガファウナ」というとなんだかカッコイイですが、メガは英語で「大きい」、ファウナは「動物たち」で、そのまま「大きな動物たち」という意味です。メガファウナの多くは哺乳類ですが、大型の鳥類や爬虫(はちゅう)類なども絶滅しました。体の大きな動物は人間の狩猟の標的になりやすいという以外にも、絶滅しやすい原因がいくつかあります。
■大型動物はほかの動物と比べて絶滅しやすい
まず、体が大きければそれだけ多くの食料と広い生息地を必要とするので、面積あたりの数も少なく、種としての総数も少なくなる傾向があります。何らかの理由で生息地がせばめられると、最初に絶滅の危機におちいるのは、こういった広い生息地を必要として比較的低密度で暮らす、大きな動物たちなのです。
また、体が大きいと性成熟する(大人になる)までに長い時間がかかり、メスが一度に産む子の数も比較的少ないので、個体群の数が増える速度もゆるやかです。つまり、何らかの原因で個体群が減少すると回復に時間がかかります。そして、その間に減少の原因が取り除かれなかったり、新たな減少要因が加わったりすると、絶滅リスクが格段に高まるのです。
さて、話をヒトの分布域の拡大に戻しましょう。ヨーロッパにホモ・サピエンスが到達したのは4万5000年ほど前だと考えられています。
その後、ホラアナライオンと呼ばれる現在のライオンに非常に近い仲間や、マンモス、サイの仲間たち、とてつもなく大きな角を持っていたギガンテウスオオツノジカなど、たくさんのメガファウナが絶滅したことがわかっています。
フランスのショーヴェ洞窟には数々の動物の壁画が残されていますが、その多くがすでに絶滅したメガファウナたちです。壁画を描いた当時のヒト属は、彼らの描いた絵がまさか絶滅動物図鑑になるとは思っていなかったことでしょう。
■かつて北米にはラクダの仲間やマンモスが生息していた
約1万5000年前にホモ・サピエンスが到達したアメリカ大陸でも、多くのメガファウナが絶滅しました。
特に北米では絶滅したメガファウナの研究が進んでいて、35属が絶滅したという記録が残っています。化石をたよりに種を同定するのが難しいので、属としてのデータ集計になっているのだと思います。仮に少なく見積もって、1つの属に平均して2種の動物がいたとすると、70種ものメガファウナが絶滅したことになります。
その代表としてよくあげられるのが、ものすごく長い牙を備えていたサーベルタイガーやアメリカライオン、アメリカチーター。そして、立ち上がると6メートルにもなる巨大なナマケモノ(図版1)の仲間たちです。

また、かつて北米にはラクダの仲間やマンモスもいました。このように、アフリカから始まったホモ・サピエンスの分布域拡大が世界中におよぶ頃には、少なくとも150属の哺乳類、2000種以上の鳥類、そして15属の大型のカメが絶滅したと報告されています。6度目の大絶滅への道は、メガファウナを中心にすでに旧石器時代に始まっていたのです。
■人間のターゲットにされてきた猛獣
6度目の大絶滅は、過去の5つの大絶滅と比較して2つの点で大きく異なっています。1つ目は、ホモ・サピエンスという1種類の生きものにより大絶滅が引き起こされているという点。2つ目は、絶滅の対象となる種類が大型の動物にかたよっているという点です。
2つ目がまさにメガファウナの絶滅なのですが、この傾向は現在も続いています。特に、私たち人間は、積極的に「猛獣」と呼ばれる生態系における頂点捕食者(食物連鎖の頂点に立つ捕食者)を絶滅させたり、絶滅に追いこんだりしてきました。
かつて日本でも本州、四国、九州と広く分布していたニホンオオカミという頂点捕食者が1900年代初めに絶滅しました(なお、かつて北海道にいて絶滅したエゾオオカミは、ニホンオオカミとは異なるタイリクオオカミの亜種だとされています)。
僕の祖父は1900年代初めの生まれですが、その祖父は、そのまた祖父からオオカミの話を聞いたのをよく覚えていて「いかにオオカミが賢かったか」を幼い僕に何度も話してくれました。一昔前までは、日本でもオオカミは身近な存在だったのでしょう。
ニホンオオカミが絶滅した原因は、イヌの伝染病がオオカミに伝染したことや、生息地の破壊、獲物の減少、そして人為的な駆除など、複数の要因がからみあっていたと考えられています。なかでも人為的な駆除は、それなりに大きな影響があったはずです。
■猛獣が駆除されてきた3つの理由
人間が「猛獣」と呼ばれる頂点捕食者を駆除し、絶滅に追いこんできた理由は大きく3つあります。
まず1つ目は、頂点捕食者は人間も襲(おそ)うことがあるからです。アフリカでは、いまだにライオンが人間を殺すことがあります。インドでも年間40〜50人がトラに襲われて命を落としているそうです。アメリカにおいてもクーガー(別名ピューマ)が人を襲うことがあり、過去100年間に20人以上が亡くなっています。ニホンオオカミもまれに人間を襲うことがあったため、駆除された個体も少なくなかったはずです。

2つ目の理由は、猛獣は、ウシ、ヤギ、ヒツジ、ブタなどの家畜を襲うことがあるからです。家畜化され、丸々と太ったおとなしい草食動物たちは、猛獣にとっても最高の獲物です。それが災いとなり、猛獣は「大切な家畜を襲う悪者」として排除されてきたのです。
そして3つ目は、人間も生態系の頂点捕食者として狩猟をして生きてきたからです。それは、他の頂点捕食者と競争関係にあることを意味します。たとえれば「オオカミさえいなければ、もっとシカやイノシシが捕(と)れたのに」という思いで、猛獣たちを駆除してきたのです。また、人間が猛獣たちと同じ獲物を捕ることで、猛獣たちのエサが不足して、間接的に猛獣を絶滅に追いこんでもきました。
■猛獣が絶滅することで生態系のバランスが崩れてしまう
こうして、地球上に「猛獣たちのいない世界」が広がっていきました。現在ではライオンもトラもジャガーもチーターも、猛獣と呼ばれる動物の多くが絶滅危惧種です。オオカミも、世界各地の個体群が絶滅しました。海の頂点捕食者であるラッコも絶滅危惧種です。
猛獣がいない世界の広がりは、人間にとっては一見、住み心地のよい、安全な世界の広がりであるかもしれません。ですが、裏を返して他の生きものの立場になってみれば「人間という手のつけられない猛獣が支配している世界」ともいえるでしょう。
では、人間にとって、猛獣たちのいない世界には、何か不都合はあるでしょうか? じつは、猛獣がいなくなると、たいへん困ったことが起こることが、生態学の研究の積み重ねでわかってきました。そのしくみの1つを、例としてあげましょう。
まず、猛獣がいなくなると、猛獣が捕食していた草食動物たちが増えます。すると、草食動物が植物を食べすぎてしまい、植物が減ります。植物が減ると、植物をたよりに生きてきた多様な生きものたち(他の草食脊椎動物や昆虫の仲間など)も減少してしまうのです。
また、猛獣が競争力が強く数の多い草食動物を捕食することで、競争力が弱く数の少ない草食動物にも生きていけるチャンスが生まれ、結果として多様な草食動物が共存できる環境が保たれることもわかっています。つまり、猛獣と呼ばれる頂点捕食者がいるおかげで、生態系全体の多様性が保たれてきた、ということです。
猛獣たちはその個体数に比較して生態系に与える影響力が大きいためにキーストーン種(キーストーン=要石(かなめいし))と呼ばれ、生態系の保全を考えるうえで大切な動物なのです。何かと悪役のイメージのある肉食獣が、じつは生態系にとって大切な存在であるとは、意外に思われた人もいるのではないでしょうか?
■ニホンオオカミが絶滅した地域ではなにが起こっているか
このように、生きものの輪が乱れて生態系のバランスに大きな不具合が生じた一つの例として、ラッコとステラーカイギュウの関係が知られています。海藻を食べるウニをラッコが捕食することによって、カイギュウが食べる海藻が維持されていたのですが、ラッコが人間の狩猟によっていなくなったため、ウニが増えすぎ、エサとなる海藻が激減してステラーカイギュウが絶滅する大きな原因となったのです。
しかし、海藻が減って困るのは、カイギュウ(ジュゴンやマナティーも含む)だけではありません。
海藻は、海中の森を形成します。海藻がおいしげる場所は、藻場(もば)とか海中林(かいちゅうりん)(ケルプ・フォレスト)とも呼ばれ、魚類やカニなどの甲殻類など、様々な生きものたちの宝庫です。藻場は、大陸棚(大陸周辺の比較的浅い海)の生態系を支える重要な役割を果たしています。
つまり、ラッコという頂点捕食者がいなくなることで、カイギュウだけではなく、海中の植物群に支えられていた多くの生きものたちも生きていけなくなるのです。
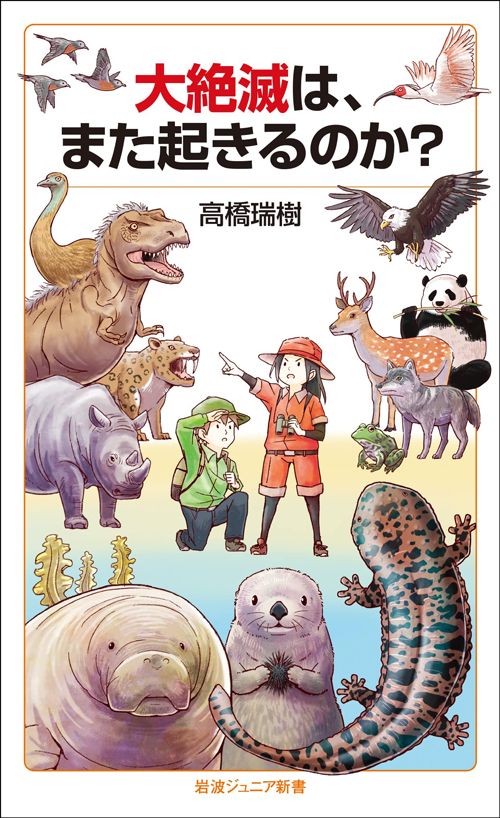
日本ではここ10年間で、農地を囲むシカやイノシシよけの柵をいたるところで目にするようになりました。これだけ草食動物が増えたのには、温暖化によって冬越しできる個体数が増えたことや、山村地域での人口減少など複数の理由がありますが、ニホンオオカミが絶滅して頂点捕食者がいなくなったことも、無関係ではないでしょう。
特にシカによる食害は深刻な問題です。被害がひどいところでは森林内の下草が全滅し、地面がむき出しになっています。地面をおおう下草がなくなると、土が風化し、斜面では土がくずれ落ちたりします。大雨の時には土が流出し、それが川に流れこむと、川の生きものにも被害がおよぶことになります。
また、シカにも好き嫌いがあるため、シカの好む植物は減少し、嫌いな植物ばかりが増えます。そうすると、森の植物の構成も変化していきます。その結果、シカが好む植物にたよっている生きもの、特に幼虫の食べる植物の種類が決まっているチョウ類などは減ってしまいます。
逆に、シカが嫌いな植物をあてにしている生きものは増えていきます。こうして生態系のバランスがくずれ、多様性だけでなく、森の機能も低下するのです。このように、草食動物が増えることによる悪影響は想像以上に深刻なものです。
■猛獣がいない世界は、平和な世界ではない
では、ニホンオオカミが果たしてきた役割(オオカミが利用してきた生態的ニッチ)を、誰(だれ)がどうやって果たしていけばよいのでしょうか? 狩猟をする人の数は少ないですし、シカを殺すのはかわいそうだと反対する人もいます。生きものを殺すことを「かわいそう」と思う、優しい気持ちは大切です。
しかし、増え続ける草食動物をこのままにしておいたら、生きものの輪はさらに壊れ、街で暮らす人間の目につかないところでより多くの生きものたちが死んでゆき、結果的に多くの種が絶滅に追いこまれる可能性があります。猛獣と呼ばれる捕食者なき世界は、じつは平和な世界ではなく、生態系に不調和が広がる、荒廃(こうはい)した世界にもなりえるのです。
----------
バックネル大学生物学部准教授
1973年生まれ。北海道出身。東京都町田市育ち。理学博士。日本ハンザキ研究所研究員。専門は保全生態学。共働きの両親のもと、町田の里山と母親の実家山形県鶴岡市羽黒の自然と生きものたちを遊び相手に育つ。筑波大学生物資源学類卒業。東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程修了。両生類の世界的減少を知り、保全生態学を学ぶため米国大学院留学。メンフィス大学生物科学部博士課程修了。2011年よりバックネル大学で生態学などを、研究休暇中は同志社大学にて日本の環境保全問題についての授業を担当。学術雑誌『Herpetological Conservation & Biology』の共同編集者。
----------
(バックネル大学生物学部准教授 高橋 瑞樹)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
13歳で論文発表!ニホンオオカミの剥製を発見した中学生と学ぶ“絶滅動物のおもしろさ”
日テレNEWS NNN / 2024年7月30日 10時41分
-
【かわいくて凛々しい! 野生イヌの魅力が満載】人気のハイイロオオカミやホッキョクギツネ、タヌキまで、60種以上のイヌ科動物が大集合!
PR TIMES / 2024年7月25日 12時15分
-
2万1000年前に人間が存在した証拠!? アルマジロ化石に「食肉解体」の痕跡 南米で発見
よろず~ニュース / 2024年7月24日 21時40分
-
中国の希少および絶滅危惧野生動物種の個体群、安定的に増加
Record China / 2024年7月8日 19時20分
-
「クルルッ」屋根裏から鳴き声と足音 蓋をあけてキャットフードを食べる アライグマ被害ついに住宅にも
RKB毎日放送 / 2024年7月2日 18時55分
ランキング
-
1「再訪したい国」日本が世界首位 人気地域に人出集中する傾向
共同通信 / 2024年7月29日 16時51分
-
2夏は「食中毒」に要注意 下痢が出たときに市販薬を服用してもOK? 症状&対処法を消化器病専門医に聞く
オトナンサー / 2024年7月30日 7時10分
-
3扇風機の「電気代」は、エアコンと比べてどれだけ安いんですか?【家電のプロが解説】
オールアバウト / 2024年7月29日 20時15分
-
4日銀の利上げで今後の住宅ローン金利は上昇傾向へ、それでも「変動金利」が有利な理由
マイナビニュース / 2024年7月29日 6時30分
-
5住民税は何歳から何歳まで払うの?未成年でも払うの?
オールアバウト / 2024年7月29日 20時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











