人命最優先では経済発展は望めない…アフリカ人が「すぐ壊れて、人も死ぬ中国製の鉄道」を愛するワケ
プレジデントオンライン / 2022年8月25日 12時15分
※本稿は、小林邦宏『鉄道ビジネスから世界を読む』(インターナショナル新書)の一部を再編集したものです。
■世界中が衝撃を受けた「事故車両を埋める」という対応
2011年7月に中国の浙江省温州市で起きた高速鉄道の衝突脱線事故は、多くの点で衝撃的だった。
落雷によって動力を失いトンネルの手前で停車していた列車に、後続の列車が追突し、一部の車両が高架橋から転落した事故直後の映像の生々しさ。乗客40名が死亡(中国政府発表)した高速鉄道の衝突事故がどのようなものかを、すでに高速鉄道を運行している国の人々もはじめて目撃したのだ。
そして、さらに衝撃的だったのが、事故後の中国側の対応だ。
高架下に落下した事故車両は、事故から5日目の時点ではすべて高架下に埋められていた(その後、解体)。当時の温家宝首相は事故の原因究明が必要だと訴えていたが、残りの車両も事故直後に中国鉄路の車両基地に搬送されていた。現場保全の原則は完全に無視され、事故から2日後には、なにごともなかったかのように通常運行も再開されたのだ。
■ナイジェリア、ケニアが事故数年後に鉄道建設を発注
普通なら「自国でこんな事故を起こし、隠蔽(いんぺい)体質まで露呈した国に鉄道建設を発注して大丈夫か?」と考えるはずだが、ナイジェリア政府もケニア政府も事故後の14年に“なにごともなかったかのように”中国と鉄道建設の新たな契約を結んでいる。日本人の感覚からすれば、これも衝撃的だ。
しかし、「事故は起こるもの」という考え方もできる。そして「起きたとしても、大したことない」という考え方もあるかもしれない。それは、中国が大事故から2日後に通常運行を再開したことで証明されたともいえる。また、中国政府は、事故の犠牲者遺族への補償(ひとり50万元=約600万円)も事故から数日で決定している。
そして、これは重要な点だが、11年の悲惨な事故後も中国の高速鉄道の利用者数は増え続けているのだ(11年には年間約3億8000万人、14年は年間5億3000万人)。
この現実が意味するものは、なんだろう?
■鉄道の価値観の軸は「安全性」だけではない
事故後に中国の高速鉄道を利用した人たちも、あの悲惨な事故を知らないはずはない。事故の原因究明が訴えられながらも車両が埋められ、証拠隠滅が図られたことも承知の上で乗っているに違いない。つまり「過去には死亡事故もあっただろうが、自分は大丈夫」という、極めて利己的で同時に人間らしい行動原理に従っているのだ。
心理学の世界では「正常性バイアス」という言葉で説明するそうだが、要するに、事故後に承知で中国の高速鉄道を利用した人たちは、まず利用する必要があったから乗車したのだ。そして、自分のその行動を正当化するために「自分は大丈夫だ」という勝手な理屈を作り出しているのである。
もちろん、それでも「あんな危険な鉄道には金輪際、乗らない」という人もいるだろう。しかし「自分は大丈夫」と考える人が多数派を占めれば、こうした乗車拒否を貫く人たちは“飛行機嫌い”と同じ扱いをされるようになるはずだ。本来、事故の確率からいえば旅客機はもっとも安全な乗り物だ。それでも断固として飛行機には乗らないという人たちも少数ながら存在するが、やはり“変わり者”として扱われているのだ。
中国高速鉄道の安全性を疑問視するのは当然だが、実際の世界は、少なくとも科学的な意味での「安全性」とは別の価値観を軸に動いているということだ。
■事故は起きるし、事故後も鉄道は走り続ける
21年5月、メキシコシティで走行中の地下鉄車両が高架橋の崩落によって落下し、乗客26名が死亡する事故が起きた。この地下鉄は建設中から工事の杜撰さが指摘されていたというが、メイド・イン・チャイナではない。工事は、フランスのアルストムと現地財閥の合弁事業で、崩落した高架橋は現地財閥の担当だったという。
ちなみに、この「現地財閥」のオーナーのカルロス・スリムは『フォーブス』誌の選定する世界長者番付で1位になったこともある人物だが、どうも、ただの富豪ではない。2010年代にジャーナリストのディエゴ・オソルノが発表した彼の評伝のタイトルは『Carlos Slim: Patrón of Mexico’s Power Mafia』。「マフィア」という単語に目がいくが、敢えて訳すのはやめておこう。
メイド・イン・チャイナでなくても事故は起きる。そして、その後も鉄道は走り続ける。このことだけが、鉄道ビジネスの現実のように思えてしまう。たしかなことは、中国もアフリカも“こちらの現実”を重視している点だ。
■「万が一」のために飛行機に脱出装置は設置しない
人命軽視というのは恐ろしいことだ。しかし実際には、中国以外の欧米先進諸国の企業が展開する旅客輸送ビジネスにおいても人命の尊重は最優先課題ではない。
もっともわかりやすい例は、私たちが普段から利用している旅客機だろう。もし、本当に人命尊重が最優先課題ならば、高度1万mで事故が起きても安全に脱出できるように、客席ひとつひとつにジェット戦闘機の操縦席と同じ脱出装置をつけてもいいはずだ。しかし、実際には旅客機ビジネスにおいて事故の際の「人命」は経営上のコストとして捉えられているようにしか思えない。

飛行機事故の確率は「1万フライトに1回」という明確な統計基準があるので、その確率で起きる事故のために高額の脱出装置を機体に備えるか、事故の際に一定額の補償金を払うか、どちらが低コストかが慎重に検討された結果、脱出装置は断念され、現在の機体装備となっているのだ。
ただし、人命尊重が最優先課題ではないからといって、安全性に無関心でいいことにはならない。航空業界も、現在「1万フライトに1回」とされている事故の確率を「10万フライトに1回」にしようと努力を続けていることは、忘れてはならない。
ただ、それでも事故によって人命が失われることも視野に入れてビジネスを展開するというのは、安全な運行を持続させるという「サスティナビリティ(持続可能性)」というグローバル・スタンダードとは相容れない考え方かもしれない。しかし、そんな非グローバル・スタンダードな鉄道ビジネスが、特にアフリカの大地では熱帯の植物が葉を繁らせるように発展を続けているのは紛れもない現実だ。
■「さすがメイド・イン・チャイナ。開通前に壊れたよ」
筆者が鉄道に興味を持ったのは、今から6、7年前のケニアだっただろうか。
ケニアの首都ナイロビ郊外、アティ・リヴァー(Athi River)と呼ばれるエリアを移動していたときのことだ。
ふと、幹線道路に沿って建設されている高架橋が目に入った。現地で長年、ドライバーを務めてくれる人間に訊いた。

「なんだあの高架橋は? 高速道路?」
「違う。高速鉄道だ。ナイロビとモンバサを結ぶ」
これが、モンバサ・ナイロビ標準軌鉄道(通称SGR)を初めて見た瞬間だ。
確かに、建設中の高架橋の横には特にアフリカでよく見かける、中国内陸部の建設会社と思われる看板もある(一般的に、中国内陸部の企業が中国政府を代表してアフリカへ進出している)。でも、アフリカではこんな景色は日常である。当時はなんとも思わなかった。
そして数カ月後、再びアティ・リヴァーへ戻る。ふと幹線道路から外の景色に目をやると、前回見かけた高架橋が無い。再びドライバーに訊く。
「あの高架橋、どうしたの?」
「ああ、あれか。早速崩壊したよ。さすが、メイド・イン・チャイナだな。開通前に壊れたよ。ワハハ。でも、どうせまたすぐ造るだろうよ」
■国によって鉄道・道路に求める価値は違う
一般的に安全第一と考えられる鉄道網に対してすら、こののんびりとした雰囲気。
さすがアフリカだと思いつつ、ああ、鉄道とはいえ、国によって、求める価値は違うのだな……。
と感じたことは今でも忘れられない。そして、この感覚をさらに裏づける出来事が隣国エチオピアであった。
同国の首都アディスアベバに滞在していたときのこと。まず、アディスアベバ郊外に張り巡らされた高速道路に驚く。運転手が自慢気に言う。
「どうだい、俺たちの国にはチャイナマネーで既にこんな立派な高速道路があるんだぜ」
「いや、でも、中国でも既に路面がボコボコになっている高速道路をよく見かけるよ」
「アハハ、ボコボコになってもいいじゃないか。そもそも、俺たちには中国の借金を返済すらできないんだから」
その後、アディスアベバの中心部を移動していると、今度は開通したばかりの新都市交通システムが現れた。
ここはエチオピアだし、利用客ももちろんエチオピア人。でも、この景色だけを切り取れば、ヨーロッパあたりのどこかの街とも言える景色である。続けてドライバーがいう。
「この借金も返せないだろうよ。でもね、俺たちは道路や電車のおかげで本当にハッピーなんだ。中国には感謝してるよ」
■日本以上に中国のものは世界で求められている
この頃からだろうか。筆者の中にも、“スタンダードというのは異なるものだ”という気持ちがより芽生えるようになった。今でいうところの、“ダイバーシティ”と呼ばれるものだろう。
昨今、SDGs(持続可能な開発目標)をはじめとして、いろいろな分野で“ダイバーシティ”といった言葉を聞くようになった。
ところが、片やアフリカや南米等でこうした社会インフラビジネスを見ると、
“スタンダードって、ダイバーシティってなんなのだろう”
と思わずにはいられなくなった。それを顕著に感じたのが、この鉄道ビジネスである。
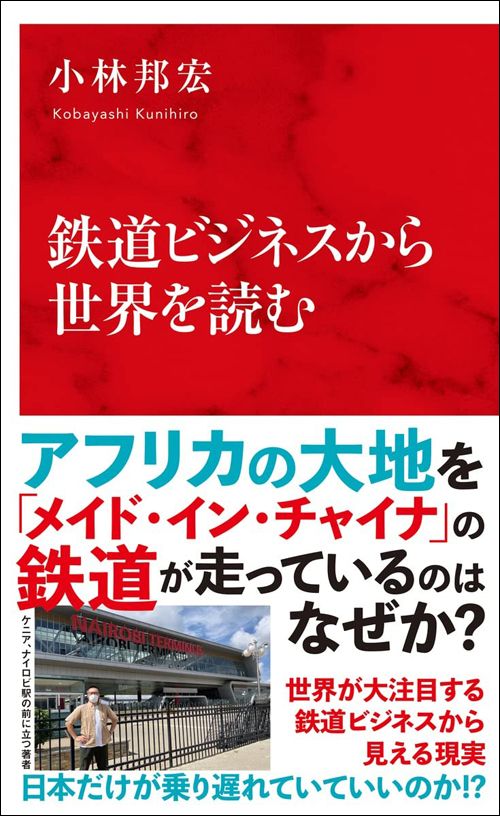
日本企業が世界にてビッグディールを成約したとき、もしくは大きな活躍をしたとき、新聞等のメディアではよく取り上げられる。
それで、誤解が生まれる。
「日本のものは世界で求められているのだ」
と。自信を持っていえるが、それは違う。
報道されているようなビッグディールや海外ビジネスはごくわずかで、それと比べて1桁も2桁も上回るディールが中国系企業によってなされているということを。
そして、それは、現地で少なからず受け入れられているということを。
----------
元住友商事社員、YouTuber
1977年生まれ。旅するビジネスマン。2001年、東京大学卒業後、住友商事株式会社入社。情報産業部門に配属されるも、世界中を旅しながら仕事をするという夢を実現するため、28歳で自ら商社を起業し、花、水産物、プラスチックなどの卸売りを開始。「大手と同じことをやっていては生き残れない」という考えのもと、南米、アフリカ、東欧、中近東などに赴き、知られていないニッチな商材を見つけ、ビジネスを展開。著書に『なぜ僕は「ケニアのバラ」を輸入したのか?』(幻冬舎)。
----------
(元住友商事社員、YouTuber 小林 邦宏)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
高速道路・都市間鉄道・一般道路を一体化、常泰長江大橋の建設進む―中国
Record China / 2024年7月23日 16時30分
-
中国、橋崩落で11人死亡・30人不明 習主席「救助に全力を」
ロイター / 2024年7月20日 16時35分
-
日本支援「ホーチミンメトロ」いまだ開業しない謎 「中国も手を出したがらない」ベトナムの事情
東洋経済オンライン / 2024年7月19日 7時0分
-
高速バスでエンジンから出火、運転手の対応に不満の声 小湊鉄道「完璧な誘導は難しいが、問題ないとは言えない」
J-CASTニュース / 2024年7月18日 13時51分
-
中国で隆盛を極めた長距離寝台バスが「お役御免」になった事情とは―香港メディア
Record China / 2024年7月15日 23時0分
ランキング
-
1「みどりの窓口は減ったけど、便利になったね」は不可能か いや、やればできるはず
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月27日 7時30分
-
2英語ができない人はチンパンジー扱い…「日本人の米グーグル副社長」が31歳から英語を猛勉強し始めたワケ
プレジデントオンライン / 2024年7月28日 9時15分
-
3『秘密のケンミンSHOW』で圧倒的に登場回数が多い都道府県は?北海道でも、沖縄県でもない、納得のワケ【齋藤孝が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月27日 8時0分
-
4ヨーカドーの商品7000点が最短30分で届く…ネットスーパー最大の欠点を解消した「鬼速のOniGo」のカラクリ
プレジデントオンライン / 2024年7月28日 8時15分
-
5激安スーパー激戦区に無料がいっぱいの街!住んだらお得な街を調査しました!
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月28日 15時2分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











