小泉進次郎氏の「失言」を忘れてはいけない…肉食ブームの日本人が知らない欧米諸国の冷ややかな視線
プレジデントオンライン / 2022年9月6日 10時15分
※本稿は、山本謙治『エシカルフード』(角川新書)の一部を再編集したものです。
■小泉進次郎氏の「失言」
2019年9月、小泉進次郎環境大臣(当時)は訪問先の米国・ニューヨークで「訪米中、ステーキはいつ食べるのか?」と記者から質問を受けてこう答えた。
「毎日でも食べたいね」
わたしたちの記憶にも新しいこの発言だが、食のエシカルの観点から、また一国の環境省のトップの発言としてはまずいものだった。
というのも近年、世界的には家畜の肉を食べること、それを拡大生産していくことに対する目が厳しくなってきているからだ。
その大きな理由が環境への悪影響である。
つまり、環境大臣という立場(当時)の小泉氏が、「ステーキを毎日でも食べたい」と発言したのは、かなり恥ずかしい態度だったといえる。
世界で進む食のエシカルの文脈を、日本はあまり真剣に考えていないんだということを露呈させてしまった出来事といってよいだろう。
欧米のエシカル意識の高い層からすれば「日本はちょっと、おかしいんじゃないの?」と言われても仕方がない。幸いなことに、現地メディアはこの発言を大きく報じてはいない。それはそもそもこの分野で日本へ期待する欧米人がおらず、注目も集まっていないということなのかもしれない。
はっきりしているのは、わたしたちがこのまま無自覚に際限なく肉を食べるべきではない、ということだ。
少なくとも世界で家畜の肉、ひいてはたまごや乳といった動物性タンパク質をどのように摂(と)るべきかということを、世界の状況を見ながら考えるべきである。
■全人類がヴィーガンなら農地は4分の1
畜産業をめぐってはさまざまな批判が存在する。
なかでも、近年指摘されるのが、畜産業がもたらす環境への負荷についてだ。
国連食糧農業機関(FAO)によれば、人間の活動によって排出される温室効果ガス(GHG)のうち、14.5%は畜産業とそれに関係する産業が原因とされる。
特に、反芻(はんすう)動物である牛は、消化の過程で強力なGHGであるメタンを排出するため、家畜全体の排出量の65%を占めるとも言われるのだ。
また、家畜の飼育や、その餌となる穀物の栽培には多くの土地と水が必要だ。ここでの推計には諸説あるが、『エシカル・コンシューマー』によると、仮に人類全員が動物性食品を摂取しないヴィーガンになると、必要な農地面積は全世界で75%減少するという。
■牛肉や豚肉などは「おそらく発がん性を有する」
畜産業従事者の人権問題への関心の高まりも見逃せない。
欧米各国がコロナ禍にあえぐ2020年中、主にと畜施設などで相次いでクラスター感染事例が発生した。
この背景には、安価な食肉供給を維持するため、低賃金でかつ過酷な労働環境に置かれる現場の労働者の実態がある。
彼らの多くが移民労働者であるということもあって、複合的なエシカル問題として、盛んに報道された。
畜産について厳しく問われているのは、環境問題や人権問題だけではない。
たとえば「肉を食べると体に悪い」というのも昨今よく耳にする話題だ。
特に、畜肉の摂取とがんの関係を懸念する声が多く、これには科学的にもある程度の裏付けが与えられている。
国際がん研究機関は2015年、「レッド・ミート」と欧米で称される、牛肉や豚肉など哺乳類の畜肉について、「おそらく発がん性を有する」という内容の評価を発表した。
いっぽう、実際にがんを発病するかどうかには、摂取量が大きく関係し、週に数回の適度な摂取であれば問題ないという、国立がん研究センターなどによる研究結果もある。
日本の2〜3倍程度の食肉摂取量を誇る欧米諸国と日本では、状況が違うという考え方もあるので、一概に肉が体に悪いとも言いきれない。
ただし日本も牛肉ブームが続くなど、食肉摂取量が増加している状況なので、注意は必要だろう。
■「新型インフルエンザ」は家畜の豚から広がった
さて、新型コロナウイルスの災禍を経た社会では、畜産業への「逆風」が勢いを増している。
というのも「集約型の工場的畜産こそ、感染症の温床だ」という見方がされているからだ。
狭いスペースで大量の家畜を飼育するためには、抗生物質を飼料などから投与することが慣行として定着している。が、これによって薬剤耐性を持つ菌やウイルスの誕生が引き起こされ、人への感染リスクも懸念されているのだ。
事実、米国のマウント・サイナイ医科大学の研究では、2009年に世界的に大流行した新型インフルエンザは、メキシコで飼育されていた家畜の豚の間で流行していたウイルスが原因であったことが判明している。
新型コロナ禍によってこうしたことがシビアに議論されるようになったが、じつは2000年代初頭から、医学の世界では薬剤耐性菌やウイルスの恐怖が囁かれていた。
2017年にはWHOが「食用家畜における抗菌性物質の使用に関するガイドライン」を発表し、各国に畜産における抗生物質(抗菌剤)の使用量を削減することを勧告した。
ここ最近また世界の感染者数が増大している新型コロナ禍をみれば、この問題がいかに恐ろしいものかよくわかるだろう。
■抗菌剤をやめれば生産量が減る
ただし、こうした勧告を受け入れて抗菌剤を飼料に添加しなくなった場合、おそらく畜産物の生産量は減少する。
というのも、抗菌剤の使用は生産量増大に直結しているからだ。
健康な家畜は餌を食べた分だけ太ったり、たまごや乳を出してくれたりするものだ。ただし、集約型の畜産では狭い場所で密飼いをするため、家畜にストレスがかかることが多い。
人がストレスで体調を崩すように、家畜も顕著に体調を崩し、お腹(なか)を下すなどしてしまう。お腹を下すというのは消化不良だから、せっかく食べた餌を摂取できず、畜産物に変換できない。
以前、若鶏(ブロイラー)の生産者に聞いた話だが、抗菌剤を添加した餌には整腸作用があるため餌の消化効率が上がり、結果的に出荷までの日数を5日程度短縮できるということだ。
100万羽、200万羽という巨大な養鶏事業において、5日間の差は大きい。その抗菌剤を使用できないとなれば、世界的に畜産物の生産効率は低下する。
しかしそれよりも耐性菌やウイルスが生まれてしまうことの方が脅威であると、WHOは考えているわけだ。
■求められる「エシカルな畜産」
このように、畜産業への批判は実に多様な角度と論点から巻き起こっている。
しかし、こうした批判の帰結が必ずしも「畜肉を食べるべきではない」ということにはならない。
畜産業が直面しているさまざまな問題は、集約型畜産と、それによって大量生産される安価な畜肉が引き起こすものであって、アニマルウェルフェアを重視したエシカルな畜産の実践によって解消できる部分は大きい。
ただし、先に述べたようにエシカルな畜産を志向し、抗菌剤の添加もやめてしまうと当然、世界の畜産物の生産量は大幅に減少することになる。
そこで重要となるのが近年、注目を集める代替肉だ。
エシカルな環境で生産された畜肉とあわせて、代替肉を食生活に取り込むことで、我々の食事はよりエシカルになるのだろうか。
■「アメリカだけで8000億円市場」代替肉の現状
代替肉と聞いて「うわ、美味しそう」「食べてみたい」と積極的に感じる人はそう多くないだろう。
わたしは率先して食べてみたいと思うが、それは食を巡るビジネスの輪の中にいる人間だからかもしれない。
ただ、代替肉と聞いて眉をひそめる人のなかには、それがどのようなものかをよく知らないで拒否している人も多いのではないだろうか。
だとしたら、基本的な部分だけでも知っておいた方がいいだろう。
代替肉には大きく分けて、2つの分野がある。
1つは大豆などの植物性タンパク質を原材料としたプラントベース(植物性肉)と呼ばれるもの。もう1つが、細胞培養技術によって動物細胞を増殖させて作られるカルチャード・ミート(培養肉)と呼ばれるものだ。
なかでもプラントベースは、米国だけで既に8000億円規模の市場を持つ立派な産業となりつつある。
このプラントベースの市場拡大を牽引(けんいん)してきたのが、2011年にカリフォルニアで誕生した2つのスタートアップ、ビヨンド・ミートとインポッシブル・フーズだ。
ビヨンド・ミートは、エンドウ豆のたんぱく質をベースとしながら、ビーツから絞ったジュースを加えることで、畜肉に比べほぼ遜色(そんしょく)ない風味を誇る商品を開発。
米国では、高級スーパー「ホールフーズ」をはじめ、多くのスーパーマーケットの店頭で販売されている。
一方のインポッシブル・フーズは大豆をベースにしているが、肉感を再現するために独自の酵母培養の技術から生まれた「ヘム」と呼ばれる物質を使用する。
同社は、大手バーガーチェーンとのコラボによって全米で「インポッシブル・バーガー」を展開し、一躍その名を知られることとなった。

■2023年には「培養フォアグラ」も実現?
次に代替肉のもう一翼、培養肉の開発は、2000年代初頭から一部の研究者の間で進められた。
2013年にはオランダ・マーストリヒト大学のマーク・ポスト教授が世界初の「培養ビーフパティ」を発表し、世界に衝撃が走った。
しかし、当時は細胞培養のための培養液などのコストが非常に高く、ポスト教授のビーフパティの価格は200gで3000万円とも言われた。
このエピソードは世界中で話題になったので、なんとなく覚えている人も多いだろう。
その後、ポスト教授が設立したスタートアップであるモサ・ミートや、ビル・ゲイツなどの著名投資家から出資を得た米国のUPSIDE Foodsをはじめ、世界各地で培養肉の低廉化に向けた研究開発が進められた。
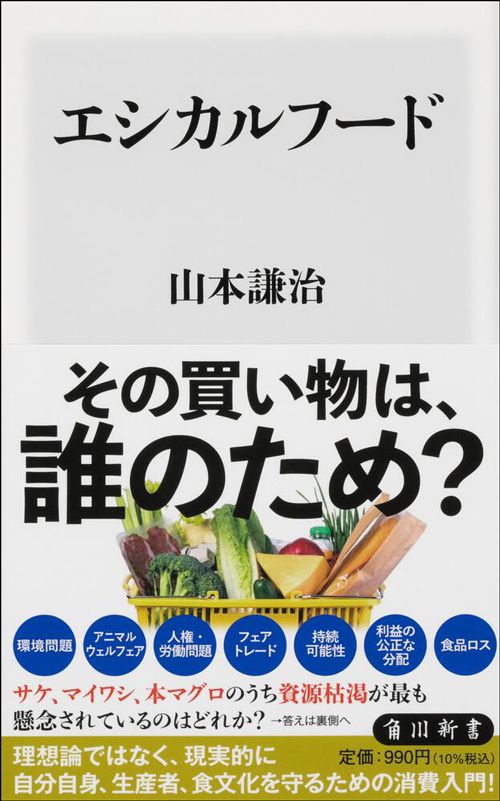
シンガポールでは米国のイート・ジャストが開発した培養チキンの販売が開始されている。日本では、インテグリカルチャーというベンチャー企業が、細胞を培養するバイオ・リアクターと呼ばれる培養槽を製品化しており、多方面から投資を受けて成長している。
同社の社長である羽生(はにゅう)雄毅(ゆうき)氏にはインタビューをしたことがあるが「2023年には培養フォアグラの製品化が実現すると思います」と言っていた。
フォアグラは脂肪の塊なので比較的作りやすいとのことで、たんぱく質が立体的な構造をもつ赤身肉を作る方が難しいそうだ。
ただ、このように世界中で開発競争がなされている状況を見ると、培養肉を我々が手に取る日も、案外近いと考えざるを得ない。
----------
農産物流通コンサルタント
1971年、愛媛県に生まれ、埼玉県で育つ。1992年、慶應義塾大学環境情報学部在学中に、畑サークル「八百藤」設立。キャンパス内外で野菜を栽培する。同大学院修士課程修了後、シンクタンク、青果流通企業を経て、2005年、(株)グッドテーブルズ設立。農畜産物流通コンサルタントとして活躍中。ブログ「やまけんの出張食い倒れ日記」。著書に『激安食品の落とし穴』(KADOKAWA)など多数。
----------
(農産物流通コンサルタント 山本 謙治)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「牛のげっぷ」抑制で温室効果ガス削減目指す<シリーズSDGsの実践者たち>【調査情報デジタル】
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月27日 7時30分
-
PwC Japan、「食卓で起きる変革と代替」 調査結果を発表
Digital PR Platform / 2024年7月22日 15時11分
-
国産飼料用米・エコフィードを活用した自家配合施設の新たな取り組み|海外依存からの脱却へ
PR TIMES / 2024年7月22日 13時45分
-
日本ハム・JA全農 畜産業の持続的発展で連携 連携の土台にサスティナビリティ
食品新聞 / 2024年7月15日 11時57分
-
「コンビニのサラダは栄養が少なそう」は大間違い…野菜研究家が「どんどん食べたほうがいい」と言い切るワケ
プレジデントオンライン / 2024年7月13日 15時15分
ランキング
-
1「夏休みは迷惑!」母親が激白 夏休み“廃止・短縮”希望が6割 SNS上では「日本もこんな悲しい国になったのか」と衝撃広がる
CBCテレビ / 2024年7月28日 10時0分
-
2男子トイレを素手で掃除「おしっこが飛び散っていて。気持ち悪かった」 女子児童に指示した小学校の職員「できるだけきれいな校舎にして卒業生を送り出したかった」
RKB毎日放送 / 2024年7月28日 12時0分
-
3口論となった40代元妻宅に窓から侵入「元夫が自宅に入って来た」通報され逃走…駐車中の車内で発見 酒酔いの54歳の男「間違いない」
北海道放送 / 2024年7月28日 8時57分
-
4東京・荒川で住宅火災、2人死亡 高齢の男女と連絡取れず
共同通信 / 2024年7月28日 13時19分
-
5【速報】ANA機がエンジントラブルで「緊急事態宣言」伊丹空港へ引き返し プロペラ2つのうち片方止まった状態で着陸 けが人なし
MBSニュース / 2024年7月28日 14時5分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











