なぜ2000年前のギリシア哲学をいまだに学ぶ人がいるのか…京大名誉教授が考える「古典」の本当の価値
プレジデントオンライン / 2022年10月14日 14時15分
※本稿は、内山勝利『変貌するギリシア哲学』(岩波書店)の一部を再編集したものです。
■19世紀まで埋もれていたミロのヴィーナス像
ギリシア彫刻の美しさを思い浮かべてみよう。たとえばミロのヴィーナスでもいい。むろんあの女神像を古代ギリシア人も美しいと思ったに違いない。そして、現代のわれわれもそれに感嘆する。長い時間をへて今日によみがえったその美しさは、しばしば「永遠の美」と言われ、「不朽の美」と称賛される。
たしかに、それは時をへだてた多くの人びとに、同じように美の規範としての感動を与える。さしあたりその意味で、それを美における「古典」と言うこともできよう。しかし、もう少し考えてみたい。実際には、この彫像も19世紀に発掘されるまで長くうち捨てられ、埋もれてきたのである。
ギリシア人にとっては神の崇高さを具現していた女神像が、後の歴史の中では、むしろ神性に反する涜神(とくしん)的なイコンとして排斥されてきた。そして再発見された近代においてそこに見いだされたのは、古代ギリシア人の美意識にはおよそありえなかった「藝術美」の理想だった(この理念はようやくカントに始まる)。
■古代ギリシア人と現代人の「美しい」は同じか
その場合、同じ一つの彫像を美しいものとして見ているにせよ、古代ギリシア人とわれわれとは、ほんとうに「同じ」美しさを感じているのだろうか。それを「同じように」美しいと思っているのだろうか。むしろ、時代も場所も大きく異なった世界にあって、両者は全く異なった美的経験と美的基準でものを見ていると考えたほうがいいだろう。とすれば、明らかに、それぞれが感受している美は異なっている、とするべきである。
おそらく、「それにもかかわらず」ミロのヴィーナスは、ギリシア人にも、現代のわれわれにも美しい彫像と見えるのである。まったく違った美意識と感覚のそれぞれに対して現われる美は、やはり別の美だと言わなければなるまい。
しかし、言い換えれば、ミロのヴィーナスはそれだけ別様な見方に応じて、それぞれに美を顕現させうるだけの重層性をその内に蔵しているのである。そして、「古典」とは、むしろそのようなあり方において位置づけられるべきではないか。
■アリストテレスの「著作」は消失してしまった
文藝や哲学思想の「古典」についても、同じことが言えよう。古代ギリシアの著作であれば、たとえばホメロス(前8世紀頃)やプラトン(前427―347年)の「不朽の価値」を、われわれはたたえる。しかし、これらの作品もけっしてあらゆる時代を通じて愛好尊重され続けてきたわけではない。むしろ、きわめて危うい伝承事情の偶然にまかされて、辛うじて今日まで伝えられてきたのである。
実際、すぐれたギリシア古典のどれほど多くが歴史の淘汰(とうた)の過程で滅失したことか。事情を哲学分野に限ってみても、まず間違いなく書かれた著作のすべてが伝存しているプラトンのような場合は、きわめてまれな例外としなければならない。他には、新プラトン主義者のプロティノス(後205―270年頃)のケースがあるだけであろう。
アリストテレス(前384―322年)の哲学書として今日伝えられているものは、分量的にはプラトンを凌駕(りょうが)するほどだが、それらはすべて、実は彼の講義草稿のたぐいを纏(まと)めたもので(それだから文献的価値が低いというわけではないが)、比較的若いころに多数書かれて公刊された文字通りの「著作」は、古代ギリシア文化の衰退とともに消失した。

■辛うじて歴史を生き抜いてきた古典
また、他にもほとんど無数の哲学者たちがいたし、プラトンやアリストテレス以上に大量の著作を残した思想家も多い。古代原子論の大成者デモクリトス(前5世紀)やストア派のポセイドニオス(前135頃―前50年頃)には、それぞれ200巻以上にも上る著述があったが、やはりすべて滅失し、他の著作家たちが引用しているわずかな断片章句が伝えられているだけである。
さしあたり強調しておきたいのは、古典とは、少なくともギリシア・ローマの古典とは、確固たる規範として維持存続されてきたものではなく、むしろ激しい毀誉(きよ)褒貶(ほうへん)にさらされつつ、辛うじて歴史を生き抜き、いくつかの時代の岐路において新たに発見されながら、それぞれの時代状況に拮抗しうる力を示現してきたものだ、ということである。
それが古典と呼ばれる所以は、むしろその多面性、重層性にあり、いまなお汲み尽くされることのない、多様な深い意味の可能性を内に湛えたマトリックスでありつづけているところにこそあるだろう。
■古代ギリシアにおける哲学の本流とは
事情を、プラトンに即して、さらに見ておきたい。――われわれにとっては意外にも思われようが、おそらくプラトンは(そしてアリストテレスも同様だが)、古代ギリシアにおいては、ついに哲学の本流に位置することはなかった、と言ってもいいのではあるまいか。むしろ1100年間にわたるギリシア哲学の歴史は、基本的に、彼ら以前の初期哲学(いわゆるソクラテス以前の哲学)の展開に終始したと見ることができよう。
それは、大まかに言えば、宇宙世界がどのように形成され、現にどのようにあるかの洞察を第一義とし、それを踏まえることで人間の生の意味と運命を見通そうとする共通の図式を骨格とした哲学であった。比較的残された断片量の多いヘラクレイトスやエンペドクレスなどについては、その全体構想をよくうかがうことができる。
われわれの通念的な了解によれば、ギリシア哲学はソクラテスの決定的影響のもとに、プラトンおよびアリストテレスによって大成されたのであり、彼ら以降のヘレニズムの哲学は古典的完成からの拡散と矮小(わいしょう)化の過程と位置づけられる。
しかし、(すでに別の機会にも述べたことだが)実際にはむしろ二人の大哲学者を置き去りにするようにして、ヘレニズム時代はふたたび初期以来の「本来の」ギリシア哲学に立ち返っているのである。
■二人の大哲学者が受け入れられなかった理由
この時代を代表するストア派やエピクロス派は、個人中心の倫理学に焦点をしぼりながらも、一面においては、ソクラテス以前の哲学の宇宙論的体質をきわめて強く受け継いでいる。
言うまでもなく、ストア派の祖ゼノン(前334―262年)やエピクロス(前341―270年)は、イオニア哲学の風土の中に生い立った人たちであり、アテナイの新しい哲学動向の洗礼を受けたのちも、それぞれにヘラクレイトス思想やアトミズム(古代原子論)の旗幟(きし)を鮮明にかかげ、それらを哲学の基盤としたのである。それは個々の教説についての継承や転用の問題ではない。踏襲されているのは、思考の骨格とスタイルである。
プラトンやアリストテレスの没後、ギリシア世界でも、彼らの哲学が長く振るわなかったことはまぎれもない。おそらく、あまりにも新しすぎた知のパラダイムとして、それらはすぐには時代に受け入れられなかったのであろう。
■プラトンが地位を確保したのは後3世紀
アリストテレスは長期にわたって影をひそめるしかなかったし、プラトンについても、ようやく紀元前後から新たな著作の編纂(へんさん)がなされたのにつづいて、いくつかの「プラトン入門」的な著作(たとえばアルキノオス)が現われるが、それらのプラトン理解はきわめて浅い。本格的なプラトン哲学復興は、後3世紀のプロティノスに始まる新プラトン主義の活動をまたなければならなかった。
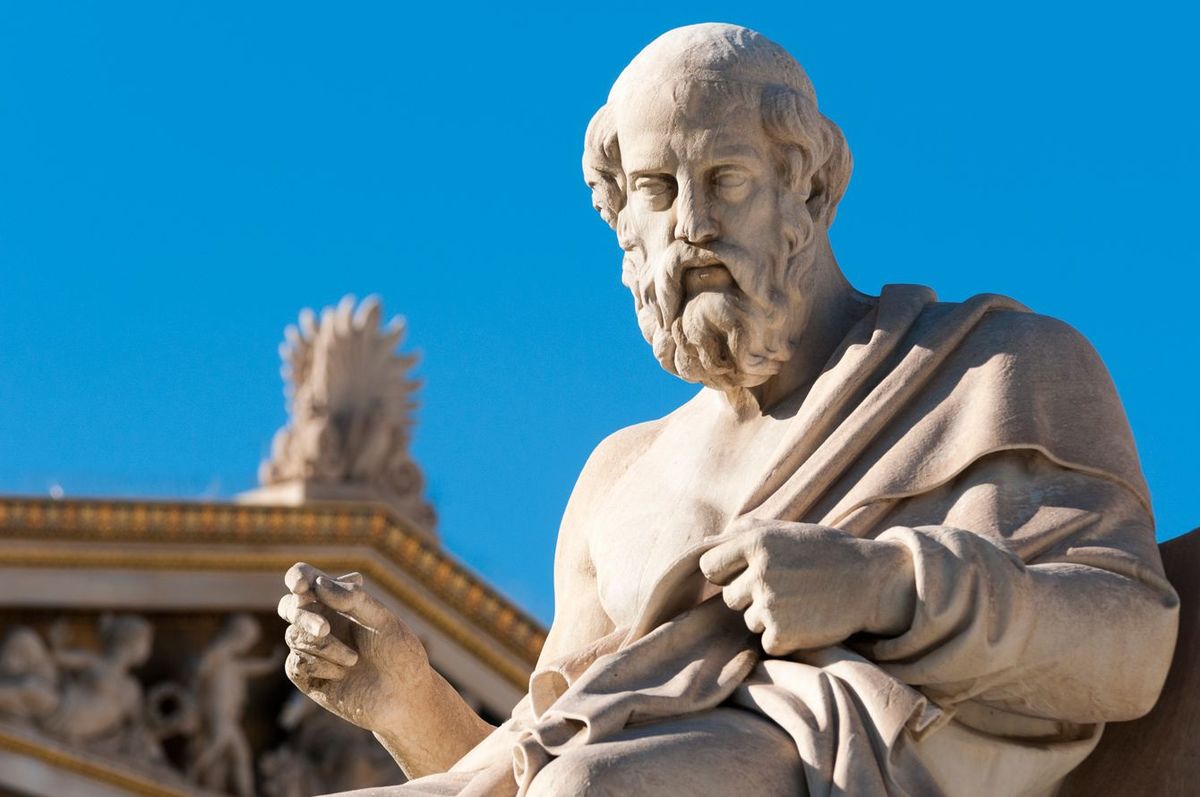
新プラトン主義的な理解によって、プラトンははじめて本格的な哲学「体系」としての地位を確保した。もっとも、それは、(ここでは深く立ち入ることはしないが)旧来の哲学観ないしヘレニズム的な立場からプラトンおよびアリストテレスの思想を一体的に同化吸収しようとした試みであった。
そうした意図をもった新プラトン主義は、その後も長くさまざまな仕方でプラトン解釈の基調となったが、必ずしもその思想的潜在力を十二分に剔出(てきしゅつ)するには至らなかった、と言わなければなるまい。
■プラトンの代表作『国家』の受容の歴史
古代思想の枠組を越え出ていたプラトニズムの本姿は、むしろ新プラトン主義を克服しようとした近現代の理解の中で、はじめて明らかになりつつあるのかもしれない。19世紀に始まった近現代的なプラトン理解と受容は、少なくとも、それ以前とはまったく様相を異にする新たなものである。
今日われわれは、言わば「同時代の哲学者」としてプラトンを読んでいる。そうした趨勢(すうせい)は、国民的「教養」理念の根幹にギリシア・ローマ古典を置いた近代西欧社会で醸成された。その広義のルネサンス(あるいは西欧の近代化の過程)の中で、とりわけプラトンは大きな役割を担った。
その一端を、J・アナスのコンパクトな叙述によりながら、19世紀イギリスにおけるプラトン『国家』受容の変遷を通して見ることにしよう。
彼女が指摘しているように、この名高い著作がプラトンの代表作とされ、そこに論じられた哲学と国家論が真剣に受け止められるようになったのは、ようやくそのころからのことである。それまでは、もっぱらファンタジックなユートピア論と見なされてきた、と言っていい。19世紀に至って本書の位置づけは劇的に変化したのである。
この時代におけるプラトン復興のきっかけとなったのは、1804年にトマス・テイラーの英語訳(けっしてすぐれたものではないが)が出たことである。もっとも、彼は旧来の新プラトン主義的ロマンティシズムの中でプラトンを理解しており、その影響も、直接的にはワーズワースのような詩人たちを始めとする文学的なものにとどまっていた。
■哲学の「専門領域」から国民的教養へ
しかしそれは、19世紀イギリスにおいて、プラトンを哲学の「専門領域」から解放し、より広範な国民的教養の書として迎えられる動向の始まりともなった。19世紀半ばのプラトン研究の最も熱心な担い手は、功利主義哲学を標榜するJ・S・ミルのサークルの人たちで、その一人が銀行家のG・グロートであった。
彼のプラトン理解は(むしろいい意味での)アマチュアリズムに立っていたが、主著の『プラトン』(1865年)は、すぐれて同時代的な視点でプラトンの生涯と著作を丹念に祖述したもので、今日もなお参照するに価する記述が少なくない。
本書においてプラトンの「対話性」を重要視し、議論による真理の探求者という新たな側面を強調したことは、その後のプラトン研究を先取りするものとなっている。また『国家』についても、重要な哲学的・政治学的著作として、正当な位置づけと評価が与えられている。
さらに、プラトンに国民的哲学書としての決定的な地位を確定したのは、理想主義の哲学者B・ジョウエットによるきわめて平明な英訳と的確な解説であった(1871年)。彼は、倫理学を基盤とした政治哲学と国家論に、プラトン哲学の基本線を見いだした。それに連動して、はじめて『国家』がプラトンの主著と見なされるようになり、そこに論じられているさまざまな議論から、ヴィクトリア朝の政治・社会状況に対する示唆が引き出された。
その影響は当時の英国社会に大きく広がった。「哲人王」の理想は、当時の社会的エリートに公正無私と献身の理念を明示し、貴族的階層社会から教育と能力評価による平等社会への移行に正当化の根拠を与えた。最もユートピア的な主張と思われた男女平等論までも、女性の教育機会と社会進出を促す機縁となったのだった。
■社会主義や独裁主義を支える理念に暗転
ついでに触れておけば、理想主義的『国家』像は、20世紀において一挙に暗転する。しかし、それもまた「生ける書」としての「古典」に負わされた宿命かもしれない。この「戦争と革命の時代」において、しばしばプラトンは政治の場に魔を呼び出す名と化した。
民族と国家が利害と理想をないまぜにしつつ世界的規模で争いを繰り返し、帝国主義支配や全体主義的動向が盛衰したこの間の様相は、そのままプラトンの時代のギリシア世界(特にスパルタ勢力とアテナイ勢力との対立抗争)に類同化され、東欧に実現した社会主義体制や西欧社会内部に現われた独裁主義国家を支える理念のうちに、プラトン哲学の反映を見ようとした人たちは少なくなかった。
古典に精通した政治学者E・バーカーの評言を借りれば、わずか20~30年の間に、プラトンは「いったんは左翼的革命家、社会主義の予言者とされたかと思うと、次には右翼的改革者、ファシズムの先駆者と見なされた」のだった。
■人々を誤解の中に迷い込ませる危険な思想家
たとえば、K・R・ポッパーの『開かれた社会とその敵たち』は、日本でも広く読まれたプラトン批判書であるが、そこには「哲人王」が直接的にレーニンやヒトラーに重ね合わされている。
むろん、彼らのプラトン「解釈」に疑義を呈することは容易い。と言う以上に、あまりにも粗雑で明白な誤りを逐一ただすことに無益な労を要するのみで、プラトンの議論とかみ合わせて批判することなど、ほとんど不可能なありさまだと言わなければなるまい。
とはいえ、たとえばポッパーを読み直してみて驚かされるのは、いかに誤謬(ごびゅう)と歪曲に満ちあふれた仕方ではあれ、プラトンの思想が現代においてもなおあれほどに激しい言葉で語ることを促すだけの、リアルな触発力を持ちえているということである。ある意味で、(たとえば)ポッパーはあやまつことなくそれを感知していたのであり、きわめて鋭敏にプラトンに反応していたとも言えよう。
『国家』に展開されているようなラディカルな挑発を、誤読に陥ることなく的確に受け止め、無数の逆説とアイロニーを通じて語られた真意を剔出していくことは、容易ではあるまい。それに共鳴するにせよ否定の立場をとるにせよ、誤解の中に迷い込むおそれに変わりはないのである。その意味では、たしかにプラトンは危険な思想家である。
■古典を読むことは、「いま」を読むこと
ここでこれ以上プラトン論には立ち入らないでおこう。当面強調しておきたかったのは、古典とはそれぞれの時代と場所において、まったく異なった相貌を現わし、まったく異なった作品として各時代の状況を大きく揺り動かす力を示してきたものである、ということだった。
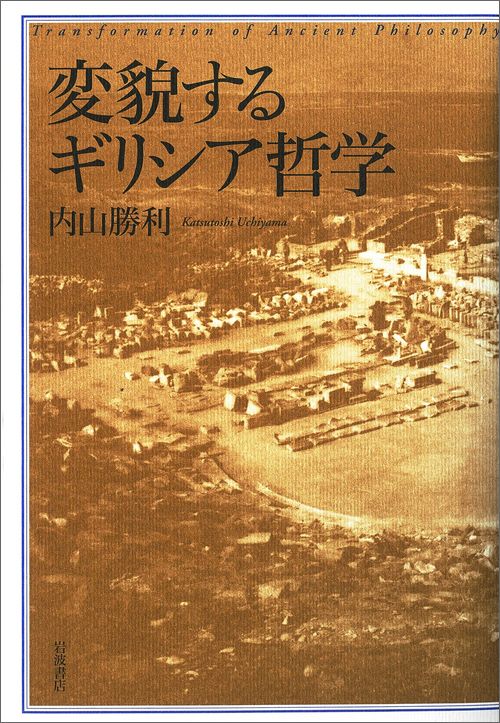
繰り返しておくならば、むしろそうした時代ごとの多様な読みに応答する多面的な解釈の可能性を内にはらみつつ、新たな思想の創出を促す無限の触発性と挑発力においてこそ、それはその地位をたえず更新しつづけていくのである。
やや一面的に強調して言えば、「いま」を生きるわれわれが、われわれ自身の発する問いを最も効果的に深化させる場として古典に対峙(たいじ)していくこと、そうして古典の形骸化を排除し、「いま」の内に賦活(ふかつ)せしめる営みを持続することが、真の古典理解を切り開く道であろう。
たえず古典を挑発し、古典から新たな挑発力を喚起することに努めなければならない。古典を読むことは、すなわち「いま」を読むことである。
----------
京都大学名誉教授
1942年生まれ。1967年京都大学文学部哲学専修卒、1975年同大学院博士課程中退。関西大学を経て1988年京都大学文学部助教授、教授、2005年定年、京都大学名誉教授。日本西洋古典学会委員長(2004.6~10.6)。専門は、古代ギリシア哲学とりわけプラトン哲学、ソクラテス以前の哲学。著書に『哲学の初源へ ギリシア思想論集』(世界思想社)、『対話という思想 プラトンの方法叙説』『ここにも神々はいます』『プラトン「国家」 逆説のユートピア』『変貌するギリシア哲学』(岩波書店)などがある。
----------
(京都大学名誉教授 内山 勝利)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
ヘーゲル哲学の現代的意義を問いながら、その核心に迫る入門書『国家はなぜ存在するのか ヘーゲル「法哲学」入門』が発売
PR TIMES / 2024年7月26日 13時40分
-
40年は1つの秩序に綻びが生じるに十分な長さ...高坂正堯「粗野な正義観と力の時代」より
ニューズウィーク日本版 / 2024年7月10日 11時5分
-
ソクラテスに人生相談できる? 名古屋大が生成AI対話システム
共同通信 / 2024年7月6日 17時11分
-
佐藤優氏と伊藤賀一氏による西洋哲学の本格ガイドブック!世界のエリートと競うのに必要かつ十分な知識が詰まった『いっきに学び直す 教養としての西洋哲学・思想』発売
PR TIMES / 2024年7月2日 16時40分
-
【教養としての哲学】他者の心をどう知るか、哲学的な視点からはこう考える
マイナビニュース / 2024年6月29日 10時30分
ランキング
-
1「うちの病院、ヤバすぎる」美容クリニック従業員がSNSで暴露…なぜ「内部告発」を止めることはできなかったのか?
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月27日 7時15分
-
2街にあふれる「アルファード」 なぜ「先代」も“高い”? すでに“型落ち”でも「現行型」に迫る「高リセール」維持する理由とは
くるまのニュース / 2024年7月26日 10時10分
-
3致命傷になる部位ってどこ? バイク事故で守るべきポイントとは
バイクのニュース / 2024年7月27日 10時10分
-
4日本のにんにくは中国産が9割。「国産にんにく」と「中国産にんにく」の違いとは? 3つの産地で比較
オールアバウト / 2024年7月26日 21時5分
-
5老眼も眼精疲労もこれで防衛できる…眼科医直伝どんなに忙しい人でも毎日続けられる"両目の自己回復習慣"
プレジデントオンライン / 2024年7月27日 10時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











