資源の乏しい国だからこそ発展した…日本の中小企業の「ものづくり」が異常にレベルが高い本当の理由
プレジデントオンライン / 2022年10月20日 11時15分
※本稿は、中沢孝夫『働くことの意味』(夕日書房)の一部を再編集したものです。
■日本の中小企業を巡ってわかったこと
「仕事」というものは、たえず具体的である。また働き方というのは、大きく分ければ精神的なものと肉体的なものとに分けることができるとは思うが、基本的には、それぞれが重なっている。
ただ、仕事は必ず「何か」目的(対象)を持っている。そこで、迂遠なようだが、現実の仕事の進み方を点検したい。
職場で働くと個人だけではなく、会社そのものも、社会環境とネットワークができる。必然的にさまざまなネットワークができると言ってもよい。筆者の場合は、「東洋経済」をはじめとして、新聞や雑誌に寄稿しているうちに、あちこちから声をかけられて広がりを持ち始めた。何冊目かの著書として『中小企業新時代』(岩波新書)を発刊するきっかけとなったモチーフは、やはり現場調査の経験から得られたものだった。
■取引の立ち位置と上下関係は必ずしもイコールではない
まず製造業を中心にたくさんの業種を訪ね歩いた。金型、板金プレス、熱処理、鋳造、鍛造、メッキ加工、塗装など、基盤技術といわれる領域だけではなく、さまざまな部品加工工場で仕事の聞き取りをしながら、モノがつくられ消費されるまでには、いくつもの流れ(節目)があるということを知った。もちろん深く考えなくとも当然のことだった。自分の職場には、前の仕事と後の仕事がある、という連続性が存在し、その中に自分がいる、ということであった。
またティア1(一次協力メーカー)、ティア2(二次協力メーカー)といったネットワークの位置づけはあるが、それは必ずしも取引の上下関係を意味しなかった。彼らは自分(たち)の持っている技能や技術に依拠しており、それがなければ価格競争だけが残ることになってしまう。
■よくある「中小企業はかわいそうだ」という評価は誤り
単に経営者の積極性というだけでなく、1990年から92、93年といった時期を見ると、ASEAN諸国が積極的に海外からの直接投資を呼び込むことに熱心になる時期だった。
自国で企業を自立してつくるよりも、資本も技術も先進国から「輸入」したほうが早いということに政策の舵を切った時代だった。シンガポールやマレーシア、そしてタイなどの工業団地の建設に伴う見学会に、中小企業が参加し、わけても経営者だけではなく中心的な従業員も参加し、工業団地にすでに進出し始めた工場や、進出を検討している工場と積極的に交流し、どのようなネットワークの中で仕事が可能なのかを考慮していた。国内の自社工場が持っている陣容、海外派遣の能力、行った先での仕事の可能性といったことは当然にして検討していた。
しかし最後の決断はいわゆる「見る前に飛べ」ということだった。いくら調べてもわからないところは残る。結局のところ、可能性は自分で切り拓くものである。
企業として、どのような仕事だったら現地で始められるか。どのような質の従業員を集めることができるか。技術・技能の移転は可能か。関連する業種は存在するか等々。こうしたことにこそ「起業家精神」の基本がある。
問題なのは、それに対する他者の評価基準である。当時、既成概念としてよく言われた「中小企業はかわいそうだ」という評価は、まったくの間違いであると筆者は思ったものだ。たしかに下請け仕事でカツカツの企業もあったが、多くの企業が生き生きとしているのが実体であって、従業員数と資本金の大きさという「規模」は、企業の実質的な「経営の健全さ」とは関係がないというのが簡単な事実であった。
■理不尽な要求には正々堂々啖呵を切る
大田区や墨田区の企業歩きによってわかったことは、しっかりとした経営者の気骨やビジネスプランがあり、後継者も育っていて、中・長期の経営計画を持っている、そういう人々の多くは「かわいそうな人々」の群れではなかったということだ。当時の「中小企業白書」などもずいぶんと読んでみたが、いわゆる中小企業研究者の多くは、中小企業学会などに所属し、30年前、40年前に教えられた通りの固定観念で中小企業を見ていたということである。
当時のマルクス経済学(学者)による中小企業理解は、「調査」によって「かわいそうな企業」を探し回ることだったのである。つまり調査と称して、自分たちの定説に当てはまる中小企業を「発見」することに徹していた。
たしかに大田区や墨田区、あるいは東大阪などにある中小企業の中には、大企業である完成品メーカーの下請け(サプライヤー)として成り立っている、立場が弱そうな工場はいくつもあった。
しかしたとえば、大田区の50人ほどの金型屋の場合(相当大きい工場)、発注元の大企業から、いわれのないコストダウン要求の連続に対して「もうオタクの仕事はしない。マレーシアやタイではもっと安く仕事をするというならそちらでやればよい。その代わりこちらは大田区すべての工場でオタクの仕事は拒否すると仲間全体に触れ回る」と、いわば啖呵を切って引き上げる企業もあった。
もっともこの発注を拒否された完成品の企業は、すぐに謝りにきて、「担当者がとんでもない間違いをして申し訳ない」と、前言を撤回したとのことだった。
■松下電器であっても怒鳴り込む
あるいは大阪で、パトカーのライトなどをつくっていた企業が、松下電器(現・パナソニック)の契約(調達)担当者から直接連絡がきて、別の熱処理メーカーを利用するように依頼(強要)され、仕方なく引き受けたところ、現場から「こんな焼きが甘い処理の部品を使ったら、モーターが壊れる」と報告があり、案の定、新しい製品は次々と故障した。ところが松下電器の担当者は、「オタクがつくった部品が壊れたのだから、修理費や補償は全部オタクが持て」と言ってきた。
経営者は松下電器に怒鳴り込んだ。「使えない熱処理業者を無理に押し込んできたのに、修理費をこちらで持てとは何事か。松下の下請け取引の不当性をマスコミに訴えるだけではなく、法的な措置をとる」と突き放した。

本来、松下電器はそのようなことをする会社ではなかったので、工場の調達部門の責任者は生じた事態に驚き、担当者を呼び事情を聞いたところ、口利きの事実を認めた。結果、その担当者は他部門への配置転換となり、補修費その他はすべて松下が負担するという決着となった。このように完成品メーカーの調達係というのは、しばしば下請けを絞ることがあった。
しかし、きちっとした技術と技能がある会社は、他のネットワークをつくり、「乾いたタオルをまだ絞る」ような会社とは手を切ることができたのである。
また前述のように、1990年頃から積極的な中小企業は、バブル景気の真っ盛りであり、若者はもとより、中高年の採用も不可能な状態となっていた。結果、採用と仕事を求めて海外へと進出し始めていた。そのような企業は「かわいそうな」存在とはかけ離れたものだった。
加えて、工場の海外進出に関して、日本国内の空洞化という表現が飛び交ったが、それもまた事実に反したものだった。海外進出に積極的な企業は、国内でもまた積極的な企業活動をしていた。拠点あるいは根拠地(いわゆるマザー工場)としての国内の足場がしっかりしていない企業は、海外に展開するだけの力を持たないからである。ネットワークを形成できる企業は「軸」をしっかりと持っていなければならない。それは国内での企業活動でも同様である。
■「理想」は現場にとって「無意味」である
理想を持つことは、たしかに精神的にも大切なことだが、しかし同時に「理論」や「理想」というものは、現実とは無関係なことが多いものだ。後述するが、それを語る者は「あるべき姿」という「理想」を語る。いわゆるコンサルタントなどは典型的だが、「理想の絵を描く」ことは、現場に対して無理(無意味)なことを語ることになる。
青木昌彦氏は『国際・学際研究 システムとしての日本企業』(ロナルド・ドーア氏との2人による編集。NTT出版、1995年12月)の「日本語版への序I」で次のように述べている。
たしかに、いかなる経済システムも、人口、技術、嗜好、資源などの環境パラメーター値が変化したり、また国際・国内における政治プロセスにおける力関係が変化すれば、それに応じて制度変化を遂げていくであろうし、そうでなければ、やがて生命力を失うであろう。
また、それぞれの経済システムは他のシステムから学習することによって、システムの自己革新を遂げていくことも出来るであろう。しかし、過去の歴史をさかのぼるまでもなく、最近の旧共産主義計画経済の市場経済への転移の過程を見てもわかるように、経済システムの変化は、その歴史的な進化過程を反映した「歴史経路依存的(Path Dependence)」という性格を色濃く持たざるをえないのである。
■ほとんどの国民が留学の成果を日本に持ち帰った
とくに問題なのは、この歴史経路依存的ということである。たとえば、明治初期から形成された日本の教育制度は、最も重要な経営資源としての人材育成の「核」になってきたが、こうした制度も日本固有の地政学的な立地条件により、大きく「制約」(プラスもマイナスも)されている。
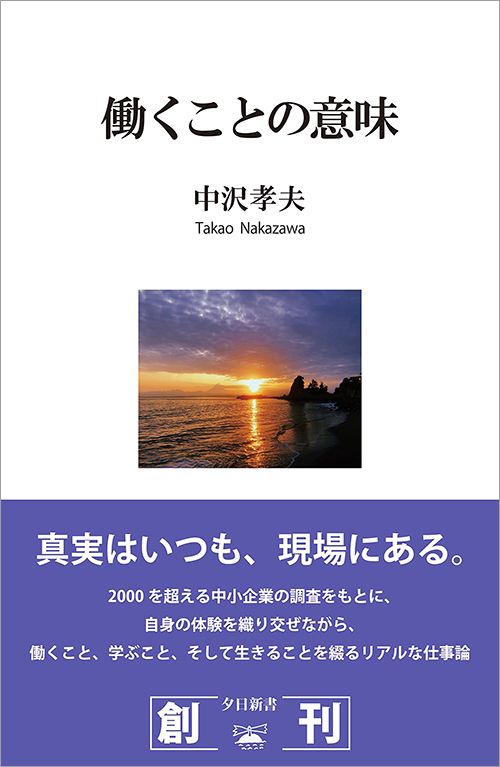
明治維新は、薩摩や長州だけではなく、全国から有能な人材を登用して国づくりを行い、法律の整備や工業技術だけではなく、鉄道や郵便など社会的なインフラの仕組みを学び、アメリカからの「独立の大切さ」の学びを含めてわずか数十年の時間幅で、先進国にキャッチアップした。それは「これほどのスピードで進められた近代国家樹立(ネーション・ビルディング)は、ほかに類を見ない」(北岡伸一『明治維新の意味』新潮選書、2020年9月)ものだった。
しかも日本は、明治時代はもとより、第二次世界大戦後になっても他の国と異なり、ほとんどの国民は、留学の結果、その成果を持ち帰った。多くの途上国では、優秀な人間はアメリカやイギリスなどにそのまま残り、「人材の流失」という結果となった。
■資源の豊富な中東諸国は二次産業が発展しない
こうした歴史経路は、それぞれの国や地域が異なっているように、モノ(物)をつくったりすることにも大いに役に立った。もちろん、日本が際立って優れているとは言えない。ただ、海に囲まれたことによって、輸出入に立地的に恵まれ、鉱物資源が少ないこともまた必ずしも悪いことではなかった。
「資源の呪い」とまでは言わないが、石油が豊かな国や内陸にあって、さまざまな希少資源に恵まれた国が、民主的なよい国に発展しないのは、地政学的なことに制約されている部分が大きい。彼らはとくに第二次産業の意味が理解できない。中東の産油国で、二次産業の発展している国がほとんどないのはそのためである。

なお、上記の青木昌彦氏の本に寄稿している浅沼萬里氏は、次のように述べている。
第一に、今日の製造業は、単一の標準的な製品の大量生産から多様化された製品のフレキシブル生産へという根本的な推移を経つつある。第二に、フレキシブル生産にかかわる製品戦略、生産戦略、およびマーケティング戦略の間には広範な補完性が存在するため、生産がフレキシビリティの度合いを進めるに従って、伝統的には互いに分離した職能を形成していた製品設計、工程設計、製造、およびマーケティングの間に、より大きなコーディネーションが必要となる。
第三に、フレキシブルで汎用性をもつ設備が使用される程度が大きくなるにつれて、垂直的統合の必要性は減じる。(なお浅沼氏のこの議論は、別途『日本の企業組織 革新的適応のメカニズム』東洋経済新報社、1997年6月、として結実している。)
ここで大切なのは、多様化された生産のフレキシビリティであった。これまでに筆者が歩いた工場は2000社を数えるが、同業者であっても、少しずつ「異なった」技術を持っていた。特定の企業との関係が深くても、オリジナルな独立した部分が絶えずあったのだ。
----------
福井県立大学名誉教授
1944年、群馬県生まれ。博士(経営学)。専門は、ものづくり論、中小企業論、人材育成論。高校卒業後、郵便局勤務から全逓本部を経て、45歳で立教大学法学部入学、1993年卒業。海外を含む2000社以上の企業からの聞き取りをし、ミクロな領域で研究活動を行ってきた。著書に『中小企業新時代』(岩波新書)、『グローバル化と中小企業』(筑摩選書)、『就活のまえに』(ちくまプリマー新書)、『転職のまえに』(ちくま新書)、『グローバル化と日本のものづくり』(藤本隆宏氏との共著、放送大学教育振興会)などがある。
----------
(福井県立大学名誉教授 中沢 孝夫)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「あと2時間コートに立っていろ」日本の窮地を救った言葉…ミュンヘン五輪男子バレー金メダルの奇跡<1>
スポーツ報知 / 2024年7月26日 12時0分
-
エンジニア人気低迷の元凶「多重下請け構造」問題 安月給で早朝から深夜まで働き、家に帰れない
東洋経済オンライン / 2024年7月23日 18時0分
-
晩年の松下幸之助、本田宗一郎との出会いで、稲盛和夫氏が確信した経営者のあるべき姿
PHPオンライン衆知 / 2024年7月22日 11時50分
-
いま岐阜がアツい!「打倒、鍛治舎」監督率いる県岐阜商が県全体の野球レベルの底上げに【甲子園「マル得」情報】
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月19日 9時26分
-
池上彰が警告「時代に乗り遅れた」日本企業の末路 2040年世界時価総額トップ50に日本は入れるか
東洋経済オンライン / 2024年7月2日 16時0分
ランキング
-
1ペットボトル収集車から遺体で見つかった男性 買い取り業者の47歳社員と判明 積み込み作業中に誤って巻き込まれたか
CBCテレビ / 2024年7月26日 20時14分
-
2小5が校外行事で意識不明 頭蓋骨骨折、2段ベッドから転落か
毎日新聞 / 2024年7月26日 21時57分
-
3大雨警戒続く山形 20代巡査長の死亡確認 高速道路陥没も
毎日新聞 / 2024年7月26日 20時32分
-
4西山ファーム元代表に有罪判決=「首謀者として主導」認定―名古屋地裁
時事通信 / 2024年7月26日 18時4分
-
5秋田県内、週末に再び大雨ピークか 1人行方不明、12カ所で氾濫
毎日新聞 / 2024年7月26日 17時23分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











