「2度の妊娠出産でアイデンティティー崩壊」一度は男として生きるのを諦めた“30代”を襲った発狂寸前の苦悩【2022編集部セレクション】
プレジデントオンライン / 2022年11月21日 13時15分
関東在住の向坂壱さん(仮名・50代)はトランスジェンダー男性(Female to Male)だ。体は女、心は男であることに子供時代から深く悩んだが、専門学校卒業後しばらくして男性と結婚。2人の子供を出産するが、性別違和のストレスによりアイデンティティが崩壊し、「離人症」を発症。その後、性同一性障害を専門に扱う精神科を受診し、「性同一性障害」と診断されたことをきっかけに「一度きりの人生、悔いなく生きたい」と思い直し、性別移行を決意した――。
■アイデンティティーの崩壊
22歳の時にパニック症を発症し、その後、離人症も発症した向坂壱さん(仮名・50代)。ひとり暮らしから関西の実家に戻って過ごすうち、徐々に落ち着きを取り戻した向坂さんは、考えた。
「学生時代からアルバイトが長続きせず、就職してからも転職を繰り返してきた自分は、働くことに向いていないのではないか」
「パニック症や離人症もあり、誰かに養ってもらうことを視野に入れて人生設計するのが最善なのではないか」
結局、以前から交際していた漫画家の男性からのプロポーズを受け入れ、1997年、向坂さん27歳、男性32歳で結婚。夫は向坂さんと結婚する数年前から、漫画の仕事が完全になくなり、ほぼニートのような生活をしていた。結婚後は彼の実家が会社を経営していたため、夫婦そろって親の会社に入り、向坂さんは事務員として働き始める。
ところが29歳で長男を、33歳で長女を出産すると、それまで経験したことのないほどのひどい離人症の発作が起き、四六時中“自分がわからない”という狂いそうな状況に陥る。育児はもちろん、家事もままならないため、食事は夫に弁当や総菜を買ってきてもらった。
「今思えば、2度の妊娠・出産という自分の性自認に対して矛盾した行為により、私のアイデンティティーが崩壊し、いよいよ限界を超えて耐えきれなくなったのかもしれません」
自分のことを考え始めると混乱し、発狂しそうになるのを防ぐため、起きている間はとにかくパソコンに張り付いて、ひたすら何かを打ち込んだ。4歳になっていた長男は、昼間は幼稚園に行っていたのでよかったが、0歳の長女には子供向けのテレビ番組を見せておいたり、一人遊びをさせておいたりすることがほとんどだった。
「娘に対する申し訳なさや、自分に対する不甲斐なさで、自責の念に苛まれたことを今でも覚えています」
自死まで考えたほどの苦しい状況の中、向坂さんを支えたもの。それは「子供の成長を是が非でもこの目で見届けたい」という強い思いだった。
■パニック症の治療と離婚
離人症の発作がパニック症からきているものだと考えた向坂さんは、「離人症を治すためにはまず、パニック症を治療しなくては」と考え、東京大学医学部附属病院が認知行動療法の治験者募集(当時)をしていることを知り、応募。無事採用され、約半年間の治療を終える頃には、パニック症も離人症も快方に向かっていた。
離人症が軽快し、アイデンティティー(自我同一性)を取り戻すにつれ、向坂さんは再び性別違和を強く感じるようになってきていた。あるとき向坂さんは、自分が本当に男性としての性自認があるのかどうかを試してみたくなり、男性としてインターネット上の趣味のコミュニティーに参加。すると向坂さんは、男性として振る舞っていることがあまりにもしっくりきて、本来の自分の感覚と一致しすぎたため、「このままでは女性としての日常に戻れなくなる」と危機感を募らせる。
2004年10月。悩んだ向坂さんは、性同一性障害を専門に扱う精神科を受診。初診で医師は、「おそらく性同一性障害と言って差し支えないでしょう」と告げ、同時に、「これまでのパニック症や離人症は、性別違和のストレスが関与していたのではないか」と言われた。
これを聞いて、一度は男性として生きることを諦めた向坂さんだったが、「一度きりの人生、悔いなく生きたい」と思い直し、性別移行を決意。
まず夫に、性同一性障害と診断されたことを告げた。だが、全く取りあわない。向坂さんが離婚を切り出すと、「自分が精神的ゲイになってもいい」「仮面夫婦でいい」と言って頑なに受け入れない。「そんな(仮面的な)両親の元で育つのは、子供にとってよくない」と説得するも、夫の耳には届かなかった。
夫は生まれてから一度も実家を出たことがない。会社経営をする親の元で、経済的に恵まれた生活をしてきたため、もともと労働意欲が感じられない人だったが、向坂さんがカミングアウトをしてからは、日に日に酒量が増えていき、仕事も休みがちになり、徐々にアルコール依存症のようになっていった。

「私は性自認に関係なく、人を見る目がなかったようです。正直なところ、私のパニック症が重症化したのは、彼の分離不安が原因だとずっと思っています。にもかかわらず彼は、私が長年パニック症や離人症で苦しんでいる姿を見ても、『自分は医者じゃないからよくわからない。そんなにつらいなら病院に行けば?』と素っ気なく言うだけでした。性別違和があってもなくても、遅かれ早かれ彼とは離婚していたということは確実に言えるでしょう」
やがて夫の弟からも、「うちの両親に、あまり精神的な負担をかけるようなことをしないでやってくれ」と言われ、義両親の世間体も考えた向坂さんは、調停離婚に踏み切る。
2006年12月、一向に離婚に応じない夫の納得を得るために、子供たちの親権は夫が持つことで離婚。向坂さんは37歳になっていた。
■母親への報告と性別移行
電話で母親に性同一性障害と診断されたことを告げると、62歳になっていた母親は、次の通院日に向坂さんに付いてきて、主治医に抗議するため診察室のドアをこじ開けようとし、制止した向坂さんと待合室でもみ合いに。いったんは断念したかに見えた母親は、今度は受付に行き、「何を根拠にここの医者は、うちの娘に性同一性障害だなんて無責任な診断をするんだ!」と怒鳴り散らした。
以降、向坂さんと母親の間で性同一性障害の話題はタブーに。父親からは一度、向坂さんの離婚後に電話があり、「独り身になったのなら、実家に帰ってきて経済的に支えてくれないか?」と打診されたが、男性ホルモンの投与を開始し、声も見た目も男性化していた向坂さんは、すでに母親から実家の敷居をまたぐことを暗に禁じられた状態であり、帰ることはできなかった。
あとで母親から、父親が電話を切ったあと、「あれは本当にうちの娘か?」と訝しがっていたことを聞いた向坂さんは、糖尿病を患い、その頃心臓の手術をしたばかりの父親の心や体の負担を考え、自分が性同一性障害だったということは一生伝えないことに決めた。そのため父親は、診断を受けてから20年近く経ち、80代になった今も、向坂さんが性同一性障害であることを知らない。
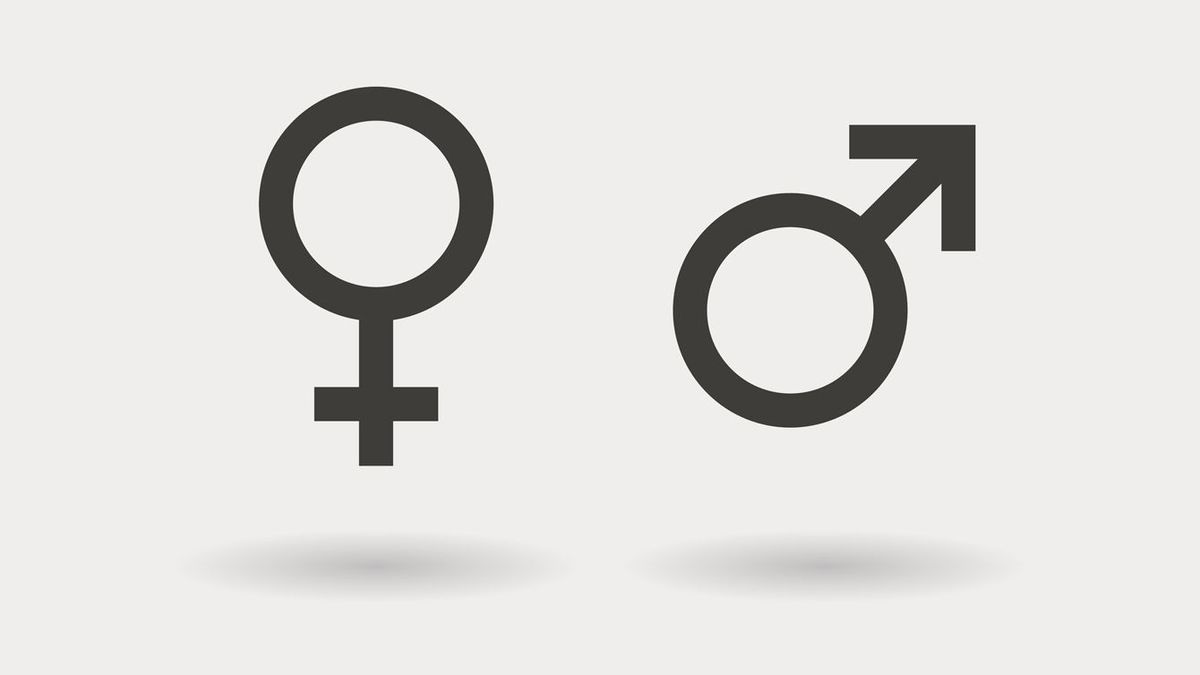
一方、子供たちとは離婚後1〜2年は週に2〜3回、その後は年2〜3回会って、お互いの近況を報告し合っていた。
2022年5月。向坂さんは長女が成人するのを待って、戸籍の性別を女性から男性に変更。変更に時間がかかったのは、性同一性障害の特例法に、「現に未成年の子がいないこと」という要件があったためだ。
向坂さんは現在、長男、長女と共に暮らしている。離婚の際、親権は元夫が持ったが、長女は中学2年の時、自ら「一緒に暮らしたい」と連絡してきた。そのとき向坂さんが、性同一性障害であることや、いわゆる世間一般の“お母さん”とは違うことなどを伝えた。
だがその後、元夫と親権を交代する際、家庭裁判所の調査官に長女は、「私が物心ついたときから母は性同一性障害だったので、一緒に暮らし始めても気にしたこともなく、わざわざ考えたこともない」と話したと聞いた。
都内でIT系の企業に就職が決まった長男も、2018年から同居するようになっていた。
「娘からすれば、自分の親が性同一性障害であることは、言葉で説明されるまでもなく、普段の生活から十分理解していたのだと思います」
かつて息子にも、「お母さんは、男かもしれないんだ」と話したことがある。するとまだ小学校1年だった息子は、「違うよ、お母さんは女だよ、だってちんちんないじゃん」と反論。そこで向坂さんは、「性同一性障害という病気で、男になってしまうかもしれないんだ」と、言い方を変えてみる。さすがに息子は驚いて、「病気? お母さん死んじゃうの?」と悲しそうな顔。慌てて、「その病気は死なないんだよ」と言うと、「そうなの? だったら別にいいや」と息子は安心した。
「息子にとっては親の性別よりも、生死のほうが重要なんだと改めて知り、何だか拍子抜けしましたが、それが本質だと思いました」
■性同一性障害は性別違和へ
一般的にはまだあまり知られていないが、これまで「性同一性障害」と呼ばれていた病名は、2013年に「性別違和」に変更されている。かつて、「性同一性障害」と診断された人たちは、「生まれた性とは反対の性になりたいと持続的に強く望む人」と説明されてきた。だが現在は、通常出生時に婦人科医や助産師などにより指定された性別と、その人により体験または表出される性別との間の不一致に伴う苦痛があり、必ずしも反対の性でなく、「他の何らかの性になりたい」という持続的な強い欲求があれば、「性別違和」があるとみなされるようになった。
近年耳にするようになった「LGBT」という言葉だが、最近は「LGBTQ」という場合も増えている。
これは、Lesbian(レズビアン、女性同性愛者)、Gay(ゲイ、男性同性愛者)、Bisexual(バイセクシュアル、両性愛者)、Transgender(トランスジェンダー、性自認が出生時に割り当てられた性別とは異なる人)、そしてQueer・Questioning(クイア「不思議な」「奇妙な」・クエスチョニング、性自認が不明確、枠に定まらない人)の頭文字をとった言葉で、性的マイノリティー(性的少数者)を表す総称のひとつとしても使われる。

日本のLGBTQの割合は、調査機関や方法によってデータにバラつきがあるが、2019年にLGBT総合研究所が行った調査では、約10.0%だった。
最近「LGBT」という言葉自体はようやく市民権を得てきたが、アルファベットが何を表しているのか理解している人は少なく、セックスとジェンダーの使い分けさえできていない人は多い。向坂さんの両親のように、わが子が性同一性障害であることを受け入れられない人は珍しくない。
■性的マイノリティーとタブー
筆者は、家庭にタブーが生まれるとき、「恥」「短絡的思考」「断絶・遮断」があると考えている。
向坂さんの両親、特に母親は、精神的に幼く、子供の頃から向坂さんや向坂さんの妹に、「お父さんは教養がない」「不潔」「ギャンブル好きで金銭に無頓着」「離婚したい」などと愚痴をこぼしたり自分の悩みを相談したり、精神的に寄りかかってくることが頻繁にあった。
そのため向坂さんは、母親の影響で、子供の頃から父親に対して「恥」を、母親に対しては「恥」ではなく「呆れ」を強く感じていたという。母親は、自分が思い描いた娘像や夫像、家庭像があり、それを大きく逸脱することが許せない人だったのではないだろうか。
だから、娘の性同一性障害を受け入れられない。向坂さんは、子供の頃から性別違和を感じていたにもかかわらず、子供にとって一番身近で頼れる存在であるはずの母親に相談できないまま大人になり、パニック症や離人症を発症してしまった。
いわば、両親が性的マイノリティーに対して「恥」「短絡的思考」を持ち、世間や向坂さんに対して「断絶・遮断」している状態だったのだ。
そして向坂さんは、自分の心を守るために、高校入学と同時に性別について考えることを強制的に中止する。それまで十分すぎるほど悩みに悩んできた向坂さんにとって、「短絡的思考」はなかったかもしれないが、考えることを強制的に中止する行為は、「断絶・遮断」だったに違いない。そのため、「女性として生きよう」と決意した向坂さんは、結婚という悪手を選んでしまった。
一方、元夫には、「短絡的思考」や「断絶・遮断」が顕著だ。フィクションや想像力をなりわいにするSF漫画家だったにもかかわらず、現実の一番身近で性別違和に悩み苦しむパートナーを理解しようとせず、ただ自分のためだけに向坂さんをつなぎ留めようとした。
もしかしたら向坂さんは、依存気質の母親の元で育ったせいで、依存気質の人を引き寄せてしまったのかもしれない。

紆余(うよ)曲折の末、性別移行が完了した今、「性同一障害を言い訳にすることなく、『ひとりの男性として人生を全うすること』を目標に生きていく」と向坂さんは語る。
思いのほか遠回りをしてしまったかもしれないが、人生に無駄なことはひとつもない。2022年6月現在、23歳の長男と20歳の長女との関係は良好。性同一性障害について話すことがタブーとなっていた母親とも、2019年に関東で十数年ぶりに再会を果たした。今まで渇望してやまなかった男性としての人生を、これから存分に享受してほしい。
----------
ライター・グラフィックデザイナー
愛知県出身。印刷会社や広告代理店でグラフィックデザイナー、アートディレクターなどを務め、2015年に独立。グルメ・イベント記事や、葬儀・お墓・介護など終活に関する連載の執筆のほか、パンフレットやガイドブックなどの企画編集、グラフィックデザイン、イラスト制作などを行う。主な執筆媒体は、東洋経済オンライン「子育てと介護 ダブルケアの現実」、毎日新聞出版『サンデー毎日「完璧な終活」』、産経新聞出版『終活読本ソナエ』、日経BP 日経ARIA「今から始める『親』のこと」、朝日新聞出版『AERA.』、鎌倉新書『月刊「仏事」』、高齢者住宅新聞社『エルダリープレス』、インプレス「シニアガイド」など。
----------
(ライター・グラフィックデザイナー 旦木 瑞穂)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「洗面器で大量の即席メンを食べた」「自分の局部を撮影」…欲求に歯止めがきかない老父に50代娘が感謝したワケ
プレジデントオンライン / 2024年7月13日 10時16分
-
「父も母も鬱病」担任教員に容姿や成績の悪さを揶揄され不登校の小3女子…40年後に"ワンオペ両親介護"の不遇
プレジデントオンライン / 2024年7月13日 10時15分
-
「自分は何者」そこまで考える必要ない?虐待、いじめ、リスカ傷痕も大切な一部 「死んではダメ」手差し伸べた恩人のため「もう一度働きたい」
47NEWS / 2024年7月9日 10時0分
-
書店には放火予告まであった…一度は発売中止になった"トランスジェンダー本"がアマゾン1位のワケ
プレジデントオンライン / 2024年7月9日 9時15分
-
独身は職場で半人前扱い…「指輪」のために恋愛・セックス無しの"友情結婚"をしたアセクシャル女性の8年後
プレジデントオンライン / 2024年6月30日 16時15分
ランキング
-
1エアコンから嫌なニオイがします……原因と対処法が知りたいです【家電のプロが回答】
オールアバウト / 2024年7月25日 21時25分
-
2国立大「学費値上げ」議論過熱 物価高騰、私大からも「格差是正のため150万円に」の声
産経ニュース / 2024年7月25日 19時32分
-
3「高血圧の薬」高齢者ほど飲むのをやめていい理由 「飲みきれない量の薬」服用する人に伝えたい解決法
東洋経済オンライン / 2024年7月25日 20時0分
-
4年金暮らしに備えて、50代のうちに見直しておきたいこと4つ
オールアバウト / 2024年7月25日 21時40分
-
5暑い夏も要注意!インフル、コロナ、手足口病…「感染症ドミノ」から身をまもる方法
女子SPA! / 2024年7月25日 8時45分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











