家族が同じ目にあっても同じ事を言えるのか…母親を強盗犯に殺された息子が「死刑廃止」に抱く強い違和感
プレジデントオンライン / 2023年2月15日 10時15分
※本稿は、宮下洋一『死刑のある国で生きる』(新潮社)の一部を再編集したものです。
■母を殺した犯人に対し「俺が殺してやりたい」
西口宗宏が逮捕され、再犯者だと分かった時、田村勇一(仮名、武子の長男)は、「こんな人間、俺が殺してやりたいわ」という怒りが爆発した。田村一家の怒りと悲しみが極限に達した状態の中、裁判は始まった。重雄(仮名、同・夫)と勇一は、最高裁での1回を除き、全公判に参加している。麻奈美(仮名、同・長女)は、一審の公判のみを傍聴した。
初公判で、3人は初めて、田村武子を殺した西口を見た。検察官側の席にいた重雄と勇一は、被告人との距離がわずか3メートルだった。報道で目にしていた厳つい写真の西口と違い、体が小さく、気の弱そうな男に見えたという。勇一がその時の印象を語る。
「お袋がこんなやつに負けたんかと思いましたね。せめて俺の手で2、3発、顔でも腹でも殴らせてくれへんかなと思いました」
感情的な発言を極力抑えようとしている重雄は、「私も、こんな男にやられたのかと思いましたね」と述べた後、警察から得た情報を明かした。
■「生きたまま溶鉱炉に落としたい」
「どうやら、車の中で西口に脅されたみたいなんです。お前の家に火をつけに行くとか、家族に手を出すとか。それと警察は、家内が西口に説法したとも言うてはりました。『人間は罪深いけれども、こういうことをすると、あんたの罪を倍加していくんや』と。日頃、家内はね、そういう話をよくしよるんですわ。お寺さんとも、しょっちゅう話をしてますんでね」
重雄は武子のことを、時々、現在形で語った。彼の中で、妻はまだ生きている。私に見えていないだけで、武子は重雄のために、目の前のキッチンで酒の肴を作っているのかもしれなかった。
勇一は、西口を睨み続けた。だが、西口は遺族とは一度も目を合わせなかったという。遺族側の意見陳述の場が提供されると、勇一は、被告に向かって激昂した。
「生きたまま溶鉱炉に落としたい」
なぜその言葉が出てきたのか。
■遺族の望んだ通り死刑が言い渡された
「お袋が殺されて、焼かれたわけでしょ。だからお前は、生きたまま苦しみを味わって死ねという感覚ですよ。これは残酷な言い方ですけど、突き落とした後、俺はお前が溶けるまで上から眺めといてやるわという勢いでしたね。苦しめばいいという」

攻撃的な言葉を述べた息子に対し、重雄は、少し穏やかなトーンで意見陳述を行った。
「愛する妻は、私にとって、家庭の中心におる太陽でした。一緒にできるであろう楽しみもあったのに、そういう夢までぶっつぶされた。非常に頭に来ている。そして、極刑を望みますと言いました」
重雄は、武子を失うと、それまで縁のなかった「無気力」という感覚に襲われたという。家の中が急に暗くなり、周りのことに関心がなくなった。年賀状や仏事のお返しも、面倒だと思うようになった。数週間、仏壇の前に座り続けていた。今では、簡単な料理を作ったり、コーヒーを淹れることくらいはできるようになった。
遺族側が望んだ通り、西口には死刑が言い渡された。裁判では、絞首刑の残虐性や、西口の精神鑑定なども争点となったが、尾崎家の遺族同様、勇一も重雄も、死刑を阻止しようとする証人や弁護側の主張に違和感を持っていた。
■死刑廃止は「家族に何もない人間が言うこと」
裁判を振り返ったことで、勇一の中に怒りが沸々と蘇ってきたようだ。私も、同じ立場だったらと考えると、彼にとっての正義である「母親の敵討」という考え方も理解できる気がした。だが、冷静に耳を傾けなくてはならない。
上半身を前のめりにさせ、勇一が続けた。
「一審も二審も、反論が馬鹿げていた。生い立ちがどうじゃの、かわいそうじゃの。ほな、生い立ちが悪ければ、みんなあんな事件を起こすのかと。素人が見ても突っ込めるような弁解ばかりだったんですわ。絞首台の床から落ちて首が飛ぶこともあると言うてはった。命は大事やから、それより大事なものはないねんけど。ほな、被害にあった家族の命はどないなんねん。そういう論法を持ってくる人間は、自分に何もなくて、家族に何もない人間が言うことやと思いました。実際に家族が巻き込まれて命を奪われると、死刑廃止とは言えませんね」
勇一の発言は次第に熱を帯びていった。じっとしていられなくなったのか、頻繁にソファから腰を上げ、キッチンの周りを歩いたり、リビングを出たりしていた。
■「死刑囚に恐怖やストレスが加わるほうが歓迎」
勇一によると、彼と母親の武子は顔も性格も瓜二つで、思いつきで話をするタイプだが、重雄と麻奈美は、その反対で、性格も穏やかだという。とりわけ、息子の母親に対する強い愛情が、私にはひしひしと伝わってきた。
武子は、亡くなる直前まで、息子の結婚式を楽しみにしていたという。両家の顔合わせも、事件直後に予定されていたようなのだ。しかし、勇一は、5年間も妻に我慢してもらわざるを得なかった。式を挙げるつもりはなかったが、マスコミが騒ぎ立てるという心配もあった。現在は、4歳の娘がいるという。
西口の死刑が確定し、絞首刑が避けられない状況となった現在、気持ちの変化はあるのか訊いてみた。事件から10年が経過している。重雄も、珍しく厳しい物言いをした。
「いつ死刑の順番が回ってくるか分からず、死刑囚は(刑務官の)靴音の恐怖があると聞きます。そういう恐怖を与えてやるほうが、遺族としてはまだ納得できますね。ちょっとでも相手にストレスが加わっているほうが歓迎です」
ゆったりと腰掛けたままの重雄は、「歓迎」という言葉を強調した。さらに、こんなことも言った。
■「日本から死刑制度がなくならないことを望んでいます」
「私は、事件が起きてから、死刑廃止論者の本もたくさん読みました。それも一理あるとは思うのですが、ほんならあんたの家族が同じことになっても、同じことを言えるんかい、と。それが私の本心ですよね。だからこの国から死刑制度がなくならないことを、ずっと望んでいます」
私が眺めている限り、重雄は物腰が柔らかく、口調も丁寧で穏やかではあるが、語る言葉の一言一言が厳格だった。
会話には終始、西口に対する怒りと不満が籠められていた。顔に出さなくとも、重雄の感情も息子の感情と一致している。ただ、勇一は時々、「あくまでも遺族としての感情ですが」という表現を使っていた。それは、医療関係者としての感情とは異なるという意味だった。
「本来、医療者なら、拘置所から連れてこられた人間でも治療しなくてはならんのです。昔、病院で働いていた時に、ある先生が言ったんですが、どんな人間でも関係なく、命は命だと。なるほどな、と思いましたよ。医療人の端くれとしては、命の重要性は分かっているつもりです。今までの私の言動の数々も、その意味では不適切なんでしょうね」
だが、それとこれとは話が別だとでも言うような顔で、彼は続ける。
「そのことと家族を奪われたということは、論理的には説明ができないですよね。感情と論理は別腹ですから。もう解決し得ない話です。感情というのは、どうしようもないんです。これはもう平行線ですよ。どっちに重きを置くか。ウチでいうたら、どっちの経験をしたかということになるんです」
■被害経験のない専門家の論理は「机上の空論」
重雄も、息子の発言に付け足すように、こう言った。
「社会常識のある人間として、そういう発言が不適切だということを十分に分かった上で、それでも被害者の遺族としてはこうだよ、ということになりますかね」
その言葉には説得力があると思った。2人は、ただ感情に流され、怒りや暴言を吐き散らしているわけではないのである。彼らが罪と罰を天秤にかける上で、被害に遭った経験のない専門家が語る論理は、「机上の空論でしかない」と批判した。
麻奈美は、壁際でずっと聞き役に徹していたが、本当はもっと伝えたいことがあるのではないかと感じた。私は、彼女が不適切な発言をしても、聞き入れる用意があった。心理学者でも臨床心理士でもないが、麻奈美の表情は、実に多くを物語っているように見えた。
■死刑か、仮釈放なしの終身刑か
もう3時間が過ぎていたが、そろそろ私が答えを探し続けてきた核心部分に迫ろうと思った。
「もし西口の死刑が執行されたら、心の平安は訪れると思いますか」
この話を被害者遺族の口から直接聞くために、日本でどれだけの時間を要したことだろう。まず、重雄が頭を捻り、こう言った。
「ひと段落したと思うでしょうね、きっと」
次に勇一が口を開いた。
「死刑で完了した、良かった、とじっくり考える暇もないでしょうね。休みなく仕事しているし、日曜日と祝日以外は休みがないんでね」
私は、心の深部を知りたかった。もう少し具体的に聞くべきだと思った。
「もし、遺族の心に平安が訪れないとなると、死刑は何のためにあるのでしょうか」
そう訊くと、勇一の答えが返ってきた。
「僕の中では、何も解決しません。西口が死のうが生きようが、母親は帰ってこないわけですからね」
意外な言葉に困惑しながら、すかさずこう訊いた。
「ならば、死刑でなくとも、仮釈放のない終身刑という考え方もあると思うのですが」
すると重雄からも、私の想像を超える意見が返ってきた。
「それやったら、まだ分からなくないです。その代わり恩赦がなく、死ぬまで監獄生活。拘置所のほうがうまいご飯も食べれるし、環境も良いというじゃないですか。ですから、そうでない悪い環境の中で一生暮らすなら、いいんやないですか。一瞬にして死刑を受けるよりも、きっと苦しくて、それが死ぬまで続くことを考えればですがね」
勇一も、「今の制度やったら、無期懲役でも出てくる可能性があるので、懲役368年みたいに、絶対に出られへんというならね」と父親に共感した。彼も仮釈放がない終身刑であれば納得できるという思いがどこかにありそうだ。
■犯人にとって何が「最も苦しい」のか
私が「心の平安」に関する質問をしたことで、彼らはこの時になって初めて自問自答している様子だった。内面に潜んでいた無意識が、言葉という形で表されたようでもあった。それは、彼らでさえ知り得なかった本心のように思えた。
2人の率直な言葉は、私の思考をぐらりと揺さぶった。殺人事件の遺族でも、死刑を望んでいるわけではないのか。彼らが発した一語一句の深部には、その思いが隠されているような気がした。私は、もう一度確認したかった。
「武子さんのような酷い殺され方なら、遺族は、何が何でも犯人の死を求めていると思っていたのですが、それは……」
そこまで語ると、奥の方から真っ先に「それはそうです」と漏らす麻奈美の声が聞こえた。その後、勇一が険しい表情を見せながら言った。
「その思いは変わらないですよ。要は犯人が、死ぬ死なんよりも、苦しみを受けろと。それが死刑(の執行)がいつ来るのか分からんという恐怖に慄くのか、一生普通の生活ができないか、どっちのほうが苦しいのかということです」
そこには、死をもって償わせるべきという響きは、必ずしも含まれていなかった。しつこいようだが、さらに突っ込んでみる。
「となると、苦しむならどんな手段であれ、それを肯定したいということですか」
重雄が「そうですね。むしろそうですね」と肯いた。勇一も、「そうです、そうです」と首を縦に振り、「それがずっと塀の中におることなのか、いつ死が来るか分からない苦しみということなのか」と考えを整理した。

■「犯人が死ねば苦しみはなくなってしまう」
彼らの処罰に対する考え方が、何となく分かってきた。私はさらに質問を重ねる。
「死んでしまえば、もう相手を苦しませることはできないですよね」
すると重雄が「そうなんです、そこなんです。だから言われる通りなんですわ。だから死刑になったら、そこで相手の苦しみはなくなるし、我々も空虚になるだけですよね」と言った。「無期懲役を楽しむもんなんかはおらんと思うので、その苦しみが続く分だけ、刑としてはきついのかなと思います。死刑をなくすけれど(仮釈放のない)終身刑に置き替える。それやったら考えられんことはないですね」
勇一も、「西口が生きていようが死んでいようが、ずっと恨みっぱなし。できることなら、生きている間は肉体的にも精神的にも苦しめと思っています」というのが行き着く先の答えのようだった。
■加害者に「死んでほしい」と思う遺族の真意
私がどうしても知りたかったことを、ようやく知れた気がした。遺族が加害者に対し、「死んでほしい」と口にする時、その言葉に込められた本当の思い。それは、この世から消える「生物学上の死」を意味しているわけではない。むしろ、「苦しみ続けてほしい」という願望のほうが強いのかもしれないのだ。ここにいる2人からは、そう感じた。
重雄が言うように、相手が処刑されたら「空虚になる」というのが、本心なのだろう。死刑によって、被害者遺族に心の平安は訪れないのかもしれない。惨殺された妻が、母親が、戻ってくるわけではないのだから……。
日本では、2008年以来、被害者や遺族が刑事裁判の公判期日に参加し、被告人質問や意見陳述できる制度がある。一般市民である裁判員は、この制度により、被害者側の言葉や表情から感情を汲み取り、その感情に敏感に反応するに違いない。
しかし、第三者である裁判員が、被害者遺族の心の中を、果たしてどこまで読み取ることができるのか。法廷で遺族が「死をもって償ってもらいたい」と言った時、実際はそれを望んでいないかもしれないことを、裁判員は汲み取れるのか。もちろん、それが被害者遺族全員に共通する感情とは限らない。だが、そういう可能性もあることを私は知った。
■「孫の顔くらい見せてやりたかった」
外は真っ暗で、雨が降っているようだった。荷物をまとめ、挨拶をすると、勇一が私を駅まで車で送ると言った。重雄は、玄関まで来て、「どうもありがとうございました」と丁寧に頭を下げ、私に靴べらを手渡した。革靴の紐を結び終え、私も深くお辞儀した。
玄関の扉が閉まる前、奥に麻奈美が立っているのが見えた。口にする言葉が適切かどうか分からないまま、私は「これからも頑張ってください」と声をかけた。麻奈美は、「はい」と言って肩を窄(すぼ)めた。
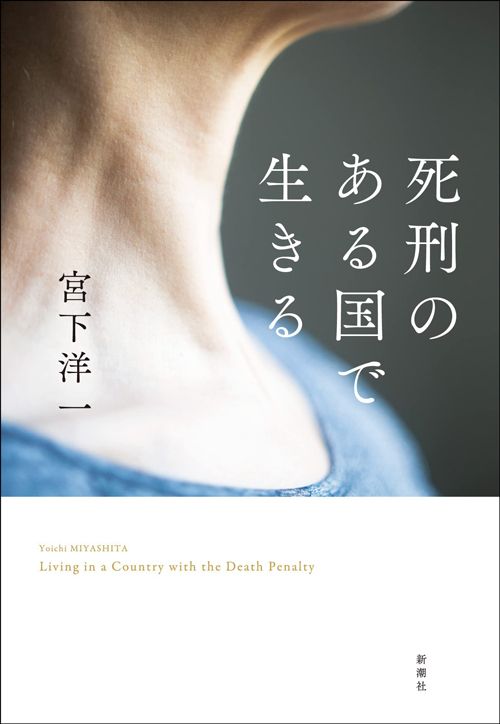
ハンドルを握る勇一は、駅までの道のりで、こんなことを呟いた。
「せめてお袋に、孫の顔くらいは見せてやりたかった。ウチのやんちゃ娘をどう扱うのか見てみたかったですね」
家の中で見せていた険しい表情とは違った。いつか彼の中に、心の平安は訪れるのだろうか。その時が来ることを、私は助手席から祈っていた。
車を降り、勇一と別れると、どっと疲れが出た。放心状態になった私は、気づけば傘をさしたまま駅の構内を歩いていた。
----------
ジャーナリスト
1976年、長野県生まれ。18歳で単身アメリカに渡り、ウエスト・バージニア州立大学外国語学部を卒業。その後、スペイン・バルセロナ大学大学院で国際論修士、同大学院コロンビア・ジャーナリズム・スクールで、ジャーナリズム修士。フランス語、スペイン語、英語、ポルトガル語、カタラン語を話す。フランスやスペインを拠点としながら世界各地を取材。主な著書に、小学館ノンフィクション大賞優秀賞を受賞した『卵子探しています 世界の不妊・生殖医療現場を訪ねて』など。
----------
(ジャーナリスト 宮下 洋一)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
犠牲者母「あの子に会いたい」=癒えぬ思い胸に、講演続ける―18日で京アニ事件から5年
時事通信 / 2024年7月17日 14時31分
-
「一緒に死んでくれるか?」父は黙ってうなずいた…パーキンソン病の90歳父を登山用ロープで絞殺 「承諾殺人」の罪に問われた61歳男 起訴内容認める
MBSニュース / 2024年7月16日 18時5分
-
「犯人に対して極刑を望みます」135万筆の署名を集めるも判決は無期懲役…《千葉小3女児殺人事件》被害者家族のその後
文春オンライン / 2024年7月16日 11時0分
-
世界では薬物注射による死刑執行が主流となりつつあるなか、なぜ日本は今も絞首刑を続けているのか
集英社オンライン / 2024年7月16日 8時0分
-
不遇な梅子はなぜ「姑の世話」をキッパリ断れたのか…現役弁護士が感心した『虎に翼』の注目シーン
プレジデントオンライン / 2024年7月11日 15時15分
ランキング
-
1「ハイオクとレギュラー」は何が違う? ハイオクが「高い」のはなぜ? “ハイオク指定車”にレギュラーを入れたらどうなる?
くるまのニュース / 2024年7月22日 21時10分
-
2腰痛に悩む女性が今すぐに取り入れるべき「3つの習慣」…“ぎっくり腰のリスク”も軽減
女子SPA! / 2024年7月22日 17時42分
-
3大人以上に暑い!?子どもの「熱中症」リスクが高い理由…異変に気づくためには?
南海放送NEWS / 2024年7月22日 17時54分
-
4天才物理学者アインシュタインの脳に見られる特徴とは?
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月23日 9時26分
-
5【マック】ナゲットの持ち方で性格診断できるだと?SNS大盛り上がり「お上品ナゲットタイプだった」「確実に神経質ナゲットタイプ」
東京バーゲンマニア / 2024年7月22日 17時16分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











