なぜ「君が代」を「我が日の本」と必ず替えて歌ったのか…「右翼政治家」と呼ばれた石原慎太郎氏の本当の思想
プレジデントオンライン / 2023年2月11日 9時15分
結局のところ「忙しくて書くのを忘れてた」という猪瀬さん。『火の鳥』を上梓した石原さんに「猪瀬さん、俺、書いたよ」と声をかけられたときのことを「しまった。そういえば約束したんだよなと思ったよ」と振り返る。 - 撮影=プレジデントオンライン編集部
■「副知事をやってくれないか」最初は断るつもりだった
――なぜ「作家・石原慎太郎」について書こうと思われたのですか。
そもそものきっかけは、ぼくが東京都の副知事を引き受けた16年前のこと。
2007年5月に石原さんに「会いたい」と連絡をもらって、赤坂の料亭で会ったんだよね。『ペルソナ 三島由紀夫伝』という著作があるぼくにとっても、三島と交流があった石原さんと話してみたかった。
20人が座れそうな座卓にふたりっきりになると、「副知事をやってくれないか」と石原さんに頭を下げられた。小泉政権下で、4年間も道路公団民営化に取り組んで疲れ果てて、物書きに専念しようと考えていた時期だったから、最初は断ろうと思ったんだよ。
ただ石原さんの口説き方がとてもうまくてね。「猪瀬くん、ひらめくんだよ。ぼくは都知事になってから7本の長編を考えた。いろいろと思いつくものだよ」と。
確かに、都政に関わったからといって、都庁をテーマにした物だけを書かなければならないわけではない。ぼく自身も体験的に分かっていたけど、物書きのひらめきは、緊張感から生まれる。緊張感がなければ、いい仕事はできない。ある意味では、それがプロの物書きの極意とも言える。
石原さんの言葉に「なるほど」と惹かれて、副知事を引き受けた。
■根源にはいつも「作家」が潜んでいる人だった
それに、石原さんは昨年亡くなる間際までずっと書いていたでしょう。
『絶筆』が発売されたのは、亡くなって9カ月が過ぎた昨年11月。石原さんは最期の最期まで作家だった。本当に大したものだ、とひとりの物書きとして感心させられたんだよね。
にもかかわらず、作家としての石原さんの評価は必ずしも高くない。
石原さんが亡くなったあと、編集者から石原さんについて書かないか、と声をかけられた時、はじめは断ろうと思った。けど、素の石原さんを知っているのはオレくらいかな、と考え直して引き受けた。先入観にとらわれずに、作家としての石原さんをきちんと評価できればな、と。

――猪瀬さんは『太陽の男』で〈石原慎太郎という人物にまつわるイメージから生じている『どうせ大した作家じゃないんでしょ』という予断が薄く広く共有されており……〉という評論家の栗原裕一郎さんの言葉を引用していますね。
石原さんの代表作は芥川賞を受賞した『太陽の季節』だけど、それ以外にもいい作品はたくさんある。とくに『亀裂』は、三島の『鏡子の家』に影響を与えるほどの作品だった。
石原さんはデビュー以来、作家として毀誉(きよ)褒貶(ほうへん)にさらされてきた。政治家になって好き勝手しゃべっているから、作家として評価がされにくかったんだろうけど、ぼくには石原さんの言動の根底には「作家」が潜んでいるように感じていた。
■「オレは3000万人を相手にしている」
――猪瀬さんと「作家・石原慎太郎」の出会いはいつですか?
あれはぼくが小学4年生の頃だったかな。記憶に残っているのは『太陽の季節』の映画ポスターが強烈だったこと。砂浜で抱き合う水着姿の男女がいままさにキスしようとしている……。1956年1月23日に芥川賞を受賞した『太陽の季節』は、早くもその年の5月に映画化されたんだけど、子ども心に不良の映画だと感じたのを覚えている。
ぼくが石原さんの小説をはじめて読んだのは高校か大学で、1960年代半ば。すでに芥川賞受賞から10年近くが経っていた。その頃、人気だったのが大江健三郎。太宰治に憧れて「自分と同じだ」と勝手に共感するような文学青年が、つぎのステップとして大江健三郎を熱心に読んでいた。当時から自分は世の中に受け入れられないアウトローだと思い込んでいる文学青年が文学の主流を担っていたわけだから、石原さんの小説はウケなかった。
ある意味で、それは当然だったと思う。文学青年に愛される作品を書いた大江健三郎と、石原さんは発想がまったく違うわけだから。石原さんは大江健三郎に対して「あなたの読者は3万人だろうけど、オレは3000万人を相手にしている」と語った。石原さんは、斜に構えてショートピースを吸う文学青年ではなく、町場の旋盤工から孤島の漁師にまでに届く小説を書こうとしていた。
■「連隊旗を渡す」三島由紀夫はその才能を見抜いていた
石原さんの小説に対する考え方が分かるのが、太宰治批判。石原さんが三島由紀夫と文学について対談すると決まって「太宰はダメだ」という話題になった。三島は「冷水摩擦したり、ラジオ体操したりすれば、太宰の悩みなんて吹っ飛んじゃう」と批判した。三島も石原さんと同じで、3万人ではなく、3000万人の読者を相手にした作家だったから、相通ずるものがあった。だからこそ、三島は石原さんに「連隊旗を渡す」と語り、後継者指名した。三島は、石原さんがアウトロー気取りの文学青年だけではなく、もっと広い世界を相手にできる才能があると見抜いていた。
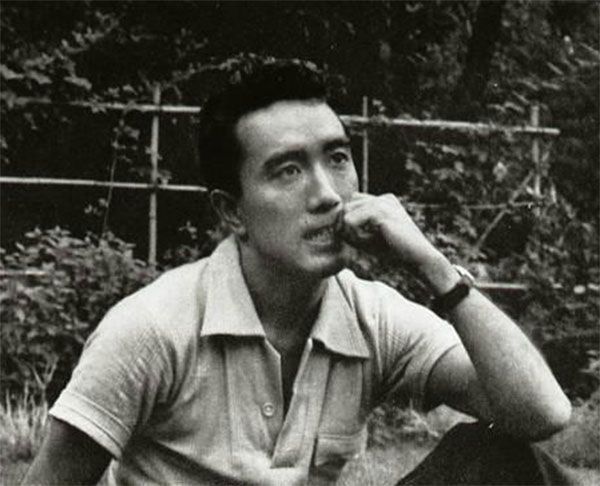
そこには、ほかの日本人作家が持っていなかった三島ならではの作家観がある。作家は小説も書くだけでなく、全人的な要素が必要とされると三島は考えていた。
ヨーロッパの作家ならトーマス・マンも、バルザックも、いち作家にとらわれない活動をしたわけでしょう。フランスのアンドレ・マルローは文化大臣を務めたし、ダンテも政治に参画した。チャーチルも政治家でありながら、文学的な文章を残した。彼らはアウトローではなく、社会のメインストリームを歩んできた。日本なら、大学教授だった夏目漱石や、官僚の森鴎外がそう。ただ田山花袋あたりから、弟子の女の子に手を出したとかいう話が世間を騒がせるようになって、作品そのものよりも醜聞や好奇心で読者の関心を惹くようになる。
その点で言えば、石原さんも三島もメジャーとマイナーの違いを分かっていて、小説とはなにか、作家とはどんな存在かという意識を共有していたんじゃないかな。
■三島研究者たちが見落としていること
――だから石原慎太郎も三島由紀夫も、一般的な小説家という枠組みでは捉えられないわけですね。『太陽の男』では、2人の対立についても詳しく描かれていますね。
三島を研究する人は、石原慎太郎という人物をまったく意識していないでしょう。眼中にないと言ってもいいくらい。
なぜ、三島は自決にいたったのか。そこに、石原さんはどう関係したのか……。
ぼくはここが重要なポイントだと思っている。もちろん自決の原因のすべてが石原慎太郎とは言えない。でも、三島は石原さんを強く意識していたのは間違いない。三島は、作家としても、ひとりの人間としても、後ろから迫ってくる石原さんの足音に耳を澄ませていた。
それは、三島が自決する2カ月前に刊行された『尚武のこころ』という対談集を読むとよく分かる。『尚武のこころ』には、石原さんをはじめ、野坂昭如、寺山修司、鶴田浩二、林房雄、堤清二ら、10人のそうそうたる有名人や文化人が登場する。あとがきで、三島はわざわざ石原さんの名前だけを出して、こんなふうに書いている。
〈非常に本質的な重要な対談だと思われたのは、石原慎太郎氏との対談であった〉〈旧知の仲ということにもよるが、相手の懐に飛び込みながら、匕首をひらめかせて、とことんまでお互いの本質を露呈したこのような対談は、私の体験上もきわめて稀である〉
■「君が代」ではなく「我が日の本」
この対談で、日本の守るべき価値について「天皇制」と語る三島に対し、石原さんは「自由」と話し、さらに日本の風土に言及した。立脚点が異なる石原さんは、日本の伝統をつくったのは「天皇制」ではなく、縄文時代から続く北海道から沖縄までの荒海と峻厳な山々だと主張した。「天皇制」は稲作文化が始まって以降に誕生したのだから、と。

だから、石原さんは東京都の式典などで「君が代」の斉唱があるたび「きみがあよおは~」とすべきところを「わがひのもとは~」と必ず替えて歌うんだよ。「君が代」ではなく「我が日の本」。
つまり石原さんは、天皇の治世ではなく、列島の風土こそ守らなければならない日本だと考えていた。石原さんについて改めて調べみると、ここに2人の本質的なすれ違いがあったのではないかと気づかされた。
石原慎太郎と三島由紀夫――2人の作家は、最後まで互いに影響を与え合ったライバルだったんだ、と。(後編に続く)
----------
作家
1946年、長野県生まれ。1987年『ミカドの肖像』で第18回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。『日本国の研究』で1996年度文藝春秋読者賞受賞。2002年6月末、小泉首相より道路関係四公団民営化推進委員会委員に任命される。2007年6月、東京都副知事に任命される。2012年12月、東京都知事に就任。2013年12月、辞任。2015年12月、大阪府・市特別顧問就任。2022年から参議院議員(日本維新の会参議院幹事長)。主な著書に『天皇の影法師』『昭和16年夏の敗戦』(以上、中公文庫)、『ペルソナ 三島由紀夫伝』(文春文庫)、『黒船の世紀』(角川ソフィア文庫)、『猪瀬直樹著作集「日本の近代」全12巻 電子版全16巻』(小学館)。
----------
(作家 猪瀬 直樹 聞き手・構成=ノンフィクションライター・山川徹)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
直木賞受賞の覆面作家・一穂ミチさん、マスク姿で登壇「パンデミック下でなければ生まれなかった小説」
読売新聞 / 2024年7月17日 21時59分
-
芥川賞、朝比奈秋さんと松永K三蔵さんがダブル受賞
毎日新聞 / 2024年7月17日 18時2分
-
知名度勝負の選挙、「キャラ立ち」の東京都知事生む? 注目度の高さ、乱立の原因に。選管も想定外の56人立候補
47NEWS / 2024年7月6日 10時0分
-
母国のためクルコフは書き続ける【沼野恭子✕リアルワールド】
OVO [オーヴォ] / 2024年6月30日 8時0分
-
三島由紀夫賞を受賞した大田ステファニー歓人さんのスピーチが胸を強く揺さぶった。(松尾潔)
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月28日 9時26分
ランキング
-
1「ハイオクとレギュラー」は何が違う? ハイオクが「高い」のはなぜ? “ハイオク指定車”にレギュラーを入れたらどうなる?
くるまのニュース / 2024年7月22日 21時10分
-
2腰痛に悩む女性が今すぐに取り入れるべき「3つの習慣」…“ぎっくり腰のリスク”も軽減
女子SPA! / 2024年7月22日 17時42分
-
3天才物理学者アインシュタインの脳に見られる特徴とは?
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月23日 9時26分
-
4「新しいiPhone」を少しでもおトクに入手する技 円安ドル高で、毎年のように値上がりしている
東洋経済オンライン / 2024年7月23日 11時0分
-
5大人以上に暑い!?子どもの「熱中症」リスクが高い理由…異変に気づくためには?
南海放送NEWS / 2024年7月22日 17時54分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











