アメリカが最大の被害者に…世界中に害悪の"タックスヘイブン"が一掃されるどころか増え続けるワケ
プレジデントオンライン / 2023年2月9日 9時15分
※本稿は、大村大次郎『お金で読み解く世界のニュース』(PHP新書)の一部を再編集したものです。
■脱税、犯罪マネーの隠し場所…タックスヘイブンのもう1つの性質
昨今の世界経済の大きな問題として「タックスヘイブン」というものがある。
タックスヘイブンとは、「租税回避地」のことであり、税金のかからない地域のことである。タックスヘイブンに住居地を置けば、個人の税金はほとんどかからない。
また各国を股にかけている多国籍企業が、本拠地をここに置いておけば、法人税の節税もできる。タックスヘイブンに本社を置いて、各国には子会社を置く。そして、各国の利益は、タックスヘイブンの本社に集中するようにしておくのだ。
そうすればその企業グループ全体では、税金を非常に安くすることができる。だから、本社をタックスヘイブンに置いている多国籍企業も多い。
特にヘッジファンドと呼ばれる投資企業の多くはタックスヘイブンに本社を置いている。
そして、タックスヘイブンには、もう1つの性質がある。
それは「守秘性」である。
タックスヘイブンは、自国内に開設された預金口座、法人などの情報を、なかなか他国に開示しないのである。たとえ犯罪に関係する預金口座、企業などであっても、よほどのことがない限り、部外者には漏らさない。
そのため、世界中から、脱税のための資産隠しをはじめ、麻薬などの犯罪に関係する金、汚職など不正な方法で蓄えた資産が集まってくるのである。
つまり、タックスヘイブンは、脱税をほう助するとともに、犯罪マネーの隠し場所にもなっているのだ。
■世界の銀行資産の半分以上がタックスヘイブンを経由
このタックスヘイブンには、現在、世界各国が頭を痛めている。
企業はちょっと大きくなるとすぐにタックスヘイブンに行ってしまう。
そして本社をタックスヘイブンに置かれたら税金がとれなくなり、税収が不足してしまうのだ。またちょっとお金を貯めた個人は、すぐにタックスヘイブンに資産を隠す。そうなると、母国での相続税などの課税は非常に難しくなる。
このタックスヘイブンで、一番被害を受けているのは、実はアメリカ政府である。
代表的なタックスヘイブンであるケイマン諸島には、1万8857の企業があり、そのうちの半分は、アメリカの関連企業である。ここでアメリカは、年間約1000億ドル(約11兆円)の税収を、失っているという。
もちろん、アメリカだけではなく、世界中の国々がタックスヘイブンの被害を受けている。
現在、世界の銀行資産の半分以上、多国籍企業の海外投資の3分の1が、タックスヘイブンを経由していると言われている。
国際通貨基金IMFは、2010年の発表で、南太平洋などの島嶼(とうしょ)部のタックスヘイブンだけで、18兆ドル(約1800兆円)の資金が集められているとしている。
18兆ドルというのは、世界総生産の約3分の1に当たる巨額のものである。
しかも、これは「過小評価と思われる」と付記されている。
国際非政府組織(NGO)の「税公正ネットワーク」は2010年末時点で、21兆~32兆ドル(約2270兆~約3450兆円)の金融資産が、タックスヘイブンに保有されていると分析している。
■野放しの背景「黒幕にイギリス」
タックスヘイブンは、世界中に害を与えているのに、なぜ先進諸国はこれを野放しにしているのか?
もちろん、各国はこれに手をこまねいているわけではない。
OECDなどが中心となって、タックスヘイブンに規制を設けようという試みは、今まで何度も行われてきた。
しかし、タックスヘイブン側がなかなかそれに応じないのである。
タックスヘイブンの主なところに、ケイマン諸島、ヴァージン諸島、香港、シンガポール、ルクセンブルク、パナマなどがある。これらの国名を見ればわかるように、お世辞にも大国とは言えないところばかりである。
なのに、なぜ先進諸国は、タックスヘイブンに強い圧力を加えることができないのか?
タックスヘイブンの中心には、大英帝国の存在があるからである。
つまりは、タックスヘイブンのバックには、イギリスがいるのである。
タックスヘイブンというと、「南太平洋などの小国が、自国に企業を誘致するために無税にしている」というイメージがある。
しかし、タックスヘイブンを最初につくったのは、イギリスであり、現在もタックスヘイブンの多くを実質的に支配しているのは、イギリスなのだ。
一般の方には、「何がなんだかわからない」と思われるだろう。
また、「この著者は、空想的陰謀論者なのか」と思った人もいるかもしれない。
しかし、イギリスがタックスヘイブンをつくったことや、現在もタックスヘイブンに大きな影響を持っていることは、金融史にも記されていることであり、誰もがすぐに確認がとれる歴然たる事実なのである。
それにしても、なぜイギリスはタックスヘイブンをつくったのか?
その経緯を説明したい。
■20世紀に凋落したイギリス
イギリスは、18世紀後半から20世紀前半まで長らく世界の金融センターとして君臨してきた。1957年の時点でも、まだポンドは世界貿易の40%で使われていたのだ。

しかし、イギリス経済の凋落とともに、アメリカにその座を奪われつつあった。
イギリスは、第二次世界大戦直後にインド、エジプトを失い、他の植民地も次々に独立していった。第二次世界大戦終結時点では7億人以上を支配していた大英帝国は、1965年にはわずか5000万人の国民を有するのみとなっていた。
イギリスは、第二次世界大戦後、経常収支の赤字、ドル準備、金準備の減少に苦しめられ、たびたびポンドの価値を維持できない「ポンド危機」に見舞われた。
1949年には、大幅な「ポンド切り下げ」を行った。そこには、世界の銀行とさえ呼ばれた、往年の大英帝国の姿はなかった。
ポンドは信用力を急速に失い、世界の基軸通貨の座をドルに明け渡すことになった。
イギリスのシティ・オブ・ロンドンが、世界の金融センターとして君臨してきたのは、強いポンドがあったからである。シティはポンドを取扱うことで、世界の金融を牛耳ってきたのだ。
しかし、ポンドの価値が下がり、基軸通貨としての役割を失えば、シティの影響力も弱まる。シティはポンドの凋落とともに、力を失っていった。
それを取り戻すために、イギリスは危険な賭けに出た。
「タックスヘイブン」の創設である。
■世界中の多国籍企業がイギリス植民地に本社を置いた理由
タックスヘイブンの起源は、19世紀にまでさかのぼる。
西洋の列強が、アジア、アメリカ、アフリカを手当たり次第に食い散らかしていた時代のことである。
当時、企業のグローバル化が起こり始めていた。そしてイギリスでは、植民地への投資を増やすために、植民地の企業の税金は安くしていた。そのため、イギリスの植民地には、多くのイギリス企業が移転してきたのだ。
そのうちイギリスだけではなく、世界中の多国籍企業が、イギリス植民地に本社を置くようになった。
当然、イギリス植民地は、潤った。
税金を安くしても、会社が本社を置けば登記費用などがかかるし、また会社はある程度、その地域にお金を落としてくれる。
イギリス植民地にとって、それは貴重な財源となったのだ。
だから、イギリスの海外領は、第二次世界大戦後も、税制はそのままにしておいた。せっかく本社を置いてくれている多国籍企業に出て行かれないためにである。
そしてイギリスの海外領は、1960年代ごろから、スイスのような秘密主義を取り入れた。
具体的に言えば、
・税金を安くする
・会社の登記などが簡単にできるようにする
・金融の秘密を守る
等である。
つまり、このときに「タックスヘイブン」が出来上がったのである。
■建前により先進国としての責任を回避
なぜ、イギリス本島ではなく、イギリス勢力圏の島々にタックスヘイブンはつくられたのか?
イギリス本島では、さすがに税金を安くすることはできない。また金融に対する規制や監視などにも、イギリスは先進国として責任を持たなければならない。
しかし、世界に点在するイギリス領の島々であれば、その責任は持たなくていい。
イギリス側は、他国から抗議がでれば「自治領なので、我々の責任外だ」という言い訳ができるからである。
イギリスは、昔から海外領を使って外交上の問題をクリアしてきた伝統がある。
たとえば、ジャージー島である。
ジャージー島とは、イギリス海峡に浮かぶイギリスの王室属領である。外交や国防については、イギリス本国が行うが、独自の憲法、議会によって自治を行っている、という建前がある。
イギリスはこのジャージー島を都合よく使った。
ヨーロッパの政治犯が、イギリスに亡命を求めてきたとき、イギリスは彼らをジャージー島に匿った。そして他国から抗議を受けても、事実上はイギリスの統治下にありながら、「ジャージー島は自治地域であり、我々の管轄外だ」と言い逃れしたのだ。
それと同様のことを、やろうと考えたのである。
イギリスには、まだ世界中にイギリス領やイギリス王室属領が点在している。そこを使って、「税金が安く」「銀行秘密法のある」地域をつくろうということである。
こうして、タックスヘイブンを誕生させたのだ。
■世界中に広がるタックスヘイブン
イギリスの海外領がタックスヘイブン化していくのを、他の国々はただ手をこまねいていたわけではない。
アメリカは、当初からタックスヘイブンの最大の被害者だった。
だから1961年ごろから、アメリカは、タックスヘイブンへの取り締まりを強化しようとしてきた。
が、イギリスの老獪(ろうかい)な対応に翻弄され、それがままならない。
そこで、今度はアメリカ自身がタックスヘイブンを創設、運営するようになった。元々アメリカは、州によっては税金が非常に安かったり、会社が非常につくりやすかったりするケースがあった。
それらの州が、イギリス領のタックスヘイブンに対抗するようになったのだ。
そしてケイマン諸島でイギリスがやったのと同様のことを、アメリカはマーシャル諸島で行い始めた。
もちろん、この流れは、アメリカだけのことではない。スイス、ルクセンブルク、オランダなどは、イギリスの海外領に対抗して、自身もタックスヘイブン化していった。
これらの地域は、元々金融の秘密性を持っていたり、税金が安かったりした。それをさらに、会社をつくりやすくしたり、金融の規制を弱めるなどして、企業や資産を呼び込もうとしたのである。
こうして、タックスヘイブンは世界中に広がることになった。
それでも、タックスヘイブンとして、もっとも有害で、もっとも金を集めているのは、イギリスの海外領だった。
2016年に公表された「パナマ文書」の主要舞台となっているヴァージン諸島も、もちろんイギリスの海外領である。
■ウォール街を凌駕するロンドンのシティ
現在、世界はマネーゲームの弊害にしばしば悩まされている。
ITバブルの崩壊や、リーマン・ショックなどで、幾度もわけのわからない不況に見舞われ、ヘッジ・ファンドの無茶な買収劇により、関係企業や従業員は右往左往させられる。
このマネーゲームの総本山といえば、我々は、ニューヨークのウォール街を真っ先に思い浮かべる。
しかし、マネーゲームの本当の総本山はウォール街ではない。
確かに、ニューヨークのウォール街は、金融取引量自体は世界一である。が、ウォール街の場合、その大半は国内の取引なのである。アメリカという市場がそれだけ大きいということだ。

マネーゲームの本当の総本山は、ロンドンのシティなのである。
世界経済全体のシェアを見てみれば、ロンドンのシティのほうが、ウォール街を凌駕しているのだ。
国際的な株取引の約半分、国際新規公開株の55%、国際通貨取引の35%は、ロンドンのシティが占めている。
またイギリスの外国為替取扱量は、1日当たり2兆7260億ドルであり、世界全体の40%を占めている。
もちろん、断トツの1位である。
2位のアメリカは、イギリスの半分以下の1兆2630億ドルである。
国際金融センターとしての地位は、いまだにロンドンのシティが握っているのである。
なぜロンドンのシティが、これほど世界金融に影響力を持っているのか?
それは、イギリスがタックスヘイブンの総元締めだからである。
国際決済銀行(BIS)によると、イギリスとその海外領のオフショア銀行預金残高は推定3兆2000億ドルであり、世界のオフショア市場の約55%を占めているという。
つまりはタックスヘイブンの金の大半は、イギリスが取り扱っているのである。
イギリスの「経済力」というのは、世界経済の中でそれほど大きいものではない。
世界のGDPのランキングでは、ここ数年第5位である。アメリカのGDPの7分の1に過ぎない。
そのイギリスが、金融の国際取引において、最大のシェアを持っているのだ。
タックスヘイブンの存在が、いかに世界のお金を歪めているか、ということである。
■リーマン・ショックはロンドン発だった
近年、イギリスはなりふり構わぬという姿勢でマネーゲームにまい進してきた。
国際経済において、イギリスが行ってきた「禁じ手」というのは、タックスヘイブンだけではない。現在、世界中で行われている「狡猾なマネーゲーム」の多くはイギリスが関与しているものである。
マネーゲームの中心地は、ウォール街ではない。ロンドンのシティなのである。ウォール街は、シティに追随しているに過ぎない。
イギリスは、金融や企業の規制が、アメリカなどに比べて非常に緩い。
規制を緩くすることにより、世界中の企業やお金を呼び込もうということである。
ロシアの企業は、海外で上場するとき、ニューヨークではなく、ロンドンのシティを選ぶ。シティは、ニューヨークやほかの地域に比べてガバナンス基準が緩いのである。
通常、各国の上場市場では、投資家を保護するために、上場する企業に対して様々な基準、規制を設けている。その規制が、ロンドンは緩いということなのだ。
上場する企業の側にとっては、上場しやすいので都合がいい。が、投資家にとっては危険が大きい。
ロンドンのこの規制の緩さにより、世界中の金融機関、投資会社がロンドンに集まることになった。そのため、ロンドンは、ニューヨーク以上の国際金融センターの地位を維持しているのだ。
■規制の緩さが金融危機の引き金に
しかし、このロンドンの規制の緩さは、しばしば世界的な問題をもたらしてきた。
たとえば、かのリーマン・ショックも、ロンドンが大きく関係しているのだ。
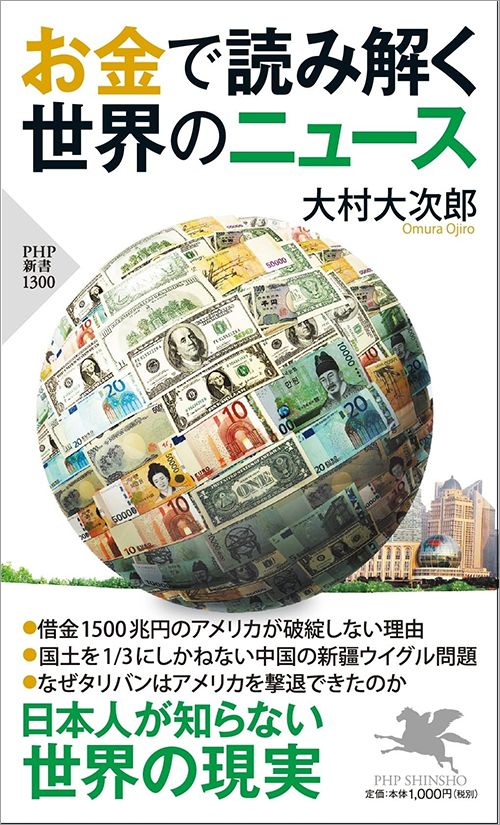
リーマン・ブラザーズが破綻した大きな要因となった「レポ105」という取引は、実はイギリスの子会社で行われたものなのである。
「レポ105」というのは、簡単に言えば決算期直前などに、手持ちの債権などを「あとで買い戻す」という条件のもとで、一時的に現金に換えるという取引である。
決算期直前にこの取引をすれば、決算書上は、現金をたくさん持っていることになる。つまり健全な経理内容のように見えるのだ。
リーマン・ブラザーズは、この「レポ105」を大掛かりに行うことによって、アメリカの監督庁の目をごまかしていた。
この「レポ105」は、リーマン・ブラザーズのイギリスの子会社で行われていたのだ。
イギリスは、この手の取引についても、法律が緩く、監査法人は簡単にゴーサインを出す。
アメリカの監査法人であれば間違いなく、制止するはずなのに、である。
リーマン・ブラザーズとしても、「アメリカでこれを行うことはできないが、イギリスでならできる」ということを踏んでいたのだろう。
またリーマン・ブラザーズと同様の戦犯である「AIG」の経営危機もロンドンが大きく関係している。
AIGは、多額のサブプライム・ローンを抱えていたことで経営危機に陥ったのだが、このサブプライム・ローンは、AIGのロンドン・オフィスが中心となって推し進められていたのである。
もちろんリーマン・ショックの要因はそれだけではないが、イギリスの金融規制の緩さが大きな要因の1つであることは間違いない。
----------
ビジネスライター
1960年生まれ。調査官として国税局に10年間勤務。退職後、出版社勤務などを経て執筆活動を始め、さまざまな媒体に寄稿。『脱税のススメ』『お金の流れでわかる世界の歴史』など著書多数。近著に『お金で読み解く世界のニュース』。
----------
(ビジネスライター 大村 大次郎)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「オバマ政権の大失政」が生み出したトランプ現象 告発された「金融業界癒着」「中間層救済放棄」
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 8時20分
-
NISA制度"改悪"で譲渡益に課税の悪夢…エコノミストが「老後はNISAを使ってはいけない」と断言するワケ
プレジデントオンライン / 2024年7月15日 9時15分
-
何かと話題の〈ビットコイン〉、発明者は正体不明の日本人?…いまさら聞けない「暗号資産」の超基本【マネックス証券アナリストが解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月6日 11時15分
-
日本は必ず復活するのだから、買うなら今だ…バブル崩壊で暴落した不動産を海外投資家が買い占めたワケ
プレジデントオンライン / 2024年7月5日 7時15分
-
中国を捨てる富裕層が世界一で過去最多、3位はインド、意外な2位は?
ニューズウィーク日本版 / 2024年6月27日 18時33分
ランキング
-
1立民・野田氏、代表選出馬に慎重=「保守系」望ましい
時事通信 / 2024年7月22日 16時19分
-
25歳娘と52歳父親の遺体見つかる 父親はダムに浮かんだ状態、娘は橋の付け根の土台に横たわる
MBSニュース / 2024年7月22日 19時15分
-
3東海道新幹線の復旧遅れ 「衝突した保守車両、破損ひどく」
毎日新聞 / 2024年7月22日 20時54分
-
4「金を出せ」郵便局に強盗 “刃物”を持った30代くらいの男が現金約150万円を奪って逃走 奈良・下市町
MBSニュース / 2024年7月22日 21時40分
-
5「人によって態度変わる」石丸伸二氏、ビートたけしの前では“借りてきた猫”に批判殺到
週刊女性PRIME / 2024年7月23日 6時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











