「フルボッコされ続けた黒歴史…」日米野球の屈辱晴らしたMVP大谷翔平の試合前の"名スピーチ"に抱く隔世の感
プレジデントオンライン / 2023年3月25日 11時15分
■“銀河系軍団”のガチなアメリカに逆転勝ちで世界一
「本気で勝ちにきているアメリカと世界一を争う真剣勝負の場で日本が勝つ日がきた」
第5回WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)でアメリカに勝って世界一になった侍ジャパン。この快挙に日本列島は今なお歓喜に湧いているが、60年近く野球を観てきた初老のライターにとっては感動とは別の感慨があった。
30年ほど前まで、日本の野球は国内で完結するスポーツだった。最高峰に位置するNPBのチームも選手も目指すはリーグ優勝とその先にある日本シリーズに勝つこと。アマチュアの社会人、学生野球も全国大会で優勝し日本一になることが最大の目標だった。世界一になりたいという者はいなかった。
もちろん世界最高峰の米MLBは野球ファンの誰もが知っていたが、別世界のことのように思っていた。
交流はあった。たとえば親善目的で行われた日米野球。よく知られているのが戦前の1934年(昭和9年)に来たアメリカ選抜チームでベーブ・ルースやルー・ゲーリックといった大スターがプレーし、16勝0敗と圧倒して帰っていった。
戦後も1949年から、ほぼ2年おきにアメリカ選抜やメジャーのチームが来日して、NPBのチームと試合をした。その成績を日本側から見ると、1949年は0勝7敗、1951年は1勝13敗2分、1953年は1勝12敗1分と、まったく歯が立たなかった。同じプロ野球でありながら、フルボッコの状態だったのだ。1960年代から一方的な試合は少なくなり勝利も増えたが、それでも1949~1988年までの20回の日米野球をトータルすると、279戦して63勝196敗20分という散々な成績だ。(90年代以降は28勝43敗8分)
日米野球のほとんどはシーズン後の秋に行われた。長いシーズンを戦った後、観光がてら来日したアメリカのチームにNPBのチームは負けてばかりいたのだ。この頃の日米の実力差は相当のものがあったといえる。
そんなMLBでもプレーした日本選手はいた。日本人メジャー第1号の村上雅則投手だ。南海ホークスに入団して2年目の村上は将来性を買われ、アメリカに野球留学することになった。マイナーリーグの1Aで左の抑えとして好投したことが目に留まり、サンフランシスコ・ジャイアンツと契約。1964年と65年の2シーズン、メジャーでプレーした。
成績を見ると、54試合に登板して5勝1敗9セーブ、防御率3.43。堂々たる成績だが、メジャーに昇格した1964年は1回目の東京オリンピックと重なったせいで、日本ではさほど注目されなかった。野球留学させた南海もメジャーでプレーさせる気はさらさらなく、すぐに日本に連れ戻した。日本で戦力になってもらう方が大事で、MLBでプレーする価値に関心がなかったことがうかがえる。
1977年にはレン・サカタという日系三世の内野手がミルウォーキー・ブルワーズにドラフト指名され、メジャーデビューしたことが話題になった。今回のWBCでは日系2世のラーズ・ヌートバー外野手が日本のリードオフマンとして大活躍して人気者になったが、当時は“日系人”がメジャーリーガーになっただけで日本のメディアやファンは喜んでいた。それほどメジャーは遠い場所だったのだ。
■ターニングポイントは1995年にLA入団の野茂英雄
その一方で、アメリカからNPBに来てプレーする選手はいて、助っ人外国人と呼ばれた。“レベルの高いアメリカからやってきたチームを助けてくれる選手”という意味であり、ほとんどが主軸を務めた。そんな選手でもメジャーのレギュラークラスは少なく、たまにレギュラーとして実績を積んだ選手が来ると、それだけで注目された。
1987年にヤクルトに入団したボブ・ホーナーがその代表格だ。日本では野球関係者もメディアもファンも、メジャーを雲の上の場所と思っていた証拠だ。
日本の野球選手に世界一を目指す選手がいない時代が続いていたと書いたが、アマチュアには世界大会があった。1938年から2011年まで開催されたIBAF(世界野球連盟)ワールドカップだ。
この大会で日本は1度優勝(1980年)、3位に5回なっているが、さほど話題にはならなかった。“真の野球世界一決定戦”と見られていなかったからだ。アマチュア対象(1998年大会からプロ解禁)だったことと、本来なら一番強いはずのアメリカが真剣に覇権を狙ってこなかったためだ。
このワールドカップで強さを発揮したのはキューバで、39回を数える大会で25回優勝。アメリカの優勝は4回に過ぎない。アメリカとしては“野球の世界最高峰リーグはMLB。そこを勝ち抜いた2チームで争うワールドシリーズの優勝チームが世界最強。アマチュアのワールドカップの優勝などどうでもいい”といった意識があるわけだ。
サッカーは世界に強豪がひしめき、FIFAワールドカップで最強国を決めるという図式がある。が、野球の場合はアメリカという揺るぎない1強があり、どこも追いつけないという意識が世界に、もちろん日本にも定着していたのだ。
ところが、そこに風穴を開ける選手が現れた。野茂英雄投手だ。
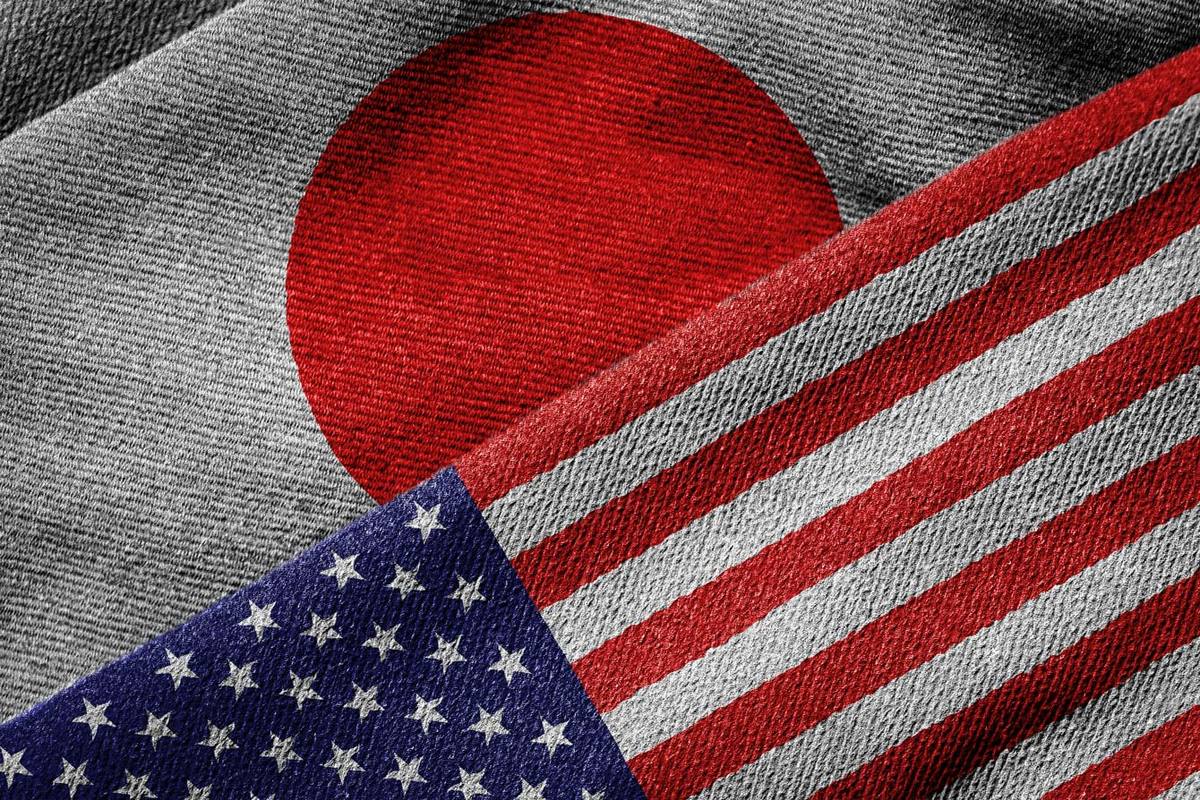
野茂は30年近く前の1995年にロサンゼルス・ドジャースに入団しメジャー挑戦のスタートを切った。この時、日本のファンは「野茂は確かに日本を代表する好投手だが、果たしてメジャーで通用するのか」という目でプレーを見ていた。
しかし、野茂はそんな疑念をことごとく覆す活躍を見せる。メジャー1年目は13勝をあげ、最多奪三振のタイトルも獲得。2年目には16勝しノーヒットノーランまでやってのけた。この活躍に勇気を得た日本人投手が次々とメジャーに挑戦するようになった。
しかし、この時点でも通用したのは投手だからであって、対応力が必要な野手(打者)は厳しいのではないか、という声も根強かった。それを2001年にメジャー挑戦をしたイチローが覆した。
こうした偉大な先人たちの活躍によって、メジャーは雲の上の場所という意識は薄れていく。ただ、彼らが活躍できるのは個々の能力や努力のたまものであって、野球全体のレベルはまだまだ差があるという意識は拭い去れなかった。
■大谷翔平の決勝前の名言「憧れるのはやめましょう」
そんな時期に始まったのがプロも含めて野球世界最強国を決める大会のWBCだ。ご存じのように、この第1回大会(2006年)は王貞治監督率いる日本がキューバを破り、第2回大会(2009年)は原辰徳監督率いる日本が韓国を破って世界一になっている。
この時も日本は快挙に沸いたが、その喜びには若干の割引が混ざる要素があった。本来の実力なら優勝争いに加わるはずのアメリカが第1回大会では第2ラウンド敗退、第2回大会では4位に終わったのだ。
この成績を見ると、アメリカはMLBの一線級を出さなかったのでは、と思われるかもしれないが、そんなことはない。第1回大会は投手では、剛球で知られたロジャー・クレメンスや前年の最優秀救援投手チャド・コルデロがいたし、野手でもデレク・ジーター、アレックス・ロドリゲスといったビッグネームが並んでいた。
第2回も投手では前年17勝のテッド・リリー、野手ではジーターや巧打者ライアン・ブラウンなどがいた。こうした巨大戦力をそろえていながら期待外れの成績に終わったのは、彼らにとって大事なのはMLBでの活躍であり、その前に行われる大会に調子を合わせてこなかったことにあるのだろう。
しかし、WBCも回を重ねるにつれ、アメリカでも重要な大会と認識されるようになっていく。このまま無冠ではいられないと考えられるようになり、第4回大会(2017年)でアメリカは初優勝した。そして連覇を狙って今大会に臨んだ。つまり本気で勝ちにきたMLBの主力選手たちがそろっていたのだ。
アメリカとの決勝の前、大谷翔平が円陣の声出しで語った言葉が注目されている。
「憧れるのはやめましょう」と切り出し、ゴールド・シュミットやマイク・トラウトの名前を出したうえで「憧れてしまっては超えられないので。今日一日だけは彼らの憧れを捨てて、勝つことだけを考えていきましょう。さあ行こう!」(一部抜粋)と続けたのだ。
大谷が生まれたのは野茂がメジャー挑戦を始めた前年の1994年。物心がつき、野球を始めた時にはイチローが活躍し、メジャーに対するコンプレックスは払拭されつつある世代だ。まして大谷自身はすでにメジャーのMVP(2021年)にもなったトップ選手。名前を出したトラウトともフランクに語り合える同僚なのだ。
しかし、「脱・憧れ」という言葉が出るのは大谷ならではのセンスだろう。意識のどこかに、MLBは雲の上の場所、別世界として歩んできた日本球界のことがあり、自分はともかく、共に戦う日本の選手にはビッグネームに対する憧れという思いが芽生え、気後れする部分があるんじゃないかと感じた。また、その奥には自分が目指したMLBに対するリスペクトもあるだろう。だからこそ、大事な一戦の前に、こんなスピーチができたのではないか。
そして、この言葉を聞いた選手たちも、勝つことに集中し、本来の力を出し切れた。

長い間、野球を見てきて、アメリカと日本の実力差を見せつけられてきた身からすれば、この言葉はしみるし、こんなことを言える大谷を改めてすごいと思う。
大谷は試合後、ダルビッシュに「3年後も出よう」と語り、ダルビッシュもその気になったという。優勝が決まる打席で大谷に三振を奪われたトラウトも「まあ、ラウンド1は彼の勝ちってことだね」と語り、さりげなく次回でのリベンジを示唆した。彼らのMLBシーズンでの活躍はもとより、次回のWBCでの対決が楽しみになった。
----------
フリーライター
1956年生まれ。月刊誌を主に取材・執筆を行ってきた。得意とするジャンルはスポーツ全般、人物インタビュー、ビジネス。著書にアメリカンフットボールのマネジメントをテーマとした『勝利者』などがある。
----------
(フリーライター 相沢 光一)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
BS朝日で生中継!オールスター前日の北海道エスコンフィールドで日韓プロ野球レジェンド選手が対決!
PR TIMES / 2024年7月20日 13時45分
-
パリ五輪目前でも盛り上がりを見せない米国 大谷の「出たい」発言が持つ意味とその影響とは
スポーツ報知 / 2024年7月17日 1時40分
-
イチロー、ダルビッシュも苦言を呈した野球のデジタル化「昔より頭を使わなくてもできる」は本当か。大谷翔平は“ビデオゲーム的な選手”の代表格?
集英社オンライン / 2024年7月12日 11時0分
-
巨人が「昭和の大企業」だとしたら、大谷翔平は「シリコンバレーの起業家」 契約金総額1015億円はグローバル資本主義がたどり着いた極致か
集英社オンライン / 2024年7月10日 11時0分
-
WBC球、ロジンの扱い方…岩隈久志の本領を発揮させた松坂大輔のアドバイス【平成球界裏面史】
東スポWEB / 2024年6月23日 9時8分
ランキング
-
1「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て
東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分
-
2扇風機の羽根に貼ってあるシール、はがしてはいけないって本当?【家電のプロが解説】
オールアバウト / 2024年7月21日 20時15分
-
3新型コロナワクチンの定期接種、10月から開始…全額自己負担の任意接種費は1万5000円程度
読売新聞 / 2024年7月21日 19時21分
-
4平日は毎日「レッドブル」を飲んでいます。「1日の飲料代」として高すぎますか? また、体への悪影響はないでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月20日 3時20分
-
5「睡眠の質が悪い人」脳が発するSOSの2つの兆候 自称「ショートスリーパー」ほど注意が必要
東洋経済オンライン / 2024年7月20日 18時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











