なぜ早稲田は「中国人留学生が最も多い大学」なのか…中国人富裕層が「安、安、安」な留学先と話すワケ
プレジデントオンライン / 2023年5月12日 9時15分
※本稿は、中島恵『中国人が日本を買う理由』(日経プレミアシリーズ)の一部を再編集したものです。
■中国人にとって「安、安、安」な留学先
日本に留学している全留学生約24万2000人のうち、ほぼ半数は中国人で、およそ11万4000人(2021年、日本学生支援機構のデータ)に達する。コロナの影響で減少した時期を除くと、日本留学を希望する中国人は過去30年間、増え続けている。
中国で、かつてエリート層の特権だった海外留学は、その後、留学を隠れ蓑にした出稼ぎ、国内の熾烈(しれつ)な受験競争の回避などを目的とするようになったが、経済発展もあって、近年、その目的は多様化、留学生を送り出す家庭も中間層にまで広がっている。
米中対立やコロナの影響もあり、彼らにとって最も身近で、学費が安く、安心・安全、つまり「安、安、安」な留学先が日本となった。
その需要に応えるため、十数年前から東京・新大久保や高田馬場駅周辺に増えてきたのが大学進学希望者を対象とする受験予備校だ。
中国人が日本に留学する際、一般的にまず日本語学校に入学するが、そこで学んだだけでは大学受験対策には不十分。その結果、増えたのが予備校なのだ。
■8割はアルバイトをする必要がない裕福な学生
高田馬場駅付近には在日中国人の間で有名な予備校が10校以上あり、経営者のほとんどが在日中国人だ。留学生にとって、中国人の専任講師や現役の大学院生(アルバイト)などから中国語で直接指導してもらえるメリットがある。
昨今、中国人の苦学生は少なくなり、コンビニなどでアルバイトするのはベトナム人、ネパール人などが増えた。
都内で働く30代の中国人女性は「実感として、私が来日した10年前は8割の中国人留学生がアルバイトしていましたが、今は8割がしていません。隔世の感があります」と話していた。
中には親が買ってくれた高級マンションに住み、一日中、家でゲームをしたり、インフルエンサー(中国語で網紅)として、中国に日本情報などを流しながら、経済的に余裕のある優雅な留学ライフを送っている学生も多い。
■留学先に早稲田大学を選ぶ歴史的な背景
日本で最も中国人留学生が多い大学は早稲田大学だ。
20年5月、中国出身(香港・台湾を除く)留学生受け入れ人数のランキングで1位が早稲田だった(2位は東京大学、3位は立命館大学=日本学生支援機構の調べ)。
早稲田大学のホームページによると、21年の中国人留学生数は3322人で、全留学生のおよそ半数。学部、大学院ともに人数は増え続けている。なぜ早稲田はこれほど中国人に人気があるのか。
以前から中国メディアで報道されてきたのは、早稲田と中国の深いつながりだ。
明治時代に清国から官費留学生13人を受け入れ、日本語教育を行い、1913(大正2)年、のちに中国共産党の創設メンバーとなる李大釗(りだいしょう)が入学した。同じく創設メンバーで、初代総書記に選出された陳独秀も早稲田で学んだ。
そうした経緯もあり、98年には江沢民、08年には胡錦濤という二人の国家主席が来日した際は、わざわざ早稲田を訪問。中国での知名度は急激に上がった。
中国の歴史教科書では日本の明治維新について教えるが、明治政府で活躍したのが早稲田の創始者、大隈重信であり、そこで学んだ留学生が中国共産党を創設したことは、中国人に強く印象づけられている。
■人口減少で偏差値を維持するのが難しい
早稲田について、私の知人関係でいえば、アジア太平洋研究科(大学院)の出身者が多い。多くは女性で、修了後は日本のメディアや商社などに就職した。
数年前に同大学院で学んだ知人の中国人は「早稲田は自由な雰囲気があって好き。メディア出身のリベラルな先生が中国での取材体験などを話してくれて、中国人の先生とは違う視点を学ぶことができました」と話していた。
早稲田自体も過去十数年間、中国人留学生の獲得に熱心に取り組んできた。2015年に同校を取材した際、応じてくれた国際部東アジア部門長の江正殷氏は「私たちは長期計画で努力を積み重ねてきました。今の早稲田の偏差値を絶対に維持しなければならないと考えているからです」と強調していた。
22年秋に取材を申し込み、久しぶりに同校を訪れると、江氏から同じ答えが返ってきた。90年代前半、早稲田の受験者数は約18万人とピークだったが、21年は約10万人と半減した。しかし合格者数は同じだ。
「今後、日本の18歳人口がますます減少すれば、それだけ優秀な学生の獲得は難しくなり、早稲田の偏差値を維持しにくくなると思います」(江氏)
そのため、世界の大学とダブルディグリー制度を実施するなどあらゆる方策を講じ、05年からは中国各地のトップランクの高校と指定校制度を締結している。各校から日本に留学を希望する学生を推薦してもらう仕組みだ。コロナ前は担当者が頻繁に中国に行き、説明会を実施したが、取材時はオンラインで開催していると話していた。
■アメリカ留学に比べて「お得感がある」
早稲田は、他大学と比べて英語で受験可能な学部が多いのが特徴だ。また、もともと英語で授業を行う国際教養学部を含め、全13学部のうち、政治経済、創造理工、基幹理工、文化構想、社会科学の6学部に英語で授業を行うコースが併設されている。
江氏は「日本語受験はコロナの影響を受けましたが、我が校には英語受験ができる強みがある。欧米に行く予定だった優秀な学生が早稲田にシフトしてきています。彼らはアメリカのアイビー・リーグ(アメリカ東海岸の名門私立8大学)に入れるくらいの実力がありますが、米中対立の関係で、以前より日本を選択するようになったのです」と話す。
英語コースがあれば、中国をはじめ、世界各国から留学生を受け入れる間口が広がる。
早稲田の文系で最も学費が高いのは国際教養学部で年間約160万円だが、他学部の英語コースは普通コースと学費はあまり変わらない。
そのことから、「お得感があると思います。アメリカの大学の学費は少なくとも3~4万ドルで生活費も高いですが、日本は学費も生活費も格安。しかも治安もよく、距離的に中国に近いことも学生や保護者にとって魅力的な要素です」(江氏)

■競争率が10分の1以下の日本で付加価値を上げる
国際課の関係者もこう話す。
「競争が激しい中国では、アメリカ留学だけでは差別化しにくいので、そこにプラスして日本にも留学するというのは、学生にとって大きなアドバンテージになります。また、一般論として、同じくらいの学力であれば、母数が多くて競争率が高い中国よりも、日本など海外に行ったほうが、ワンランク上の大学に進学できる可能性が高い、と考える学生もいます」
ある学生は、高校の成績が北京市内の上位校の一角である北京師範大学(日本でいえば筑波大、東京学芸大などに近いイメージ)に届かないくらいだったが、英語受験によって、実力よりも偏差値が上の早稲田に合格できたそうだ。
考えてみれば当たり前の話だが、人口が中国の10分の1以下の日本のほうが中国より競争率は低い。レベルの高い大学で、自分の付加価値を少しでも上げたいと望む中国人にとって、幼い頃から学んできた英語で受験できるいい学校が日本に増えれば、そちらを選ぶケースも増えていくだろう。
中国人の高校生を日本に留学させようと奮闘している人がいる。上海や深圳などで学校経営をしている信男(しんなん)国際教育グループ理事長の魯林氏だ。
魯氏は日本式の教育に感銘を受け、中国に「信男教育学園」を創立した。独自に学校を作るわけではなく、上海文来高校、深圳第三高校、長沙市明達高校など既存の高校に「中日班」という特別クラスを設置している。
■日本の教育は小、中、高校が「とくにすばらしい」
学生は「中日班」で日本の高校のカリキュラムを2年間学び、日本の高校2年の2学期(9月)に、日本各地にある32校の提携校に編入するという仕組みだ。通常なら中国の高校を3年間で卒業し、日本の大学に留学する「3+0」が、魯氏は中国で2年、日本で1年半勉強する、自身が考えた「2+1.5」にこだわる。そこには、ある思いがある。
「私は日本の小、中、高校、つまり大学以前の教育がとくにすばらしいと思っています。私自身も九州大学で学んだ留学経験者ですが、日本人の挨拶、掃除、整理整頓、クラブ活動、給食当番、時間を守ることなど、規律正しい生活を中国の若者たちに学んでほしいと思ってきました。成人前に日本の教育を受ければ、より日本文化や社会を理解しやすくなると思うからです。
大学からの留学だと半分大人になっています。集団行動が減り、日本人との交流も限られ、学問以外、『日本社会』について学ぶ機会は少なくなる。大学生は誰にも干渉されませんから、個人の考え方によって生活はかなり変わってしまいます。
高校の途中からでも日本式教育を受ければかなり違う。自立した人間を育てられるし、日本人から受ける刺激も多くなる。担任の先生もいます。そう考えて、このような仕組みを考えました」
■中国では家も車も親が世話してくれるが…
これまでにのべ1000人以上の学生が日本の高校に編入した。そのほとんどが指定校推薦を受けて、日本の大学に合格している。魯氏はいう。
「日本人と集団生活を送り、クラブ活動を行ったりすることで、自然と礼儀正しくなると思います。ある保護者は、子どもが中国に戻ってきたとき、自分から祖父母へ挨拶に行ったり、家事を手伝ったりしてくれて、親の苦労もわかるようになったと喜んでいました。
中国では成績はまあまあだったが、日本で人間的にも、学力面でも成長し、筑波大学に合格した学生もいます。私が最も感じるのは、1年でも早く若いうちに日本を経験することで、自立した人間になることです。自分のことは何でもできるようになります」
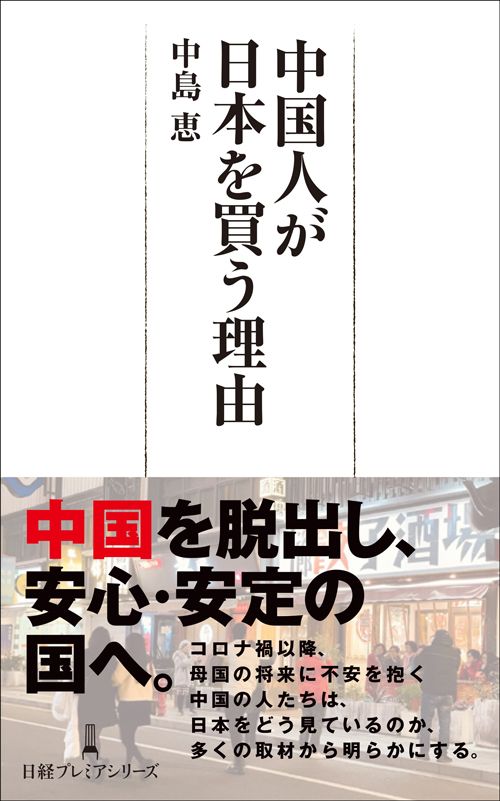
「日本に来たから自立できた」という話は複数の中国人から耳にした。東北地方の高校を卒業後、来日して10年になる30代の中国人はこう語る。
「ずっと中国に住んでいたら、親が家も車も買ってくれただろうし、世話もしてくれる。いい面もありますが、困難に直面したとき、自分で解決できない人間になってしまったかもしれません。
日本にいても中国の親を頼る人はいますが、せっかく留学したので、自分のことは自分でやろうと思い、病気で入院したときも、心配をかけるので親には連絡せず、退院するときもひとりでした。心細かったですけど、自信がつき、自分で何でもできるようになりました」
----------
フリージャーナリスト
山梨県生まれ。主に中国、東アジアの社会事情、経済事情などを雑誌・ネット等に執筆。著書は『なぜ中国人は財布を持たないのか』(日経プレミアシリーズ)、『爆買い後、彼らはどこに向かうのか』(プレジデント社)、『なぜ中国人は日本のトイレの虜になるのか』(中央公論新社)、『中国人は見ている。』『日本の「中国人」社会』(ともに、日経プレミアシリーズ)など多数。新著に『中国人のお金の使い道 彼らはどれほどお金持ちになったのか』(PHP新書)、『いま中国人は中国をこう見る』『中国人が日本を買う理由』(日経プレミアシリーズ)などがある。
----------
(フリージャーナリスト 中島 恵)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「三つ子で1人だけ浪人した」彼が2浪で掴んだ道 次男は早稲田、三男は米国の大学に進学したが
東洋経済オンライン / 2025年2月9日 9時0分
-
【海外医学部への道】アメリカ、イタリア、ハンガリー、中国など7カ国の海外医学部の特徴を公開
@Press / 2025年2月7日 9時30分
-
欧米に続き日本でも「不法移民」の問題がかまびすしいが、合法で来日している留学生にも「ある疑惑」が持ち上がっている
PR TIMES / 2025年2月4日 18時45分
-
「京大3回不合格」20歳上彼女に振られた彼の変化 浪人を重ねたことで、彼が学んだこととは?
東洋経済オンライン / 2025年2月2日 8時0分
-
北海学園が留学生との交流イベント「Multilingual Meetup」を開催 ― 1月23日「Chinese Day」、24日「Korean Day」
Digital PR Platform / 2025年1月14日 20時5分
ランキング
-
1義理チョコは「人間関係の潤滑油」? 義理でもうれしい…“義理チョコ文化”に対する男性の“本音”
オトナンサー / 2025年2月10日 20時10分
-
2「めっちゃうま!」セブンで買える、SNSで話題のスイーツ3選。贅沢気分に浸れる美味しさ。
東京バーゲンマニア / 2025年2月10日 18時3分
-
3「油」で生理痛やPMS解消、栄養士が教える上手な“選び方”と“とり方” 注目は「カメリナオイル」
週刊女性PRIME / 2025年2月11日 6時0分
-
4「コンビニおにぎり」各社の人気ランキング、1位は? - おにぎり協会調査
マイナビニュース / 2025年2月10日 13時53分
-
5疲れるのは夏だけじゃない!? - 冬の疲れの原因、乗り切るための対策とは
マイナビニュース / 2025年2月10日 12時33分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










