「この国って、ほんとうに民主主義なのかな」インドに赴任した外交官のあまりに率直で極めて深い問い
プレジデントオンライン / 2023年5月15日 9時15分
※本稿は、伊藤融『インドの正体「未来の大国」の虚と実』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。
■インドは「理想的なパートナー」なのか
(2022年3月19日『インディアン・エクスプレス紙(インド)への岸田総理大臣寄稿』)
わが国でインドとの関係の重要性が語られるとき、かならず登場するのが「基本的価値観の共有」という前提だろう。中国や北朝鮮、ロシアはどうみても独裁・権威主義体制だ。現在の韓国とは自由民主主義体制で親和性があるとしても、歴史認識ではわが国と大きな隔たりがある。こうした国々の向こう側にある大国インドは、われわれにとって理想的なパートナーのように映る。
なぜか? まずなんといっても、インドは日本同様、第2次大戦後のアジアにおいて、一党独裁や軍事政権を経験したことのない稀有な国だからである。韓国や東南アジアの多くの新興独立国は、経済成長を錦の御旗にした「開発独裁」の道を採用した。けれどもインドは違った。その貧しい独立当初から、民主的な選挙を連邦、州、地方、村落のあらゆるレベルでつづけてきたのだ。たとえ一時であっても、ひとびとの生活を犠牲にするような政治が行われれば、そんなリーダーは選挙で淘汰されるはずだ。インド人のノーベル経済学賞受賞者、アマルティア・センは、独立後のインドにおいては中国などと違い、飢饉が起きたことはないとして民主主義の意義を評価している。
■中国リスクがインドへの評価を高めた
もちろんその結果として、上からの開発を強制的に推し進めた他国に比べて、インドは国家レベルの発展が遅れたのではないか、という議論もありえよう。大規模な外資でもって、農民から強制的に土地を買収し、空港や道路、電力施設、工場などを一気に建設するといったようなことは、この国では過去から今日に至るまで起こりえない話だ。トップを抱き込みさえすれば、なんとかなる国と比べると、この巨大な民主主義国でのビジネスは、一筋縄ではいかない。
それでもインドが評価されるのはなぜか? それは自由民主主義の価値が、冷戦終焉により普遍化したと思われたにもかかわらず、その価値と相容れない中国の台頭がもたらすリスクを、西側の政治・経済の指導者がひろく認識しはじめたことによる。レアアースや半導体を中国に依存したサプライチェーンがいかに危ういものであるか、それはいまや多くの関係者が実感しているであろう。その意味で、中国とは対極にある、われわれと価値を共有すると思われる大国との関係が重要だと論じられるようになった。
■「世界最大の民主主義国インドへようこそ」という看板
この点でインドは、政治では独立以来、一貫して民主主義を守ってきた国だ。同じ英領インドから誕生したパキスタンは、これまで何度もクーデターを経験し、長期にわたって軍事政権がつづいた。そのパキスタンからインドに陸路で入ると、「世界最大の民主主義国インドへようこそ」という看板が出迎えてくれる。自分たちは中国やパキスタンとは違い、民主主義国なのだというのは、インド人の誇りのようだ。
ただ、経済では、この国は長年にわたって閉鎖的で、社会主義的混合経済といわれる体制に固執してきたのも事実である。しかしそれも、1991年に大規模な自由化が行われ、規制緩和や外資の導入が図られた。その後も、経済自由化の流れは変わらなかった。とくに2014年に発足したモディ政権下では、製造業、卸売業、保険業、国防産業など、多くの分野で外資規制の撤廃や緩和が進んだ。いまや、政治だけでなく、経済体制においても西側にとって好ましい国になってきたのである。
■反日感情もインドには存在しない
アジアの一部で依然みられるような反日感情も、インドには存在しない。戦時中、日本軍はインド北東部のインパールへの侵攻を試みたものの、大失敗に終わった。結局、日本がインドを支配することはなかった。独立の父、マハトマ・ガンディーはたしかに、日本の中国支配や、ドイツ、イタリアとの三国同盟に疑問を投げかけた。ただそのガンディーも、ロシアに抗し、独立運動にとっての直接の敵であるイギリスと戦う、日本への期待感をのぞかせることもあった。さらにチャンドラ・ボースのように、日本軍と手を携えて独立をめざすインド国民軍の動きもあった。先の大戦をめぐっては、わが国は同盟国アメリカとのあいだでさえ、原爆投下や東京裁判などをめぐって、歴史認識を共有できているとはいいがたい。
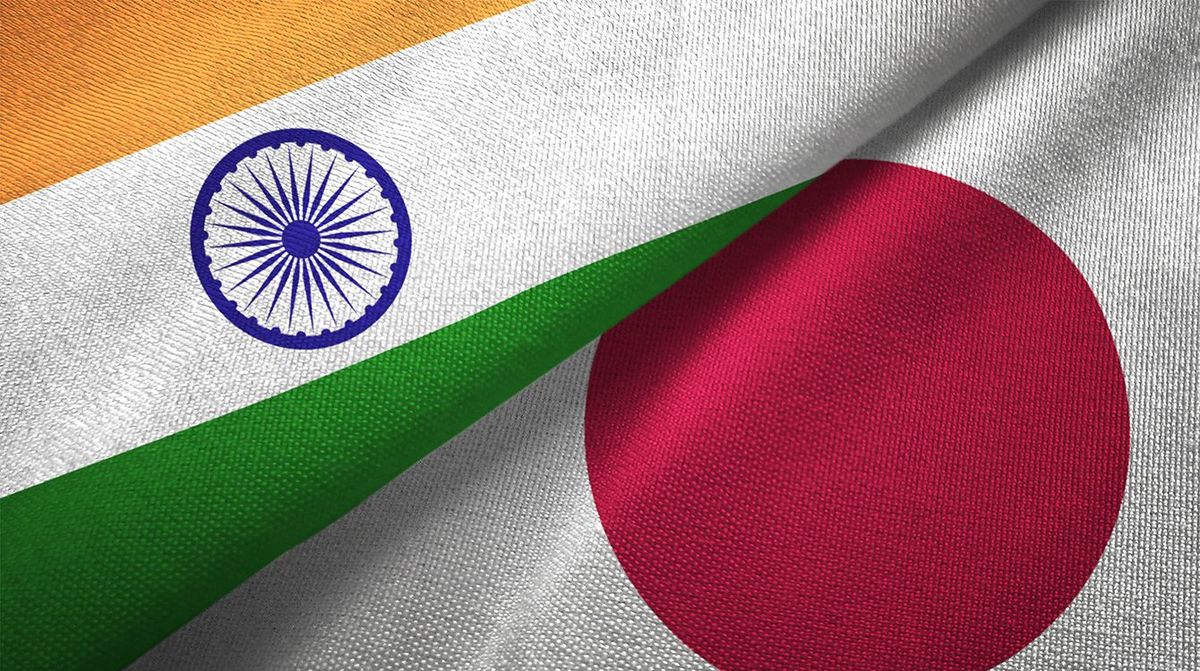
そう考えると、インドほど、日本にとって価値観の一致する国はないようにみえる。
■「いかにインド人を黙らせ、日本人に喋らせるか」
これに対して、われわれがインドと価値観を共有している、というストーリー自体に違和感をもつ向きもあるだろう。そもそもインド人は、日本人とは対照的に自己主張が強いことで知られる。国際会議の司会者は、「いかにインド人を黙らせ、日本人に喋らせるか」が成功のカギだという有名なジョークもある。日本人からすると、あのヒンディー語訛りの英語、「ヒングリッシュ」で、堂々と、そして延々と話しつづける精神は理解しがたいところがあるだろう。

しかも、しばしばインドの指導層や有識者からは、「われわれは世界大国へ向かっている」などといった声も聞かれる。ときに傲慢とすら感じるほどの自信に満ちた物言いの背景には、自分たちの文明や歴史に対する強い誇りがうかがえる。なんにおいても控えめで、自信がなく、周りに配慮することを美徳とする日本人とはかなり違っている。
■カーストは「4階級」だけではない
また、かつて社会人類学者の中根千枝が、名著『タテ社会の人間関係』のなかで看破したように、日本とインドは集団意識も対照的だ。インドの集団概念としては、なんといっても「カースト」が大きな意味をもつことは、よく知られている。
日本では、カーストといえば、司祭階級のバラモン、武士階級のクシャトリヤ、商人階級のヴァイシャ、農民・サービス階級のシュードラの4階級と、その「枠外」におかれる不可触民のダリトの身分制を指すと考えられているようだ。これはカーストにおけるヴァルナと呼ばれる仕組みだ。
しかし、現実のカーストはそれだけではない。むしろ、インドの多くのひとびとが意識するカーストとは、大工とか漁師、羊飼い、洗濯人(ドービー)といったような、数千ともいわれる職業と結びついたジャーティである。婚姻も同じジャーティのなかで行われることが多く、ジャーティはインド人のカースト意識の中核にあるといってよい。
■身分差別や女性への暴力も残っているのではないか
中根は、会社のような「場」への所属を重視する日本とは対照的に、インドのカーストは「資格」の一種であり、同じ「資格」をもつ者のあいだでは対等だという意識が強いと結論づけた。たしかに、研究会で若手研究者が大御所に対してモノ申す、という光景は、インドではそう珍しくない。日本であれば、「空気を読まない奴」と切り捨てられるのだろうが。どうみても、日本人とインド人のあいだには、同じ「アジア人」として括ることができないほどの違いがある。
民主主義とか自由といった社会的な価値観を共有しているかどうかとなると、もっと疑わしいと思うかもしれない。インドは古くからのカースト制にもとづく身分差別が根強く、女性に対する暴力もまん延している社会なのではないのか? 中国やパキスタンなど他国に対してだけでなく、国内で異論を唱えるようなひとびとに対しても、すぐに銃口を向けるような国ではないのか? 自由化したとはいっても、長期にわたった規制だらけの社会主義経済の影響が色濃く、根本的にはいまでも腐敗や汚職がはびこる体質は、変わっていないのではないか?
■片手を失った老人が車の窓を叩いて物乞い
そういった問いは、インドに行ったことのない人でも、なんとなく浮かんでくるだろう。しかし実際に旅をし、暮らし、働いてみると、その疑問は解消されるどころか、さらに大きくふくらむようだ。筆者自身、今世紀初めにニューデリーの日本大使館で勤務していたとき、片手を失った老人が車の窓をトントンと叩いて物乞いをする姿を、毎日同じ交差点の真ん中で目にしたが、そのたびに、「この社会はどうなっているのか」と胸が締め付けられるような憤りを覚えたことを思い出す。また、初めてパキスタンとの係争地であり、分離武装勢力の活動するカシミールを訪れた際には、数十メートルおきにライフル銃を構えて並ぶ兵士の姿、抗議の声をあげる若者を容赦なく棒で殴りつける警官をみて背筋が寒くなった。

私が赴任して1年半ほどたったころのことだ。私の直属の上司にあたる政務班長が新たに着任してきた(ちなみにこの班長はその後、複数の国で大使を歴任された方である)。家探しや挨拶回りで外出先から帰ってきた彼は、執務室に入るなり大きなため息をついて私にこう問いかけた。「伊藤さん、この国って、ほんとうに民主主義なのかなあ?」キャリア外交官のあまりに直截な問いに、まわりの館員からは思わず笑い声があがった。しかし、よく考えてみると、深い問いである。永田町や霞が関で語られる「民主主義国インド」と、現場の姿には相当の乖離があったのだろう。
■「生まれ」を甘受して暮らしてきたひとびと
この問いを投げかけられたころには、私は毎日出会う、あの老人のまなざしから自分なりの答えらしきものを感じ取っていた。私が勝手に心の底で期待していたような、社会や政治に対する憤りのようなものはそこにはなかった。それはみずからの運命を受け入れつつ、そのなかで日々を精一杯生きていこうとする姿のように思われた。
ここで、カーストについてもう少し詳しく触れるべきだろう。
よく考えてみれば、インドにおけるカーストは「生まれ」であり、ひとびとは長く、みずからの置かれたその「生まれ」を甘受して暮らしてきた。それはさまざまな矛盾を抱えた巨大な国のなかで、社会を安定化させる装置として、つまり社会秩序として機能してきたのではないか。だとすれば、現代のわれわれの目線からは、議会や政府の失政、あるいは不作為に映る貧困や差別が、インドの誇る民主主義制度と共存してきたとしても不思議はない。
■民主主義を「目的」として捉える傾向
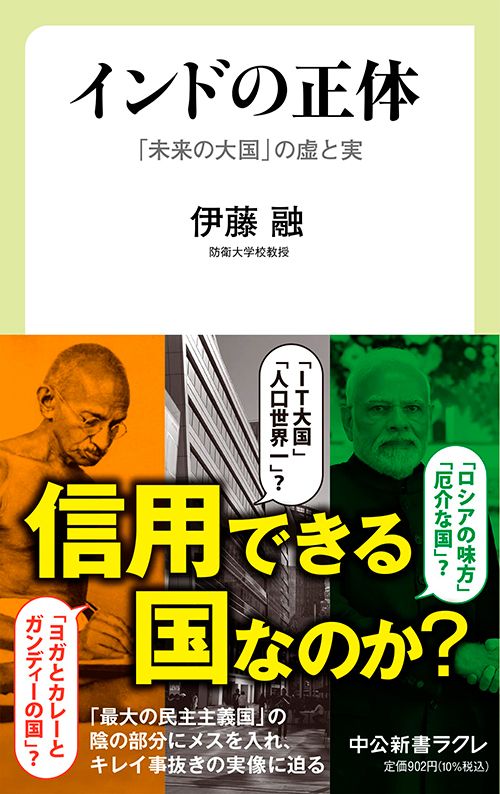
長くインド政治を研究してきた広瀬崇子が指摘するように、インドでは民主主義を、生活を改善する「手段」としてとらえるよりも、それ自体を「目的」としてとらえる傾向が強かった。言い換えれば、民主主義にとって大切なのは、選挙などの手続き・制度なのであって、それさえしっかりしていれば、自由や平等が達成されたかどうかは問題にならない、という話だ。
もっとも今日では、識字率を含め、教育の進展やメディアの普及に伴って、ひとびとの意識には徐々に変化も生じている。いくつかの州においては被差別・後進カーストを基盤にした政党が台頭した。最貧困州として知られるビハール州の農村を研究した中溝和弥は、選挙によって最底辺のひとびとが政治権力を奪取する「下剋上」が起きたと論じている。インドでも、自分たちの暮らしを良くするための政治参加という考え方が広がりつつある。
----------
防衛大学校教授
1969年広島県生まれ。防衛大学校人文社会科学群国際関係学科教授。中央大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程後期単位取得退学、博士(学術)。在インド日本国大使館専門調査員、島根大学法文学部准教授等を経て2009年より防衛大学校に勤務し、21年より現職。『新興大国インドの行動原理 独自リアリズム外交のゆくえ』(慶應義塾大学出版会)など、インド外交や南アジアの国際関係に関わる著作多数。
----------
(防衛大学校教授 伊藤 融)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
ニュースの核心 トランプ氏、きょう銃撃後初演説 大統領復活ならアジアに重点シフト、日本に「憲法改正」迫るか 鍵握る〝強硬派〟バンス氏
zakzak by夕刊フジ / 2024年7月19日 11時34分
-
インド株式が堅調な理由は?10年後の株価水準をイメージする(香川睦)
トウシル / 2024年7月19日 7時0分
-
トランプもバイデンもイスラエルを支援する理由 聖書と冷戦が生んだ米国とイスラエルの同盟
東洋経済オンライン / 2024年7月17日 9時0分
-
社説:印のモディ政権 後退招いた強権、脱却を
京都新聞 / 2024年7月4日 16時0分
-
「反共主義」のためならナチスの残党も利用する…長らく"孤立主義"だったアメリカを大きく変えた「2つの脅威」
プレジデントオンライン / 2024年6月25日 9時15分
ランキング
-
1蓮舫氏は「都知事選で惨敗した人」で終わるのか…二重国籍問題以上に致命的な"政治家としての最大の欠点"
プレジデントオンライン / 2024年7月20日 9時15分
-
2「警察に関係なかろうが!」自衛官が警察官に暴行で逮捕 直前に飲酒した状態で自転車運転か
RKB毎日放送 / 2024年7月20日 13時40分
-
3大型の台風3号(ケーミー)発生 暴風域伴い沖縄に接近するおそれ 進路に注意
ウェザーニュース / 2024年7月20日 16時0分
-
4海自墜落ヘリの主要部分発見 水深5000m超、無人探査で
共同通信 / 2024年7月20日 11時49分
-
5米海兵隊、週末の飲酒検査を強化 国内全基地で 性的暴行事件受け
毎日新聞 / 2024年7月20日 16時51分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











