これでは光源氏に雑に扱われても仕方ない…紫式部が『源氏物語』で「最も愚か」と描いた女性の特徴
プレジデントオンライン / 2023年6月9日 15時15分
■光源氏は多様な種類の女性と関係を持った
源氏は何人かの妻を、次つぎとめとったが、その間にも様ざまな情人を持った。
それは彼が人並み外れた多情な男だったというより、当時の貴族社会の風習であった。
ただ作者紫式部が、恐らく自分の満たされない欲望を空想のなかで解き放って作りあげたこの小説の主人公は、行状そのものは当時の風習に従っているとしても、恋愛におけるその心の放蕩ぶりは、いかにも女性向きにできている。そこのところが興味深い。
まず、第一に源氏は様ざまな型の女性のあいだを遍歴している。男性によっては、その理想の女性の型はひとつだけで、何人、情人を持っても妻と同じ型の女である、という場合があるが、源氏はその正反対で、ほとんどあらゆる型の女性に関心を持ち、いわば自分のその恋の多様性そのもの、ひとりひとりの女の違いそのものを愉しんでいる。
■紫式部は源氏に「愚かな女」を冷淡に扱わせた
第二は、作者自身が、好きな女と嫌いな女との間に差別を立て、そして主人公源氏に、その差別に従って愛情の度合を左右させている。
作者が軽蔑しているのは、愚かな女である。そして、女は愚かさによって、男から冷淡に扱われても仕方ない、と突き離している。
■「抱かれるまで眠りこけている女」を愚かだと描いた
源氏は雨夜の品定めの翌日、方違に行って老いたる地方官の若妻、空蟬を知り、彼女に夢中になったのだったが、一度、無理じいされたあとの空蟬は、源氏のいうなりにならない。
そのために源氏はいよいよ強くこの中流の女に惹かれていって、ある晩、とうとう彼女の寝室に忍びこんでしまう。そして、そこに寝ている女と関係するのだが、途中でそれが目ざす女でなく、宵のうちに彼女と碁を打っている姿を隙見した、空蟬の継娘であることに気付いた。
その娘、軒端(のきば)の荻(おぎ)は、快活で軽薄で、華やかな女だった。肉感的な、今日でいえばグラマーであった。それは継母空蟬のつつましやかで知的なのとは、正反対で、男の軽い浮気心をそそる。
だから源氏は相手を間違えたと気が付いた途端に、自分の気持を浮気心にとり換えて、彼女と関係を結んでしまう。
作者はこの女を、男が忍んで来て抱かれるまで眠りこけているような愚かな女として描き、そうしてその後は源氏に極めて冷淡にこの女を扱わせている。
女が愚かなのだから、仕方がないだろう、と作者はいおうとしているように見える。
彼女はその後、別の男と結婚したのだが、源氏はその婿が相手の処女でないことに気付いても、最初の男が源氏であると判れば諦めるだろうと、いい気なことを考えている。この場合の源氏は甚だ厭味な男だが、作者としては主人公の厭らしさに気付いていないくらい、軒端の荻をばかにしているようである。
魅力の少ない女は、つつましく身を退いている方が賢明で、軒端の荻のように有頂天になるのはみっともない、というのが紫式部の考え方らしい。
■特別な美貌を持ち合わせなかった花散里の生き方
軒端の荻と対照的なのは、花散里(はなちるさと)である。
彼女の姉は、源氏の父桐壺帝の女御のひとりだったが、子供もなく後見者もないので、父帝の崩御のあとでは、源氏が世話をしていた。妹の花散里とは源氏は、姉の女御が後宮で暮していた時に、情人の関係になっていた。
しかし彼女は特別な美貌でもなく、才気もなかったから、源氏は特に彼女を深く愛していたわけではない。が、花散里は軒端の荻のように、はしたない女ではないから、世にもすぐれた恋人に対して、自分の分を守ろうとした。
その出過ぎない態度が、源氏には快く、時おり、姉の女御を見舞うついでに、同居している妹の方をも訪問するようにして、関係が続いていた。
そうして、やがて彼女は源氏の本邸二条院に引きとられ、「夏の御殿」が与えられた。(「春の御殿」が紫の上、「冬の御殿」が明石の上であるから、ずいぶん、彼女は優遇されているわけである)
彼女はそうして正式に源氏の妻のひとりとなったわけであるが、そうなるとなおさら彼女は控えめになり、源氏一家という大家族のなかで、専ら家政婦のような役割に自分を限定した。彼女は源氏と、肉体的な関係は断ち、そうして源氏の子供の夕霧を育てたり、さらには夕霧の成人後は、今度は彼の娘を養女にして世話をしたりした。一家の衣類の面倒をみたりするのも、彼女の仕事だった。
こうしたつつましさによって、彼女は源氏にとって、不可欠な女性となることに成功した。
作者もそうした彼女の生き方に、明らかに好意を見せている。
しかし、現代の女性たちにとっては、軒端の荻の、自分の感情を率直に表現したり、嬉しい時には浮きうきしたりするのは、かえって好ましいかもしれず、花散里の生き方は、もどかしくも、時には狡くも感じられるかもしれない。
■朧月夜と朝顔の対照的な愛欲のあり方
そういう魅力の少ない女性とは逆に、激しい情熱に源氏を狂わせてしまう女たちもいる。
そのなかで最も対照的な一組を選ぶと、朧月夜(おぼろづきよ)の尚侍(ないしのかみ)と、朝顔(あさがお)の斎院である。朧月夜はその肉体によって源氏を夢中にさせ、彼の人生を動顚させてしまうし、朝顔は最後まで源氏に身を許さないことによって、やはり彼の家庭生活に波乱を生じさせる。これは両極端なひと組である。そしてその共通点は、源氏を徹底的に支配し、前後を忘れさせてしまったという点である。
男に身を許してしまったら女の負けであるという説が世間にはある。また、逆に、男女の仲は結局、肉が関与しなければ続くものではない、という意見も一般化している。しかし、朧月夜と朝顔との場合を見ると、男は相手の女の肉を知ればしるほど深く溺れていくということもあり、また、逆に拒否されればされるほど惹かれていくということもある、という真実が見られる。
つまり、両極端の通説が、相手の女次第でどちらも否定されるような恐ろしい事態が発生する、ということで、男というものはなんと弱いものであるか、ということにもなり、そのように弱くなって女の自由になっている瞬間の男は、あるいは彼の生涯のなかで最も幸福な状態にいるかもしれないとも思われる。それが愛欲の不思議さというものだろう。

■源氏を失脚させるほどの「危険な恋」
源氏が朧月夜を知ったのは19歳の時だった。そしてその関係は50歳近くまで、30年間にわたって断続して続くのである。
宮中の桜の宴の果てた後、若い源氏は酔った勢いで後宮の庭をさまよい歩いているあいだに、ひとりの見知らぬ高貴の娘が「朧月夜に似るものぞなき」と古歌を口ずさみながら通りかかった。春の夜の宴会のあとで、心の浮きたっている娘に闇のなかで出会う。それは浮気心をかきたてるすべての条件が、そこに集中したようなものである。
源氏は娘を一室に抱きこみ、そのまま深い仲になる。別れる時にお互いの扇を取り換えて、名前は知らせずに立ってしまう。いかにも一時のはかない浮気心にふさわしいやり方である。
ところがこの一時の出来心が、それだけでは終らなかった。
その女は、源氏の兄帝のところに入内することに決っており、しかも彼女の姉は宮中を支配していた弘徽殿(こきでん)の女御で、彼女の一族は源氏を政治的に敵視して、失脚させる機会を狙っていたのである。それなら2人は関係を断ってしまえば安全なのに、女は兄帝の寵姫となった後も、積極的に源氏を迎え入れた。
そうして隙をみては、あるいは宮中で、あるいは女の私邸で、危険きわまりない密会が続けられ、ある日、とうとう彼女の父に現場に踏みこまれてしまう。
こうなっては、源氏の保身の唯一の手段は、都を離れることである。そうして彼の須磨流遇の時代がはじまる。つまり、この女の官能の魔力が、とうとう男を社会的に失脚させてしまったのである。
源氏の兄帝はしかし、この朧月夜を愛していた。そして源氏に対する彼女の想いも知っており、寝室のなかでも源氏のことをいい出しては、彼女を苦しめた。帝は一方で弟の源氏をも深く愛しているのだから、優しい帝の態度は、なおさら彼女にはつらかった。
それなのに、源氏が政治的に復活して帰京すると、2人の関係も復活してしまう。その愛欲の強さは、理性の力をあざわらっているように思える。
■処女のまま一生を終えた朝顔の斎院
一方の朝顔はやはり源氏がまだ空蟬などを知るまえから想いを寄せていた女性である。
しかし女は彼に許さなかった。父親は2人の仲を認めようとしていたにもかかわらずである。
そのうちに、女は斎院になる。厳重に処女を守らなければならない身分である。にもかかわらず、相変らず源氏は彼女にいい寄っているという噂が流れる。この噂も源氏の須磨流遇の理由のひとつとなった。
やがて女はまた世俗の人に戻る。源氏の恋心は燃え上るばかりである。ついには彼は最も愛していた正室紫の上をさえ避けて、宮中でばかり暮し、もっぱら朝顔を口説きつづけることが、唯一の仕事のようになってしまう。
源氏の従者たちまで、主人の好色を苦々しく思うまでの乱れぶりであった。
あまりはしたない露骨な嫉妬を示さない紫の上さえ、怨み言をいいはじめる。しかも女は源氏になびかない。
朝顔は意志の強固な、そして、珍しく物事を冷静に眺めることを知っている女性であった。恋に身を任せ、情の命ずるままに行動するのが普通であったこの時代に、源氏の恋心の真剣であることを知りながら、また源氏の男性的魅力には惹かれながら、しかも、父も願い、父の亡きあとは彼女の周囲の人々に強く受け入れるようにすすめられながらも、最後まで源氏を拒否しつづけた。そうして処女のまま一生を送った。
■「源氏が愛する多数の女の一人」になりたくなかった
どうしてだったのだろう。――彼女は源氏の魅力に抗いがたく惹かれていた。しかし同じ魅力が当然、他の女性をも陥落させてしまうことも判っていた。
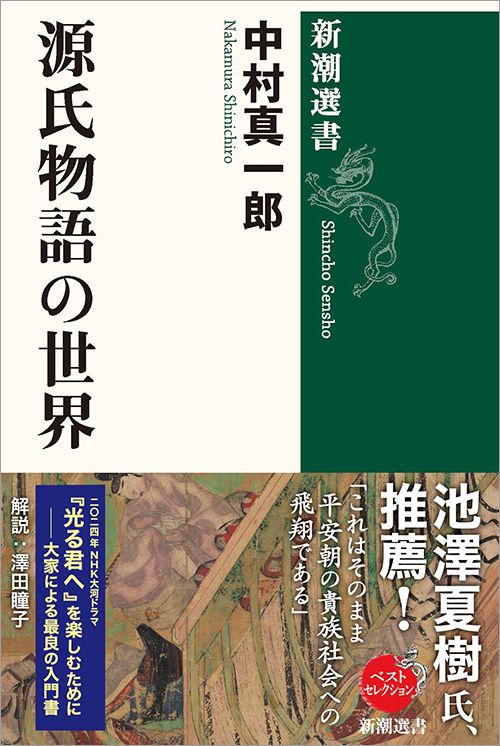
現に彼女の眼のまえで次つぎと源氏を巡る女たちの悲劇が展開していた。彼女はあの葵の上と六条御息所との車争いの事件の目撃者でもあった。
彼女はそうした女たちのひとりになりたくなかったのである。
それでいて、稀に面会することがあると、誇り高い源氏が我を忘れてしまうようなことになるのは、彼女自身が余程、魅力のあった女性だということになる。
源氏は誇りを傷つけられたから意地になって征服しようとした、というのではない。抗いがたい吸引力によって惹きつけられ続け、やはり朧月夜の場合と同じように、実にこの情熱は30年間、長持ちした。
それはやはり、朧月夜の場合と正反対でありながら、理性を超越した愛欲の力のものすごさを物語っている、というべきだろう。
そうして、源氏は一生の間、ついに我がものとすることのできなかった朝顔のことを思うたびに、甘美な苦しみが胸を満たすのを感じたことだろう。
----------
作家
1918(大正7)年、東京生まれ。東京大学仏文科卒。1942年、福永武彦らと新しい詩運動「マチネ・ポエティック」を結成。1947年『死の影の下に』で戦後文学の一翼を担う。「春」に始まる四部作『四季』『夏』(谷崎潤一郎賞)『秋』『冬』(日本文学大賞)、『頼山陽とその時代』(芸術選奨文部大臣賞)『蠣崎波響の生涯』(読売文学賞、日本芸術院賞)『私のフランス』など多数の著書と訳詩書がある。『源氏物語の世界』のほか『王朝の文学』『王朝文学の世界』『私説 源氏物語』など平安期文学についての著書も多い。1997年没。
----------
(作家 中村 真一郎)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
【光村推古書院】美しいビジュアルと、古典文学・歴史学・考古学、それぞれの分野からの考察で紫式部の生きざまに迫る『史実でたどる紫式部 ――「源氏物語」は、こうして生まれた。』を7月20日(土)に発売。
PR TIMES / 2024年7月18日 13時40分
-
なぜ『源氏物語』は男女の色恋沙汰ばかりなのか…平安時代の宮廷が紫式部たち"女房"を重用したワケ
プレジデントオンライン / 2024年6月30日 18時15分
-
定子の面子崩す「道長の策略」まさかの人物の憤慨 道長と近しい人も、数々の行いに苦言を呈した
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 12時30分
-
「千年古びない浮気描写」の妙を角田光代と語る 源氏物語の新訳に挑んだ5年がもたらしたもの
東洋経済オンライン / 2024年6月25日 9時0分
-
光源氏の浮気心に翻弄される女、それぞれの転機 「源氏物語」を角田光代の現代訳で読む・葵①
東洋経済オンライン / 2024年6月23日 17時0分
ランキング
-
1大谷翔平&真美子さんのレッドカーペット中継に… 人気アイドルが「思いっきり映ってる」と話題
Sirabee / 2024年7月18日 15時40分
-
2「縁起の良い数字」のナンバープレートとは? “13種類”の人気番号ってなに? 「358」の気になる意味は?
くるまのニュース / 2024年7月19日 21時10分
-
3毎日テレビをつけっぱなしで寝る夫。年間どれだけ電気代を損している?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月18日 8時50分
-
4義母と元夫は減塩生活中!? 嫁に去られた親子の今…【お義母さん! 味が濃すぎです Vol.48】
Woman.excite / 2024年7月15日 21時0分
-
5「風呂の温度がぬるい!」小柄な女性バイトを狙ってクレームをつける50代男性。県内全てのスーパー銭湯を出禁になるまで
日刊SPA! / 2024年7月19日 8時54分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











