膣に猛毒を持つ虫の死骸を詰め込む…古代ギリシャの女性が「生理」を乗り越えるためにやっていたこと
プレジデントオンライン / 2023年6月30日 14時15分
■ローマ人は「不健康が当たり前」だった
これお決まりの質問だ。日常生活の歴史を取り上げた僕の最初の本『100万年を1日で(未邦訳)』のプロモーション・ツアーでは、公開イベントを開催するたびに、最もよく訊かれた質問がこれだった。もちろん僕は答えることができるよ、アリー。しかし人類の発祥以来、地球上でこれまでに約540億人の女性が生きていた。その多種多様な経験をすべて取り上げることは不可能だ。そこで、ここでは僕が最もよく理解している地域、つまりヨーロッパとアメリカに範囲を限定する。
最初に言っておきたいが、多くの女性にとって「生理」とは、単に月に一度訪れる不愉快な出血というだけでなく、健康状態の変化という気がかりな問題にも関係していた。抗生物質が誕生する以前の時代には、食料は少なく病気は風土に根ざし、多くの人がビタミン不足、病気、ストレス、あるいは過労に悩んでいた。
医療の歴史に詳しい歴史学者のクリスティ・アップソン=サイア博士は、ローマ人にとっては不健康こそが普通の状態で、健康な状態はめったにない幸運だったと、以前ポッドキャストで対談した際に僕に教えてくれた。
実際、18世紀のエディンバラでは、栄養豊富な食べ物の乏しい冬になると、貧しい女性たちは生理が止まってしまうことが多かったと、国立アメリカ歴史博物館のアレクサンドラ・ロード博士も述べている。1671年には助産婦ジェイン・シャープが、生理の出血は「早すぎたり遅すぎたり、多すぎたり、あるいは少なすぎたりする。完全に止まってしまうこともある」と記している。
■経血は汚染物質だとみなされていた
古代と中世において、こうしたホルモンの乱れは十分理解されていたとはいえない。ギリシアの名高い医者であるヒポクラテス(紀元前460頃~370頃)やガレノス(129頃~200頃)のような、強い影響力を持つ思想家たちは、人体を四体液説にもとづいて理解していた。
4つの体液(黒胆汁、黄胆汁、粘液、血液)は、人の性格や「気質」――ここからさまざまな性質を形容する憂鬱(ゆううつ)質(メランコリック)、胆汁質(コレリック)、粘液質(フレグマティック)、多血質(サンギーヌ)という言葉が生まれた――を決定するだけでなく、ホルモンの乱れは病気を引き起こすと考えられた。
一般論として、内臓は、「過度に熱くなったり冷たくなったり、湿ったり乾燥したりする場合がある」とされたのだ。その主な治療法は、体の本来のバランスを取り戻すことを目的とした食事療法や瀉血(しゃけつ)だった。
ヒポクラテス以降の伝統思想によると、男は熱く乾燥しており、これは暴力的な気質につながるが、同時に排尿、排便、発汗、鼻血、ひげ、そして太い血管を通じて、体に不要な不純物を効率的に排出できる。
一方、女は冷たく湿っているため、鼻血が出ず、ひげも生えず、血管は細く、そして男ほど食物をよく消化しない。そのため、不用物の排出には、子宮を経由するよりほかないとされた。しかし体が排出するということは、その排出物は体にいいものではないということで、要するに明らかに危険だということではないか?
こうした考えは、宗教教義にも影響を及ぼしたようだ。旧約聖書の『レビ記』第15章には、体からの排出物は不浄かつ不潔だと記されている。また正統ユダヤ教の法典ハラハーは、生理中の女性は、1週間白いシーツの上で眠り、それから聖なるミクヴェ(水槽)で沐浴(もくよく)したあとでなければ性行為を行ってはいけないと命じている。同じような戒律が、イスラムやヒンドゥー教の一部の宗派にも存在する。経血は、不快なものとみなされただけでなく、汚染物質だと広く理解されていたのだ。
■古代ローマ人の経血への誤解
経血に対する恐怖について最も途方もない主張を繰り広げたのは、博識なローマの博物学者大プリニウスだ。紀元79年にヴェスヴィオ火山が噴火したとき、みんながそこから逃げ出しているのに1人だけ向こうみずにも火山に近づいて死んだこの男は、経血とは化学物質の投棄場からにじみ出る毒物のようなものであると述べ、次のように説明した。
「(これに触れた)新酒は酸っぱくなり、農作物は実らず、接木は枯死し、庭に蒔かれた種子はひからび、果物は果樹から落下し、金属の刃は切れ味が悪くなり、象牙の光沢は失われ、蜂は巣のなかで死に、青銅や鉄でさえただちに錆びつき、空気は恐ろしい悪臭に満たされる。これを口にした犬は発狂し、噛みついたものを治療不可能な毒に感染させる」。
もしこんなイカれた奴が電車で君の隣に座り、妹の生理のせいで蜂の巣が全滅した、なんてささやきはじめたら、君は絶対に席を変えるだろうね。
■「経血=危険」という誤解は広まり続けた
ギリシア・ローマ時代以来のこうした思考はその後もまるで貝のようにしつこく存続し、中世になると、男はホルモンの影響下にある女に見つめられただけで呪われるとか、また経血は、単に女の子宮内の血液というだけでなく、敏感なペニスの皮膚を焼くと、広く信じられるようになった。
中世の男が勇敢にも、あるいは好色にも、生理中の女性を妊娠させた場合、男の情熱によって女は力を得る一方で、男のほうは、女の冷たさと湿り気で力を失い、また生まれた赤ん坊は弱々しく奇形で赤毛(赤毛のみなさんには申し訳ない……)になるといわれた。
さらに、女の危険は年齢を重ねれば収まるわけではなかった。閉経前後の女は、それまでに排出しきらなかった危険な経血を体内にため込んでおり、目や鼻から噴き出た有毒なガスが周囲の赤ん坊や動物を病気にする、あるいは殺害する可能性があるとされたのだ。
■古代の医学者たちが考えた生理痛の治療法
もちろん、過去の多くの女性がつらい生理痛に苦しんだに違いない。中世の女子修道院長ヒルデガルド・フォン・ビンゲンは生理痛について、アダムに禁断の果実を食べるように勧めたエバに下された罰だと説明している。
僕がこのことを特に記しているのは、中世の一部の尼僧は極端な絶食や瀉血を通じて生理を止めることに成功しており、これは彼女らの賞賛すべき聖性を嘉(よみ)した神が、代々女性たちに与えられた罰から彼女たちを解放した印と解釈されたからだ。現在では、このいわゆる「奇跡の拒食」、つまり極端な貧血の結果、先に述べた冬の栄養不足に苦しんだ18世紀のエディンバラの女性たちと同じことが、彼女たちの体内で起こっていたのだとわかっている。
こうした脅かしは別として、古代の医学者たちは、規則的な月経周期は女性の健康にとって非常に重要だと述べていた。したがって多くの女性たちが何より優先すべきこと、それは不規則な生殖サイクルを軌道に乗せることだった。
医学の手引き書には、生理痛に悩む既婚女性は、定期的にセックスして健康な食事をとるべきだと書かれているが、これは優れたアドバイスだと僕も思う。その効果がなかった場合の穏やかな治療法のなかには、薬草や葡萄酒を含む薬、すりつぶした果物や野菜でつくった膣ペッサリーなどがあった。

■「生理不順」を治療する恐ろしい方法
幸い、床屋のナイフは不規則な生理を治療する最後の手段にとどまっていた(近世以前、西洋では床屋は安価な外科医として活動し、簡単な手術を行うこともあった)。しかしヒポクラテスは、若い女性の血管から瀉血させることについて、思い悩むことはなかったようだ。彼にとって、血液は所詮血液に過ぎなかったからだ。
これがうまくいかない場合、次に選ばれた治療法は、子宮をかき回して活性化することだった。なんと恐ろしい! ヒポクラテスの治療法では、甲虫の死骸、特に有毒な化学物質を分泌するツチハンミョウを膣のなかに詰め込むことを勧めている。この分泌物(カンタリジン)は、血管を膨張させ、血流の増加を促すとされるからだ。スパニッシュ・フライとしても知られるツチハンミョウは、歴史上最も悪名高い毒薬あるいは催淫剤――服用量による――という名誉を担っている。2つの可能性があるというのは、ベッドタイムの賭け事としてはリスクが大きすぎると思うが。
昔の医者は、この言語道断な処置の必要性を信じていた。そうしないと水分を失って干からびた子宮が、うるおいに満ちた臓器に取りつこうとして体内をさまよいはじめると考えられていたからだ。
ギリシアの外科医アレタイオス(2世紀頃)も、子宮は、人間の体内に独立して存在する動物のようなものだと考えていたようだ。幸い彼は、子宮は強い香りに反応するため、患者が強烈な臭いの調合薬を飲むことで、またはよい香りの膣ペッサリーを使って、子宮を元の位置に戻すことができるとしている。つまりタイミングよく与えたソーセージで、リス狩り中の犬の気をそらすようなものだ。
■ヒステリーという言葉は「子宮」が由来
こうした治療法は、女性の生殖能力を完全に回復させることを目的としていた。子どもを産むことは結局のところ、重要な宗教的・社会的な責務だったからだ。同時に外科医が恐れていたのは、治療を受けなかったすべての女性の心臓付近に人を狂わせる経血がたまることだった。これは発熱、発作、気鬱、そして――恐ろしいことに!――たとえば悪態をつく、怒る、大声で意見を述べるなどの、過度に男性的な行動を引き起こすと信じられたからだ。
1600年までに、こうした現象はヒステリー性疾患として知られるようになり、その後(ギリシア語で「子宮」を意味するhysteraから)ヒステリー(hysteria)として定着した。ただしこのいきさつはけっして明快ではない。
当初は子宮の不調とされていたものが、1600年代になると、男性も罹患(りかん)する神経性の病気とする理解が広まっていたからだ(不調の原因を器質的なものとする学派と心因的なものとする学派の間で、19世紀から20世紀初頭にかけて激しい論争が起きた。ジグムント・フロイトも何度も考えを変えたあげく、最終的には男性もヒステリー患者になると結論づけている。それにもかかわらず、「ヒステリー」という言葉はいまだに非常にジェンダー的な色合いが濃く、興奮を露わにしていると判断された女性に対して使用される場合が多い。ただし奇妙なことに、とても陽気な人間に対する褒め言葉としても使われる。この謎めいた言葉には、さまざまなニュアンスが含まれているのだ)。
■2000年以上前の女性もナプキンを使用していた
以上が、月経困難症に悩む近世以前のヨーロッパ人女性が従うべきだとされたアドバイスだった。そこで次に、健康な女性が生理のときにどうしていたかという問題に移ろう。インターネットで見つけた説を信じる(けっして推奨できる習慣ではないが)なら、小さな木片をやわらかい布で包んだものが、原始的なタンポンとしてヒポクラテスの著作に登場するという。可能性はあると思わないかい?
残念ながらこの主張に関しては、おそらく近年の誤解の結果であり、古代の生殖医学を専門とするヘレン・キング教授によって否定されている。タンポンが古代世界で本当に使用されていたとしても、その物的証拠はまったく存在しないのだ。
しかし2000年前の古代ローマの女性が生理の際にナプキンを使用していたことについては、証拠が存在し、この習慣はさらに古い時代にさかのぼる可能性がある。ナプキンをつくるのに、複雑な技術は必要ない。再利用された、あるいは低品質の布を脚の間に固定して経血を吸わせ、その後洗濯してふたたび利用するだけのことだ。
その名は時代とともに変化したが、聖書には「menstruous rag(生理用のぼろ布)」と記されている。一方シェイクスピアの時代のイングランドでは「clout(ぼろ布)」として知られていたことを、中世史家のサラ・リード博士がつきとめた。
■ショーツを着ない女性はどうやって布を固定したか
ぼろ布は、女性の下着のなかに詰め込んで使用されたに違いないと思うだろう。それも無理はない。しかし――驚くべきことに――実はショーツは近年の発明品なのだ。1800年以前には、ヨーロッパ人女性の大半はショーツを穿いていなかった。ということは当然、次の質問は、「ぼろ布は、なぜ落ちなかったの?」だ。
イギリスの女王エリザベス1世は黒い絹製ガードルを3枚所有していたことが知られており、彼女はこれを腰に締め、リネン製の生理用ナプキン、あるいは麻布を固定していた。絹製は高価すぎたとしても、同種のものは、さまざまな階層の女たちが広く利用していたことだろう。
別の広く行われていた習慣は、あて布など使わず、着衣にしみ込ませたり床に血液が流れるままにすることだった。現在ではそうする人がほとんどいないのは、おそらく19世紀後半の「バイキン理論」革命のせいだろう。バクテリアやウイルスという恐ろしい存在が知られるようになり、その結果、個人の衛生意識が非常に高まったのだ。そして登場したのが高級石鹸ブランドや初期の制汗剤だ。
■現在のナプキンの原型となった「野戦看護婦の包帯」
そんなわけで、1900~1910年代のエドワード朝時代の優雅な女性たちは、スカートの下に「生理用エプロン」を着けていたのかもしれない。これは洗濯可能なリネン製のおむつのようなもので、ガードルやベルトで腰に固定し、後部に垂らしたゴム製スカートによって、服に染みがつき、それを目撃されるという恥ずかしい事態を回避した。
さらに暖かさや、慎み深いという評判を保つため、その上には足首丈の、股下があいたブルマーが穿かれた。しかしかさばり、着脱が面倒なこの一式は、昔から存在する技術にひとひねり加えた、使い捨ての衛生的なナプキンやタンポンなどが登場すると、徐々に姿を消していった。
第一次世界大戦中、塹壕(ざんごう)の兵士たちのために開発された木質繊維製の野戦用包帯(セルコットン)が、生理中の野戦看護婦にも利用され、下着のなかに突っ込まれていることを、キンバリー・クラーク社という会社が知った。どうやら同社が開発したセルコットンは、ぼろ布の後継となる吸収力の高い、衛生的な素材だったらしい。

噂を耳にした本社は、看護婦たちに説教するよりもむしろ、「コテックス」という新たな商品ブランドとして生理用ナプキンを売り出すことを決意し、信頼できる商品として着け心地のよさと不快感の軽減を強調する広告キャンペーンを行った。これは賢明な決断だった。
■タンポンの特許を巡る歴史
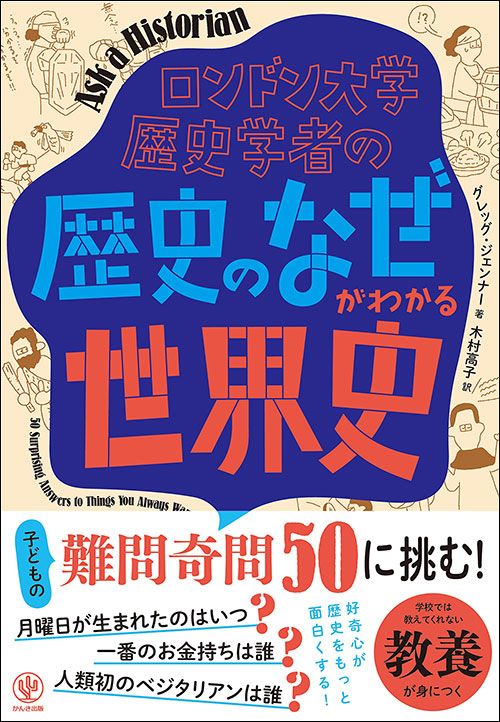
タンポンのほうは、アメリカ人の整骨医アール・ハース博士によって発明されている。1920年代に開発された彼の「アプリケーター付きタンポン」のおかげで、女性は性器に触れずにこの綿製品を膣に挿入できるようになった。
すばらしいアイデアにもかかわらず、なかなか売り上げが伸びなかったため、1933年にハースは勤勉なドイツ系移民ゲルトルード・テンドリヒに特許を売却している。彼女はミシンと空気圧縮機だけを使って、タンポンを手づくりしはじめた。1人の女性から始まった製作所はやがてタンパックス社となり、世界中のタンポンの売り上げの半分を占めるまでに成長した〔現在の所有者はプロクター・アンド・ギャンブル(P&G)社〕。アール・ハースの子孫は、自社株を所有しつづけなかった不運をさぞ嘆いていることだろう。
----------
ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ校の名誉研究員。BBCの子ども向け歴史番組「Horrible Histories」のコンサルタントを務める。軽妙な語り口から、イギリスでは歴史の面白さに目覚める子どもや大人が続出している。著書に『A Million Years in a Day: A Curious History of Daily Life』『Dead Famous: An Unexpected History of Celebrity from Bronze Age to Silver Screen』がある(いずれも未邦訳)。
----------
(歴史学者、キャスター、作家 グレッグ・ジェンナー)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
『GBA × yoiコラボ企画』集英社ウェブメディア「yoi」読者へ向けて、Be-A Japanが運営する女性支援プロジェクト「GBA(ジービーエー)」が生理セミナーを開催
PR TIMES / 2024年7月19日 16時45分
-
勉強に支障が出るケースも…小中学生の重い「生理痛」どう対応すればいい? 産婦人科医に聞いた
オトナンサー / 2024年7月5日 9時10分
-
「今までと違うのは、更年期だから?」生理の始まりと終わり、尿もれ。不快さをカバーするには
OTONA SALONE / 2024年6月29日 11時31分
-
更年期の生理。経血量の多い月・少ない月の差が激しすぎ。快適さのためにすぐにできることは?
OTONA SALONE / 2024年6月29日 11時30分
-
夏の生理の夜も快適に!エアコン冷えもムレも解消できる「夜用オーガニックコットン吸水ショーツKAANE(カーネ)」期間限定サマーキャンペーン開催
PR TIMES / 2024年6月26日 11時45分
ランキング
-
1大谷翔平&真美子さんのレッドカーペット中継に… 人気アイドルが「思いっきり映ってる」と話題
Sirabee / 2024年7月18日 15時40分
-
2Q. スイカの皮は食べられますか? 【管理栄養士が回答】
オールアバウト / 2024年7月18日 20時45分
-
3「持ち運び用の最適解...」無印の"990円"充電器、価格以上の優秀さだった。
東京バーゲンマニア / 2024年7月18日 20時8分
-
4がんや早死にのリスクを高めるだけ…和田秀樹が「女性は絶対に飲んではいけない」と話す危険な薬の名前
プレジデントオンライン / 2024年7月19日 10時15分
-
5義母と元夫は減塩生活中!? 嫁に去られた親子の今…【お義母さん! 味が濃すぎです Vol.48】
Woman.excite / 2024年7月15日 21時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











