なぜ15歳の殺人犯にそこまでするのか…国選弁護人が語る「出会った責任」という重すぎる言葉
プレジデントオンライン / 2023年8月5日 11時16分
※本稿は、岡田行雄編著『非行少年の被害に向き合おう! 被害者としての非行少年』(現代人文社)の一部を再編集したものです。
(前編から続く)
■頼もしかった「ばっちゃん」の存在
少年の面会は、3名いる弁護人のなかでも、ほぼ私ひとりの役割となっていきました。
裁判員裁判となって以降も、週1回は面会に行くことにしていました。ただ、当然のことですが、15歳の少年にとって、接する大人が私だけという状況が望ましいとはいえません。
しかし、少年の家族は、少年に虐待を加えていた加害者であり、面会は期待できませんし、仮に面会をしたとしても、かえって悪影響となることが予想されます。
そんななか、頼もしかったのが「ばっちゃん」の存在でした。
■多くの少年や受刑者と文通
K少年が起訴されて間もないころ、矯正関係のOBの方から電話をいただき「ある人を紹介するので、少年と文通をしてもらったらいいのではないか」との提案をいただきました。
その方は、他県で40年以上も前から、ひとりで子ども食堂のような活動を続けてこられており、現在は、それを組織化して、NPO法人の理事長をされている方です。
私も、少年問題に関わるひとりとして、もちろんお名前はうかがったことがありましたが、直接の面識はありませんでした。
さっそくばっちゃんの携帯番号を聞き、電話をかけさせてもらうと、90歳近いという年齢をまったく感じさせない元気な声で、これまで関わってきた子どもたちのこと、多くの少年や受刑者と文通をしていることなどを話してくれました。
そのなかには、ばっちゃんの著作を読んで、手紙を送ってきた無期懲役の受刑者もいるそうです。
そのようなひとたちと文通するというのは、一生関わるという覚悟がないとなかなかできることではありません。
■「どうせ仕事で相手をしているだけなんだ」
K少年の生い立ちを聴けば聴くほど、少年の身の回りには、信頼できる、安定した大人がいませんでした。
自分の都合で子どもの面倒を見ることを放棄し、虐待を加える親。
兄から虐待を受けても、お腹をすかせていても、まったく助けてくれない親族たち。
精神的にも不安定な人が多かったようであり、少年は乱高下するまわりの大人たちの気分に翻弄されながら、育ってきたようでした。

そんな大人に囲まれて育ったK少年は、その後、転々とした施設の職員に対しても、「どうせ仕事で相手をしているだけなんだ」「いつか見捨てるのだ」と信頼感をいだくことができず、やさしくされればされるほど、かえって反発を感じるようになっていたそうです。
■「他人のためにここまでできるって、本当にすごい人ですね」
K少年には、ありのままに自分を受け入れてくれ、安定して、継続的に関わってくれる、裏切らない、切り捨てない大人が必要だと思っていたのですが、この点、ばっちゃんは、まさに適任だといえました。
さっそく少年に、ばっちゃんの活動を紹介した書籍を差し入れました。
少年は、書籍を読んで「他人のためにここまでできるって、本当にすごい人ですね」「でも、本当にこんな人がいるんですか」と懐疑的な様子でしたが「文通をしてくれる、というのであれば、ぜひやってみたいです」と申し出ました。
こうして、K少年とばっちゃんの文通がはじまったのでした。
■「こんなにきちんとした手紙が書ける子なんやね」
K少年が、ばっちゃんに最初に書いた手紙は、とても丁寧なもので、「こんなにきちんとした手紙が書ける子なんやね」とばっちゃんも驚いていました。
その後も、読書をしたり、漢字の勉強をしていることなどを熱心に綴っていました。
でも、それから数カ月すると、「せっかく送ってくれたお金もぜんぶマンガ本を買うのに使ってしまいました。いまはダラダラ過ごしています」などという、やる気のない感じが満載の失礼な手紙が送られてくることもありました。
だからといって、ばっちゃんはそんな手紙くらいで怒ったりしません。
「育ちざかりなんだから、出てきたものは、ちゃんと食べんといかんよ」などと優しく返します。
■「ホットケーキをおなか一杯食べたいです」
このような手紙の内容のブレも、人格が未統合、という少年の特性の表れとも考えられます。また、このひとはどこまで自分に関わってくれるのか、一時的な思いで関わっているだけで、いつか裏切られるのではないか、を推し量るための「試し行動」の一種だったのかもしれません。
そんなやりとりが繰り返されていたある日、次のような手紙が届いたと、ばっちゃんが笑いながら、私に電話をしてきました。
共感性がないと言われたK少年が、ばっちゃんとの手紙のやりとりを通じて、失礼で、わがままな表現ではあるものの、ばっちゃんの長生きを望んだことは、小さいながらも成長といえるのではないか、と思えました。ばっちゃんも同じように感じたようでした。

■「僕はとても恵まれていると思います」
さらに手紙は続きます。
僕は、いろいろな施設を転々として、ずっと嫌われて、ずっとひとりぼっちでした。
こんな大きな事件をおかしたのに、弁護士さんが会いに来てくれて、ばっちゃんが手紙をくれるなんて、僕はとても恵まれていると思います。
僕は、ばっちゃんと知り合うまでは、このまま施設に入っていたほうが楽だし、そのほうがいいのかな、と思っていました。でも、いまはいつか外に出て、ばっちゃんに会いたいです。だから長生きしてください。
そのとおり、K少年は私が、最初に警察署に面会にいっていたころ、「今が一人で落ち着く」「ずっと施設にいたので、別に少年院だろうと、刑務所だろうと一緒です」と言っていたのです。
その言葉は強がりでもなんでもなく、社会に出ても待ってくれている人も、受け入れてくれる人もいないK少年の本音だったのだと思います。

そんなK少年が「いつか外に出て、ばっちゃんに会いたい」と思うようになったのです。
それは、私が出会ったときのK少年からは、決して出てこない言葉でした。
■「責任を感じ、怒りを覚えています」
判決からしばらくして、K少年から手紙が届いたよ、とばっちゃんから電話をもらいました。そこには、このような記載がありました。
一人で悩んで、相談できる人がいなくて、生きることに苦しくて、死にたいと思ってつらかったのだろう、と思いました。
「共感性」がない、と指摘されていた少年ですが、自分と似た境遇の少女に対しては、深い共感をよせることができたようです。これも、K少年がわずかでも成長していっている証かもしれません。
■「どう接していいか、いまもまだわからないのです」
手紙は続きます。
ばっちゃんから、僕のことを、本当の孫のように思っている、と言われたときは、心に南からの暖かい風が吹いてきたように感じ、とてもうれしかったです。
でも、それでも、ばっちゃんのことも、知名先生のことも、まだ信用してはいないです。今まで出会ってきた人々とは全然違うし、自分のことを理解しようとしてくれるひとが現れたのは、初めてのことなので、どう接していいか、いまもまだわからないのです。
もちろん、私も、ばっちゃんも「まだ信用してはいない」と言われたからといって、怒りもしないし、傷つくこともありません。むしろ、「そうだろう、そうだろう、いままでがつらかったんだもんね。今のほんとうの気持ちを打ち明けてくれてありがとうね」と、K少年のことをいとおしく思うくらいです。
■見守り続けなければならない
福岡県北九州市でホームレス支援をされている認定NPO法人抱樸(ほうぼく)の代表・奥田知志さんは、いつも「出会った責任」という言葉を使われます。
一度、関わった以上、出会ってしまった以上、その人に対し、責任が生じるのだ、と。少年問題に関わる人間も、同じ言葉を胸に抱いていなければならない、と私は思います。
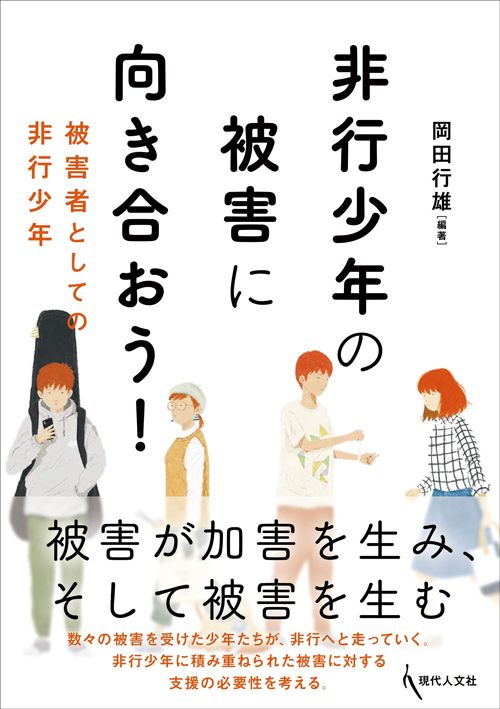
K少年が虐待を受けるようになってから、K少年をさらに傷つけるような裁判員裁判が終わるまで、ちょうど10年程度。少年が人を信頼できるようになるには、もしかしたら、同じくらいの月日が必要なのかもしれません。
いつの日か、K少年が、われわれのことを信用している、と素直に口にできるようになるその日まで、私とばっちゃんは、安定して、継続して、K少年を見守り続けなければならない、と思うのです。だから、私からも言いたいと思います。
ばっちゃん、長生きしてください。
*事実関係、法廷でのやりとりなどについては、もととなった事件において報道された事実の範囲に限定して記載させていただきました。また、その他の事実関係、少年との手紙のやりとり、会話の内容などは、プライバシーに配慮して、一部修正等が加えられていることについて、ご了承ください。
----------
弁護士
1974年長崎県佐世保市生まれ。1997年熊本大学法学部卒。2003年弁護士登録。福岡県弁護士会所属弁護士。NPO法人福岡県就労支援事業者機構理事。福岡大学法科大学院非常勤講師(「子どもの権利」)。少年の就労を通じた更生支援に力を入れている。共著に『非行少年の被害に向き合おう! 被害者としての非行少年』(現代人文社)がある。
----------
(弁護士 知名 健太郎定信)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
殺害された保護司、「よそ行きの服がいるやろ」とジャケット…刑務所への手紙に「社会の門をくぐって来て」
読売新聞 / 2024年6月16日 10時40分
-
待ち伏せていた元カレに首を絞められ…新宿タワマン刺殺事件だけではない「ストーカー化する人」の危険な特徴
プレジデントオンライン / 2024年6月15日 9時15分
-
亡き娘胸に新たな一歩 社会福祉士資格取得、本郷由美子さん 池田小児童殺傷事件23年
産経ニュース / 2024年6月7日 18時47分
-
「幼少期の悲惨な境遇」は減刑の理由にはならない…パパ活詐欺に「懲役9年」という冷徹な判決が下った理由
プレジデントオンライン / 2024年5月31日 10時15分
-
「顔も腫れあがり、髪の毛もむしり取られていた」妹が殺され償いを求めた遺族 加害者へ賠償求めても全額払われず 相手の口座に残っていたのはたった"931円"「憎みたくなくても憎んでしまう...今の制度では」
MBSニュース / 2024年5月19日 19時40分
ランキング
-
1これするだけで筋トレ効果倍増!【医師解説】50代からの「たるんだ体」改善エクササイズ
ハルメク365 / 2024年6月15日 21時30分
-
2一人暮らし経験者が選ぶ「買わなくてよかったと思う家電」ランキング 2位は「テレビ」
まいどなニュース / 2024年6月15日 21時0分
-
3【専門医が監修】「疲労度診断テスト」にトライ!効果的な解消法とは?
ハルメク365 / 2024年6月15日 14時50分
-
4日産「新型“高級”ノート」初公開! 「オシャブルー」内装&斬新グリル採用! 史上初の超豪華仕様「オーラ“AUTECH”」24年7月に発売へ
くるまのニュース / 2024年6月13日 15時10分
-
5BMWが誇る「M」を冠するスーパーバイクの実力 雨の「もてぎ」で元GPライダー先導で試乗した
東洋経済オンライン / 2024年6月16日 7時20分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












