「まさか自分が育児と仕事を両立できないなんて」産後うつになった父親が抱えていたプレッシャーの正体
プレジデントオンライン / 2023年8月5日 13時15分
本稿は、平野翔大『ポストイクメンの男性育児 妊娠初期から始まる育業のススメ』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。
■1人目の子どもが産まれて、妻が産後うつになった
これから紹介する「父親の産後うつ」の事例は、「有害な男らしさ=トキシック・マスキュニティ」が目立った一例だ。母親の産後うつには多くない、まさに父親に特徴的なパターンであり、父親の育休が増えるにつれて、今後多くなってくるであろうと思われる問題だ。
この方は、「まさか自分が、育児と仕事を両立できなくなるとは思っていなかった」と語っている。
この父親がうつになったのは、2人目の子どもが産まれた後だった。1人目の子どもが産まれた時、赤ちゃんにトラブルがあり、新生児集中治療室(NICU)に入室することとなった。子どものNICU入室は、多くの母親に「自分のせいではないか」「その後の発達に影響したりしないだろうか」とストレスを与えることが知られている。この父親の妻も退院後、思い詰めていたという。これに夜泣きが加わり、産後数カ月の時に妻が倒れてしまった。まさに父親の産後うつのリスクの1つである、「妻の産後うつ」である。
その時、父親はサラリーマンとして朝から夜まで働いていたが、実両親・義両親の家が近かったこともあり、双方の協力を得て仕事は続けつつ、土日は可能な限り子どもの面倒を見て妻を休ませた。その後妻は体調を回復し、2人目を授かる。
■「2人の父親になったし、頑張らないと」
2人目の妊娠中に、「今度子どもが大きくなれば、今のマンションでは手狭になる」と考え、家を購入することを決意した。同時に自らの希望ではなかったが、部署異動の話もあり、今後のキャリアも考え引き受けることとした。もちろん、1人目の反省もあり、きちんと子育てに関わるということは決めていた。
出産後、家の手続きや転居、そして異動先での激務と育児を両立。大変さは感じていたが、「2人の父親になったし、頑張らないと」と自分を励まして働き続けた。しかし2人目が1歳を迎える前くらいから、徐々に眠れない日が増えていった。頭痛や原因不明の熱も出てきたが、それでも3カ月頑張った。しかし限界を感じたが、妻には迷惑をかけられないと、内緒で心療内科を受診したところ、うつと診断された。
何を優先するのか悩んだが、仕事を犠牲にすることを決意。妻と上司に診断結果を伝え、仕事内容や分量を大きく変えてもらい、休職はせずになんとか乗り切った。今では3人目にも恵まれ、3人目はこの反省も活かして仕事をセーブしつつ、無事に育児を続けている。
この父親は、自らが倒れたエピソードを振り返り、「『勝手な使命感』に駆られていた」と分析する。妻の産後うつが父親の産後うつのリスクであることは本書の第2章で述べたが、これに「有害な男らしさ」が重なった事例と言えよう。第1子の時に、祖父母の力は借りつつも、妻のケアと自らの仕事を両立できたというのも、ある意味根拠のない自信を持つ原因になってしまった。
■父親の産後うつは「共有できない」
1人目の時は妻の産後うつ以外の要因はなかったが、2人目の時は「家を買う」「異動」というストレスがかかりやすいイベントを2つも重ねてしまっている。しかしそれでも「自分が頑張らねばならない」と抱え込み、自分の体調不良を自覚してもなお3カ月頑張り、最終的に妻には伝えないで受診をしている。病んでもなお、「父親は強くあらねばならない、弱みを見せてはならない」という「有害な男らしさ」を抱え続けていた。
実はこの事例の元となった方は、心理学部の出身であり、メンタルヘルス不調についてある程度の知識を持ち合わせていた。自身がうつとなったことを契機に、男性の育児に関するうつについて調べたが、当時はあまりに情報が少ないことを感じていた。
そして何より、その後も続いたのが「共有できない辛さ」であったという。父親の知り合いや会社の同僚には、「育児が原因でうつになりました」とはなかなか言えなかった。唯一言えたのは自らも産後うつに悩まされた妻であり、通院先の医師も育児に関するうつについてはあまり相談できなかった。自身にも「弱みを見せたくない」という感情はあったが、それを乗り越えて相談しようとしても、「共有できる場所がない」のである。

■父親も母親も「育児で孤立」すれば「産後うつ」になる
本書で紹介している事例すべてに共通しているのは、まさに「孤立」である。一人での夜泣き対応やワンオペ育児、そして相談できない環境。父親は自ら相談することも難しいが、相談する場もないのである。第2章で父親の産後うつのリスク要因に、「孤立感」「周囲のサポートが乏しい」ことがあると表で示したが、この2点は共通して見られた。
別にこれは父親に限った話ではない。「ワンオペ育児」は、母親が育児で父親の支援を受けられないことによって孤立していることを指し、まさに産後うつの原因になっている。根本的にはそれが父親であるか、母親であるかは関係なく、「育児で孤立」すれば「産後うつのリスクは高い」のである。だからこそ、「育児をする人であれば、すべて支援されるべき」なのだ。
しかし本書では、敢えて「父親の」を強調して書いている。それは現在の支援の枠組みの中に父親がいないことを問題視しており、今後父親の育児参加が増えれば、必ず「母親の二の舞」を踏むと考えているからだ。
■育児をする人はみんな支援される必要がある
たとえ父親が育児参加し、母親の孤立が避けられたとしても、今度は「家族が孤立」したらどうだろうか。これまで「子育て世帯の孤立」はほぼ「母親の孤立」と同義で語られてきており、明らかなデータや影響は示されていない。しかし片方の産後うつがもう片方の産後うつのリスクであることは判明しており、「母親が追い込まれる→父親が追い込まれる」、もしくは逆の構図が成り立つことからすれば、ここに第三者が介入できない、孤立状態となるのは非常に高いリスクである。双方がメンタルヘルス不調となれば虐待・ネグレクトなどの問題にもつながりかねないため、可能な限り片方が発症した段階で、すぐ家庭全体を支援するのが望ましいのは言うまでもない。
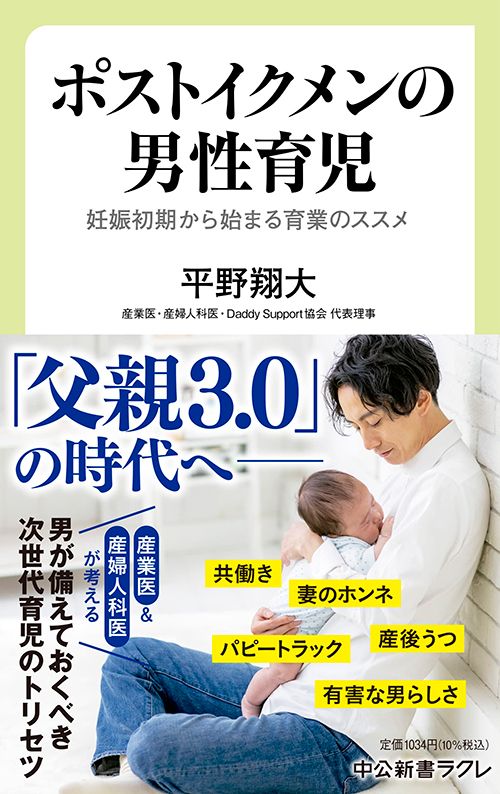
実際に、母親の産後うつが子どもの睡眠や認知・情緒的発達のみならず、身体症状や病気・事故の発生にまで影響を与えることが示されており、父親の産後うつも子どものうつ病・精神問題に影響を与えることが示されている。
つまり、育児をする母親も、父親も、そして家族も、きちんと社会支援システムの中に組み込まなければならないのである。それこそが、「育児と仕事を両立できる社会」ではないだろうか。
育児支援が女性に偏ったことは、母親に「育児をメインで、プラスαで仕事」、父親に「仕事をメインで、プラスαで育児」という不均衡をもたらした。これでは「育児と仕事を両立」できているとは言い難い。
----------
産業医、産婦人科医
1993年生まれ。慶應義塾大学医学部卒業後、産業医・産婦人科医として、大企業の健康経営戦略からベンチャー企業の産業保健体制立ち上げまで幅広く担う傍ら、ヘルスケアベンチャーの専門的支援、医療ライターとしての記事執筆や講演なども幅広く手掛ける。2022年にDaddy Support協会を立ち上げ、支援活動を展開している。著書に『ポストイクメンの男性育児 妊娠初期から始まる育業のススメ』(中公新書ラクレ)がある。
----------
(産業医、産婦人科医 平野 翔大)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
突然「30分後に友達つれて帰るわ」と夫。産後の妻が夫を怒鳴りつける瞬間/結婚人気記事BEST
女子SPA! / 2024年6月13日 8時47分
-
幼い娘3人殺害 思い悩んだ母親は「心理的孤独」だったか 懲役23年の判決をどう見た?「産後うつ」乗り越えた2児の母に聞く【チャント!解説】
CBCテレビ / 2024年6月12日 18時59分
-
赤ちゃん目線で見てみたら、不安や悩みがスッキリ解消!『まんがでわかる! はじめての妊娠・出産あんしんバイブル!』6月11日発売
PR TIMES / 2024年6月11日 12時45分
-
出産直後に押しかけ「息子にそっくり」無神経な実母と妻との板挟みに苦しむ夫…多くの読者が「同じことされた」
Woman.excite / 2024年6月9日 16時0分
-
子育ての孤立を防ぐ、“カフェラウンジ併設型 産後ケア施設”「葉ノ月助産院 supported by NESCAFE」奈良県生駒市で5月30日(木)より本格営業を開始
PR TIMES / 2024年5月30日 14時15分
ランキング
-
1これするだけで筋トレ効果倍増!【医師解説】50代からの「たるんだ体」改善エクササイズ
ハルメク365 / 2024年6月15日 21時30分
-
2一人暮らし経験者が選ぶ「買わなくてよかったと思う家電」ランキング 2位は「テレビ」
まいどなニュース / 2024年6月15日 21時0分
-
3【専門医が監修】「疲労度診断テスト」にトライ!効果的な解消法とは?
ハルメク365 / 2024年6月15日 14時50分
-
4日産「新型“高級”ノート」初公開! 「オシャブルー」内装&斬新グリル採用! 史上初の超豪華仕様「オーラ“AUTECH”」24年7月に発売へ
くるまのニュース / 2024年6月13日 15時10分
-
5BMWが誇る「M」を冠するスーパーバイクの実力 雨の「もてぎ」で元GPライダー先導で試乗した
東洋経済オンライン / 2024年6月16日 7時20分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












