外国人観光客は「日本的な生活」に憧れている…日本人が過小評価している「日本式インフラ」のすごい価値
プレジデントオンライン / 2023年8月16日 9時15分
※本稿は、上念司『経済で読み解く地政学』(扶桑社)の一部を再編集したものです。
■新たな「世界の工場」になり得る国はどこか
国際社会から中国のデカップリングが進んでいけば、当然、これまで世界の工場として注目を浴びてきた中国から撤退する企業も増えていきます。その際、どこの国が世界の工場になり得るか。それは、日本ではないでしょうか。
中国が台頭する前のものづくり大国と言えば、日本とドイツでした。そして、その下請けを行う国が各国の周辺に散らばっていました。
現在、ドイツの下請けを行っているのは、東欧地域やイランが中心です。しかし、今後はロシアの存在がネックとなり、ドイツの下請けとなる国々には政治リスクが付きまといます。
一方、日本の下請けを行うのは、中国をはじめ、韓国や台湾、そして東南アジアなどの新興国が中心です。台湾については中国と軍事衝突するリスクがあるため積極的な投資はしづらい部分があります。韓国は中国との関係性が強いため、アメリカから半導体輸出を制限する経済措置を検討されたこともあり、同じくリスクを抱えています。また、東南アジアの新興国については、2022年の欧米の利上げの影響で2023年以降に経済危機を起こす可能性もあります。
■日本はモノが足りない時代の救世主になれるはず
そうなれば、新規の投資対象として残るのはドイツと日本。この2カ国が今後世界の工場として復活する可能性があります。これからのインフレ基調では、モノが足りない時代が来るので、その重要性はますます増していくはず。
日本人が世界の中で活躍する日は、もうすぐそこまで来ているのです。
ただ一つの懸念点としては、今後の日本人が、これまで海外の下請け国にやってもらっていた作業を、自国で供給しなければならない可能性が出てくる点です。働き方改革などが進む中、働き方が制限される風潮もあります。きちんと働いた分だけ儲かるシステムになれば、きっと日本人もその状況を受け入れるはずです。
■大インフレ時代に必要なのは生産性の向上
世界の工場として活躍するために、日本が率先してやるべきこと。それは、生産性の向上でしょう。ここ十数年ほどずっと掲げられてきたテーマではありますが、日本人が生産性を上げることは、私自身はそんなに難しいことだとは思っていません。
そもそも、これまで日本の生産性を下げていた最大の原因はデフレです。たとえば、お店に来客が1日1人でも、10人でも固定費は変わりません。デフレで需要が低迷することで、売り上げに対する費用の割合が高く、それが必要以上に日本の生産性を低く見せていました。デフレが終わり、インフレになるだけでこの問題は大部分解決します。
しかし、問題はその先です。
たとえば、私が新入社員だった1993年、銀行には携帯電話やタブレットはありませんでした。コンピュータはかろうじてありましたが、マウスもなく、使い勝手は非常に悪かった。ソフトも「一太郎」や「Lotus 1-2-3」しか入っていないし、インターネットもつながっていません。
あらゆるものは紙のやり取りで、お茶をくむためだけの一般職の女子社員が雇われるなど、非効率的な作業の連続でした。
■省力化に向けたデジタル化、規制緩和も大切
でも、時代は変わりました。当時の銀行でワンフロア全員でかかりきりだった仕事も、これだけDX化が進んだ現在ならば、1人でやることは可能でしょう。AIの登場によって、人手すらも不要になるかもしれません。ところが、マスコミはマイナンバーと保険証の一本化にすら大反対している。これは本当に情けない。
人口減少と騒ぐなら、省力化に向けた努力は絶対に必要です。テクノロジーの進化がそれを大部分解決してくれるだろうと私は考えています。
もっとも、さらに生産性を上げるには、規制緩和も大切です。
自由な経済を生むには、いろんなアイデアをイノベーションに変える必要があります。
イノベーションを生んで社会を動かした人は、きちんとリターンが得られて、私有財産が得られるサイクルも必要です。これこそ、まさに自由で開かれた社会と言えるでしょう。この理念をしっかり守らず、社会主義的な規制を強化したり、増税ばかりを重ねたりするような世の中では、誰しもやる気を失います。
イノベーションを起こした人にはリターンが得られるような仕組みであれば、働く人たち自身がどんどん効率を上げようと努力します。仮に、1人で数人の高齢者を支える未来になっても、1人の収入がいまの20倍になれば何の問題もありません。人口が1%近く減っても、生産性の上昇が一桁台後半から十数%なら、カバーできます。
■世界トップレベルを誇る日本のインフラを輸出せよ
これからの日本が世界市場で生き抜く上での武器になるのではと私が考えているのが、日本の生活環境、社会システムの海外輸出です。
2000年以降、日本は非常に衛生的で快適な国になったと強く思います。私が小学生のころは、日本はまだまだ生活インフラについては後進国だったはずです。1968年に世界第2位のGDP大国にはなったものの、ショッピングモールなどもないし、駅のホームや飲食店内で煙草を吸う人も大勢いるし、街中で立ち小便をする人も少なくありませんでした。最近ジェンダーレストイレの導入が話題になっていますが、当時は男女共同便所も当たり前でした。
しかし、1980年代に入ってから大型スーパーが台頭し、2000年からはショッピングモールも増えていきました。
アメリカで1978年に公開された『ドーン・オブ・ザ・デッド(邦題:ゾンビ)』は、ショッピングモールでゾンビと戦う様子が描かれています。当然、映画内にはショッピングモールのシーンがいっぱい出てくるのですが、その様子を見ると、まさにいまのイオンモールのようです。

屋内にもかかわらずキレイな橋や噴水、子ども用のカートなどもあるし、お店の種類も豊富です。登場人物は銃の販売店から銃を奪ってゾンビを撃ち殺す。1978年の時点で、アメリカにはアイスクリーム屋から服屋までが回廊の両側に並ぶ大規模な商業施設が完成していたのです。
■安全保障を節約しながらインフラを整備した
そこから20年遅れて日本にはショッピングモールが建設されます。でも、20年の遅れがあったにせよ、現在の日本ではアメリカのモールの清潔さを超えるインフラが生まれたと私は感じます。
先日、GDPで日本を抜いたと言われる台湾へ旅行に行きましたが、台北市の外に出ればトイレに使用した紙が流せず、使用したトイレットペーパーをゴミ箱に捨てるようなトイレがまだまだ主流でした。
日本も世界第2位の経済大国になってからインフラが整備されるまで、20年ほどの歳月を要しました。その間、日本は軍備にほとんどお金を使わないで済みました。なぜなら、80年代の後半からソ連崩壊などを経て東側諸国もいなくなり、目先の脅威が消えたからです。さらに、日米安保のおかげでアメリカの軍事力に乗っかり、軽武装で済んだため、安全保障に予算を振らずとも助かった。
結果、社会インフラの整備にこれらのお金を全部投じて、1945年から2000年までの55年間に、やっとここまでインフラを整備できたわけです。
■トイレや公共交通機関、食事は日本の財産
台湾や韓国がGDPで日本を抜いたとしても、目の前の脅威に軍事費をそれなりに使わなければなりません。そうした制限がある中で社会インフラを整備するのは、なかなか大変なことです。
彼らに、日本が辿ってきた道を教えて、日本よりもさらに効率良く実践してもらうことで、インフラ整備などが進んでいくはずです。
日本型の暮らしは、広い家ではなくとも快適ですし、トイレも清潔。どんな場所でもだいたい鉄道やバスなどの公共機関を使えば移動できるし、食事もおいしい。
こうした日本の都市インフラや快適な家のシステムを輸出できるのではないかと思います。かつて、元都知事の石原慎太郎氏が「日本の水道システムはすごいから、システムごと海外に売れるんだ」とおっしゃっていましたが、まさにその通りです。
安倍元総理も日本のインフラを「質の高いインフラ」と呼んでおられましたが、こういうものを日本の財産と捉えて、海外に日本型生活モデルを売っていくことはできないのだろうかと感じます。その先には、生活面で「JAPAN as No.1」と言われる時代が来るかもしれません。
■日本的な生活に憧れさせて、ビジネスにつなげる
今後、日本的なインフラや暮らしやグルメなどを含めて、世界の人が「これは良い」と思ってくれているものをどんどん海外に輸出して、インフラビジネスを発信すれば、新たなビジネスになるのではないかと思います。
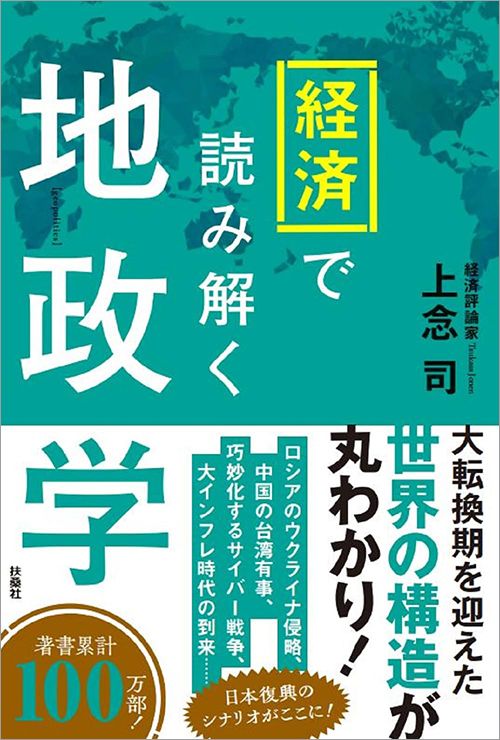
石川県には「加賀屋」という有名な旅館がありますが、2010年に「日勝生加賀屋」として台湾に進出。現地で高い人気を誇っています。台湾の加賀屋に行った台湾人が、あまりのホスピタリティや施設の完成度に感動してファンになり、「日本の加賀屋にも行きたい」と石川県にある加賀屋の本店に大勢押し寄せています。
加賀屋のようなシステムが台湾で人気を博して、日本に観光客を呼ぶ起爆剤になっているのであれば、質が高くて快適で日本的な生活を憧れさせるだけではなく、「あなたの国でも、日本のような清潔で快適なインフラが体感できますよ」と売り込んで、輸出することもできるでしょう。
----------
経済評論家
1969年、東京都生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。在学中は創立1901年の日本最古の弁論部・辞達学会に所属。日本長期信用銀行、臨海セミナーを経て独立。2007年、経済評論家・勝間和代氏と株式会社「監査と分析」を設立。取締役・共同事業パートナーに就任(現在は代表取締役)。2010年、米国イェール大学経済学部の浜田宏一教授に師事し、薫陶を受ける。金融、財政、外交、防衛問題に精通し、積極的な評論、著述活動を展開している。
----------
(経済評論家 上念 司)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
【解説】大企業過去最高益、日本に還流せず 日本に投資を取り戻す、政府、財界の案は?
日テレNEWS NNN / 2024年7月17日 7時0分
-
知らないと本当に大損する…エミン・ユルマズ「2050年に日経平均株価が30万円になる4つの固い要因」
プレジデントオンライン / 2024年7月12日 6時15分
-
元気な企業を見てみれば、日本の実像はそんなに悪くない
ニューズウィーク日本版 / 2024年7月9日 16時40分
-
失業した若者が階段や公園で行き倒れている…不動産バブルがはじけた中国の「ゾンビ経済」の実態
プレジデントオンライン / 2024年7月5日 8時15分
-
経済的威圧を強める中国、これまでの動きから見えてくる規制対象品選出の条件
マイナビニュース / 2024年7月5日 7時15分
ランキング
-
1貯金ゼロの貧乏ママが“資産1億円”を達成するまで。1日14時間以上の勤務に疲れ果て「これは続けられない」
日刊SPA! / 2024年7月17日 8時52分
-
2《衝撃の大ゲンカ》"フェラーリ”がF1鈴鹿サーキットを“出禁”になっていた!「フェラーリ社長があるトラブルを起こして…」
文春オンライン / 2024年7月17日 16時0分
-
3「石丸伸二を支持する人」の熱が冷めてきた事情 小泉純・橋下両氏に並ぶ「SNS時代」のトリックスター
東洋経済オンライン / 2024年7月17日 8時40分
-
4「九州南部が梅雨明け 他の地域の梅雨明けは?」 週末以降は10年に1度レベルの著しい高温
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月17日 12時44分
-
5長野県の黒川ダムに車転落、女子学生が死亡…救助に飛び込んだ学校職員が行方不明
読売新聞 / 2024年7月17日 15時4分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











