だから子供にゲームを与えてはいけない…神経内科専門医が「20歳未満にゲームは危険すぎる」と訴えるワケ
プレジデントオンライン / 2023年9月7日 10時15分
※本稿は、駒ヶ嶺朋子『死の医学』(集英社インターナショナル新書)の一部を再編集したものです。
■オンラインゲーム依存症が精神科診断マニュアルに掲載
シミュレーションと熱中できる運動という2つの面から、ゲームによるリハビリの可能性は無限大だと思われる。しかし現時点でゲームがリハビリプログラムに取り入れられているかというとまだわずかである。
医学論文の数では、インターネットやデジタルゲームを医学応用したという報告より、ゲームの危険性、特に依存性についての報告のほうが多い。
精神医療の標準化を目的として編纂(へんさん)されている『精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM)』という、辞書のような本がある。2013年に改訂された第5版ではとうとう、「今後の研究のための病態」の項に、「インターネットゲーム障害」が登場した。
デジタルゲームへの依存症は、特にオンラインゲームでよく起きるので、こうした病名になった。
依存が起きやすいゲームの種類も調査されており、マルチプレーヤー参加型オンライン・ロールプレイング・ゲームで最も依存症の頻度が高い(※1)。
※1 Smyth JM. Beyond self-selection in video game play: an experimental examination of the consequences of massively multiplayer online role-playing game play.Cyberpsychol Behav 2007;10:717-721.
■3割弱の人が「依存していた時期がある」と回答
インターネットゲーム障害はゲーマー全体の1割ほどと考えられている(※2)。
※2 Gentile DA et al.Internet gaming disorder in children and adolescents. Pediatrics 2017:140;S2:S81-S85.
さらに自己申告で「人生の一時期でもゲームに依存したことがあるかどうか」という、最もスパンの広い調査をしたところでは、3割弱の人が「依存していた時期がある」と答えたという(※3)。
※3 Wittek CT et al. Prevalence and Predictors of Video Game Addiction: A Study Based on a National Representative Sample of Gamers. Int J Ment Health Addict. 2016;14:672-686.
私自身も任天堂の初代ファミリーコンピュータを買ってもらって、学校から帰宅するなりランドセルを背負ったままマリオを数時間続けるという異様な執着を示して、1週間かそこらで取り上げられてしまった、という経験がある。
普通にゲームを楽しむこととは別に「問題となるゲームの仕方」というものがあるので、それを避けようという啓蒙(けいもう)は必要だと考えられている。
■ゲーム依存症はアルコール依存症と似ている
「インターネットゲーム障害」は、ただ単に長時間連続でゲームをするだけでは該当しない。
ゲームをしていない時もゲームのことを考え続け、取り上げられた時にイライラしたり不安になったり、それからだんだんとゲーム時間が長くなっていったり、現実生活での関係性がどうでもよくなってしまったり、現実逃避のためにゲームに没頭したりするかどうかで診断される(※4)。
※4 アメリカ精神医学会. 日本語版: 日本精神神経学会監修. DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル. 医学書院;東京;2014.
項目的にはアルコール依存症と似ている。
というのも、メカニズムはまだ分かっていないものの、ゲーム依存はその他の依存症と大して変わらないのではないか、と推察されるからである。

■若ければ若いほど依存も強固になりやすい
依存症は脳の「報酬系」と呼ばれる経路と、扁桃(へんとう)体という快・不快を判断する構造に関係する。
年をとれば脳が変性し、神経伝達物質は誰でも緩やかに枯渇していく。
反対に若ければ若いほど、脳の神経伝達物質はたくさん出て、それを受け取る報酬系の受容体もしっかり機能する。そのため依存も強固になりやすい。
■20歳になってから始めたほうがいい
だから依存症の原因となるようなものは、なるべく脳の反応が衰えてから始めた方がよい。ゲームも砂糖もお酒も報酬系の賦活(ふかつ)化という意味では同じだ。依存の観点だけで言えば20歳になってから始める方がたしなみ程度で済むだろう。
ゲーム依存のリスク要因として、「若年」「男性」「独身」「短い教育歴」「無職」「注意欠陥多動症(ADHD)」が関係することが明らかになってきている。
ADHDの場合、大きな強制力より、目前に迫る小さな強制力にとらわれてしまう傾向があるため、ゲーム依存になりやすいと考えられている。

■ゲーム依存はADHDの重症度と関連する
ゲームの種類を通信性ロールプレイングゲーム、通信のないロールプレイングゲーム、サバイバル、カーレース、ホラーなど12種に分け、それぞれの依存の強さを検討したある研究では、ゲームの種類よりもむしろADHDの重症度と関連したと報告されている(※5)。
※5 Mathews CL et al. Video game addiction, ADHD symptomatology, and videogame reinforcement. Am J Drug Alcohol Abuse 2019;45:67-76.
インターネットゲーム障害は基本的には精神科で相談される事項であるので、患者さんは内科にはあまり来院しない。
脳神経内科では、頭痛や不眠があって学校に行けないという主訴で来院される10代の方の中に、ゲームやネット依存の方が含まれている例に出会う。
まだ子どもであるので、自分でゲームを購入したわけではない。そこで「なぜ、それが与えられたのか(始めたのか)」を考えてもらい、「抜け出せなければ何が起きるのか」を自分で考えてもらうことにしている。
■「子どもにゲームを与える」は支配や搾取につながる
ゲームを始めた理由はそれぞれで、友人がやっているから自分もという場合もあれば、試験勉強のご褒美(ほうび)、大病した際に一人きりで過ごすのがかわいそうで与えた、という場合もあるだろう。また、おとなしく黙って座っていてもらうために親から渡される場合もあり得る。
大人の集まりに子どもを連れていって騒がれ、「静かにしなさい」と叱るよりも、ゲームを与えるほうがいい、という軽い気持ちかもしれない。ただ、大袈裟(おおげさ)に言うと、そういう与え方自体が、子どもに対する支配や搾取(さくしゅ)を目的としているとも言える。

■「言うことを聞く子どもにしてやる」と覚せい剤を打たれた
依存症の形成には、脳の中で報酬系という「やればその個体にとって有益であるので、褒めてその行動を促すために進化してきた経路」の活性化が関わる。褒めて育てるので報酬系というわけである。
報酬系の刺激を欲しがるのは、脳がとても健気(けなげ)であるためだ。
本来は生物として個体の生存を高める行動に対して、報酬系が作動する。
その報酬系ではドパミンという神経伝達物質のやりとりがメインとなる。
がんばった時や、熱中した時に報酬系が活性化し、ドパミンが出るのが「自然」な状態だ。
このドパミンを、そういう出来事をすっとばして直接放出させる物質の一つに覚せい剤がある。
「言うことを聞く子どもにしてやる」と父親に覚せい剤を打たれたのが、覚せい剤を使用した最初だとおっしゃる、年配の依存症の方に、筆者は出会ったことがある。
■ゲームが上手いほうが内視鏡手術が上手い
ゲームをする時間が長時間にわたり、頭痛や、不眠による不登校をきたして、外来に連れて来られる方がいる。ただ、その中には、将来ゲームクリエイターになりたい、コンピューターのプロになって、新しいプログラムを創り出したい、だから、長時間をゲームに費やしている、という少年少女もいる。
近年では、「e-スポーツ」も台頭しつつある。いずれ、寝たきり状態の方が、e-スポーツの選手として活躍する、といった時代が来るのだろう。
リハビリや医療を担当する医師たちの中にも、ゲームで育った世代が増えている。
近年、外科手術の主流は内視鏡手術に移ってきているが、ビデオゲーム歴があった方が内視鏡手術が上手い、あるいは、ビデオゲームが上手いほうが内視鏡手術が上手い、という論文も多々ある(※6、7)。
※6 Sammut M et al. The benefits of being a video gamer in laparoscopic surgery. IntJ Surg 2017;45:42-46.
※7 Datta R et al. Are gamers better laparoscopic surgeons? Impact of gaming skills on laparoscopic performance in "Generation Y" students. PLoS One 2020;15:e0232341. doi: 10.1371/journal.pone.0232341
モニターを見ながら手元を操作する技術が、ゲームを通じて身についているためだろう。
■ゲーム依存が悪かどうかは人による
時代に応じて生き抜く手段は更新されていく。
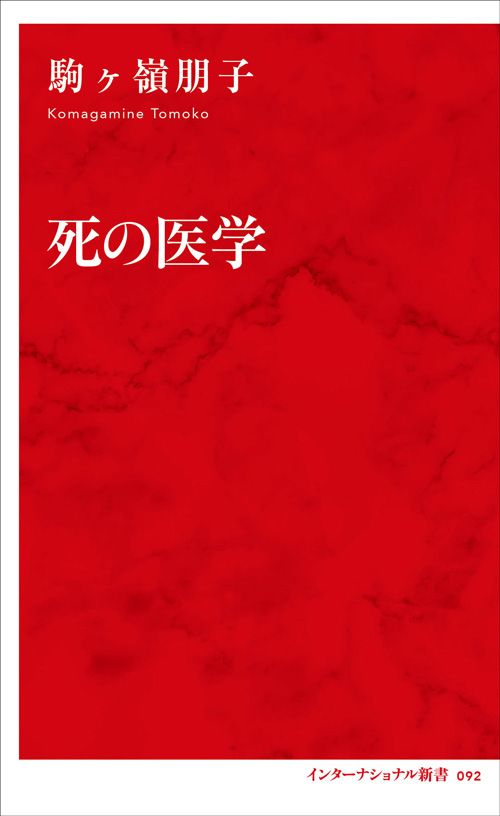
依存症で生活がままならない、あるいは、依存の仕組みによって誰かに支配され、搾取される、ゲーム自体が夢であっても、依存に陥り逆に夢が遠のいてしまう。
もしそうした状況にあるならば、依存症から抜け出す手立てを考えるべきだ。
しかし、ゲームの全てが悪というわけではない。「ゲームに没頭する力」をもって、技術を磨き、社会に新しい価値をもたらしてくれるなら、ゲーム依存を全否定できないのではと思う。
万が一、最初の出会いが、親が子どもを黙らせるために与えたのであったとしても、そのゲームを自分の力に変えることもできるだろう。
ゲームに没頭する時間が自己実現につながるのか、それとも誰かに搾取されるだけなのか。
その答えは一人一人異なる。
----------
獨協医科大学大学病院 脳神経内科医
1977年生。早稲田大学第一文学部哲学科社会学専修・獨協医科大学医学部医学科・同大学院医学研究科卒。博士(医学)。獨協医科大学大学病院にて脳神経内科医として診療にあたる。2000年第38回現代詩手帖賞受賞(駒ヶ嶺朋乎名)。著書に『怪談に学ぶ脳神経内科』(中外医学社)、詩集に『背丈ほどあるワレモコウ』『系統樹に灯る』(思潮社)がある。
----------
(獨協医科大学大学病院 脳神経内科医 駒ヶ嶺 朋子)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
会話の中で「アレ」「コレ」が増えたら要注意…最新研究が明らかにした「おりがみ脳活」の驚くべき効果
プレジデントオンライン / 2024年7月5日 7時15分
-
ボケ防止には「匿名でネットに書き込み」は悪くない…脳神経内科医が「高齢者こそSNSを使うべし」というワケ
プレジデントオンライン / 2024年7月2日 10時15分
-
「年寄りにはわからないから」と敬遠していると脳が老いる…高齢者が本当に使うべき「デジタルツール」とは
プレジデントオンライン / 2024年6月26日 10時15分
-
「攻めのリハビリ」を実践するために“いい医者連携”が必要なのはなぜか【正解のリハビリ、最善の介護】
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月26日 9時26分
-
「つらい人生」はただの栄養不足。不調を招く食習慣を改善し、病気を予防する、健康になる食習慣をはじめよう! 「自分で治す栄養療法」で心と体の不調はみるみる改善!
PR TIMES / 2024年6月21日 11時15分
ランキング
-
1ドラマ「西園寺さん」ヒットの予感しかない3理由 「逃げ恥」「家政夫ナギサさん」に続く良作となるか
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 20時0分
-
2月々のスマホ代を「高いと感じる」…「2000円もすることに驚いた」「安いプランなのに高い」格安プランに乗り換える?
まいどなニュース / 2024年7月16日 19時45分
-
3「これは奇跡...」破格の1人前"550円"寿司ランチ。もうこれ毎日通いたい美味しさ...。《編集部レポ》
東京バーゲンマニア / 2024年7月16日 7時2分
-
4丁寧な言葉遣いで一見おとなしい人ほど陰湿攻撃がエグい…「目に見えない攻撃」を繰り出す人「6パターン」
プレジデントオンライン / 2024年7月16日 15時15分
-
5「ダイエットの成否」を分ける"睡眠時間の壁" 寝不足では「運動」や「栄養管理」も意味がない
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 18時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











