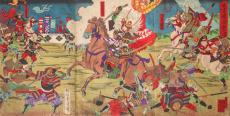史実からかけ離れた歴史ドラマはアリなのか…直木賞作家が「司馬史観を批判するのはおかしい」というワケ
プレジデントオンライン / 2023年9月7日 10時15分
※本稿は、今村翔吾『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)の一部を再編集したものです
■「歴史小説」とはそもそも何を指すのか
そもそも「歴史小説」とはいったいどういうものなのでしょう。歴史小説の定義はさまざまあり、どれが正解とも言い切れません。
ただ、簡潔にいうと、歴史小説とは「歴史的な事件や人物をテーマにして、史実をもとに書かれた小説」のことです。
ここで読者の中には、こんな疑問を抱く人がいるかもしれません。「『時代小説』というのも聞いたことがあるけど、歴史小説とどう違うの?」
時代小説とは、古い時代の事件や人物を素材とした小説を意味します。そう聞くと「同じじゃないか」と思われそうですが、歴史小説が史実を重んじるのに対して、時代小説は単に過去の時代を背景にしているという違いがあります。別の言い方をすれば、時代小説はフィクション性がより強く、その時代を生きた人と人との関わりを濃密に描く傾向があります。
私が二つの小説の違いを尋ねられたときには、「ごく簡単に言い切れば」と断った上で、「大河ドラマのようなものが歴史小説で、『水戸黄門』のようなものが時代小説」と答えています。なんとなくイメージがつかめたでしょうか。
■『真田太平記』は歴史小説、『鬼平犯科帳』は時代小説
もともと歴史小説と時代小説は、ほとんど同じものとされていました。戦後間もない頃まで歴史小説・時代小説の区分はあいまいで、どちらとも分類できない作品や、両方を執筆する書き手もたくさんいました。歴史を題材にした小説をひっくるめて、歴史小説とか時代小説と呼んでいたのです。
しかし、あるときから急に少しずつ両者が分かれ始め、いつの間にか歴史小説の書き手と時代小説の書き手が別物と分類されるようになりました。それぞれが専業化していき、いずれか一方しか書かない作家が増えてきたのです。

戦後に活躍した作家の中で、歴史・時代の両方で成功した書き手は池波正太郎くらいだと思います。池波作品を例に挙げれば、『真田太平記』は歴史小説、『鬼平犯科帳』や『剣客商売』は時代小説ということになります。
司馬遼太郎は初期作品こそ時代小説の雰囲気がありましたが、中期以降は完全に歴史小説に特化していますし、藤沢周平は完全に時代小説に特化しています。
山田風太郎は時代小説寄りで、陳舜臣や宮城谷昌光は歴史寄り。髙田郁、佐伯泰英といった書き手は時代小説で、天野純希、木下昌輝、澤田瞳子は歴史小説。こんな具合に、どちらかに寄る傾向が顕著となっています。
■池波作品の愛読で自然に身についた「二刀流」
私自身は、中高生の頃、両者のごちゃまぜ時代の書き手にどっぷり耽溺したおかげで、歴史小説と時代小説の違いをあまり意識しないまま、プロの書き手となりました。
結果的に、今では珍しい歴史小説と時代小説の二刀流になっています。過去の作品でいうと、『童の神』『八本目の槍』『じんかん』などは歴史小説に、『羽州ぼろ鳶組』や『くらまし屋稼業』シリーズは時代小説に分類されます。
もしかすると、歴史小説と時代小説の違いは、お笑いでいうところのピン芸(単身での活動)と漫才の違いのようなものかもしれません。お笑いの世界では漫才に特化している芸人さんもいれば、ピン芸に特化している人もいます。ただ、ときどき漫才コンビの1人がピン芸を披露したり、ピン芸人がユニットを組んでM-1グランプリにチャレンジしたりすることもあります。
私にしてみれば、「ああ、今日の池波先生はピンでやっている」「今日はコンビで出ている」という感覚で池波先生の作品に親しんできたので、特殊な訓練を経なくても両方できるようになりました。
■今や太平洋戦争時代も「歴史」の範囲
業界内では歴史・時代の区分は明確ですが、一般の読者が両者を厳密に区分しているわけではありません。新聞やテレビなどでは歴史小説を「時代小説」ということもありますし、その逆もあります。そこをあえて私たちが否定するべきものでもないですし、厳密な定義にこだわる必要もないと考えています。
この本では、話をわかりやすくする便宜上、基本的には歴史小説と時代小説を合わせて「歴史小説」と記述することにします。

では、歴史小説がテーマとする「歴史」は、いつまでを指すのでしょうか。
10年ほど前までは、大正時代までが歴史小説と現代小説の境界線という解釈が一般的だったように思います。出来事でいえば、日露戦争や第一次世界大戦、関東大震災くらいまでが歴史小説の範疇(はんちゅう)という感じです。
しかし最近、特に令和以降は、昭和期の太平洋戦争を扱った作品も歴史小説とみなされるようになってきました。それまで太平洋戦争を描いた小説は、「戦争小説」という別ジャンルに括(くく)られていましたが、徐々に歴史小説に吸収された印象があります。いよいよ昭和も歴史になったわけです。
その意味では、ゼロ戦の特攻パイロットを描いてベストセラーとなった『永遠の0』(百田尚樹著、講談社文庫)も歴史小説といえるのでしょうし、このペースでいけば、令和が終わる頃には平成時代が歴史小説の範疇になっている可能性さえあります。
■米軍占領時代を境に起きた日本史の「断絶」
けれども、私の予想では平成という時代はいつまで経っても歴史小説の雰囲気を持たないような気がしています。というのも、日本という国や日本人を大きく変えた出来事がいくつかある中で、史上最大の変化が起きたのは第二次世界大戦後だと考えているからです。
私は戦後の歴史を「新日本の歴史」と捉えています。だから、戦後の史実に基づいた小説は新歴史小説ではあるけれど、オーソドックスな歴史小説とは別物であるように思うのです。
日本の歴史を時系列で見ていくと、「この出来事があったからこうなってきた」というつながりを発見できます。しかし、第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の占領時代の頃から、そのつながりは断絶したように見えます。占領期間以降の日本は、良くも悪くも日本人が日本人らしくなくなる時代に突入しています。
つまり、現在は猛烈なスピードで歴史小説のイメージが変貌しつつある状況ともいえます。大正期の人が、歴史小説を「祖先の物語」として身近に感じていたのに対し、近未来の人は、異世界の物語として受け止めるようになっている可能性があります。
将来的には、自分たちの先祖の話であるにもかかわらず、失われた国を観察するような感覚で歴史小説を読むことになるのかもしれません。
■「歴史小説」と「歴史書」は別物である
これから本格的に歴史小説を読もうとする人に注意してほしいのは、小説と歴史書は別物だということです。
歴史小説家は、あくまでも物語を楽しんでもらいながら、知らない間に歴史が好きになり、歴史の知識を身につけてくれたら嬉しい、というくらいの思いで作品を書いています。「歴史を学べ、もっと知れ」と思っているとしたら、その書き手は正しく歴史小説を書けていないとさえいえます。
同業者の悪口はあまり言いたくないのですが、実際に「俺はこれだけ調べたぞ」と言わんばかりに、調べた情報をすべて盛り込もうとする書き手がいます。物語の本筋とは無関係の情報なのですが、調べた苦労を思うと披露せずにはいられないのでしょう。
「実は、このときの○○の妹は後に□□となり、90歳まで生き延びることとなるが、これはまた別の話である」。こういった記述は、読者に対するただの押しつけです。
押しつけがましさを回避しながら歴史の知識を伝え、次の作品を読みたくなるように誘うのが歴史小説家のテクニック。このジャンルの入口を担っている書き手の1人として、それを忘れないように作品を書いていますし、それができている書き手の本を読んでほしいのです。
■「司馬史観」はなぜ生まれたのか
話を元に戻します。
歴史と歴史小説の違いを語るときに、避けて通れないのが司馬遼太郎という作家の存在です。司馬遼太郎は戦後を代表する国民的作家の1人であり、作品を通じて提示した歴史の見方は「司馬史観」と呼ばれます。
たしかに司馬遼太郎が描いた作品には、フィクションの要素や現在の研究では間違いとされていることが多いのは事実です。ただ、司馬遼太郎があまりに読書界を席巻したがために、彼の描く歴史が本当の歴史だと考える人をたくさん生み出してしまいました。
■もし司馬遼太郎が歴史家になっていたら
平成に入った頃から、その反動で歴史家の間で司馬史観を批判する声が高まるようになります。ネットの普及とともに、さらに個人の読者からも「司馬遼太郎が書いたことを信じているなんておかしい」といった発信が行われるようになりました。司馬遼太郎が非難され、貶(おとしめ)られる時代が始まり、今でもその論調が完全に下火になっていないのが現状です。
しかし、私自身はそれを不当なバッシングだと考えています。みんなが勝手に司馬遼太郎を歴史家のように持ち上げたのであり、本人は自らの学説が正しいと主張したことなど一度もありません。
東京大学史料編纂所教授の本郷和人氏は、「司馬遼太郎を批判する歴史家は多いけれど、仮に彼が歴史家になっていたら、彼を批判する歴史家よりももっと素晴らしい研究成果を残していたはずだ」といったことを語っています。
その通りであり、司馬遼太郎は娯楽作家としてエンターテインメントを追求しただけなのです。結局のところ、どんなジャンルでも傑出(けっしゅつ)しすぎると叩かれるのが運命なのでしょう。
■「リアルな再現」一辺倒では小説は成立しない
実は私自身、歴史小説を書いていて、学者の方から批判を受けることがあります。代表的なのが、「平安時代の人は、こんな言葉を話していなかった」という指摘です。
では、本当に小説で平安時代の話し言葉をリアルに再現したらどうなるでしょうか。読者はまったくついてこられないでしょうし、すぐに本を投げ出すに違いありません。
小説家は、歴史の案内人としてわかりやすく伝える工夫をしているのです。工夫を怠って「読める人だけ読めばいい」という文章を書いている限り、歴史ファンは一生増えないでしょう。
歴史小説をきっかけに、広義の歴史好きが増えていくからこそ、その母体から本格的な研究者も生まれるわけです。それなのに、歴史家が歴史小説家の揚(あ)げ足をとっていたのでは、研究を志す人が増えないのも当然です。
■「創作だとわかった上で引き込まれる」のが優れた作品
歴史小説家と歴史家を対立軸で捉える向きが少なくないのですが、それは大きな間違いです。史実を確定していくのが歴史家の仕事であり、史実の見方を提示するのが歴史小説家の仕事です。両者は対立などしなくても、お互いに協力しながら共存できるはずです。
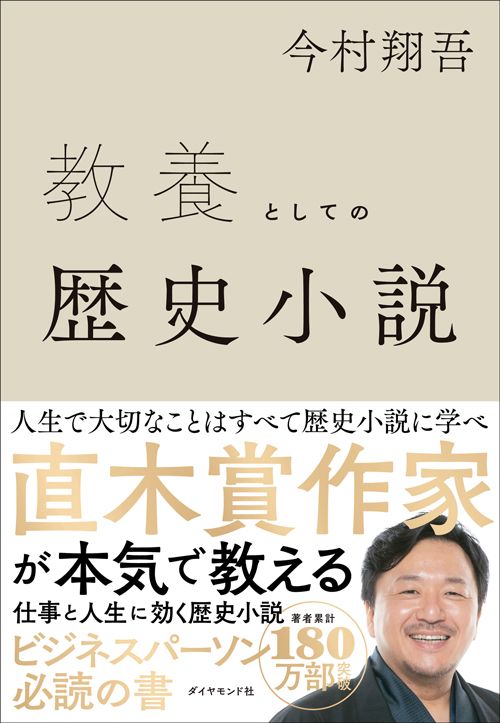
これは現実の警察官と警察小説を書く作家の関係を考えればよくわかります。
警察小説に書かれている物語には、事実もあれば脚色されたエピソードもあります。現職の警察官からすれば「いやいや、それは盛りすぎでしょ」とツッコみたくなる部分も多々あるはずですが、警察官が警察小説の書き手を名指しで批判したという話を聞いたことがありません。警察官は、警察小説をエンターテインメントとして理解し、許容しています。
小説家が提示するのは一つの見解です。その中には想像や脚色も多分に含まれています。読者は、あらかじめそういうものだと理解した上で読む必要があります。創作だとはわかっていても、それを忘れてしまうくらいに引き込まれてしまうのが優れた歴史小説であり、司馬遼太郎はそのレベルの作品を残したということなのです。
----------
小説家
1984年京都府加茂町(現・木津川市)生まれ。関西大学文学部卒。小学5年生のときに読んだ池波正太郎著『真田太平記』をきっかけに歴史小説に没頭。32歳のとき『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』でデビュー。2022年『塞王の楯』で第166回直木三十五賞受賞。著書に『イクサガミ 天』『イクサガミ 地』(いずれも講談社文庫)、『八本目の槍』(新潮文庫)、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)など。
----------
(小説家 今村 翔吾)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
最後の徳川将軍と同じ名前、歴史を書く圧倒的な説得力 作家・門井慶喜さん 一聞百見
産経ニュース / 2024年7月12日 14時0分
-
『塞王の楯』今村翔吾×『逃げ上手の若君』松井優征「情報量の管理を意識することで、歴史エンタメの可能性を更新する」
集英社オンライン / 2024年7月6日 11時0分
-
日本の宣戦布告の理由は「南下するロシアの脅威に耐えかねて」ではなかった?…「日露戦争」開戦の知られざる“真実”【世界史】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月2日 10時0分
-
第26回司馬遼太郎メモリアル・デー参加者募集
PR TIMES / 2024年6月21日 11時45分
-
【1962(昭和37)年6月21日】司馬遼太郎『竜馬がゆく』の連載開始
トウシル / 2024年6月21日 7時30分
ランキング
-
1ドラマ「西園寺さん」ヒットの予感しかない3理由 「逃げ恥」「家政夫ナギサさん」に続く良作となるか
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 20時0分
-
2月々のスマホ代を「高いと感じる」…「2000円もすることに驚いた」「安いプランなのに高い」格安プランに乗り換える?
まいどなニュース / 2024年7月16日 19時45分
-
3「これは奇跡...」破格の1人前"550円"寿司ランチ。もうこれ毎日通いたい美味しさ...。《編集部レポ》
東京バーゲンマニア / 2024年7月16日 7時2分
-
4丁寧な言葉遣いで一見おとなしい人ほど陰湿攻撃がエグい…「目に見えない攻撃」を繰り出す人「6パターン」
プレジデントオンライン / 2024年7月16日 15時15分
-
5「ダイエットの成否」を分ける"睡眠時間の壁" 寝不足では「運動」や「栄養管理」も意味がない
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 18時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください